【後悔しない位牌の選び方】5つのチェックポイント|サイズやデザイン・文字入れの疑問を解消
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
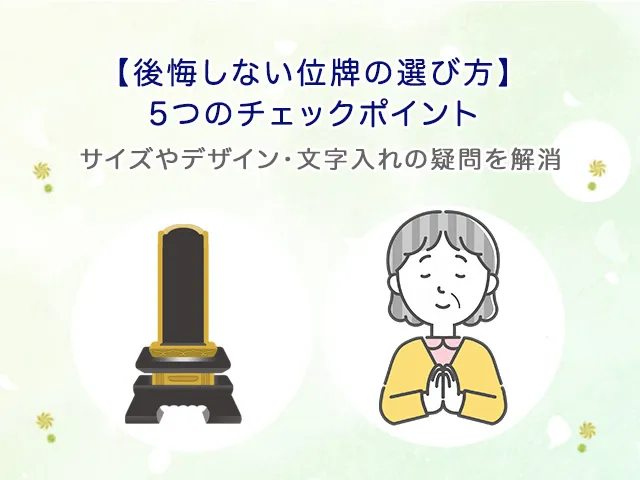
位牌の選び方に悩んでいる方は決して少なくありません。特に、親や配偶者など身近な人を亡くした直後は、悲しみの中で多くの準備に追われ、ゆっくりと検討する時間が取れないこともあるでしょう。
このコラムでは、これから位牌を用意する方に向けて、後悔しない選び方や押さえておきたい注意点をわかりやすく解説していきます。最後まで読むことで、納得のいく位牌を選ぶためのポイントが理解できるようになるでしょう。ぜひ参考になさってください。
1.位牌とは

位牌とは、故人様の戒名(※1)や没年月日が記された札板であり、仏教の多くの宗派においては、故人様の魂が宿る「よりしろ」として大切に扱われます。
位牌は一般的に、「白木位牌(仮位牌)」と「本位牌」の2種類に大きく分けられます。それぞれの特徴は以下の通りです。
【白木位牌】
- ・塗装のない白木で作られた位牌
- ・葬儀から四十九日法要までの期間に使用される
- ・通常、葬儀社や寺院によって用意される
【本位牌】
- ・四十九日以降に使用する正式な位牌
- ・材質やデザイン、彫刻の方法などさまざまな種類がある
- ・基本的にご遺族が用意する
この記事では、本位牌の選び方について詳しくご紹介します。
(※1)仏門に入った際に僧侶から授かる名前。「あの世での名前」でもある。
2.【位牌の選び方】後悔しないための5つのチェックポイント

位牌を用意する機会は人生においてそう多くはありません。「なんとなく」で選んでしまうと、後悔することもあるでしょう。
こちらでは、納得のいく位牌を選ぶために必要な5つのチェックポイントをご紹介します。
1.宗派のルール【最重要】
位牌の選び方で最も重要なのは「宗派のルールに沿うこと」です。例えば浄土真宗の場合、「亡くなった人の魂はすぐに極楽浄土に行く」という考えから、魂のよりどころである位牌を必要としません(※2)。また、位牌を必要とする宗派でも位牌に刻む文字がそれぞれ異なるため、まずは故人様が信仰していた宗派を確認しましょう。
宗派ごとの位牌のルールは、菩提(ぼだい)寺(※3)に確認するのが最も正確です。菩提寺がない場合は、位牌を取り扱っている仏具店や葬儀社などに相談するとよいでしょう。また、位牌は無宗教の方でも作成することができます。無宗教の場合は戒名の有無で位牌に刻む文字が変わりますので、こちらも仏具店や葬儀社にご相談ください。
(※2)位牌の代わりに「法名軸(ほうみょうじく)」や「過去帳」を用意するのが一般的
(※3)先祖代々がお世話になっている、つながりの深い寺院のこと
2.位牌の種類
位牌には、目的や形、素材、デザインによってさまざまな種類があります。位牌のデザインや材質には、宗派による決まりは基本的にありません。選び方のポイントは「仏壇にまつった時の印象」「ご先祖様の位牌との調和」で考えるとよいでしょう。こちらより、位牌の主な種類について、解説します。
塗り位牌

「塗り位牌」は、漆で塗装され、金箔や金粉で華やかに装飾された位牌のことを指します。深い黒の光沢が特徴的で、一般的に「位牌」と聞いて多くの人が思い浮かべるのがこちらのタイプでしょう。
塗り位牌は使用される木材や漆の種類、塗りの技法、装飾に用いる金の質などによって、仕上がりや価格に大きな違いが生まれます。例えば合成塗料を使い、大量生産される位牌は比較的安価であるのに対し、「会津位牌」のように伝統技術を受け継ぐ職人が手作りする位牌は高額になる傾向があります。
「伝統的な位牌を用意したい」「仏壇にまつられているご先祖様の位牌が塗り位牌だった」という場合におすすめです。
唐木位牌

黒檀(こくたん)や紫檀(したん)などの高級木材に、クリアな塗装を施したものが「唐木位牌(からきいはい)」です。名前の由来は、かつてこれらの木材を中国(唐)経由で輸入していたことにありますが、現在では国産の木材を使う製品も多く見られます。
唐木位牌は、木目の美しさと自然な質感を活かした落ち着いた風合いが魅力で、耐久性にも優れています。装飾を抑えた品のある佇まいから、上質な印象を大切にしたい方に適した位牌です。
モダン位牌

従来の位牌の形式や素材にとらわれず、デザインの自由度を重視しているのが「モダン位牌」です。
木材だけでなく、ガラスや天然石などを用いたものもあり、現代の住まいの雰囲気に合わせて選べる点が特徴です。暮らしに自然に溶け込む仏具を求める方や、インテリアとの調和を大切にしたいという希望に応える、新しい発想の位牌として注目されています。
その他の種類については「位牌の種類」の記事でご紹介しておりますので、ぜひ併せてご覧ください。
3.位牌の形状
位牌の形にもさまざまな種類があります。こちらも宗派による決まりはないため、仏壇にまつった時の印象や、選ばれる方の好みで決めるとよいでしょう。以下に、代表的なものをご紹介します。
春日型

位牌の中では最もベーシックな形の「春日型」は、四角の台に、頭が半円になった札が立っています。装飾を抑えたシンプルなデザインであるため、宗派や仏壇のデザインを問わず受け入れやすいのが特徴です。
勝美型

春日型に見られる「半円」とは異なり、札の頭が木瓜(ぼけ)という花の形に似ているのが「勝美型」です。また、板を支える台座には独特な前垂れがついており、「金虫喰い」という金箔の装飾が施されています。
葵角切

全体的に丸みを帯びているのが「葵角切(あおいすみきり)」です。台には蓮の花の装飾が施されている他、和風の門構えのような前垂れがついています。
他の位牌と比べて札の幅が広いため、夫婦連名の位牌を用意したい方、なめらかな曲線から受ける「やわらかい印象の位牌」を探している方におすすめです。
切高欄

台座の中央に高欄(こうらん)と呼ばれる仕切り板がついた位牌の形状を「切高欄(きりこうらん)」と言います。高欄は寺院や仏壇にも取り付けられていることが多く、位牌にも荘厳な雰囲気をかもし出してくれるでしょう。他の位牌と比べて高さがあるため、選ぶ際はサイズ感に注意が必要です。
4.位牌のサイズ
位牌のサイズは「寸」と表し、1寸は約3㎝です。500mlのペットボトルを一回り小さくした程の高さ(3.5~4.5寸)が主流ですが、選ぶ際は以下の注意点を踏まえることが重要です。
【位牌のサイズ選びのポイント】
- ・仏壇のサイズや、位牌を置くスペースを考慮する
- ・仏壇の上段にまつっているご本尊の高さや、目線を超えないようにする
5.位牌に刻む文字
位牌に刻む文字は主に「戒名」「俗名(※4)」「没年月日」「梵字(ぼんじ)」「没年齢」の5つです。基本的に、白木位牌に刻まれているものを参考にします。
「梵字」は、宗派の信仰の対象をサンスクリット語で表した、1~ 2文字程度の言葉です。

例えば浄土宗は「キリーク」、真言宗は「ア」と読む梵字が用いられることがあります。宗派によって梵字は異なり、梵字を用いない宗派もあるため、必ず確認するようにしましょう。
「戒名」は主に約6~12文字で構成されますが、宗派や戒名の位によって、文字数や構成が異なります。「戒名と法名の違い」にて詳しく解説しておりますので、そちらをご覧ください。
なお、位牌に文字を入れる方法は「彫刻」と「位牌に直接書く方法」があり、それぞれ「機械加工」か「手加工」かが選べます。手間と技術を要するほど価格が高くなる傾向にあるため、位牌の費用を考える際の参考にされるとよいでしょう。
(※4)故人様の本名
3.完成した位牌の確認も大切

完成した位牌は、必ず受け取り時に確認することが大切です。実際に手に取ってみると「イメージと違う」と感じたり、不具合が見つかったりすることがあるためです。
特に注意すべきポイントとしては、戒名や日付の誤字脱字といった単純なミス、塗装の仕上がり具合、位牌に対する文字のサイズとバランスなどが挙げられます。位牌は長く手元に残る大切なものだからこそ、納品時には細部までしっかりと確認し、不明点があれば遠慮せずお店に相談しましょう。後述する「位牌選びでよくある失敗と対策」も参考にしてください。
4.位牌はどこで買う?購入場所による違い・選び方

位牌は「寺院」「仏具店」「ネット通販」「葬儀社」などから購入することができます。以下の各購入先のメリット・デメリットを見て、「どこで買うのが自分にとってベストなのか」を考えてみましょう。
| 購入先 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 寺院 | 法要の相談も一緒に行える | 位牌の選択肢が少ない |
| 仏具店 | 実物を見て相談しながら選ぶことができる他、位牌以外の仏具もまとめて購入できる | 店舗に直接行く手間がかかる |
| ネット通販 | 時間や場所を選ばずに購入でき、費用の比較が簡単 | 実物とイメージに差が出やすい |
| 葬儀社 | 位牌の作製依頼とともに葬儀、法要、お墓などの相談が一括で行える | 仏具店やネット通販と比較すると位牌の選択肢が少ない傾向にある |
5.位牌の価格相場~価格差が生まれる理由~

位牌の価格は「材質」「デザイン」「製法・技術」「製造場所」「ブランド」によって大きく異なり、相場は1~15万円とされています。高級品やモダン位牌では15万円以上、伝統工芸品や特注品では30万円を超える場合もあります。一例として、高額に分類される位牌にはどのような特徴があるのかを見てみましょう。
【材質】
高級な木材や塗装剤を使い、装飾が多い
例)黒檀や本漆、高品質な金箔
【デザイン】
凝ったデザインである
例)複雑な装飾が施されている切高欄など
【製法・技術】
洗練された職人の手でひとつひとつ丁寧に作られている
例)手塗りや手掘り加工
【製造場所】
国産である
【ブランド】
国産高級位牌ブランドとして知られるメーカーのものを選ぶ
例)まつたに位牌、会津位牌 など
位牌の価格を抑えたいと考える方も少なくありませんが、位牌は故人様の魂のよりどころであり、長く手元に置く大切なものです。安さだけを重視して選ぶと、仕上がりや素材の質に不満が残り、後悔につながる可能性もあります。
価格だけでなく、品質やデザイン、耐久性にも目を向け、さまざまな位牌を比較検討することが大切です。納得のいく「価値ある位牌」を選ぶことで、心から安心できる供養へとつながっていくでしょう。
6.位牌選びから四十九日までのスケジュール

本位牌は、注文してから届くまでに通常1~2週間程度を要します。四十九日法要の際に白木位牌から本位牌へと変えるのが一般的ですが、その際には魂を移すための儀式も必要です。準備が後回しになると、四十九日に間に合わないこともあるかもしれません。
慌てずに落ち着いて準備を進めるために、こちらでは、本位牌を作成するまでの主な流れとスケジュールの目安をご紹介します。
1.位牌の選定
葬儀後1週間以内を目安に、故人様の信仰していた宗派を確認した上で、位牌の「種類」「形状」「サイズ」などを選定します。少しでも時間的余裕を作りたい場合は、葬儀の準備と共に位牌の手配もできる葬儀社への依頼がおすすめです。
2.文字入れ内容の決定
白木位牌に記載されている文字を基に、本位牌に刻む文字の内容、加工方法を決定します。梵字や戒名に間違いがないか、複数名でのチェックを心がけましょう。この作業も、位牌の選定と同じく葬儀後1週間以内に済ませられるのが理想です。
3.【制作側】位牌の作製・検品
依頼を受けた業者が注文内容に沿って位牌の作製と検品を行います。制作から納品までにかかる日数は平均して1~2週間ですが、加工内容やお届け先の距離などに応じて異なりますので、注文時に必ず確認しておくことが大切です。
4.納品・開眼供養の準備
納品は「店舗での受け取り」または「郵送」が選べます。受け取ったら必ず位牌の状態を確認し、問題がある場合はすぐに相談しましょう。
白木位牌から本位牌へと変える際、故人様の魂を移す「開眼(かいげん)供養」という儀式が必要です。四十九日法要の際に行われることが一般的ですので、それまでに「僧侶への依頼」「参列者への案内」などの準備を進めましょう。
手順やスケジュールに関してさらに理解を深めたい方は「位牌作成の手順や必要な情報」も併せてご覧ください。
7.位牌選びでよくある失敗と対策

位牌の選び方で失敗しないためには、どのようなポイントに気を付けたらよいのでしょうか。
こちらでは、位牌選びでよくある失敗を例に、対策をご紹介します。
実際の文字がイメージと違っていた
位牌の文字色は金色が一般的ですが、明確な決まりがあるわけではなく、地域や宗派によって青や黒、白(彫るだけで色を入れない)などが用いられることもあります。
自由に選んだ結果、「完成した位牌の文字が、位牌本体の色と調和せず違和感を覚えた」ということも起こり得るでしょう。また、「文字の書体や間隔が思っていたものと異なった」「ご先祖様の位牌と同じ業者に依頼したのに仕上がりがまったく違った」というケースもあるようです。
こうした失敗を防ぐために、必ず注文前に完成イメージを確認しましょう。可能であれば実物を見ながら決めるとより安心です。
ネットで安く買ったけど、実物は安っぽかった
ネットを使うと、安価な位牌を探しやすくなります。しかし安さを重視して購入した結果、実物の見た目が予想以上に安っぽく、後悔したという声も少なくありません。安すぎる位牌には、塗装のムラや金箔の剥がれ、文字のかすれなど、細かな仕上がりに不満が残る可能性があることを押さえておきましょう。
位牌選びは、価格だけで判断せず、品質とのバランスを見極めることが大切です。位牌には多様な種類があり、購入先によって価格帯や仕上がり、付随するサービスの内容も多岐に渡ります。時間が許す限り複数の商品を見比べ、自分や家族が納得できるものを選ぶことが、後悔のない選択につながるでしょう。
頼んだ位牌が、思ったより大きかった
購入した位牌が予想よりも大きく、仏壇に納まらなかったという失敗例もあります。特に、位牌の高さがご本尊より上回ってしまうと、宗教的な作法として問題が生じる場合があり、買い直しを検討することになるかもしれません。
位牌のサイズは「寸」で表記されますが、この「寸」は札板部分の長さであり、台座を含めた全体の高さではありません。つまり、「寸」だけを見て判断すると、実際のサイズ感とずれてしまう可能性があるのです。位牌を選ぶ際には、必ず「全長(台を含めた高さ)」を確認し、仏壇のスペースに合うかを事前にチェックすることが失敗を防ぐポイントです。
8.位牌の選び方に関するQ&A

A.位牌のデザインには性別や年齢による違いはないため、選ぶ方の好みや仏壇にまつった時のバランスで考えましょう。
細かな装飾や形の違いはあるものの、位牌は全ての方にお使いいただけるデザインとなっています。選ぶ際は「仏壇のスペースに無理なく置けるか」「すでにある位牌との調和が取れるか」「故人様の人柄や雰囲気にふさわしいか」といった視点を重視するとよいでしょう。見た目の印象や大きさを含めて、全体のバランスを考えて選ぶことが大切です。
A.3~3.5寸を目安に、実際の仏壇のサイズやスペースを測ってから決めましょう。
小さな仏壇には、3~3.5寸(約9~10.5cm)の位牌が多く選ばれますが、「寸」は札板の長さであり、台座を含んだ全体の高さではない点に注意が必要です。必ず購入前に仏壇にあるご本尊の高さや設置スペースを確認し、位牌の全長が収まるかをしっかり測っておきましょう。
A.「ご先祖様の位牌のサイズや見た目になるべく合わせる」のが一般的ですが、数が多く新たな安置が難しい場合は、ご先祖様の位牌をひとつにまとめる方法もあります。
ご先祖様の位牌が仏壇に並んでいる場合、新しい位牌はサイズやデザインをできるだけそろえるのが一般的です。そうすることで、全体の調和が取りやすくなります。
ご先祖様の位牌が多く、仏壇のスペースに限りがある場合は「繰り出し位牌」を作成する方法もあります。繰り出し位牌とは、戒名が書かれた10枚程度の札を内部に収納できる構造の位牌で、ご先祖様の位牌を一つにまとめる目的で用いられます。
繰り出し位牌を作成した場合の新しい位牌は、形やデザインを比較的自由に選んでも差し支えないでしょう。
A.基本的に自由ですが、朱色には条件があります。
位牌の文字色は金色が一般的ですが、地域や宗派によって青や黒、白(彫刻のみで着色しない)などが使われることもあります。ただし、朱色は生前に戒名を授かっていた人に使うことが通例となっているため、注意が必要です。
色の決定は、位牌本体とのバランスや、ご先祖様の位牌、地域の慣習などを参考にされるとよいでしょう。
9.選び方のポイントを押さえて納得のいく位牌を用意しよう

位牌を購入する機会はそう多くなく、種類も豊富にあるため、初めての方には難しく感じられるかもしれません。後悔のない位牌を用意するためには、位牌の選び方のポイントや、注文から納品までの流れを事前に把握しておくことが大切です。
位牌選びのお悩みは、花葬儀にお任せください。葬儀の専門家だからこそ提案できる、価値ある位牌を取りそろえております。また、通夜・葬儀、お墓、法要などをまとめてご相談いただくことで、ご遺族のご負担を大幅に軽減することが可能です。ご相談は24時間365日対応の電話、または無料の事前相談にて承っております。この機会にぜひご検討ください。




























