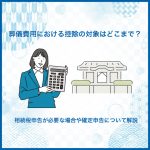葬儀費用は相続財産から払える?立て替えるべき?支払い方法の選び方や注意点
- 作成日:
- 【 相続に関わるお金 】
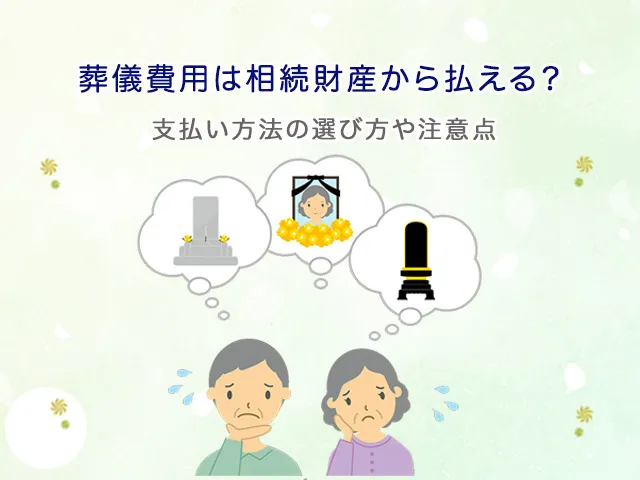
相続を開始するにあたり、「葬儀費用は相続予定の財産から払える?」と悩む方は多くいらっしゃいます。葬儀費用は相続財産からの支払い、もしくは相続人による立て替え、どちらがよいのでしょうか。
そこで今回は、葬儀費用の支払いについて、相続とからめて解説します。このコラムを読むことで基本的な考え方やよくあるトラブル、葬儀費用と控除についてなどが理解できるようになるでしょう。難解な法律用語もやさしい言葉で解説してまいりますので、ぜひ最後までお読みください。
1.まずは知っておきたい葬儀費用の基本

葬儀費用と相続財産について触れる前に、まずは葬儀費用の基本を押さえましょう。全体像を把握することで、理解がより深まります。
こちらでは「葬儀費用の相場」「故人様の葬儀費用は誰が払うのが一般的なのか」の2点を解説します。
葬儀費用の相場・内訳は?
株式会社鎌倉新書が運営する「いい葬儀」が2024年に行った調査によると、全国の葬儀費用の平均相場は118.5万円でした。内訳は以下の通りです。
【基本料金 75.7万円】
斎場利用料、火葬代、祭壇費用、棺、遺影、搬送費など、葬儀を行う上で必要になる費用
【飲食費 20.7万円】
通夜振る舞いや精進落としなど、参列者にふるまう飲食費
【返礼品費 22.0万円】
参列者に渡す会葬礼費や、香典返しにかかる費用
また、葬儀の形式別の平均費用は以下の通りでした。
| 葬儀の種類 | 葬儀費用の総額(平均) | 最も回答が多い価格帯 |
|---|---|---|
| 家族葬 | 105.7万円 | 60万円以上~80万円未満 |
| 一般葬 | 161.3万円 | 120万円以上~140万円未満 |
| 一日葬 | 87.5万円 | 20万円以上~40万円未満 |
| 直葬・火葬式 | 42.8万円 | 20万円以上~40万円未満 |
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年)
掲載:株式会社鎌倉新書 いい葬儀
URL:https://www.e-sogi.com/guide/55135/
葬儀費用はさらに地域や僧侶(宗教者)の有無、演出内容によっても大きく異なります。いずれにしても、まとまったお金が必要になることを押さえておきましょう。
葬儀費用は誰が負担するのが一般的?
葬儀費用を支払う人について法的な決まりはありませんが、葬儀を取り仕切る役目を担う「喪主」が負担するのが一般的です。喪主とは別に葬儀費用を負担する「施主」を立てた場合や、複数の相続人で分担して支払うこともあります。
2.相続財産は葬儀費用に使える?
まとまったお金がすぐに用意できないという場合もあるでしょう。そのような場合、相続する予定の財産から、故人様の葬儀費用を払うことは可能なのでしょうか?
結論から言うと、相続財産から葬儀費用を支払うことは原則可能です。ただし、相続人一人の独断で財産を使ってしまうと大きなトラブルに発展する恐れがあるため、決定は慎重に行う必要があります。
また、相続財産を「相続放棄(※1)」する場合は特に注意が必要です。法律上、相続放棄をしても社会通念上相当とされる範囲の葬儀費用を相続財産から支出することは認められています。しかし故人様の財産を安易に使ってしまうと「相続の意思がある」とみなされ、本人に相続の意思がなくても財産を全て相続しなければならなくなる恐れがあります。
なお、相続において、亡くなった方の財産や負債を無条件・無制限にすべて引き継ぐ相続方法を「単純承認」と言います。
(※1)受け継ぐ予定の財産を全て放棄すること。
3.相続財産を葬儀費用に充てる「預貯金の仮払い制度」とは

「葬儀費用は相続財産から払うことが可能」とご説明しましたが、実行するにはいくつかの手続きが必要です。
こちらでは、相続財産を葬儀費用に充てるために使える制度について、仕組みと注意点を解説します。
口座凍結後でも使える「預貯金の仮払い制度」とは
金融機関は、口座名義人が亡くなったことを確認すると、故人様の財産を守るために口座を凍結します。凍結は相続手続きが完了するまで原則解かれることはなく、その期間中に預金を引き出すことはできません。
そのような状況下において、葬儀費用を払うために活用できるのが「預貯金の仮払い制度」です。金融機関に対し手続きを行うことで、相続手続きが完了する前であっても、故人様の凍結された口座から預金を引き出すことができるようになります。ただし、引き出すことのできる金額には上限が定められています。
預貯金の仮払い制度の上限額
預貯金の仮払い制度で引き落とせる金額には上限があり、その具体的な金額は以下のいずれかのうち「金額が低い方」です。
- ・故人様が死亡した時の預貯金残高×法定相続分(※2)×3分の1
- ・150万円
複数の金融機関に口座があった場合、金融機関ごとに規定が適用されるため、結果として引き出せる金額が増えることがあります。なお、上限額を超えた預貯金を引き落としたい場合は、家庭裁判所にて「仮処分申し立て」を行う必要があります。
(※2)民法によって定められた法定相続人(相続の権利を持つ人)に割り振られた、「相続できる割合の目安」。
預貯金の仮払い制度を利用するときの注意点
預貯金の仮払い制度は、相続人全員の同意がなくても個別で手続きが可能です。しかし利用には以下の注意点があります。
【単純承認になる可能性がある】
社会的地位や身分に不相応とされる豪華な葬儀を執り行ってしまうと、財産を不当に処分したとみなされ(民法第921条)、相続放棄が認められなくなる可能性がある。
【遺言書の内容によっては制度を利用できない】
遺言書に相続人として書かれていない人は、預貯金の仮払い制度を利用することができない。
【引き出した金額は遺産分割のときに調整される】
預貯金の仮払い制度で引き出した預貯金は「すでに相続したもの」と見なされるため、後の遺産分割の際に、本来の相続分から引き出した金額を差し引くのが一般的。
【葬儀の明細は必ず保管する】
いつ、何に、いくら使ったのかが分かる明細(領収書など)を保管しておくことで、相続トラブルを避けやすくなる。
単純承認の判断や、遺産分割時の調整の有無などは、ケースバイケースです。不安がある場合は、専門家に相談されてから決めることをおすすめします。
4.葬儀費用は相続財産から払う?立て替える?それぞれを比較

ここまでで、葬儀費用はご遺族が支払うことも、故人様の口座から支払うことも可能であることがわかりました。では実際にご家族が亡くなったとき、支払い方法はどのようにして決めたらよいのでしょうか。
こちらでは、「葬儀費用を相続財産から支払う場合」「ご遺族が立て替える場合」それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。支払い方法を選ぶ際の参考になさってください。
葬儀費用を相続財産から支払う場合のメリット・デメリット
相続財産から故人様の葬儀費用を支払う最大のメリットは、ご遺族の負担が軽減されることです。誰が費用を立て替えるかで揉めるリスクを避けやすい点も挙げられるでしょう。
一方デメリットとしては、先述したように「単純承認と見なされる可能性がある」「遺言書の内容によっては故人様の財産を使うことができない」などが考えられます。また、独断で預貯金を引き出した結果、他の相続人から不当な使い込みを疑われたり、その後の遺産分割で揉めたりといったことも考えられるでしょう。
相続財産は相続人全員にとってデリケートな問題であるため、独断で判断せず、全員とよく相談した上で決定することが大切です。
葬儀費用をご遺族が立て替える場合のメリット・デメリット
預貯金の仮払い制度の利用は金融機関への申請が必要で、上限額以上の財産を引き落としたい場合は家庭裁判所で手続きを行わなくてはなりません。特に家庭裁判所からの仮処分決定までには時間がかかるため、こうした手間がないのが立て替えのメリットです。
しかし、葬儀費用は高額になることが多く、立て替えはご遺族にとって負担になります。葬儀だけでなく、故人様がお世話になっていた病院の精算や家賃といった支払いもあるため、相続人で分担して立て替える必要が出てくるかもしれません。
「故人様が死亡保険(※3)や葬儀保険に加入していなかったか」「葬儀の生前契約をしていなかったか」などを確認した上で、立て替えの割合を検討されるとよいでしょう。
(※3)受取人が指定されていれば、受取人固有の財産として認められる。ただし、非常に高額であり、相続財産に占める割合が大きい場合は、他の相続人との公平性を保つため、遺産分割で分与額を調整することがある。
5.葬儀費用と相続に関するよくあるトラブル事例と対策

葬儀費用をめぐって、親族間でトラブルに発展することは珍しくありません。
こちらでは、葬儀費用と相続に関するトラブル事例と、その対策をご紹介します。
事例①葬儀費用の負担割合が原因で相続時に揉める
葬儀費用をご遺族で立て替えることになった際、「誰が」「いくら立て替えるのか」で揉めることがあります。具体例は以下の通りです。
複数の相続人で、葬儀費用を分担して立て替えることになったが、「遺産を多くもらった人がより多く負担すべき」という主張と「遺産とは切り離して考えるべき」という主張が上がり対立した。
葬儀費用の負担割合が原因のトラブルを回避するためには、事前にきちんとした話し合いの場を設けることが重要です。特に、以下のポイントに注意して全員の合意を得るようにしましょう。
- ・相続人それぞれの所得や年齢、相続予定の財産額などを考慮して、負担割合を決める
- ・葬儀費用を負担した人だけが不利益を被ることがないよう、財産を公平に分ける
- ・決まった内容は書面などに残しておく
事例②預金を無断使用して使い込みを疑われる
相続手続きが完了するまでの財産は、相続人全員の共有財産です。そのため、事前の相談なく引き出された葬儀費用を「私欲のために使っているのではないか」と疑われてしまうケースもあります。
このようなトラブルを避けるためには、以下の対策が効果的です。
- ・葬儀費用を故人様の財産から支払うことに対し、相続人全員の了承を得ておく
- ・引き出した額を記帳しておく
- ・使った金額の明細を保管しておく
6.相続手続きの流れとスケジュール

こちらでは、相続手続きの流れとおおまかなスケジュールをご紹介します。全体の流れを把握しておくことで、葬儀費用をどこから、どのように支払うかがスムーズに決めやすくなるでしょう。
死後3カ月以内に行う手続き
故人様の死後3カ月以内に行うべき手続きは、以下の通りです。なお、手続きや調査には時間がかかるため、なるべく早いうちから取り組むことをおすすめします。
【遺言書の有無、内容確認】
遺言書の有無と内容の確認を行う。遺言書の種類によっては、家庭裁判所での手続きが別途必要。
【相続人と相続財産の調査】
故人様が遺言書を残していなかった場合、法定相続人と財産内容を把握するために、調査を行う。
【相続放棄の手続き】
相続放棄をしたい場合は、家庭裁判所に必要書類を提出。相続の開始を知った日から3カ月を過ぎた場合、相続放棄は原則認められない。
死後4カ月以内に行う手続き
故人様の死後4カ月以内に行う主な手続きは「所得税の準確定申告」です。準確定申告とは故人様の確定申告を意味します。故人様が勤めていた会社が年末調整を行ってくれる場合などでは、不要となることもあります。
申告によって、納税の義務が発生したり、還付金が受け取れたりすることがあります。なお、準確定申告の期限は「相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内」です。
死後10カ月以内に行う手続き
故人様の死後10カ月以内に行うべき手続きは、以下の通りです。
【遺産分割協議】
相続人全員で、「誰が、何を、どのくらい相続するのか」を協議すること。遺言書があり、内容に全員が納得している場合は省略されることもある。遺産分割協議で決まった内容は「遺産分割協議書」に残し、全員の署名と捺印をつける。
【相続税の申告と納税】
一定の金額を超えた財産を相続する場合は、「故人様の死亡を知った日から10カ月以内」に申告しなくてはならない。
故人様の死後に行う手続きは、相続以外も含めると数十種類にものぼります。詳しくは「死亡後に行うべき手続きの流れ」で紹介しておりますので、併せてご覧ください。
7.葬儀費用は相続税申告で控除できる?対象となる費用・ならない費用

葬儀にかかった費用の一部は、相続税の申告で控除を受けることができますが、相続財産が基礎控除額以下の場合は、もともと相続税がかかりません。そのため、控除により相続税が軽減されるのは、以下を満たしている場合(相続税がかかるとき)のみです。
注)
課税価格 :課税対象となる財産の価格
基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数
国税庁の「相続税法基本通達」では、控除の対象になる費用、ならない費用を以下のように定めています。
| 控除の対象になる費用 |
・火葬、埋葬、納骨費用 ・葬儀前後に生じた「欠かせない」費用 (斎場利用料、棺、位牌、安置、通夜、精進落としなどの飲食、会葬御礼、宗教者へのお布施、戒名、生花、葬儀を手伝ってくれた人への心づけなど) ・死亡診断書作成費用 ・ご遺体の捜索費用 ・ご遺体やご遺骨の運搬費用 |
|---|---|
| ならない費用 | ・香典返し ・参列者の交通費、宿泊費 ・墓石などの祭祀(さいし)財産の購入費 ・法事全般にかかる費用 |
相続税や控除の計算は、非常に複雑です。「葬儀費用における控除」の記事では、相続税の計算方法や葬儀費用における控除の対象までわかりやすく解説しております。ぜひご覧ください。
8.相続・葬儀費用についての相談先・窓口の選び方

相続や葬儀費用に関係する制度やルールは難解なものが多いため、不安を抱く方もいらっしゃるでしょう。
こちらでは、相続や葬儀費用についての相談先を、ケース別にご紹介します。
【悩み別】相続・葬儀費用についての相談先
「何に困っているか」によって、相談先は異なります。まずは、自分が直面している問題に合った専門家を頼りましょう。
悩み1:他の相続人と相続や葬儀費用で揉めている
相続人同士の揉め事は、その後の手続きにも大きく影響します。相続人間でトラブルが発生した場合は「弁護士」に相談しましょう。弁護士はトラブルを解決するための法律的なサポートを専門としており、相続に関して主に以下の対応が可能です。
- ・遺産分割協議に代理人として参加、交渉
- ・裁判所での調停、審判に代理人として出席
- ・相続人や財産の調査 など
悩み2:相続の手続き方法がわからない
相続の手続きに疑問がある場合は、司法書士への相談がおすすめです。法的な効力を持つ書類作成や法律上の手続きに強い司法書士は、主に以下のサポートを行ってくれます。
- ・相続人や財産の調査
- ・戸籍など、手続き上必要となる書類の取り寄せ
- ・不動産の名義変更 など
悩み3:相続税に関することがわからない
相続税については、税務のプロである税理士が頼りになります。相続において税理士ができる内容は以下の通りです。
- ・相続税の試算、申告のサポート全般
- ・節税アドバイス
相続全般の相談は花葬儀にご相談ください
お悩みごとの専門家をご紹介しましたが、複数のサポートを必要とする場合は並行して各所に相談しなくてはなりません。それだけで大きな負担に感じる方もいらっしゃるでしょう。
相続に関する様々なお悩みは、花葬儀にお任せください。花葬儀では前述した各専門家と連携しているため、一つの窓口でさまざまなお悩みや不安をまとめて解決することができます。もちろん相続だけでなく、葬儀にかかる費用について中立的な立場からサポートすることも可能です。
「相続に関する悩みはまだないけれど、相続を開始する前に知っておくべきことを把握したい」といった内容も喜んでお受けします。まずは一度、相続について自由にお話してみませんか?ぜひお気軽にご相談ください。
9.葬儀費用と相続に関するQ&A
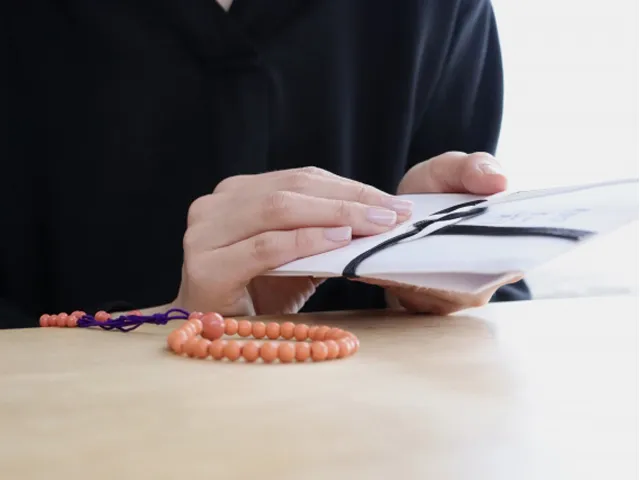
A.相続人の経済状況や相続割合、年齢などの基準を考慮することが大切です。
葬儀費用の支払いは喪主様が負担するのが通例ですが、法的な決まりはありません。喪主様や施主様、複数の相続人による折半も可能です。葬儀費用の負担について話し合う際は、以下の基準を考慮されるとよいでしょう。
- ・年収や経済状況
- ・年齢
- ・相続人内での立場
- ・遺産相続の割合 など
A.お香典は葬儀の喪主様に宛てて送られたものになるため、喪主様のものです。相続財産にはあたりません。
お悔やみの気持ちの表れであるお香典には、ご遺族の費用負担を軽減する意味合いもあります。お香典は喪主様への贈与と考えられ、相続財産ではありません。また、所得税や贈与税の課税対象外です。
いただいたお香典をどうするかは喪主様が決めることになりますが、葬儀費用の支払いに充てるのが一般的なようです。
A.請求可能かはケースバイケースですが、「請求できない」という判例が過去に出ています。
立て替えた葬儀費用を他の相続人に請求できるかは、それぞれの背景や事情によって異なります。例えば、最初に折半することに同意した相続人が後から支払いを拒否した場合、同意したことを証明できる文書があれば請求が通りやすくなるでしょう。
一方で、喪主を務め費用を立て替えた相続人が親族に対して起こした裁判では、「喪主が負担するのが相当」という判決が出ています。
請求できるかはケースバイケースであるため、詳しくは専門家に相談されることをおすすめします。
10.相続財産から葬儀費用を払うことは可能|支払い方法はよく相談を

葬儀にかかる費用は、故人様の財産から支払うことができます。ただし、相続トラブルを避けるためにも、他の相続人の同意を得ておくことが重要です。葬儀費用の支払い方法も同様に、相続人でよく話し合って決めましょう。
相続ならび葬儀費用に関するお悩みは、花葬儀までお寄せください。ご相談には、花葬儀のメンバーシップクラブ「リベントファミリー」へのご加入がおすすめです。葬儀費用の割引、枕花のプレゼントなどお得な特典も豊富です。ぜひこの機会にご検討ください。