オンライン法要の進め方|メリット・デメリットからポイント・マナーまで解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
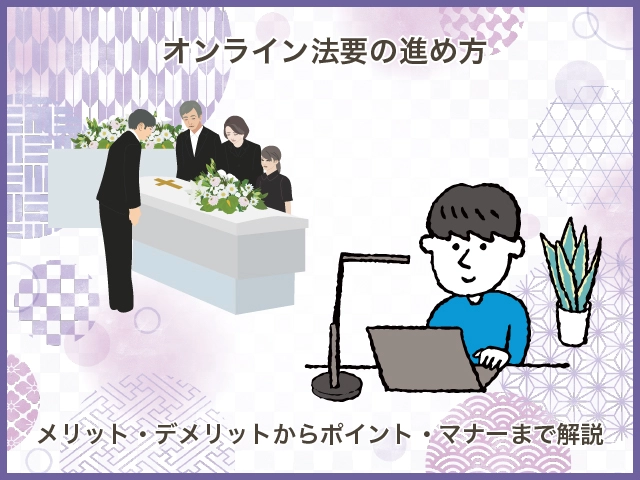
「オンライン法要」という言葉を聞いたことはあるでしょうか?場所を選ばずに参列できる方法として注目された、比較的新しい供養のかたちです。しかし、まだ一般的とはいえない面もあり、不慣れな形式に戸惑う方や、故人様への思いがきちんと届くのか不安を抱く方も少なくありません。
そこで今回は、オンライン法要の基本と進め方をご紹介します。メリット、デメリットの他、オンライン法要を進める上の注意点などをわかりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
1.オンライン法要の基礎知識

まずはオンライン法要の基本的な概要や、オンライン法要に対する寺院の考え方をご紹介します。
自宅から参加できる「オンライン法要」
オンライン法要とは、オンライン上で参列する法要のことです。Zoomや葬儀社が提供する専用ツールを通じて、参列者は自宅などから僧侶の読経やお焼香の様子をリアルタイムで見守ることができます。
すべての参列者がオンラインで参加するだけでなく、一部の参列者のみがオンラインで参加する形式も見られます。なお近年では、法要だけでなく、葬儀そのものをオンライン上で行うことあります。
オンライン法要が登場した背景
オンライン法要が広まり始めたきっかけは、2020年ごろに起こった新型コロナウイルス感染症の流行です。感染予防の観点から、非対面での手段が急速に普及していく中、安心して供養を行える方法としてオンライン形式が注目されるようになりました。
オンライン法要の需要は当時に比べて落ち着いてきたものの、現在も必要に応じて活用されています。
僧侶・寺院の対応と意見
オンライン法要を検討する際、気になるのが僧侶や寺院の反応です。ネットを通じて参列することに対し、どのような意見を持っているのでしょうか。
実は新型コロナウイルス感染症が落ち着いた現在でも、引き続きオンライン法要を取り入れている寺院はあります。「本来は対面が望ましい」という考えを持ちつつも、遠方や体調不良などやむを得ない事情がある場合の手段として、認める傾向が強いようです。
しかしオンライン法要を導入している寺院でも、進行方法やマナー、配信の対応はさまざまです。また、浄土真宗や曹洞宗など、宗派によっても運用に対する考えは異なります。具体的な対応や意見は、お世話になる予定の寺院に確認することをおすすめします。
2.オンライン法要のメリット
対面ではなく、オンラインで法要に参列することにどのようなメリットがあるのでしょうか。
こちらで詳しくご紹介します。
場所や体調に左右されない
オンライン法要の大きな魅力は、場所や体調の制約を受けずに参加できる点です。特別な会場を用意する必要がなく、ご自宅など安心できる環境から参列できます。
外出が難しい方や体調に不安のある方はもちろん、海外を含む遠方にお住まいのご親族とも供養のひとときを共有できるでしょう。「無理のない形で故人様をしのぶ方法」として、多くの方にとって心強い選択肢となっています。
感染症リスクを回避できる
多くの人が集まる場である葬儀や法要は感染リスクが高まりやすく、とくに高齢者や妊娠中の方にとっては重症化の不安もあります。その点、オンライン法要であれば非対面での参列が可能なため、インフルエンザなどの感染症が流行している時期でも、安心して参加することができます。
健康不安を解消して故人様をしのべる点も、オンライン形式ならではの大きなメリットです。
移動や準備の負担軽減につながる
法要の会場から離れた場所に住んでいる方にとっては、長距離の移動が大きな負担になることも少なくありません。オンライン法要にすることで、そのような負担を減らすことができるでしょう。
さらに、オンライン法要では会食を行わない形式が一般的であるため、施主様の準備にかかる手間も抑えられます。
3.オンライン法要のデメリット・注意点
一方で、オンライン法要には以下のようなデメリットもあります。
機器や通信環境が必須
オンライン法要に参加するには、安定したインターネット環境と端末(パソコンやスマートフォン、タブレットなど)が必要です。これらが整っていない場合は、新たに準備するか、現地での参列を検討することになります。
さらに、きちんと準備したつもりでも、通信トラブルや回線の不具合が生じると、法要の映像配信が中断されることがあります。こうしたオンライン特有のリスクについて、あらかじめ理解しておくことも大切です。
厳粛さ・一体感を感じにくい
オンライン法要では、実際の場に漂う線香の匂いや静かな空気、参列者同士の表情や気持ちのやりとりといった雰囲気を味わいにくい面があります。厳かな空気や連帯感を感じられなかった結果、法要という区切りの機会であっても「心の整理がつかない」ということになるかもしれません。
こうしたリスクを回避するためには、儀式らしい緊張感を共有できるよう施主様が進行を丁寧に段取りしたり、各自が線香を焚いたりするなどの工夫が求められます。
オンラインならではの準備が必要
オンライン法要に参加するには、ネット環境の整備や端末の操作が必要です。機器や操作に不慣れな方にとっては、参加までの準備が大きな負担になることもあるでしょう。
施主様には、参列者が安心して参加できるよう、接続方法などを丁寧に説明する配慮が求められます。場合によってはサポートや同席が必要になることもあるため、事前に手順をしっかり把握しておくことも重要です。
4.オンライン法要の流れ・やり方
オンライン法要と従来の法要では、内容に大きく違うところはあるのでしょうか。
こちらでは、オンライン法要の一般的な流れや内容について、詳しく解説します。
1.相談・申込み
まずは、オンライン法要を導入している葬儀社や寺院などを探して、法要の相談を行います。相見積もりを取ると、費用・サービス面で納得のいくものを選びやすくなるのでおすすめです。
前述したように、オンライン法要の内容やルールは寺院、または宗派ごとに異なります。契約を結ぶ前に、必ず確認しておきましょう。
2.事前打ち合わせ
オンライン法要の内容について打ち合わせを行います。具体的には主に以下の通りです。
・日程
・配信方法
・参列者の人数
・僧侶の手配
・通信テストの有無
・精算方法
・受付、お焼香、お香典の扱いについて など
3.お布施(サービス料)の納金
法要で読経をしていただく僧侶にはお布施を、運営をサポートしてくれる葬儀社にはサービス料を納めます。通常の法要の場合は、当日にお布施をお渡しするのが一般的ですが、オンライン法要では、事前に銀行振り込みや現金書留などでお渡しすることもあります。
納金については寺院・葬儀社側から案内がありますので、それぞれの案内に従って納めるようにしましょう。
4.招待URL発行・通信テスト
故人様やご家族のプライバシーを守り、無関係な方の参列を防ぐための対策として、オンライン法要では参列者に招待用のURLやパスワードが発行されます。また、当日はスムーズに進行できるよう、事前に通信テストを行うこともあります。
5.参列者へ案内
参列者に向けて案内を行います。オンライン法要に明るくない参列者が困惑しないよう、以下の内容を必ず伝えましょう。
・日程
・オンライン法要であるということ
・法要への参列方法(必要機器や環境の説明)
・URL、パスワードの配布
・お香典の扱いについて
・服装について
6.法要当日
オンライン法要は、一般的な法要とほぼ同じ流れで進行します。具体的には以下の通りです。
1.指定された時間に、参列者が招待URLを使ってアクセスする
2.法要会場の配信が開始し、僧侶が登場
3.施主様による挨拶
4.僧侶による読経、焼香
5.僧侶による法話
6.喪主様による挨拶
7.終了
オンラインで参列している方は、手を合わせながら故人様をしのびます。寺院や葬儀社によっては、オンライン上でできる「焼香システム」を設けておりますので、案内に従って行いましょう。
一般的な法要では、法要後に会食の席を設けますが、オンライン法要は省略されるケースがほとんどです。法要が終了次第接続を解除して、解散となります。
「四十九日法要における喪主の挨拶」の記事に、挨拶のタイミングや例文が載っておりますので、ぜひ参考になさってください。
5.オンライン法要を滞りなく進めるための事前準備
オンライン法要をスムーズに進めるためには、喪主様、参列者それぞれにきちんとした準備が必要です。
こちらでは、オンライン法要で失敗しないための事前準備について詳しくご紹介します。
ネット環境とデバイスの確認
オンライン法要のためには、「動画を閲覧できるデバイス(端末)」と「安定したインターネット環境」が欠かせません。必要なものがそろっているかを確認し、当日に慌てないよう、事前に接続方法を試しておきましょう。
施主様は参列者の状況を確認し、不足している方には貸し出しを検討したり、他の参列者と一緒に参列してもらったりなどの対応を行います。「接続の方法がわからない」といった方には、丁寧なサポートも必要です。
また、施主様が直接法要会場から配信を行う場合は、中継ができるような端末やスタンドなどが別途必要になります。貸し出しを行っている葬儀社や寺院もありますが、費用が発生するかはケースバイケースですので、必ず事前に確認しておきましょう。
静かで落ち着いた場所の確保
オンライン法要は好きな場所で参列できるメリットがあるとはいえ、法要の厳粛な雰囲気を壊すような環境からの参加は、控えるのがマナーです。静かで落ち着いた場所の確保をするために、以下を心がけておきましょう。
・基本的に法要中のマイクはオフにしておく
・法要にふさわしくないものが映らないよう、背景を確認しておく
・参列者以外の人に配信を見られる可能性が高い、公共施設や飲食店での参列は控える
経本やお線香・お焼香などの準備
オンライン法要での経本やお焼香などは、寺院や葬儀社によってさまざまです。法要中に利用できるよう、オンラインで配布、またはアプリを提供しているところもあれば、自身で用意するよう案内が来ることもあります。それぞれの方針に従って準備しましょう。
オンライン法要に初めて参加する方は、何を用意すればよいのか不安になりやすいため、喪主様が必要な情報を確認し、丁寧な説明を心がけます。対面式の法要と違い、当日はトラブルへの迅速な対応が難しくなるため、事前の備えはしっかりと行いましょう。
参列時の服装・身だしなみの心構え
オンライン法要に参列する際の服装は、通常の法要と同等であると丁寧です。特に四十九日や一周忌といった大きな節目にあたる法要では、礼を尽くした装いを心がけましょう。男女それぞれの身だしなみは以下を参考になさってください。
【男性】
・黒やダークグレー、濃紺などの色で、かつ無地のダークスーツ
・白無地のシャツ
・黒無地で光沢のないネクタイ、靴
【女性】
・黒やダークグレー、濃紺などの色で、落ち着いたデザインのスーツやワンピース
・20デニール程度の黒のストッキング
・黒無地で光沢のない靴
「法事・法要の服装マナー」の記事では、さらに詳しくご覧いただけます。「礼を尽くした装い」とご説明しましたが、けがや体調不良などで礼服の着用が難しい方は、無理をせず普段着でも構いません。不安がある場合は、事前に僧侶や葬儀社に相談し、ご親族と服装の方針を共有しておくことで、安心して参列できるでしょう。
6.【参列者向け】オンライン法要に参列するときのマナー
こちらでは、参列者向けのオンライン法要のマナーをご紹介します。オンライン法要に参列することになった場合、どのようなマナーに気を付けたらよいのでしょうか。
お香典の渡し方
施主様から辞退の案内がない限り、オンライン法要に参列する人もお香典を用意するのがマナーです。施主様に直接会っての手渡しが難しい場合は現金書留を利用しましょう。お手紙も添えるとより丁寧です。
金額については、以下にご紹介する一周忌のお香典の相場を参考に、ご家族で話し合ってご用意ください。
| 故人様との関係 | 相場 |
|---|---|
| 子・親 | 3~10万円 |
| 兄弟姉妹 | 1~5万円 |
| 祖父母・孫 | 〃 |
| 叔父・叔母・甥・姪 | 1~3万円 |
供花・お供え物の手配
お香典と同様、施主様から辞退の案内がない限りは、供花やお供え物を手配することができます。送る際のマナーは以下の通りです。
・花の種類は相手の宗教宗派の考えを尊重する
(例:神道では白い花、創価学会では樒(しきみ)を大切にしている)
・お供え物には弔事用の掛け紙を使う
・受け取り側の負担にならないようなタイミングに送る
・生ものや壊れやすいものなどは送らない
詳しくは「お供物料とお供え物」の記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。
その他のマナー
対面式、オンラインに関わらず、法要で心がける姿勢は同じです。法要中の飲食、通話、不用意な離席はマナー違反ですので注意しましょう。やむを得ず離席する場合は、カメラをオフにするなど周囲への配慮を忘れず、可能な限り早めに戻ります。大切な供養の場であることを意識し、緊張感を持って、静かに落ち着いた態度で参列しましょう。
7.オンライン法要に関するQ&A
A.失礼とはなりませんのでご安心ください。大切なのは「方法」ではなく「気持ち」です。
オンライン法要は手軽に参列できるぶん、どこか不誠実さを感じてしまうという方がいらっしゃるかもしれません。しかし、オンラインでの法要であっても、故人様やご先祖様にとって失礼とはならないのでどうぞご安心ください。
大切なのは「どこで行うか」ではなく、「どのような気持ちで参列するか」です。心を込めて手を合わせれば、故人様を思う気持ちは十分伝わるでしょう。
A.サポートできる体制が整っていれば十分可能です。
オンライン法要への参列が心配な方には「ご家族や身近な人が事前に使い方を教える」「当日一緒に参列する」などの方法があります。このようなサポートがあれば、機器の操作に自信がない人でも、安心して参加できるでしょう。
ただし「操作に詳しい人が誰もいない」「同席しての参列が難しい」といった場合は、オンライン法要ではなく、法要の会場に行って供養するほうが適切かもしれません。オンライン法要に対応している葬儀社や寺院にも相談しながら決めるとよいでしょう。
A.対面でのお渡しよりも、現金書留やキャッシュレス決済などが多いようです。
法要で読経をしていただく僧侶へのお布施は、法要当日、もしくは後日寺院を訪問してのお渡しがほとんどです。しかしオンライン法要では、離れた場所でも法要に参列できるという利点を活かし、「現金書留」「銀行振り込み」「オンライン決済(クレジットカードなど)」でお布施をお渡しするケースが多いようです。
お布施の渡し方はそれぞれの寺院ごとに異なりますので、指定された方法の中から選ぶとよいでしょう。お布施の金額の目安や包み方について悩まれる方は、「法要のお布施」の記事を参考になさってください。
A.会食は省略することが多いようです。
一般的な法要では終了後に会食の席を設ける傾向にありますが、遠方にいらっしゃる方でも参列できるオンライン法要では、省略されることがほとんどです。
希望される場合は、葬儀社や寺院側が用意したものとは別の「会食をするためのURL」を設け、オンライン上でつながりながら食事をいただく方法があります。ご自身で専用の場所を用意する必要がありますが、故人様の思い出を共有しながらお食事をするのも供養のひとつですので、一度検討されてみてはいかがでしょうか。
8.しっかりとした準備で心にあたたかく残るオンライン法要を
場所や体調に左右されず参列できるのがオンライン法要の強みですが、中には「きちんとした供養になっているのか」と悩まれる方もいらっしゃいます。大切なのは、方法ではなく故人様を想う気持ちです。そのためにも事前準備はきちんと行い、心に残るあたたかな法要を執り行いましょう。
弊社花葬儀でも、オンライン法要のお手伝いや、オンライン法要に対応した僧侶のご紹介を承っております。無料の事前相談では、法要全般に関するお悩みのご相談が可能です。この機会に「どのような供養が最適か」を一度じっくりお話ししてみませんか?ぜひご検討ください。




























