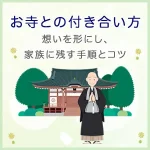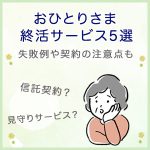終活でペットの将来を考えよう~大切な家族の生涯のために、今からできること~
- 作成日:
- 【 終活の基礎知識 】

終活に取り組む際は、大切なペットのことも忘れてはいけません。いざという時のために備えておくことで、より充実した時間を過ごすことができるようになるでしょう。
今回のコラムでは、ペットの終活について、備え方やポイントをわかりやすく解説します。この機会に「大切な家族のために何ができるのか」を考えてみませんか?ぜひ最後までお付き合いください。
1.ペットのための終活とは?

「終活」とは財産、医療、介護、葬儀、お墓など、人生の最後に向けた活動の総称です。
では「ペットのために行う終活」とは具体的にどのような内容を指すのでしょうか。
こちらで解説します。
ペットの終活が大切な理由
そもそもなぜペットの終活が必要なのでしょうか。その答えは少し先の未来を具体的に想像することで、自然と見えてきます。
【もしも飼い主が先に亡くなったら】
- ・ペットの世話は誰に見てもらえばいい?
- ・ペットの世話をしてもらうために必要なお金はどれくらい用意したらいい?
- ・ペットに関する希望を、自分の代わりに実現してもらえる方法や制度はある?
【もしもペットに死期が訪れたら】
- ・どのような看取りをするのがベスト?
- ・治療法や治療費は?
- ・葬儀やお墓はどのように準備すればいい?
飼い主自身の終活と併せてペットの終活を進めることで、将来への不安を幅広くカバーし、より安心した日々を過ごせるようになります。これが、ペットの終活が大切とされる理由です。
ペットの終活で準備する主な項目
ペットの終活は「飼い主の老後や死後に備えた活動」と「ペットの老後や死後に備えた活動」の二つに大きく分けることができます。ペットの終活で準備する主な項目は以下の通りです。
【飼い主の老後や死後に備えた活動の一例】
- ・財産整理をし、財産の分け方を考える
- ・ペットに関する情報や希望をまとめる
- ・世話ができなくなった時のペットの預け先を確保する
- ・ペットを守るための制度やサービスの把握、または契約をする
【ペットの老後や死後に備えた活動の一例】
- ・ペットの老後~死亡までに必要な事柄や費用を調べる
- ・ペットの看取りから葬儀・埋葬までの流れを把握する
- ・ペットの容体が悪化した際の方針を、ご家族と話し合う
2.飼い主がペットの終活を始めるタイミング

終活を始める時期に決まりはありませんが、何かあってからでは必要な準備が間に合わないこともあるでしょう。
こちらでは、ペットの終活を始めるタイミングをご紹介します。
ペットの年齢や健康状態から考える
ひとつめのタイミングは、ペットの年齢や健康状態に変化を感じた時です。例えば「ペットが高齢にさしかかってきた」「以前のような元気がなくなってきた」「ペットの健康面で気がかりな点が出てきた」といった場面が挙げられます。容体の急変は予測できないため、急な事態にも対応してくれる相談先を調べておくと安心です。
飼い主自身の変化をきっかけにする
自分の体調や将来について不安を感じた時も、ペットの終活を考え始めるよいタイミングです。例えば「体力や記憶力の衰えを自覚した」「健康診断の結果がよくなかった」「生活資金への不安を感じた」などが挙げられます。
こうしたきっかけからペットを含めた終活に取り組む人は増えており、元気なうちから準備を進めておくことで、心のゆとりにもつながるでしょう。
3.もしもの時、ペットを託せる預け先・後見人の準備

「終活を始めるのは、元気なうちから」とお伝えしましたが、万が一の時に備えて、ペットの預け先をあらかじめ確保しておくことは非常に重要です。ペットがこれまで通り安心して暮らすためには、信頼できる相手に託す必要がありますが、すぐに見つかるとは限りません。
こちらでは、飼い主が世話を続けられなくなった時の、ペットの預け先の候補をご紹介します。
飼い主が怪我や病気で世話が難しい時の預け先
飼い主が怪我や病気などで入院、または通常通りの世話ができなくなった時、一時的な預け先としては以下が考えられます。
- ・ご家族
- ・近所の方
- ・友人
- ・ペットショップ(宿泊)
ペットを一時的に他の人に預ける場合は、必ず事前に了承を得ておきましょう。急なお願いでは相手も困ってしまいますし、引き受ける際にも相応の準備が必要になるためです。
また、環境が変わるとペットが不安を感じやすいため、普段の生活リズムや食事の量、持病の有無や体調のサイン、好きなおもちゃなど、細かな情報を伝えておきましょう。ペットにも預かる側にも、安心を与える大切な配慮が大切です。
飼い主の老後・死後の預け先
飼い主が完全にお世話ができなくなった時の預け先としては以下が考えられます。
- ・ご家族
- ・近所の方、友人を含め引き取りたいと思ってくれる方
- ・動物愛護団体やNPO団体
- ・老犬・老猫ホーム
数は限られますが、ペットと一緒に入所できる介護施設も存在します。ペットを人に預けることに不安を感じる方は、そのような施設の利用も選択肢のひとつです。
一方で、引き取り先が見つからない場合、ペットは保健所に送られ、最終的に処分される可能性が高まります。そうならないためにも、飼い主が責任を持ってペットが最後まで穏やかに過ごせる場所を用意しておきましょう。
4.ペットを守る法的な契約・制度

いざという時にペットを守ることができる法的な契約や制度があることをご存じでしょうか?賢く利用することで、より強固な安心が築けるようになるかもしれません。こちらで詳しくご紹介します。
ペット信託
「信託」とは、財産を始めとする自分の大切なものを、信頼できる他の人に託すことです。そのうちの「ペット信託」では、飼い主の財産を第三者に託し、その財産でペットの面倒をみてもらう仕組みを指します。ペット信託が結べる相手とそれぞれの概要は以下の通りです。
【ご家族】
- ・飼い主に代わってご家族が財産の管理・運用、ペットの面倒を見る
【銀行・保険会社】
- ・まとまったお金(信託財産)を銀行に預け、飼い主の死後、あらかじめ選任していたペットの預け先に銀行が財産を支払う(金銭信託型)
- ・会社の商品である生命保険に加入することで、金銭信託よりも低い金額でペットの信託が行える(生命保険型)
- ・「飼い主が飼えなくなった場合のペットの保護」「ペットに関する遺言書の作成、保管、執行サポート」などのサービスが会社ごとにある
【NPO団体】
- ・里親探し、保護施設の用意や、看取りなどを行ってもらえる
遺言
「信託ではなく、ペットに自分の財産を相続させたい」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、民法上相続権を持つのは「人」に限られるため、ペットへの相続はできません。遺言を使い、ペットのために自分の財産を使う方法としては「負担付遺贈」が考えられます。
「負担付遺贈」とは、なんらかの義務を負担させることを条件に、相続人に財産を残すことです。この場合、指定された相続人は、ペットの飼育の義務を負うことになります。ただし、負担付遺贈を検討する際は、以下の点に注意が必要です。
- ・遺言書に不備があると、内容が無効になることがある
- ・指定された相続人が財産の受け取りを拒否(相続放棄)した場合、ペットの処遇も白紙になる
- ・ペットの世話を条件に現金や不動産などの財産を渡した場合、その財産部分には相続税が課される
トラブルを避けるためにも、ペットの世話を任せたい相続人にはあらかじめ相談し、合意を得ておくことが大切です。遺言書の作成や詳細について詳しく知りたい方は「遺言書の作成方法」の記事をご覧ください。
任意後見契約
加齢によって飼い主の判断力が低下したり、認知症になったりした場合に備えて、任意の相手に支援内容を依頼し、契約することができます。これを「任意後見契約」と言います。
任意後見契約の詳細は以下の通りです。
【依頼できること一例】
- ・財産の管理、税金などの支払い
- ・相続が発生した時の話し合いなど、本人が本来行う予定であった法律行為
- ・入院、入所手続き
- ・各所申請手続き など
ペットの世話は、別途「準委任契約」を結ぶことで依頼することができます。
【任意後見人になれる人】
- ・成人で、かつ民法上ふさわしいと判断された人(家族や知人など)
- ・弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家
【契約が履行されるタイミング】
- ・任意後見契約を結んだ人(飼い主)の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人
(任意後見人が正しく契約を履行できるか監督する人)を選任した時
任意後見契約の進め方など具体的な方法は、厚生労働省による案内も参考になさってください。
厚生労働省「任意後見制度とは(手続きの流れ、費用)」
https://guardianship.mhlw.go.jp/personal/type/optional_guardianship/
死後事務委任契約
前述した任意後見契約が有効なのは、契約者(飼い主)が生きている間のみです。自身の死亡後に必要となる諸手続きについては、「死後事務委任契約」を結ぶことで解決できます。死後事務委任契約の概要は以下の通りです。
【依頼できること一例】
- ・葬儀、埋葬に関する手続き
- ・行政手続き
- ・契約やお金に関する手続き
- ・医療費や介護施設への精算
- ・遺品整理
- ・ペットの世話
【死後事務委任契約を結べる相手】
- ・成人済みで信頼できるご家族、友人、知人
- ・弁護士、司法書士
- ・社会福祉協議会
- ・民間企業 など
自身の終活とペットの終活、さらに生前と死後と分けて契約するのは大きな負担です。飼い主自身の終活も含めて、ワンストップで相談できる窓口を設けているところもありますので、積極的に相談してみるとよいでしょう。
5.知っておきたい、ペットの看取りから見送りまでの準備

前述した任意後見契約や死後事務委任契約は、「飼い主が飼えなくなった時」に関するものです。そのため、それとは別にペットが病気または死亡したケースについても備えなくてはなりません。
こちらでは、ペットの看取りから見送りまでの流れと、今からできる備えについてご紹介します。
ペットの最期に向き合う準備
「ペットが元気なうちから最期のことを考えるのはつらい」と感じる方も多いでしょう。しかし、あらかじめ意思を固めておくことで、いざ重い病気や介護が必要になった時、すぐに適切な対応がとれるようになります。
迷わず行動できることが、ペットの苦しみを和らげる助けになることもありますし、飼い主自身が「もっとこうすればよかった」と悔やむ気持ちを減らすことにもつながります。
いつか必ず訪れるペットの最期への備えとして、以下のうち、できることから取り組んでみましょう。
- 1.写真や動画など、ペットとの思い出を残す
- 2.ペットの医療、介護に関する方針をご家族内で話し合う
・介護が必要になった時の役割分担
・看取る場所
・治療方針、安楽死の是非 など
- 3.治療、看取り、葬儀にそれぞれかかる費用を調べる
- 4.葬儀、埋葬の方法を決める
- 5.ペットロスについて知る
葬儀・火葬の主な種類
ペットの葬儀、火葬の基本的な種類についてご紹介します。
ペットの葬儀
ペットの葬儀の内容に決まりはありません。愛するペットとの思い出を振り返り、あたたかく見送れるような演出を自由に考えることができるのが特徴です。そのため、納得のいく葬儀は信頼できる葬儀社に依頼できるかどうかがカギとなります。
以下を参考に、相見積もりや事前相談で複数社を比較しながら決めるとよいでしょう。
【納得のいくペット葬を執り行うために|葬儀社選びのポイント】
- ・スタッフの対応や雰囲気に問題はないか(自分たちの想いを親身に受け止めようとしてくれているか)
- ・見積もりは明瞭であるか、また疑問点は丁寧に答えてくれるか
- ・自宅でゆっくりお別れしたい方向けの「自宅葬」、思い出と愛情を込めた「花の演出」など、多様なプランを提案してくれるか
ペットの火葬
ペットの火葬方法は「合同火葬」「個別火葬」「特別火葬」に大きく分けられ、それぞれ以下の特徴があります。
【合同火葬】
- ・他の家のペットと共に火葬し、共同墓地に埋葬する方法
【個別火葬】
- ・個別に火葬する方法。葬儀スタッフに火葬から収骨までを一任し、飼い主は立ち会わない
- ・「個別一任火葬」と、立ち会う「個別立会火葬」がある
【特別火葬】
- ・飼い主の希望に沿う形で自由にお見送りした後、火葬をする方法
- ・通夜や特別な祭壇の設置、読経、花の演出など、オーダーメイドで特別なセレモニーや演出ができる
ペットの葬儀、火葬について詳しくは「ペット葬とは?」の記事も併せてご覧ください。
供養の方法
日本の法律では土葬が制限されていますが、ペットはその限りではないため、自宅の敷地内にペットを埋葬することは問題ありません。しかし周辺環境への配慮などから、火葬を選択する方も多くいらっしゃいます。
火葬後のペットのご遺骨の供養方法としては、以下が挙げられます。どの供養方法が最も良いかは、ご家族でよく話し合って決めましょう。
【埋葬】
ペット納骨堂や、ペット霊園など
【散骨】
粉末状にしたご遺骨を、自宅の敷地、条例で禁じられていない海や山などの自然にまく
【手元供養】
ご遺骨の一部または全てを、自宅に保管して供養する
- ・骨壺に納める
- ・遺骨アクセサリーに納めて身に着ける
- ・ペットの爪や毛、骨などを使ってジュエリーを作る など
6.ペットの終活にかかる費用、安心の備え方
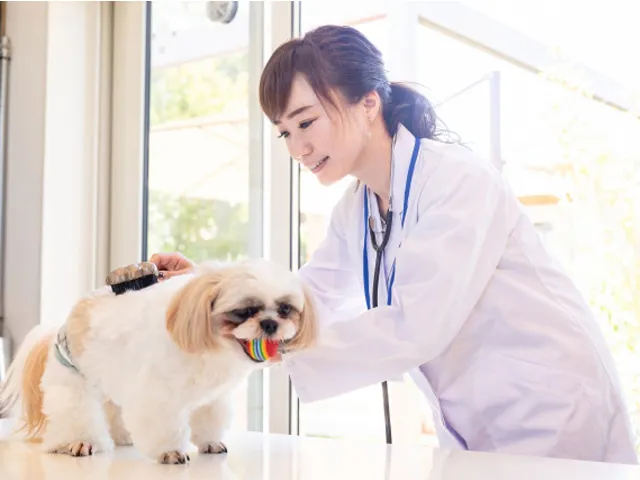
ペットの終活で後悔しないためには、必要な費用を把握し、用意しておくことも大切です。そうすることで、ペットのためのよりよい選択ができるようになります。
ペットの終活にかかる費用と備え方についてご紹介します。
ペットとの暮らしにかかる費用
一般社団法人ペットフード協会が2024年に実施した調査によると、犬1頭の飼育にかかる生涯費用の平均は271万1875円、猫1匹は160万6097円でした。
飼育にかかる費用の内訳と、種類別に見る年間飼育費用の目安は以下の通りです。
【犬、猫共通して飼育にかかる費用】
- ・食事(おやつも含む)
- ・医療費(ワクチン、治療費、手術費など)
- ・トリミングなどのケア
- ・保険
- ・おもちゃや衣類などの雑貨
| 種類 | 体格や飼育状況 | 年間平均額 |
|---|---|---|
| 犬 | ||
| 超小型 | 約16~20万円 | |
| 小型 | 約15~20万円 | |
| 中・大型 | 約17~21万円 | |
| 猫 | ||
| 外に出たことがある | 約7~15万円 | |
| 外に出たことがない | 約8~15万円 |
出典:一般社団法人ペットフード協会「令和6年(2024年)全国犬猫飼育実体調査」
https://petfood.or.jp/data-chart/
ペットの終活にかかる費用
ペットの加齢による衰えや病気で必要になる費用は、主に以下の通りです。
【介護費:年間約5万円~数十万円】
オムツやスロープなどの介護用品/介護用食事/老犬・老猫ホーム/ペットシッター など
【医療費:年間約10万円~】
治療/定期健診/リハビリ/薬/終末期医療(場合によっては安楽死) など
【その他:年間数万円~数十万円】
通院などにかかる交通費/飼い主自身に何かあった時のペットホテル利用費 など
葬儀・火葬・供養にかかる費用
大切なペットが亡くなった時にかかる費用とその相場をご紹介します。
葬儀・火葬にかかる費用
火葬別、動物別に見る、葬儀から火葬までにかかる費用は以下の通りです。
【小動物/小鳥・ハムスターなど】
- ・合同火葬:6千円~8千円
- ・個別火葬:1万円~2万円
- ・特別火葬:2万円~3.5万円
【猫やウサギ/5㎏まで】
- ・合同火葬:1.2万円
- ・個別火葬:2.5万円~3万円
- ・特別火葬:3.5万円~
【犬/15㎏まで】
- ・合同火葬:2.2万円
- ・個別火葬:3.5万円
- ・特別火葬:4万円~
供養にかかる費用
それぞれの供養にかかる費用は以下の通りです。
- ・納骨堂:1万円~数十万円(年間)
- ・合祀(ごうし)墓:1万円~1.5万円
- ・個別墓:10万円~60万円
- ・個別共同墓:30万円~40万円
- ・散骨:数千円(粉骨代)
- ・手元供養:数千円~数十万円(骨壺やジュエリー代のみ)
費用はあくまでも目安であり、葬儀やお墓の種類によって金額は変わります。
ペットの終活に向けた備え
このように、ペットの暮らしと終活には大きなお金が必要になります。しかしペットには人間のような公的な健康保険制度や介護制度はありません。
そこで活用したいのが「ペット保険」です。ペット保険とは、ペットが病気や怪我をした時に、治療費や通院費、手術代などを一部補償してくれる保険を指します。早いうちから加入することで、自己負担額を大きく減らすことができるでしょう。
また、ペット葬の備えとして、葬儀の生前契約を結ぶことも有効です。生前契約には「冷静なうちに納得できる形を選ぶことができる」「突然の出費や混乱を避けることができる」といったメリットがあります。不安が軽減されることで、残されたペットとの時間を穏やかに過ごすゆとりも生まれるでしょう。
7.ペットのためにエンディングノートに情報を残そう

終活では「エンディングノート」を活用しましょう。エンディングノートとは、医療や財産などに関する希望、第三者に知っておいてほしい情報を自由にまとめるためのツールです。
こちらでは、エンディングノートに残しておきたい「ペットの情報」について、その必要性と書くべき内容をご紹介します。
エンディングノートがペットを守る手助けになる
エンディングノートには、ペットの性格や日常の習慣、健康状態、希望する預け先なども記すことが可能です。飼い主に万が一のことがあっても、情報がしっかり残されていれば周囲も迷わず対応することができるでしょう。ペットが安心して暮らし続けるためにも、エンディングノートで情報や希望を残し、共有することが最も大切です。
書いておきたいペットの情報
エンディングノートにまとめておきたいペットの情報は、以下の通りです。
【ペットに関する基本情報】
- ・ペットの名前、犬種、性別、誕生日、体重 など
- ・既往歴や現在かかっている病気
- ・服薬情報
- ・アレルギーの有無
- ・去勢または避妊手術の有無
- ・飼い主の名前
- ・ワクチンの接種状況
- ・マイクロチップの有無
【その他情報】
- ・(加入している場合)ペット保険やペット信託の内容
- ・ペットのくせや落ち着いて過ごせる環境の整え方
- ・任意後見契約や死後事務委任契約の有無(ペットに関して何を依頼しているか)
【ペットに関する希望】
- ・医療、介護に関する希望
- ・葬儀、埋葬に関する希望
- ・飼い主がいなくなった後、ペットにどのように接してほしいか など
エンディングノートは自由に書き込めるのが特徴ですが、法的効力がない点に注意が必要です。詳しくは「エンディングノートの書き方」で解説しておりますので、そちらもご覧ください。
8.ペットのための終活に関するQ&A

A.事前に決めていた預け先のもとに引き取られますが、引き取り先がない場合は保健所に行くことになります。
飼い主が急死した場合、ペットは事前に契約していた「ペット信託」や「死後事務委任契約」などの決まりに基づいて第三者に託されます。
飼い主のご遺族が引き継ぐこともありますが、何の準備もなく、ご遺族も受け入れを拒否した場合、ペットは保健所に送られます。新たな飼い主が見つからなければ、最悪の場合殺処分となってしまうかもしれません。そうした事態を避けるためにも、元気なうちからペットの将来に備えておくことが重要です。
A.だれでもペットロスになる可能性はあることを受け入れ、悲しみから抜け出す方法を知ることで備えることができます。
ペットロスとは、愛するペットとの別れによって心や体に不調が生じる状態を指します。程度の差はあれ、多くの人が経験するごく自然な反応です。
この不安への対策としてまず大切なのは、「ペットロスは、だれにでも起こりうることだ」と理解することです。さらに「ペットの終活を始める」「悲しみから抜け出す方法を調べる」ことで、ペットとの別れと向き合う準備が次第に整い、心の支えとなるでしょう。
ペットロスについて、詳しくは「ペットロスの症状と克服する方法」でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
A.「残す情報」「金銭面」「預け先の確保」に不足がないようにすることです。
複数のペットを飼っている場合、終活で取り組むべきことも多くなります。エンディングノートに記す情報や希望は1匹ずつ丁寧に確認し、費用も必要なぶんをきちんと用意しておきましょう。
預け先となる相手には、全て一緒に託せるのか、分ける必要があるのか事前に確認しておくことも大切です。すべてのペットが等しく幸せに暮らせるよう、責任を持って備える姿勢が求められます。
A.ペットと一緒に埋葬できるお墓は数が限られているため、どのような施設があるかを事前に調べ、必要に応じて生前契約を結んでおきましょう。
日本で最も宗教人口が多い仏教では、動物と人が同じお墓に入ることをタブーとしてきました。そのため、既存のお墓にペットのご遺骨を埋葬するのは難しいのが現状です。
しかし近年は、ペットと共に眠ることを前提としたお墓や納骨堂が少しずつ増えています。一般的なお墓に比べると数はまだ限られているため、希望する場合は早めに生前契約をしておくと安心です。
9.飼い主もペットも元気なうちから終活で備えよう

ペットの終活は、万が一への備えだけでなく、今そばにいるペットとの時間をより愛し、大切に過ごすことにもつながります。自分やペットの体調に不安を感じる前に、できることから少しずつ準備を進めておきましょう。
ペットやご自身の終活についてのお悩みは、花葬儀にお任せください。葬儀やお墓、相続など、終活でのお困りごとを、専門家を交えながらワンストップでご相談いただけます。また、現在メンバーシップクラブ「リベントファミリー」にご加入いただいた方に、葬儀費用の割引や枕花のサービスなどの特典をプレゼント中です。この機会にぜひご検討ください。