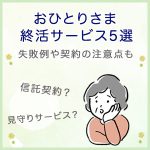遺影写真は終活で準備する|自分らしい1枚を残すための撮影ポイントと写真選びのコツ
- 作成日: 更新日:
- 【 終活の基礎知識 】
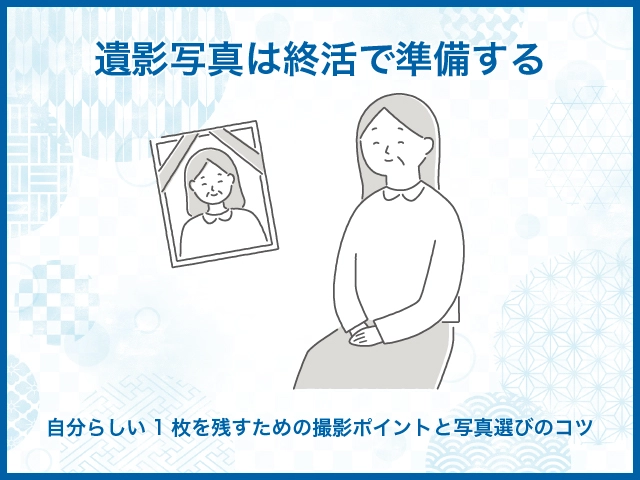
「遺影写真」と聞くと、「亡くなった後にご家族が用意するもの」という印象を持たれるかもしれません。しかし近年では、終活の一環として、生前のうちに自分の遺影写真を準備する方が増えています。
この記事では、終活として遺影写真を用意する際に押さえておきたいポイントを、わかりやすく解説します。生前準備のメリットや、写真選びのコツ、撮り方の工夫など、役立つ情報をまとめましたので、ぜひ最後までお付き合いください。
1.そもそも遺影写真とは

「遺影(いえい)写真」とは、故人様をしのぶために祭壇や仏壇などに飾られる写真のことです。
かつて遺影写真といえば、モノクロで表情の少ない厳粛な姿が主流でした。故人様の面影を残すというよりは、儀礼的な一面が大きかったかもしれません。しかし、時代の変化とともにそのあり方も大きく変わり、現代は「その人らしさ」が表れている写真が多く選ばれています。
遺影写真は絶対必要?
葬儀の前に用意することがほぼ当たり前となっている遺影写真ですが、遺影そのものに宗教的な意味合いはないため、実は必須ではありません。
しかし、遺影写真を用意することで、故人様の在りし日の姿を思い返したり、言葉をかけやすくなったりするため、特別な事情がない限りは用意することをおすすめします。葬儀で飾られるだけでなく、その後の仏壇などに長く飾られることも多く、日々の暮らしの中で語りかける存在となることもあります。
遺影写真の規格や飾り方に決まりはある?
遺影写真には明確な決まりはなく、基本的にはご本人やご家族の意向に沿って自由に選ぶことができます。四つ切りサイズ(254mm×305mm)が一般的ですが、葬儀の規模や会場によってサイズはさまざまです。また、写真に限らず、故人様の肖像画を遺影として使用するケースもあります。
ただし、宗教や宗派によっては、遺影を飾る位置や形式に一定のしきたりがある場合もありますので、事前に確認しておくと安心です。
2.終活で遺影写真を用意する意義とは?
終活とは、人生の終わりに向けて、自分や家族のために準備をしておく活動の総称です。具体的には以下の活動を指します。
| テーマ | 詳細 | |
|---|---|---|
| 1 | 身辺整理 | ・大事なものと不用品を分け、不用品は処分(いわゆる「断捨離」) ・インターネット上の個人情報の整理 |
| 2 | エンディングノート・遺言書の作成 | ・エンディングノートへの記載 ・必要に応じて、遺言書により財産の相続先を明確にする |
| 3 | 介護・医療に関する意思表示 | ・介護に関する自分の希望をご家族に伝える ・延命治療、終末期の意向について意思表示 |
| 4 | 財産の管理と整理 | ・預貯金や有価証券といった資産だけでなく、負債も含めて書き出して整理 ・定期的な財産状況の見直し |
| 5 | 葬儀の準備と契約・手続き | ・葬儀の際に知らせてほしい人のリストを作成 ・葬儀社の情報収集、費用の準備、契約 ・遺影写真の準備 |
| 6 | お墓、埋葬方法の検討・手続き | ・お墓や埋葬方法について、希望する場所や費用などを調べる ・必要に応じて、購入・契約の手続きをする |
※さらに詳しく知りたい方は「終活でやること12選」をご覧ください。
そのうちの「5.葬儀の準備と契約・手続き」で行っておくとよいもののひとつが「遺影写真の準備」です。
遺影写真は、単なる記録写真ではありません。ご本人の雰囲気や人生観がにじみ出るような一枚を残すことで、ご家族にとっても「その人らしいね」と語りかけたくなる、記憶の拠り所となります。また、「どんな自分として覚えていてほしいか」を考える過程は、自らの人生を振り返る貴重な機会です。人生の締めくくりを、自分の言葉や物ではなく「表情」や「空気感」で表すという点で、遺影は非常に深い意味を持つものといえるでしょう。
3.終活で生前に遺影写真を用意しておくことのメリット
生前のうちに自分の遺影写真を用意しておくことについて、抵抗感を抱く方もいらっしゃるでしょう。しかし、生前からの備えは大きく分けて2つのメリットがあります。
ひとつは「自分が納得できる1枚を残せる」という点です。自分らしい笑顔や自然な表情、趣味の最中や旅行先での笑顔など、「こんな自分を覚えていてほしい」という気持ちを残しておくことができます。
もうひとつは「ご家族の負担を軽減できる」点です。多くの場合、ご遺族は限られた時間の中で葬儀の準備をしなければならず、忙しく過ごされます。慌ただしく写真を探し、選定し、加工を依頼するのは心身ともに大きな負担となるでしょう。
事前に準備されていれば、その時間と手間を省けるだけでなく、ご遺族が故人様と向き合う大切な時間をゆっくり持つことができるようになります。
4.「遺影写真」はいつの写真でもOK
終活で遺影写真を準備する際、「亡くなる1~5年前以内の写真であるべき」と考える方が多いようですが、遺影写真に使用する写真の年数に決まりはありません。
記事の冒頭でも触れたように、現代の遺影写真では「その人らしさ」が重視されるようになってきています。大切なのは、「いつ撮った写真か」ではなく、「どんな自分を残したいか」という視点です。
昔の若々しい頃の写真や、家族と過ごす自然な笑顔など、ご自身が「これが私らしい」と思える写真であれば、それが最良の選択です。年数にとらわれず、心から納得できる1枚を選ぶことが、後悔のない準備につながります。
5.終活で遺影写真を準備する3つの方法
終活で自分の遺影写真を用意する方法と、それぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。
1.過去に撮影した写真の中から選ぶ
これまで撮りためた写真の中から、お気に入りの一枚を遺影として選びます。
【メリット】
・費用負担が少ない
・自分の人生を振り返ることもできる
【デメリット】
・現像したものやデータなど、全てをチェックするのに時間がかかる
【費用目安】
・0円
・ただし、選んだ写真をプロに加工・修正してもらう場合は、1万円前後の費用がかかることもある
2.遺影用に自分で撮影、またはご家族に撮影してもらう
ご家族に撮ってもらったり、三脚などを使ってセルフ撮影したりする方法です。
【メリット】
・費用負担が少ない
・何度でも撮り直しができる
【デメリット】
・写真の加工、修正が必要になる場合は別途負担がかかる
【費用目安】
・ほぼ0円
・プリント代や額代などの実費はかかる
3.写真館や遺影専門業者に依頼して撮影してもらう
写真館や出張カメラマンに、遺影用の写真を撮影してもらう方法です。
【メリット】
・プロならではのクオリティの高い写真を撮ってもらえる
・自分の手間が少ない
【デメリット】
・撮影費用がかかる
【費用目安】
・1万円~数万円程度
・撮影料のほか、修正、プリント料金などが含まれることが多い
いずれの方法を選ぶにしても、最も大切なのは金額そのものよりも「結果に心から納得できるか」という点です。特にプロに依頼する場合は、料金の安さだけで判断せず、サービス内容(修正範囲や納品形態など)をしっかり確認しましょう。事前に丁寧な相談ができるかどうかも、信頼できる業者を見極める重要なポイントです。
次項では、遺影写真を撮影して準備する方法を解説いたします。
6.最高の遺影写真を撮る5つのポイント
「今の自分らしい姿を最高の形で残したい」と考える方に向けて、遺影写真を新たに撮影する際の重要なポイントと、気になる費用について解説いたします。
1.遺影写真を用意するタイミング
遺影写真の撮影に適した時期は人それぞれです。落ち着いて撮影できるよう、体調が安定していて、気持ちの面でも前向きに取り組めるタイミングを選ぶとよいでしょう。たとえば、退職後や節目の誕生日など、人生の区切りとなる出来事を機に撮影を決める方も増えています。そうした節目は、「今の自分を残しておきたい」という気持ちに自然とつながるものです。
2.撮影方法
撮影方法には、大きく分けて「プロに依頼する」方法と「ご自身やご家族で撮影する」方法の2つがあります。
●プロ(写真館・カメラマン)に依頼する
照明や構図などプロの技術で、高品質な写真に仕上がります。肌や服装の色味もきれいに再現されるため、長く飾る遺影写真として、品質を確保できます。プロのカメラマンが自然な表情を引き出してくれる点も、大きなメリットです。
●ご自身やご家族が撮影する
リラックスした日常の場面で自然な表情を捉えやすいのが特長です。しかし、プロの撮影と比べると、専門的な機材や技術がないことによる差が出てしまう点は考慮しなくてはなりません。いつも通りの自然な表情を残したいと思っても、いざカメラを向けられると表情が硬くなってしまうことも少なくありません。
どちらの方法にも一長一短がありますので、ご自身の目的や価値観に合わせて選ぶことが大切です。
3.背景・撮影場所
背景は、必ずしも無地にこだわる必要はありません。思い出の場所や旅行先の風景など、「その人らしさ」が感じられる場所で撮影された写真も、遺影として十分ふさわしいものになります。
また、どうしても背景が気になる場合は、加工アプリやプロの写真店に依頼することで、調整や差し替えも可能です。そのため、最初から完璧な1枚を用意しようと構えすぎず、表情や雰囲気を第一に考えて撮影するとよいでしょう。
4.服装・小物
遺影写真の服装にも決まりはありません。喪服やフォーマルウェアである必要はなく、普段の雰囲気が伝わるスタイルを選ぶとよいでしょう。趣味の道具や愛用の品、大切なペットと一緒に写るのも素敵です。その人柄がより深く伝わる、物語性のある一枚になります。
5.目線・表情
遺影写真は、一般的に正面を向いているものが好ましいとされています。参列者に「語りかけられているように感じる」「見守られているような気持ちになる」という安心感を与えることができるためです。また、祭壇に飾った際にバランスがとりやすいという理由もあります。
しかし、これはあくまで一般的な傾向であり、厳格なルールではありません。少し斜めを向いた横顔など、ご自身やご家族が「その人らしい」と感じる一枚であれば、そちらを選んでも全く差し支えないでしょう。
表情については、「自分らしさ」や「残したい自分の顔」を意識するとよいでしょう。例えば、厳格なイメージを大切にしたい場合は落ち着いた表情や引き締まった顔つきを選ぶのがおすすめです。一方、温かく親しみやすい印象を残したい場合は、やわらかく微笑む表情や、自然体の穏やかな顔つきを選ぶといった具合です。
写真は言葉以上に、その人の人柄や雰囲気を伝えます。どのように見られたいか、どんな印象を残したいかを考えながら、ご自身が納得できる表情を選ぶことが、遺影写真の満足度を高めるポイントです。
7.終活をする方必見|遺影写真の選び方と注意点
ここまでは、新たに写真を撮影する際のポイントを中心に解説しました。一方で、「思い出の詰まった一枚から選びたい」と考える方も多くいらっしゃるでしょう。
ここからは、ご自身で撮りためた写真の中から、最高の遺影を選ぶための注意点をご紹介します。
ピントと解像度
過去の写真から遺影を選ぶ場合、特に注意したいのが「ピント」です。ピントとは、カメラにおける焦点を意味し、ピントが合った被写体は、はっきりと写ることができます。
遺影用に写真を撮る場合は、ピントが合っていて、最低でも200万画素以上になるようにしましょう。画素とは画像を構成する色の単位で、画素数が多いとより鮮明に、反対に少ないと粗く見える原因となってしまいます。
遺影写真は大きく引き伸ばされて使われることが多いため、顔立ちや表情がはっきりわかる、鮮明な写真を選ぶことが大切です。
サイズとデータ形式
遺影写真は「祭壇用」と「焼香台用(自宅の仏壇用)」をそれぞれ用意します。同じ写真データから、用途に合わせて大小2種類のサイズにプリントして用意することも可能です。それぞれのサイズは以下を参考になさってください。
・祭壇用:四つ切(254mm×305mm)、A4(210mm×297mm)など
・焼香台用:・L判(89mm×127mm)、2L判(127mm×178mm)など
画像のデータはJPEGなどの一般的な形式であれば問題ありません。ただし、写真の加工やプリントを業者に依頼する際は、対応形式が異なる場合もあるため、事前に確認が必要です。
8.遺影写真をより魅力的に見せる「加工」のポイントと注意点
ご自身で撮影した写真や、たくさんの中から選んだ一枚は、必要に応じて加工を施すことで、さらに魅力的に仕上げることができます。祭壇用の遺影写真は大きいため、引き伸ばす工程が必要ですが、それとは別に、遺影に選んだ写真をさらに魅力的に整える目的として、加工することもあります。
こちらでは、遺影写真を加工するための方法や加工のポイントをご紹介します。
アプリを使って遺影写真を加工する
近年は、簡単に写真を明るく補正したり、背景をぼかしたりできる加工アプリが数多く登場しています。明るさ・コントラストの調整、肌の質感の自然な補正などを行うことで、印象はより柔らかくなるでしょう。
ただし、過度な加工はかえって違和感を与えることもあるため、「見た目を整える」より「雰囲気を整える」ことを意識するのがポイントです。
プロによる遺影写真の補正・修正
自分での加工に不安がある場合や、より丁寧な仕上がりを求める場合には、プロによる補正サービスの利用がおすすめです。
プロに依頼することで、背景の差し替え、不要物の削除、肌色の自然な補正、衣装の整えなど、高度な技術を駆使して写真を美しく仕上げてもらえます。また、印刷用に高解像度データで納品してもらえることも多く、ご家族やご親族と共有することも可能です。
遺影写真の加工を行ってくれる場所
遺影写真の加工の依頼先は、遺影専門業者や写真館などがあります。依頼先によってオプションやサービス内容は異なりますが、生前のうちに取り掛かればゆっくりと比較・検討することができ、満足感の高い仕上がりになるでしょう。
加工費用の目安
プロによる加工費用(撮影は含まない)の費用は、利用するサービスによっても異なりますがおよそ1万円前後です。
葬儀社に依頼する場合は、遺影写真の費用が葬儀プランに含まれているケースが多いため、葬儀社へ個別にお問い合わせください。
9.終活で準備した遺影写真を大切に残すには?
遺影写真が準備できたら、大切に未来へ残すための準備をしましょう。ここでは、写真を良い状態で保管する方法と、遺影写真を入れる額の選び方について解説いたします。
保管場所について
写真は高温多湿な環境下では劣化しやすくなるため、風通しの良い冷暗所で保管しましょう。データで保管する場合は、万が一の時に備えてバックアップをとっておくことをおすすめします。
遺影写真を用意した後は、ご家族にその旨を伝えることも忘れてはいけません。ご家族が存在を知らないと、遺影写真に使ってもらえない可能性が高まるためです。
事前に伝えるのが難しい場合は、エンディングノートなどに遺影写真の有無と保管場所を記しておきましょう。エンディングノートとは、財産や介護、葬儀などに関する希望を自由にまとめられる終活ツールです。詳しくは「エンディングノートの書き方」の記事を参考になさってください。
フレーム(額)
終活として準備するなら、「祭壇には、この写真立てを使ってほしい」というように、ご自身の希望として額まで指定しておくのも良いでしょう。
遺影写真を入れるフレーム(額)にも、決まりはありません。昔は黒色のシンプルなものが主流でしたが、近年は白やブラウンなどの自然色や、パステルカラーのフレームが人気です。素材やデザインも豊富にあるので、好みや飾った時のイメージなどを考えながら決めるとよいでしょう。
ここまでご紹介した内容については「遺影写真の選び方」とも併せて参考になさってください。
10.終活の遺影写真に関するFAQ
A.大きく引き伸ばした時に鮮明になる状態であれば問題ありません。
近年はデジタルカメラよりもスマートフォンで写真を撮る機会が増えてきました。もちろん、スマートフォンで撮影した写真を遺影写真に使うことも可能です。
ただし、祭壇に飾る遺影写真は大きく引き伸ばす必要があるため、「ピントが合っている」「200万画素以上」のものになるよう注意しましょう。
A.多くの場合、遺影写真のない状態で火葬されます。
死後の希望や備えが何も残されていない状態で亡くなった場合、事件性の有無を確認したうえで火葬されるのが通例です。その際、火葬の直前にごく簡単な儀式が執り行われるのみで、遺影写真も用意されることはありません。
誰にも知られず、見送られることもなく人生を終える——そんな静かな幕の引き方は、やはりどこか寂しさを感じさせます。身寄りのない方やおひとりさまこそ、生前のうちにご自身のための準備を整えておくことが大切です。「身寄りのない方が老後に備えるには?」の記事を参考に、できることから始めてみましょう。
A.問題ありません。ただしご家族には念のため相談しておきましょう。
遺影写真に明確な決まりはなく、近年では正装や厳粛な表情に限らず、笑顔や趣味の一場面、日常の姿など、その人の個性や思い出が伝わる写真を選ぶ方が増えています。
ペットと共に暮らし、深い絆を育んできた方にとっては、その存在が人生の一部であり、写真にも自然に表れるものです。したがって、ペットと一緒に写った写真を遺影とすることは問題ありません。
ただし、祭壇に飾る際は、ご家族やご親族の価値観、また宗教や宗派の考え方によって意見が分かれることもあります。事前に家族と話し合って理解を得ておく、あるいはペットと一緒の写真を「自分の希望する遺影」としてエンディングノートなどに明記しておくと安心です。
A.免許証からでも遺影写真を作成することはできますが、時間に余裕のある終活の中でこそ、自分らしさが伝わる自然な写真を意識的に残しておくことも大切です。
急な葬儀で写真を探す時間がない場合や、適切な写真が手元にない場合は、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの証明写真を遺影として使用することも可能です。これらの写真は正面を向いており、顔がはっきりと写っているため、祭壇に飾る写真として一定の基準を満たしています。
ただし、終活の一環として遺影写真を準備するのであれば、時間にゆとりがあるからこそ、より自分らしい1枚を残すことができます。たとえば、趣味を楽しんでいる姿や旅行先での自然な表情など、日常の中で「自分らしさ」がにじみ出る瞬間を積極的に写真に残してみてはいかがでしょうか。
A.「自分らしい写真を残しておきたい」「いざという時に、みんなが慌てなくて済むように」と、前向きな想いを素直に伝えるのが良いでしょう。
遺影写真の話は、ご家族も最初は少し驚くかもしれません。しかし、話の中で「なるほど」と納得し、安心して見守ってくれることが多いようです。
中には、ご家族と一緒にスタジオを訪れ、撮影の場を共有される方もいらっしゃいます。撮影後に仕上がった写真を見ながら語らう時間は、家族のつながりを再確認するかけがえのない時間にもなります。遺影写真の準備を通じて、家族がこれまで以上に心を通わせるきっかけとなることもあるでしょう。
A.定期的に見直して「今の自分」に更新していく選択肢もあります。
年齢を重ねれば表情や雰囲気も変わりますし、「もっと自分らしい一枚が撮れるのでは」と思うようになる方もいらっしゃいます。そのため、遺影用の写真は定期的に見直すことが大切です。
たとえば3年に一度、誕生日や記念日のタイミングで撮り直しを検討するのもおすすめです。遺影写真は一度準備して終わりではなく、「いまの自分」を映すものとして、折に触れて更新していくことで、より納得のいく形で残すことができます。
11.終活を通して「家族に残したい遺影写真」を用意しよう
終活で遺影写真を準備するのは、人生の終わりを意識するというより、「今の自分らしさを未来に伝える」前向きな行動です。どのような写真を選び、どのような表情で残すのか、そのひとつひとつの選択が、ご家族の心をやさしく支えるかたちとなって遺ります。
とはいえ、「自分で決めるのは少し不安」「何から始めればいいのかわからない」と感じる方もいらっしゃるでしょう。そんな時は、葬儀のプロである花葬儀にご相談ください。経験豊富なスタッフが、写真の準備だけでなく、終活全体の不安に寄り添いながら、丁寧に対応いたします。ご相談は無料の事前相談の利用がおすすめです。
また、花葬儀では、自分という存在を軸に、ご家族のつながりを広げていくことをコンセプトとしたツール「つなごう」をご用意しております。遺影写真の準備と併せて、この機会にぜひご検討ください。