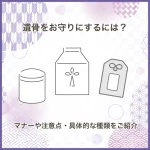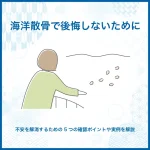遺骨を自宅で保管するには?注意すべき点と6つの保管方法を紹介
- 作成日:
- 【 お墓 】
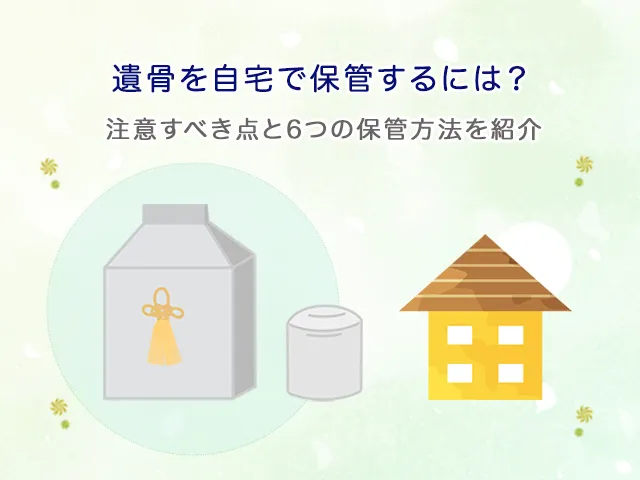
近年、ご遺骨を自宅で保管し、供養する形が注目を集めています。お墓に埋葬しない供養とは、具体的にどのようなものなのでしょうか。
今回は「自宅でご遺骨を保管するには?」をテーマとしたコラムをお届けします。このコラムを読むことで、「ご遺骨の自宅保管は問題ない?」「メリット・デメリットは?」「具体的な保管方法は?」などが網羅的に理解できるようになるでしょう。
現在ご遺骨の供養方法でお悩みの方、お墓に埋葬する以外の供養について知りたい方はぜひ最後までお読みください。
1.遺骨の自宅保管は法律違反?知っておきたい基本ルール

結論からお伝えすると、ご遺骨を自宅で「保管」することは、法律違反にはあたりません。
ご遺骨を埋葬する場所については、「墓地、埋葬等に関する法律」によって以下のように定められています。
埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
(引用:墓地、埋葬等に関する法律
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048)
自宅や私有地、山林などは、法律で定められた「墓地」ではないため、ご遺骨を埋葬することはできません。違反した場合、罰則が科せられる可能性があります。
しかし、この法律はご遺骨を埋葬せずに自宅で「保管」することを禁止しているわけではありません。したがって、庭などに埋葬しない限り、自宅での保管や供養は自由に行うことができます。このような供養方法は「手元供養」と呼ばれ、近年注目されています。
2.遺骨の自宅保管が注目される背景
ご遺骨をお墓に埋葬するのではなく、自宅で保管することが注目されているのはなぜでしょうか。
こちらでは、その背景をご紹介します。
お墓の維持管理・承継が困難
遺骨の自宅保管が増えている背景の一つとして、まず挙げられるのが、従来のお墓の維持管理や承継が難しくなっている現状です。
かつては、先祖代々のお墓にご遺骨を埋葬することが主流でした。お墓を継いだ人は、定期的な清掃や墓地管理者への管理費の支払い、古くなったお墓の修繕など、お墓の維持・管理を担ってきました。
しかし近年では少子高齢化や核家族化の進行により、承継者が減少しているため、こうしたお墓の維持・管理が困難な状況になりつつあるのが現状です。
ライフスタイルや住環境の変化
ライフスタイルや住環境が変わりつつあることも、供養のかたちが変化している要因です。転勤や移住が珍しくなくなった近代では、お墓との物理的な距離は避けられない問題となりました。また、大きな仏壇を置く「仏間」がないスタイルが主流となる中、故人様に対し手を合わせる場所を身近に求める気持ちが高まっていることも考えられます。
供養に対する価値観の多様化
近年はお墓や供養の方法、宗教観などに対する価値観が多様化し、「故人様を身近に感じたい」「自分たちらしい形で行いたい」といった個人の想いが尊重される傾向が強まっています。また、自分の死後について考えた時に「家族にお墓の管理で負担をかけさせたくない」と考える方が増えているのも、背景のひとつとして考えられるでしょう。
3.遺骨を自宅で保管するメリット・デメリット

ご遺骨を自宅で供養することのメリットやデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。
こちらで詳しく解説します。
メリット
自宅でご遺骨を保管することのメリットは、以下の通りです。
日常的に故人様をしのぶことができる
故人様をいつも身近に感じながら、日常的に供養することができる点が、ご遺骨を自宅で保管する最大のメリットです。お墓が遠方にあると、年に数回しか故人様と会えないという方も少なくありません。しかし自宅にご遺骨があれば、日々の暮らしの中で手を合わせたり語りかけたりと、日常の中で故人様をしのぶことができるようになります。
身体的な負担を軽減できる
お墓の場所が自宅から遠く離れていると、墓参りをするために時間をかけて移動しなくてはなりません。また、墓参りの日が雨や雪といった場合、屋外での供養は大きな負担になるでしょう。
自宅にご遺骨を保管すれば、天候やスケジュールを気にせずいつでも好きな時に供養が行えます。このように、お墓参りに係る身体的な負担が無いのもメリットです。
お墓の維持管理の負担を軽減できる
お墓に埋葬して供養するためには、主に以下の費用や役割が必要となります。
- ・お墓を建てる費用
- ・墓地管理者に支払う管理費
- ・修繕費(必要に応じて)
- ・定期的な掃除や草むしり など
ご遺骨を自宅で保管する場合、これらの金銭的・時間的な負担は発生しません。ただし、ご遺骨の一部を手元に残し、残りを散骨や別の場所へ埋葬する場合、納骨先で別途費用が発生する可能性があります。
デメリット
自宅でご遺骨を保管する行為はメリットだけではありません。デメリットも含めて把握することで、最適な決定が下しやすくなります。
自宅にご遺骨を保管することのデメリットは、以下の通りです。
遺骨の手入れ・管理の責任がある
自宅に保管したご遺骨は、全て自己管理となります。湿度の高い日本では、自宅内に保管したご遺骨からカビが生えることがあるため、定期的な手入れが必要です。また、落下などによる破損や、火事や地震といった災害による紛失のリスクにも備えなくてはなりません。
将来的に遺骨を任せる人が必要
病気や死亡など、ご自身がご遺骨を管理・保管できなくなった時のことも考えなくてはなりません。承継者がいなくなったご遺骨は、「無縁遺骨」として納骨堂に安置されたり、他の人のご遺骨と一緒に埋葬されたりする可能性が高くなります。
大切な方のご遺骨を責任もって供養していくためにも、「将来的に誰に・どこで供養してもらうのか」を決めておくことが大切です。
ご家族で意見が分かれることがある
手元供養は近年注目を集めているものの、まだ一般的とは言い切れません。そのため、「自宅にご遺骨を保管すること」に対して、抵抗感を覚える方もいらっしゃいます。自宅での保管を検討する際は、そうした考え方の違いに対する丁寧な対応が求められます。
ご家族全員が心から納得できる形で供養できるよう、事前に話し合いをきちんと行っておくことが大切です。
4.遺骨の自宅保管をスムーズに進める秘訣

ご遺骨の扱いで後悔することのないよう、ご遺骨を自宅で保管する際は入念な準備が必要です。
前述したデメリットを解消するためにできることを、こちらで詳しくご紹介します。
ご家族・ご親族と話し合う
ご遺骨を自宅で供養するために最も重要なのは、手元供養についてご家族やご親族としっかり話し合うことです。お墓の在り方や供養方法に対する考え方は、人によって異なります。自分だけの意向で決めてしまうと、周りから不満や反対の声が挙がってしまうかもしれません。
故人様の供養方法をめぐってトラブルが起こらないようにするためにも、独断で決定せず、ご家族全員が納得できるように話し合うことが大切です。それぞれの立場や考えを尊重し合いながら、対話を重ねましょう。
将来的なご遺骨の最終的な行き先を決めておく
病気や死亡などによって、ご遺骨を自宅に保管していた人が管理できなくなった時のために、対策を考えておきましょう。その際も、ご家族やご親戚に相談してから決めることを忘れないようにします。
将来的なご遺骨の供養方法については、「自宅保管のその後は?さまざまな供養の選択肢」にて後述しますので、そちらをぜひご覧ください。
5.遺骨を自宅で保管する6つの方法

「自宅でご遺骨を保管する」と一口に言っても、その方法はさまざまです。こちらでは手元供養におすすめの方法を6つご紹介します。
ご自身や故人様にとって最適な供養方法はどれか、以下の価格も参考にしながらぜひご覧ください。
| アイテム | 相場 |
|---|---|
| 骨壺・ミニ骨壺 | 5千円~数万円 |
| 遺骨収納アクセサリー | 2万円~数百万円 |
| ミニ仏壇 | 1万円~数十万円 |
| インテリアオブジェ | 5千円~30万円 |
| 自宅墓 | 5万円~30万円 |
| 遺骨ジュエリー | 数千円~数十万円 |
骨壺・ミニ骨壺
お墓に埋葬するご遺骨は骨壺に納められることがほとんどですが、その骨壺をご自宅に置くことも可能です。
通常の骨壺は地域によって主流となるサイズが異なり、西日本では6寸(高さ21㎝、幅18㎝)、東日本では7寸(高さ25.5㎝、幅22㎝)が多く使用されています。通常のサイズででは自宅内では目立ちやすいため、手元供養ではミニ骨壺を選ぶ方が多くいらっしゃいます。
ミニ骨壺の多くは手のひらの中に収まるサイズであり、色味やデザイン、材質の種類が豊富です。デザイン性の高い骨壺を用いることで、部屋の家具やインテリアと調和しつつ、ご遺骨を大切に保管することができるでしょう。
遺骨収納アクセサリー
「遺骨収納アクセサリー」とは、ご遺骨の一部や、ご遺骨を砕いた遺灰をアクセサリーの中に納めて保管できるアイテムです。ペンダントやリング、ブレスレットといった種類があり、また材質も安価なステンレス製から高価なプラチナ製までさまざまです。
肌身離さず身に着けることができるため、「故人様と一緒に出掛けたい」「故人様の存在をより近くで感じたい」との要望にも応えられます。
ミニ仏壇
日本で古くから用いられてきた一般的な仏壇は、高さが150~180㎝と大型です。それに対し、小さなスペースでも置けるように作られたのが「ミニ仏壇」です。
種類にもよりますが、30~60㎝ほどの高さで、リビングの棚の上などに置くことができます。伝統的な仏壇を小さくしたようなデザインだけでなく、インテリアになじむモダンなデザインも人気です。
ミニ仏壇には一般的な仏壇と同じように、位牌や香炉、遺影などを置くことができます。扉付きのタイプであれば、来客時などに閉めることもできて安心です。
インテリアオブジェ
写真立てやプレート、ぬいぐるみなどを使った供養方法が「インテリアオブジェ」です。「メモリアルオブジェ」とも呼ばれます。ご遺骨を専用のインテリアオブジェの中に納めるものや、ご遺骨を金属などに溶かしてプレートなどのアイテムとして加工するタイプもあります。
一目見ただけではご遺骨が納められているとわかりにくいため、室内に違和感なく飾ることができ、ご家族が集うリビングなど、好きな場所で故人様を供養することが可能です。
小型墓石タイプ
一般的な墓石を小さくしたようなアイテムです。サイズは両方の手のひらの中に収まる程度の大きさからあるため、室内に置くこともできます。御影石を使用したものもあり、一般的な墓石のような厳かさを重視したい方におすすめです。
外観は通常のお墓に似ていますが、屋外に設置する場合、ご遺骨の入った骨壺を納めると法律違反にあたるので注意しましょう。また、ミニ仏壇やインテリアオブジェと比較して重量があるため、設置場所は慎重に選ぶことも必要です。
遺骨ジュエリー
ご遺骨に含まれる炭素を抽出して作る宝石を「遺骨ジュエリー」と言います。ご遺骨が美しい宝石へと生まれ変わるため、故人様の新たな姿として、より前向きな気持ちで受け入れやすいと感じる方もいらっしゃいます。劣化せず永く残る宝石は「ずっと一緒にいる」という安心感にもつながり、心を癒してくれるでしょう。
6.遺骨を自宅で大切に保管するための注意点

ご遺骨を自宅で保管する際には、想定されるリスクやトラブルへの備えが必要です。
いつまでも心穏やかに故人様と過ごすためにも、以下のポイントを押さえておきましょう。
カビ対策、衛生管理はしっかりと
湿度の高い日本では、カビの発生に気を付けなくてはなりません。火葬を終えたばかりのご遺骨はほぼ無菌状態ですが、その後の環境によっては骨壺の中でカビが発生してしまう可能性があります。以下の点に注意し、衛生管理をしっかりと行いましょう。
【ご遺骨にカビが生えやすい環境】
- ・直射日光が当たる場所
- ・風通しが悪い場所
- ・時間や季節によって室内の気温差が激しくなる場所
カビの発生を防ぐために、乾燥剤を使用する他、ご遺骨を粉骨して真空保管するのもひとつの方法です。粉骨することで、設置スペースを小さくすることもできます。
また、火葬の際に「六価クロム」という強い酸性の物質がご遺骨に含まれることがあります。六価クロムは気化して人体に影響を及ぼすことはありませんので、通常の取り扱いで過度に心配する必要はありません。
適切な保管場所を選ぶ
カビの発生を防ぐためにも、ご遺骨を保管する場所は重要です。キッチンや浴室など水回りは避け、リビングや寝室など、室温が安定している場所がよいでしょう。
また、「転倒や破損の原因にならない場所」を意識することも大切です。腰の高さ程度の棚に置いたり、耐震マットで固定したりといった工夫をしましょう。
ご家族や来客に配慮することも大切
自分にとっては身近に置いておきたいご遺骨が、他の人にとっても同じであるとは限りません。ご遺骨が自宅にあることに、強い抵抗感を覚えてしまう方もいらっしゃいます。自宅で供養する際は、「自分の寝室に置く」「扉付きの棚に保管する」といった配慮も必要です。
7.自宅保管のその後は?さまざまな供養の選択肢

自分にもしものことがあった場合、自宅に保管していたご遺骨はどうなるのでしょうか?また、将来に備える場合、どのような選択肢があるのでしょうか?
自宅保管した後のご遺骨の供養について、こちらで詳しくご紹介します。
お墓・納骨堂
一つ目の選択肢は「お墓に埋葬する」です。承継したお墓、もしくは新しく建てたお墓に埋葬しましょう。
「承継者がいない」「お墓参りに定期的に行くことができない」といった場合は、納骨堂がおすすめです。納骨堂とは、屋内にあるお墓を指し、お墓の形態も「仏壇型」や「ロッカー型」などの中から選ぶことができます。維持や管理の負担が屋外のお墓に比べて少ない点も魅力です。
合祀墓
「合祀(ごうし)」とは、骨壺から取り出したご遺骨を、血の繋がりのない他人のご遺骨と共に埋葬することです。合祀のためのお墓を「合祀墓」と言います。管理者である寺院や霊園が、永代(※)にわたって供養・管理を行うため、「永代供養墓」の一種とされています。一度合祀されたご遺骨は取り戻すことができなくなるため、判断は慎重に行いましょう。
永代供養の種類やメリット、費用については「永代供養とは?」の記事が参考になりますのでご覧ください。
(※)墓地が存続する限りという意味。永遠ではない。
散骨
パウダー状に砕いたご遺骨(遺灰)を、海や山に撒いて供養するのが「散骨」です。散骨は、好きな山や海に自由に撒いてよいわけではありません。そのため、散骨を取り扱っている葬儀社に依頼して行うのが一般的です。
樹木葬
樹木を墓石の代わりとし、その下にご遺骨を埋葬することを「樹木葬」と言います。多くの場合、宗教や宗派を問わず利用でき、継承者を必要としない永代供養のプランが用意されていることもあります。
8.遺骨の自宅保管に関するQ&A

A.ご遺骨の供養方法について「いつまでに考えなくてはならない」という決まりはありません。
一般的には四十九日を迎えて納骨をするまでに決定する方が多いようです。しかし、必ずしも納骨までに決断する必要はなく、お墓に埋葬した後に検討しても問題ありません。納骨時期までに決まらない場合は、一度お墓に埋葬してからじっくり考えてもよいでしょう。ただし、合祀を選択した場合、ご遺骨を取り戻すことができないため、注意が必要です。
A.もちろん可能です。
マンションなどの賃貸住宅でも、ご遺骨を自宅で供養することは可能です。ただし、賃貸であるかどうかに関係なく、墓地ではない場所へご遺骨を埋葬することは法律で禁じられているため、必ず自宅の中で保管しましょう。
A.必ずしも分骨するわけではありません。分骨するかどうかはご家族で相談の上決めることができます。
「分骨」とは、ご遺骨を2箇所以上の場所に分けて供養することです。自宅で供養する場合、ご遺骨の全てを保管するか、分骨するかは自由に決めることができます。ただし多くの場合、全てのご遺骨を自宅で保管・供養することが困難であるため、分骨する傾向にあります。
分骨する際は、市町村役場に申請して「分骨証明書」の取得が必要です。詳しくは「分骨の方法は?」にてご紹介しておりますのでぜひ参考になさってください。
9.遺骨の自宅保管はご家族との対話と同意が大事

供養の方法が多様になりつつある昨今、自宅内にご遺骨を保管する「手元供養」が注目を集めています。豊富なデザインや種類の中から、故人様やご家族にとってふさわしいものを選ぶとよいでしょう。ただし、手元供養は独断で決めず、必ずご家族に相談し、了承を得ることが大切です。
手元供養を始めとした供養方法でお悩みの方は、花葬儀にお任せください。ご相談は、年会費無料のメンバーシップクラブ「リベントファミリー」へのご加入がお得です。
供養方法だけでなく、相続や遺品などにまつわるお悩みをワンストップで解決することができます。会員限定チケットやイベントのご案内など特典も豊富ですので、この機会にぜひご検討ください。