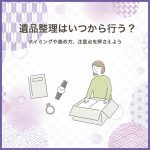親の遺品で“残すもの”とは?後悔しないための考え方を解説
- 作成日: 更新日:
- 【 遺産・遺品整理 】

親の遺品を前に「残すものはなにか」を考えることは、ご遺族にとって重くもあり大切な作業です。遺品には物としての価値だけでなく思い出や愛情が詰まっているため、その意味を理解しながら選ぶことが心の整理にもつながります。
この記事では、遺品の基本的な意味から、残すものの具体例、選び方の基準、親の遺品との向き合い方まで、納得して判断ができるようにするためのポイントを丁寧に解説します。「親の遺品整理で後悔したくない」という方はぜひ最後までお読みください。
【もくじ】
1.親の「遺品」とは|残す前に知っておきたい基本

まずは「遺品」についての基本と、遺品整理のタイミングや心構えについてご紹介します。この基本を押さえることで、判断が明確になるでしょう。
遺品と形見の違い
「遺品」とは、故人様が生前所有していた物全てを指し、家具・衣類・書籍・家電・趣味で使っていた道具類、不動産や契約上の権利義務なども含まれます。その中でも特にご家族やご友人にとって思い入れが強く、故人様をしのぶために残したい特別な品が「形見」です。
形見は金銭的価値の高さではなく、「故人様が大切にしていたもの」や「思い出が詰まった品」が選ばれる傾向にあります。
遺品と形見の違いを意識することは、自分やご家族にとって本当に大切だと思えるものを取り分けるための第一歩です。形見として何を残すかの基準を持つことで、整理を進める際の迷いを減らすことができます。
遺品が持つ意味と思い出の重み
遺品には、単なる物理的な価値だけでなく、その人がどのように生きてきたかを物語る時間や背景がやどっています。たとえば、毎朝使っていた湯のみや、愛用していたカバンなど、それらには使われていた時間や場面が自然と記憶として刻まれているのです。
遺品を見たり触れたりすることで、故人様の口癖やしぐさ、日々のルーティンなどが鮮やかによみがえることがあります。それは、写真とはまた違ったかたちで「生きた存在」を感じる体験といえるでしょう。
しかし同時に、それが重荷になることもあります。「捨ててしまったら忘れてしまうのでは」「自分が大事にしないといけないのでは」といったプレッシャーが生まれやすいのも、遺品の持つ力ゆえです。感情に飲み込まれないための判断の基準は、「どう選ぶ?残すものの判断基準」でご紹介します。
遺品整理を始める時期
遺品整理のタイミングとして一般的なのは、四十九日を過ぎた頃です。忌明けを一区切りとして、気持ちの整理も少しずつついてくる時期に始める方が多いようです。
しかし、心の準備が整う時期には個人差があるため、四十九日に合わせて無理に行う必要はありません。亡くなってから数か月、数年経って手をつけてもよいのです。
また、精神的につらいときは、一人で進めようとせず、兄弟姉妹や信頼できる友人、あるいは専門家と一緒に作業することが大切です。小さなスペースから始める、一部だけ触れてみるなど、「完了」を目指さず「きっかけ」を作るような意識で臨むとよいでしょう。
大切な人の遺品をどうするか決めることは、気持ちに大きな負荷がかかります。迷いがあって当然と受け止め、整理は「ゆっくり・丁寧に・感情を否定しない」という姿勢で進めることが、後悔を減らす近道になります。
2.どう選ぶ?残すものの判断基準
全ては保管できないとわかっていても、親の遺品整理においては「どれを残すべきか」「どこまで残すか」といった迷いがつきものです。
ここからは、感情面や実用性など、複数の視点から「残す判断」の軸となる考え方をご紹介します。
捨ててはいけない「重要なもの」がないかあらためて確認する
遺品の整理を始める前に、まず現金、預金通帳、不動産の権利書といった、手続きや相続に関わる可能性のあるものがないか、確認しましょう。
これらは感情で残す・残さないを「選ぶ」ものではなく、法的に取り扱いが決まっている場合があります。注意が必要なものの詳細については、「貴重品や捨ててはいけないもの」で解説しておりますので、こちらもあわせてご覧ください。
思い出や故人様らしさで選ぶ
遺品を選ぶうえで最も大切な視点の一つが、「その人らしさを感じられるかどうか」です。故人様の人柄や人生の一場面を特に思い出せるような品はどれかを考えてみましょう。
一方で、「自分にとっての思い出」と「他の家族にとっての思い出」は異なることがあります。同じ品でも、見る人によって感じ方が異なるため、複数人で判断する際は、それぞれの思いを丁寧に共有することが大切です。
自分にはそれほど思い入れがなくても、他の家族には特別な意味があることもあります。会話を通じて故人様の記憶をたどる時間も、遺品整理の大切な一部です。
実用性・保管のしやすさで選ぶ
遺品を「今後の生活で使えるか」「管理しやすいか」という視点で考えることも重要です。思い入れが強くても、サイズが大きすぎる家具や、劣化が進んだ家電などは、長期的な保管が難しくなります。
実用性や現実的な管理のしやすさも含めて判断することで、無理のない形で故人様の思い出をそばに残すことができるようになるでしょう。保管の難しい遺品の残し方については後述する「残した遺品の保管と生かし方」を参考になさってください。
共有するもの/個人で持つものに分ける
親の遺品の中には、ご家族で共有した方がよいものと、個人で所有する方が自然なものがあります。たとえば、アルバムやビデオなどは、スキャンやコピーによって複数人で共有できるため、誰か一人の手元に置く必要はありません。
また、料理道具や趣味の作品などは、使う人・思い入れのある人が引き取ることで、無理のない承継ができるでしょう。指輪や時計などの装飾品は、基本的に一人にひとつずつ渡すことが多いため、「公平さ」よりも「想いの強さ」や「関係性」を優先して分けるケースが多く見られます。
このように、遺品を「共有するか・個別で保管するか」の視点で考えることも、より納得のいく遺品整理への一歩です。
3.親の遺品整理で残すものの具体例
前章では、手続きや相続に必須の遺品や、故人様らしさを感じるものなど、残すべきものの選定基準について解説しました。こちらでは、その中でも故人様との思い出が色濃く残る品に焦点を当て、実際によく残されている遺品をご紹介します。親の面影を感じやすいもの、実用的なものなど、多様な観点から見ていきましょう。
衣類・アクセサリーなど身につけていたもの
衣類やアクセサリーなど、故人様が日常的に身につけていたものは、「その人らしさ」を感じやすい代表的な遺品です。着慣れていたセーターや、いつも使っていた帽子、大切にしていたブローチやスカーフなどは、視覚や触感、さらには香りまでもが記憶を呼び起こしてくれます。
ただし、全てを保管するのは現実的ではありません。数点に絞り、「これだけは残したい」と思えるものを選ぶようにしましょう。
写真・手紙など記憶をつなぐもの
故人様の写真やアルバムは、特に感情を強く揺さぶる遺品です。昔の家族旅行や日常のスナップ、若かりし頃の記念写真など、それぞれに人生の断片が刻まれています。写真の裏に手書きのメッセージなどが記されていることもありますので、しっかり確認しておきましょう。
また、故人様が書いた手紙や日記、ノートなどの文字が残る品も 「その人らしさ」が感じられる貴重な遺品です。ただし、手紙や日記はプライバシー性が高いため、取り扱いには十分な配慮が必要です。
趣味の品・道具類
趣味の品や愛用していた道具は、その人の「生き方」や「価値観」が強く反映された遺品のひとつです。カメラ・釣り道具・陶芸作品・模型・絵画・日曜大工の工具など、使い込まれた様子や工夫の跡に、その人らしさがやどります。
故人様の面影が強いぶん、全てを残しておきたい気持ちが強く出てしまいがちですが、特に象徴的な一部だけを残すことが現実的です。写真に記録を残したうえで、実物は手放すという方法などを検討してみましょう。
家具・家電など生活の一部だったもの
故人様の生活空間を形作っていた家具や家電もまた、日常の記憶と強く結びついた遺品です。たとえば、いつも座っていた椅子や食卓、仏壇、スマートフォン、使い込まれた調理道具などは、生活の延長に「その人の気配」を感じさせてくれます。幼い頃から使っていたものがあれば、親と過ごした日々をあたたかく思い出させてくれることでしょう。
家具・家電については、思い出が詰まっていても、年式や安全性の問題から使用が難しい場合もあります。「現実的な使用・保管が可能か」という点を意識して整理することが大切です。
4.形見分けの基本とマナー|遺品を丁寧に残すために
形見分けとは、故人様の遺品のうち、特別な想いのこもった品を親しい人と分かち合うことです。単なる「物の受け渡し」ではなく、故人様の記憶や思い出を受け継ぐ供養の意味合いもあります。
ここでは、形見分けの注意点やトラブルを避けるための方法についてご紹介します。
渡す・受け取る際の注意点
形見分けを行う際には、相手の気持ちを第一に考えることが重要です。どんなに大切な品であっても、相手が受け取りを望まない場合は無理に渡すべきではありません。事前に「形見分けとして何か受け取ってもらえますか?」と確認を取り、了承のうえで渡すようにしましょう。
また、受け取る側も「故人様の思いを大切に扱う」という心づもりを持つことが求められます。形見を分けてもらえた意味をよく考え、保管には十分注意しましょう。
トラブルを避けるための約束と配慮
遺品整理、とりわけ形見分けの場面では、親族同士の感情のズレや誤解からトラブルが起こることも少なくありません。「自分がもらうはずだった」「勝手に持ち出された」「なぜ相談なく処分されたのか」といった問題は、特別な品ほど発生しやすくなります。
こうした事態を防ぐには、事前の話し合いと、記録の共有が不可欠です。形見分けをする前に、誰がどの品に関心を持っているか、どう分けるのが公平か、という点をあらかじめ確認しておきましょう。形見分けが終わったら、「どの品を誰に渡したか」を記録に残しておくと、後からの誤解を避けることができます。
また、金銭的価値のある遺品(貴金属、骨董品など)については、形見ではなく相続財産として扱われる場合があります。こうした品については、感情だけでなく法律や相続の観点もふまえて判断しなくてはなりません。
5.遺品を処分する際の注意点
残す遺品を決めたあとに向き合うのが、「残さないものをどう処分するか」という問題です。こちらでは、親の遺品の処分方法と注意点をご紹介します。
法的・税的に重要な遺品の取り扱いを知っておく
前述のように、遺品の中には、法律や税務上の手続きが必要な相続財産もあります。相続財産には、現金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も全て含まれます。勝手に相続財産を処分した場合、以下の大きな影響が考えられます。
・「遺産隠し」とみなされ、他の相続人とのトラブルになる可能性
・相続する意思があると見なされ、相続放棄ができなくなり、故人様が残した借金などの「マイナスの財産」を全て相続しなくてはならなくなる可能性
手続きの中には期限付きのものもありますので、処分の前に、名義や手続きの有無をしっかり確認しましょう。
捨てる場合のルールとマナーを守る
遺品を捨てる際は、自治体のルールに従って正しく分別しましょう。特に「家電リサイクル法」の対象となるテレビ・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどは、指定引取所への持ち込みやリサイクル料金を支払わなくてはなりません。ルールを守らず誤った方法で処分してしまうと、罰則の対象になることもあるため注意が必要です。
売却を検討する
貴金属・ブランド品・骨董品・カメラ・美術品・古書などは、売却するのもひとつの方法です。ただし、遺品ひとつの売上金額が30万円を超えた分に対しては所得税がかかりますので、不安な場合は専門家に一度相談することをおすすめします。
6.親と進める生前整理|遺品で困らないための準備
親の遺品整理は亡くなってから始めるよりも、生前のうちから少しずつ進めておくことで、心や体の負担を大きく減らすことができます。とくに、親自身の意志や希望を反映させながら整理ができていれば、「本当にこれでよかったのだろうか」と迷うことも少なくなるでしょう。
とはいえ、「そろそろ生前整理を始めてほしい」と切り出すのは、なかなか勇気がいるものです。そんなときは、「昔のアルバムを一緒に見ようか」「思い出話を聞かせて」など、前向きな会話から始めると、自然と整理につながっていきます。
身の回りの物を一緒に見直していく中で、「これは大切に取っておきたい」「これはもう手放してもいいかな」と、親自身が気づくきっかけにもなります。
こうした生前整理は「終活」のひとつであり、取り組む方の人生を充実させるためだけでなく、残されるご家族の負担を減らす活動として近年注目を集めています。お互いが納得して過ごせるよう、「親への終活の切り出し方とサポート」を参考にぜひ進めてみてはいかがでしょうか。
7.残した遺品の保管と生かし方|思い出を未来へつなぐ方法
遺品は、ただ残すだけでなく、「どう保管するか」「どう活かすか」という視点を持つことで、故人様の思い出を未来につなぐ手段となります。
ここでは多様な方法を通じて、親の遺品を日々の暮らしに生かす考え方をご紹介します。
遺品の保管・手入れの基本
遺品を長く大切に保つためには、正しい保管方法を知ることが大切です。特に衣類・写真・紙類・木製家具などは、湿気や虫、日光による劣化が起きやすいため、環境を整える工夫が求められます。
衣類の場合は、洗濯・陰干しをしてから通気性のある袋や箱に収納し、防虫剤や乾燥剤を併用すると効果的です。湿気がこもらないよう、押し入れやクローゼットに入れたままにせず、定期的に空気を通すことも忘れないようにしましょう。古い写真や手紙も、除湿剤と一緒に、直射日光のあたらない風通しのよい場所に保管すると劣化を防ぎやすくなります。
リメイクして残す
遺品をただ保管するだけでなく、以下のようにリメイクして形を変える方法もあります。
・母の着物をバッグに仕立て直す
・父の鞄をブックカバーに作り替える
・ブローチをネックレスやお守りに作り替える など
こうした方法は、故人様の面影を日常の中に自然に取り入れることができる、あたたかな工夫です。同じ素材から複数のアイテムを作り、ご家族で分け合うのもよいでしょう。遺品を「過去のもの」としてしまうのではなく、「これからも一緒に生きていく存在」として大切にしていくことで、心にも前向きなつながりが生まれていくかもしれません。
デジタルで保存する
写真やビデオテープ、大型の家具など、そのまま保管するのが難しいものについては写真に撮ってデジタルで保存するという方法もあります。こうすることで、「省スペース」「劣化防止」「家族間での共有」が実現できるでしょう。
ただし、家族間で共有する際は外部の人が閲覧できないよう、パスワードをつけるなどの工夫が必要です。
故人様の価値観を受け継ぐ
「愛用していた料理道具で故人様のレシピを再現してみる」「故人様の釣り竿を使ってよく行っていた海辺で実際に釣りをしてみる」──このように、形だけでなく「想い」や「姿勢」を行動として受け継ぐことも、大切な供養の一つです。
また、手帳や日記に残された言葉や記録を読み返す中で、「こんなふうに考えていたんだ」「こんな優しさがあったんだ」と、新たな一面に気づくこともあります。そこから、自分自身の生き方や人との向き合い方を見直すきっかけになることもあるでしょう。
遺品は、単なるモノではありません。その中には、故人様の価値観や人生の軌跡が込められています。モノにやどる想いを感じ取りながら、日々の暮らしの中で少しずつ実践していくことで、遺品があなたの人生にあたたかく寄り添ってくれるかもしれません。
8.親の遺品と残すものに関するFAQ
A.「デジタル遺品」と言って、整理が必要になります。
「デジタル遺品」とは、故人様のパソコンやスマートフォンに入っている情報や、ネット上に登録されている個人アカウントなどを指します。つまりそれも「遺品」としてご遺族が整理し、「残すもの」と「消去するもの」に分けなくてはいけません。
ただしデジタル遺品の多くはパスワードで管理されています。故人様が生前のうちにアクセス方法を残していなかった場合、作業は難航するでしょう。デジタル遺品の中にはネット銀行や電子マネーなど、財産価値のあるものもあり、ご遺族がアクセスできないと相続できないといった問題も発生します。
A.その後の手続きで必要になることもあるため、残しておきましょう。
ご家族が亡くなった後に行う手続きは、多岐に渡ります。手続きにはさまざまな書類が必要となり、内容によっては健康保険資格確認書やマイナンバーカードが必要になる可能性もあります。そのため、故人様の本人確認書類にあたるものはすぐに処分せず、保管しておくようにしましょう。
A.遺品整理業者、弁護士、司法書士、葬儀社などが挙げられます。
親の遺品整理に関する悩みは、大きく分けて次の3つに集約されます。
・精神的、体力的な負担を減らしたい
・相続や税金に関する手続きを知りたい
・遺品をめぐる親族間のトラブルを解決したい
こうしたお悩みに対しては、遺品整理業者や司法書士、弁護士などがそれぞれの分野でサポートしてくれます。ただし、「遺品整理の実務」と「相続税に関する相談」は別の専門家に依頼する必要があるため、相談先が複数に分かれ、負担に感じることも少なくありません。
これらの課題をまとめて相談できる窓口として、葬儀社を活用する方法もあります。信頼できる葬儀社であれば、必要に応じて各専門家とも連携しながら、スムーズな対応をサポートしてくれるでしょう。
A.間取りによって異なりますが、3~20万円以上が目安です。
遺品整理業者には「遺品の仕分け」「処分」「家の簡易清掃」「遺品の査定・買い取り」を主に任せることができます。その費用は間取りによって異なり、例えば1Kなら3万円から、4DK以上なら20万円からが一般的な目安です。
実際の金額は間取り以外にも「遺品の量」や「家の所在地」などによっても異なりますので、相見積もりを取って比較することをおすすめします。詳しくは「遺品整理の費用」をご覧ください。
9.親の遺品整理で残すものはゆっくり・焦らず判断を
親の遺品整理は、深い悲しみと向き合いながら進めるとても繊細な作業です。物の量が多いほど心身への負担も大きくなり、「残すべきか」「処分してもよいか」と迷ってしまう場面も少なくありません。
そのようなときは、一人で抱え込まず、ご家族や親しい人、あるいは専門家に相談してみることも大切です。誰かと気持ちを共有することで、少しずつ心が整理されていくこともあります。
遺品整理に明確な期限はありません。焦らず時間をかけて、「どんな思いを受け継ぎたいか」を考えながら進めていくことで、きっと納得のいくかたちで大切な品々を残すことができるでしょう。
遺品整理や生前整理に関するお悩みは、花葬儀でも承っております。弁護士や司法書士と提携し、一般的な遺品整理に関する問題から、専門的なものまで幅広くサポートいたします。ご相談には会員限定で使えるお得なチケットやイベントのご案内などの特典がつく「リベントファミリー」へのご加入がおすすめです。この機会にぜひご検討ください。