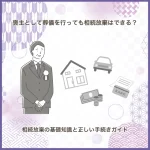親が危篤と告げられたとき|家族がとるべき行動と心の備え
- 作成日: 更新日:
- 【 相続の基礎知識 】
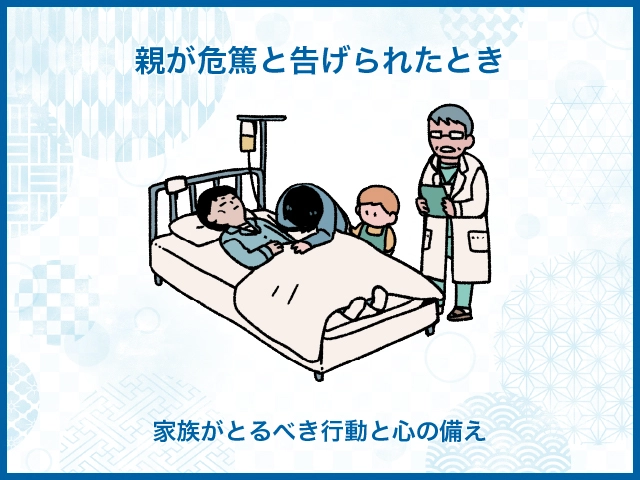
「親が危篤である」と告げられたとき、冷静でいられる人はほとんどいないでしょう。突然その知らせを受けた家族にとっては、「何をすればよいか」「誰に伝えればよいか」「どう過ごせばいいか」がわからず、混乱してしまうのも無理のないことです。
今回の記事では、「親が危篤」と伝えられたときにまず知っておきたい基礎知識から、直後の対応、最期の時間の過ごし方などを解説します。ご家族の心を守り、後悔をできるだけ減らすための考え方についても丁寧にご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
1.親が危篤と告げられたら?知っておきたい基礎知識

「危篤」と宣告されることは、ご家族にとって非常にショックな出来事です。しかし、言葉の意味や診断の背景を理解しておくことで、次に何をすべきかが次第に見えてきます。こちらでは、「危篤」の基本的な意味や、危篤と告げられた際のご家族の心構えについてご紹介します。
危篤とはどのような状態か?
「危篤」とは、「死が目前に迫っており、回復の見込みが非常に低い状態」を指します。医師から危篤を告げられたご家族は、心の準備をするとともに、可能な限りの行動をとる必要があります。
ただし、「危篤=すぐに亡くなる」ではありません。実際には、危篤と告げられてから数時間後に亡くなってしまうこともあれば、数日〜数週間持ちこたえることもあります。また「重篤(じゅうとく)」という用語と混同されがちですが、重篤は「状態が著しく悪い状態」を指す言葉であり、必ずしも死が近いという意味ではありません。
危篤を告げられたときの心構え
告知を受けた瞬間、動揺や戸惑いが生じるのは当然のことです。しかし、混乱したまま行動を起こすと、取り返しのつかないミスにつながる可能性もあります。
まずは深呼吸をして、できるだけ心を落ち着け、頭を整理することが大切です。次に、医師からの説明を逃さず受け取る姿勢を持ちましょう。容態や今後の見通しなどを確認し、曖昧な点を残さないよう努めることで、次に何をすべきか冷静に判断することができます。
2.親が危篤と告げられた直後にすべき対応
親が危篤であると診断されたら、以下の対応を迅速に行いましょう。
親の居るところに向かう
まず最優先すべきは、「親の居るところまで向かう」です。多くの場合、危篤を告げる医師からは「できるだけ早く来てください」と言われるため、時間との勝負になります。
病院や介護施設など、親のもとに駆けつける際の持ち物としては、以下が挙げられます。
・身分証明書(病院の受付や身元確認に必要)
・現金、交通系ICカード(タクシーや公共交通機関を利用する場合)
・携帯電話と充電器
・着替え(泊まり込みの可能性も想定)
・メモ帳、筆記用具(医師の説明や連絡事項の記録)
移動は公共交通機関やタクシーなどの利用をおすすめします。やむを得ず運転する場合は「冷静に運転する」「事故を起こさない」ことが重要です。緊急時ほど事故が起こりやすいため、安全を第一に行動しましょう。
ご家族・ご親族に連絡する
親の居るところまでの移動と並行して、危篤をご家族・ご親族に伝えることも重要です。全員に個別連絡をしていると時間がかかってしまうため、連絡役を一人決め、その人がまとめて情報共有できるようにすると混乱を防ぐことができます。
連絡の際には、以下の情報を簡潔に伝えましょう。
・誰が危篤か
・現在の親の所在地
・来られる場合の交通手段
・危篤の連絡を回してしてほしい相手 など
勤務先や学校に連絡する
ご自身が働いている場合は、勤務先にも速やかに連絡しましょう。危篤は「家族の重大な緊急事態」に該当するため、多くの職場では休暇や早退が認められています。可能な限り電話で連絡を入れ、今後の業務について直属の上司と相談しましょう。代理対応や引継ぎについても簡単に伝えられると、相手側もスムーズに動くことができます。
お子様がいる場合は、通っている学校にも連絡が必要です。お子様の欠席・遅刻の連絡とともに、担任の先生に現在の家庭の状況を伝え、お子様の心のケアについて協力を仰ぎましょう。
なお、危篤時の休暇の取り扱いについては、「親の危篤に関するQ&A」でも解説しておりますので、そちらもご覧ください。
葬儀社・菩提寺などに相談し葬儀の準備を進める
危篤の段階で葬儀の準備を進めることに、後ろめたさを感じる方も多くいらっしゃいます。しかし、いざという時に慌てないためにも、事前に段取りをしておくことは非常に重要です。「菩提寺(※1)はあるか」「互助会(※2)に入っているか」などの基本的な情報を、ご親族に確認しておきましょう。
具体的な葬儀社の選び方など、ご家族で話し合うべき詳細については、後の「臨終の前に家族で話し合っておきたいこと」で詳しく解説しています。
(※1)ぼだいじ。先祖代々がお世話になっている縁の深い寺院。
(※2)冠婚葬祭に備えてお金を積み立てていくサービス。加入していると、積立金に応じたプランを利用することができる。
3.親との最期の時間をどう過ごすか|後悔しないための接し方
危篤状態の親と過ごす時間は、短くても心に深く刻まれるものです。言葉が交わせない状態であっても、耳や肌で感じる刺激は、最後まで感覚が残るとされます。「育ててくれてありがとう」「心配しなくて大丈夫だよ」と語りかけながら体に触れることで、想いが届くかもしれません。
もし、声かけが難しい状態である場合は、衣類の乱れや布団を整えてあげましょう。そのような行為も、心を通わせる大切な時間となります。
4.臨終の前に家族で話し合っておきたいこと
親が危篤の場面では、感情が大きく揺れ動く中で、慌ただしく過ごすことになります。事前にご家族間で方針を共有しておくことで、後々の後悔や混乱を防ぐことができるでしょう。
親が臨終を迎える前に、ご家族間で話し合っておくべきことをご紹介します。
葬儀の形式や希望
葬儀を執り行うためには、形式や会場、参列者の範囲など、さまざまな項目を決めなくてはなりません。いざ亡くなってからでは考える時間が足りず、後悔の残るお別れになってしまう可能性もあります。
ご家族内で以下の項目について相談しておくと、その後の準備がスムーズになるでしょう。
・喪主様を誰にするか
・葬儀形式(一般葬、家族葬、一日葬など)
・参列者の規模
・おおまかな予算
・葬儀費用を誰が負担するか
また、親が葬儀に関する希望を残している場合は、その意志を尊重することが大切です。記録がない場合は、喪主様となる方を中心に、方針を決めていきましょう。
病院から葬儀社を紹介されることもありますが、よく考えずに決めてしまった結果、後悔することも少なくありません。「信頼できる葬儀社の選び方」を参考に、不安や悲しみに寄り添ってくれる葬儀社を探しましょう。
財産や相続に関する基本的な確認
この段階で遺産の詳細を話し合う必要はありませんが、財産や相続に関する手続きには期限が設けられているため、以下の基本的な情報を押さえておくと安心です。
・遺言書の有無
・誰が中心となって手続きを進めるか(代表者の決定)
・法定相続人の確認
5.臨終後すぐに必要な対応と葬儀準備の流れ
別れの時が訪れた直後にも、ご家族は迅速な対応を求められます。まずは早急に葬儀社に連絡を取り、お体を搬送する手配が必要です。こちらでは、葬儀社への連絡以外に行うべき対応と、臨終後の基本的な流れを具体的に解説します。
医師による死亡確認と死亡診断書の受け取り
臨終を迎えて最初に行われるのが医師による死亡確認です。確認が終わると、「死亡の日時」「死亡の原因」などの情報が記載された「死亡診断書」が発行されます。この死亡診断書は、その後の火葬や埋葬を始め、各種手続きに必要となりますので、大切に保管しましょう。コピーを5部ほど取っておくと役立ちます。
なお、死亡診断書の発行は医療費控除の対象外であり、3千円~1万円ほどの費用がかかります。詳しくは「死亡診断書の料金はいくら?」をご参照ください。
ご親族・関係者への訃報連絡
ご家族、ご親族、会社関係者などに訃報を伝えます。以下の内容を明確に共有できるようにしましょう。
・亡くなった人
・亡くなった時間
・亡くなった理由
・故人様、ならびに連絡をしている人が今どこにいるのか
菩提寺がある場合は、僧侶にも訃報をお伝えしましょう。
故人様の搬送・安置
病院や高齢者施設などで亡くなられた場合、故人様を一定時間内に搬送する必要があります。搬送先は「ご自宅」もしくは「安置所」が一般的です。葬儀社のスタッフがお迎えにあがり、葬儀社のスタッフまたは看護師が故人様にエンゼルケアを行った後、搬送します。
葬儀社との打ち合わせ
故人様を安置したら、葬儀社と打ち合わせを行います。相談内容は主に以下の通りです。
【葬儀形式について】
一般葬、家族葬、一日葬、火葬式 など
【葬儀の規模や日程について】
葬儀日程、場所、参列者の規模、喪主様の決定、宗教宗派の確認 など
【葬儀の内容について】
祭壇や花、会葬礼状や訃報連絡、斎場内の装飾、会食、返礼品、遺影写真、位牌、参列者の移動手段、初七日法要の有無 など
【その他】
見積もりの確認、次回の打ち合わせのスケジュール、今後の流れの確認 など
大切な人を亡くした直後は気が動転しているものです。メモを取ったり、2人以上で打ち合わせに参加したりすることで、聞き逃しを防ぐことができるでしょう。
死亡届の提出
役所に死亡届を提出します。死亡届は、医師からもらう死亡診断書とセットになっていることが多いため、個別で用意する必要はありません。死亡届を提出する際には、火葬・埋葬に必要な「火葬許可証」も一緒に申請します。
死亡届の提出は、死亡を知った日から7日以内と定められており、正当な理由なく遅延すると5万円以下の過料が科される可能性があるため、ご注意ください。また、死亡届以外にも期限が設けられている手続きがあります。「死亡後に行うべき手続き」に目を通しておくと、おおまかなスケジュールが把握でき、落ち着いて行動しやすくなるでしょう。
出典:戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)(令和7年10月1日 施行)
https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000224#Mp-Ch_4-Se_9-At_86
通夜・葬儀当日
通夜、葬儀を執り行います。近年は火葬場が混雑していることから、亡くなってから葬儀までに1週間ほどかかることもあります。通夜、葬儀の具体的な流れは「死亡後の葬儀の流れ」にてご紹介しておりますので、参考になさってください。
6.親の危篤から看取り後の心の整理方法
親が危篤状態になってからは、気持ちが乱れる中、非常に慌ただしく過ごすことになります。葬儀や手続きを終えた後、ご家族の心には深い疲労や後悔の気持ちが残ることもあるかもしれません。こちらでは、そうした思いとどのように向き合い、心を整えていくかについてご紹介します。
「もっと話せばよかった」と後悔する場合
親が危篤と告げられた後、「もっと話しておけばよかった」「感謝の気持ちを伝えきれなかった」と、ご自身の言動を振り返って後悔する方は少なくありません。そのような気持ちを和らげ、心の整理を進める手段として、「想いをかたちにする」という方法があります。
たとえば、手紙を書くという行為は、自分の心と向き合い、伝えきれなかった気持ちを丁寧に言葉にする時間になります。「育ててくれてありがとう」「もっと一緒に過ごしたかった」など、率直な思いを自由につづることで、落ち着きを取り戻すきっかけになるかもしれません。
手紙は必ずしも誰かに見せる必要はなく、写真と一緒に保管するだけでも、その人とのつながりを実感できるようになるでしょう。
また、写真や動画を見返すのも効果的です。ご家族と一緒に思い出を振り返る時間を持つことで、悲しみの中にある温かな記憶がよみがえり、「一緒に過ごせたことへの幸福や感謝」を実感できるようになります。
最期の場に間に合わなかった場合
親の危篤を知り急いで駆けつけたものの、最期の瞬間に立ち会えず、強い後悔や罪悪感が残ることもあります。しかし、間に合わなかったことが、親不孝というわけでは決してありません。命の最期のタイミングは予測できず、医療現場でも容態の急変は日常的に起こります。
大切なのは、それまでの関係性や想いの積み重ねです。日常の中で交わされた優しさや気遣いは、あなたの親にとってかけがえのない贈り物だったはずです。最期の瞬間に立ち会えなかったからといって、その想いが届いていないわけではありません。
また、人によっては「誰にも見られずに静かに旅立ちたい」と願うこともあります。「もしかしたら周りに辛い思いをさせないよう、ひとりで旅立つ道を選んだのかもしれない」と受け止めることで、気持ちが少し楽になることもあるでしょう。
亡くなった後の後悔や悲しみを和らげるには、「今からできること」に目を向けるのもひとつの方法です。「仏壇に手を合わせる」「好きだった花や食べ物を供える」「故人様の言葉を日々の中で思い出す」なども深い想いの表れであり、親とのつながりを今も大切にしている証です。
焦らず、ご自身のペースで心を整えていくことが、穏やかな日々への第一歩となるでしょう。
辛いときには専門家に頼る
辛い気持ちは一人で抱え込まず、時には専門家に頼ることも必要です。大切な人を失った悲しみからくる精神的・身体的不調(グリーフ)を軽くするケア全般は「グリーフケア」と呼ばれ、多くの支援団体、相談先があります。詳しくは「グリーフケアとは?」の記事をご覧ください。
7.親の危篤に関するQ&A
A.忌引き休暇の対象にはならないことが一般的です。
「忌引き休暇」とは、ご家族が亡くなった際に取得する休暇を指します。法律で定められている休暇ではないため、休暇扱いになるご家族の範囲や休暇の日数は会社によって異なります。
危篤状態では、忌引き休暇の条件である「家族の死亡」ではないため、有給休暇扱いになることが一般的です。詳細は勤めている会社に直接確認することをおすすめします。
A.故人様にとって近しい関係の方には、すぐに連絡することをおすすめします。
危篤は命の危険が迫った緊急の状況であり、できるだけ早く関係者に連絡することが大切です。親から見て三親等程度までのご親族には、早朝や深夜であってもためらわずに連絡するのが望ましいとされています。特に親しい関係であれば、早めに知らせることで、看取りの時間を共有できる可能性が高まります。
ただし、長く交流がなく疎遠になっているご親戚については、状況や故人様の希望、ご家族の判断をもとに、連絡の有無を検討してもよいでしょう。いずれにしても、ためらいが判断の遅れにつながらないよう、冷静に、そしてできるだけ早く行動することが大切です。
A.事前の確認や面会先での配慮は心がけましょう。
親が危篤と知らされ、子どもを連れて行ってよいか迷う方もいますが、基本的には問題ありません。お子様にとっても、大切なご家族とお別れの時間を過ごすかけがえのない時間となります。
ただし、病院や施設によっては年齢制限や面会制限があるため、事前に確認が必要です。また、お子様には年齢に応じた説明を行い、安心できるよう配慮しましょう。年齢が低いお子様には、静かに過ごせるよう絵本やおもちゃを準備しておくと安心です。
8.親が危篤の時は冷静な行動を心がけることが後悔を減らすカギ
親が危篤と知らされた瞬間、心は大きく揺れ、冷静な判断が難しくなります。しかし、その時こそ「何を優先すべきか」「何を伝えたいか」を意識して行動することが、ご自身やご家族の心の負担を減らす助けになります。今のうちから必要な情報や心構えに触れておくことで、納得のいく決断ができるようになるでしょう。
大切なご家族の「もしもの時」は、花葬儀まで至急ご連絡ください。早朝、深夜に関わらず、経験豊富なスタッフがお客様の心強い味方としてサポートいたします。お急ぎのご用命はフリーダイヤル、もしくは「お急ぎの方へ」をご覧ください。