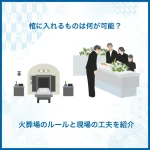家族葬にはデメリットもある?事前に考えておくべきことは?
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

葬儀で故人様と縁の深い方だけが参列する「家族葬」という形式の葬儀があります。最近は注目度が高まっており、選ばれることも増えていますが、もちろんメリットだけでなくデメリットも存在します。そこで今回は、家族葬のメリット・デメリットに注目して、家族葬を営む際、事前に考えておくべきことをご紹介いたします。
1.家族葬のメリット
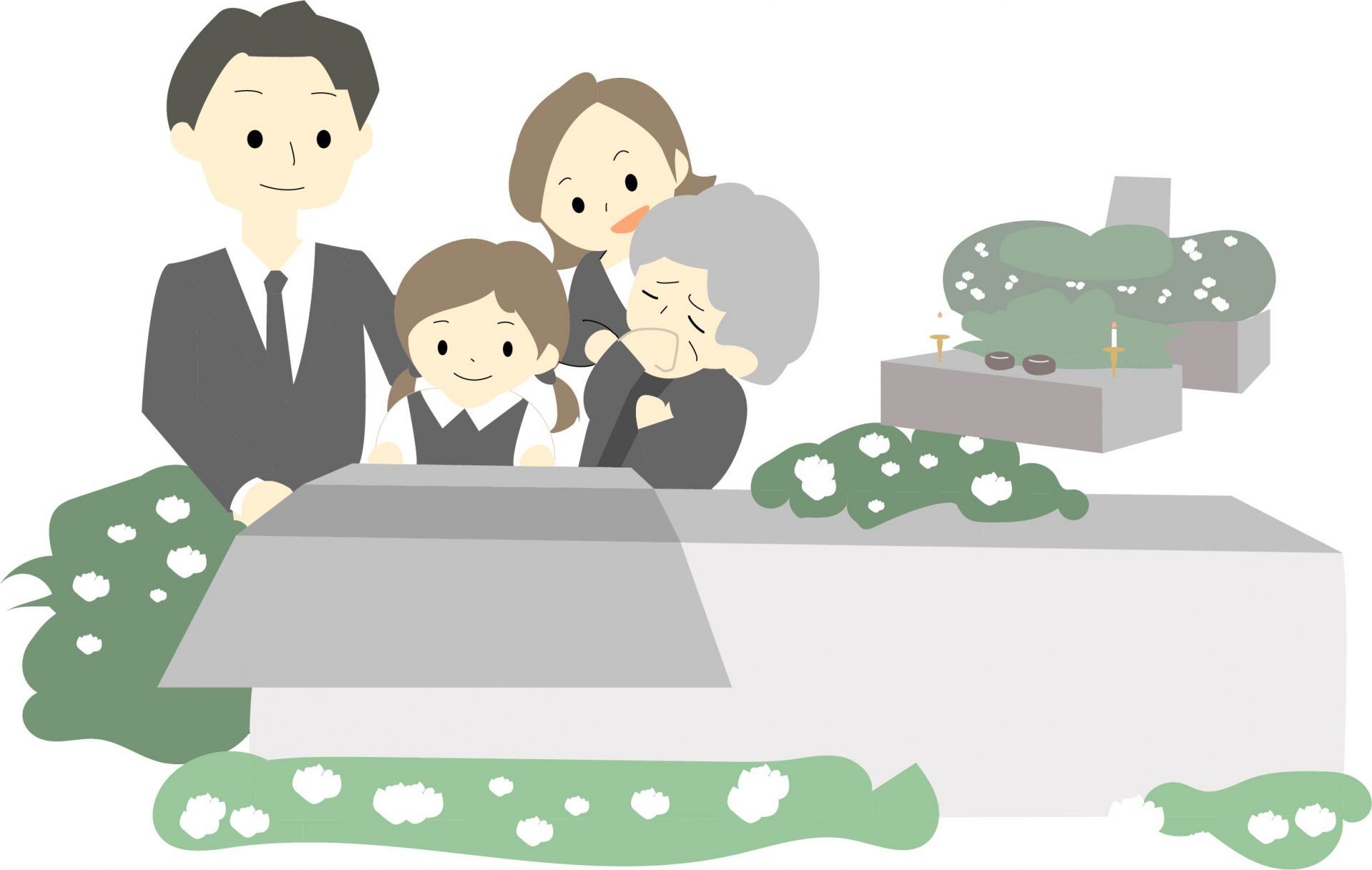
まずは家族葬のメリットについてふれてみましょう。
ご家族や親しい人だけでお別れができる
家族葬は、一般葬ほど多くの方を呼びません。ですので、ご家族をはじめ、故人様と親しい方だけでお見送りをすることができます。ご参列者が顔なじみの方であることと、参列者も少なくなれば、故人様とゆっくりお別れをする時間が長くとれるというメリットがあります。
時間と負担を抑えられる
一般葬はご参列者が多く、挨拶や接待への時間や負担が大きくかかることが多いようです。しかし、規模が小さく顔なじみの方が多い家族葬は、ご参列者への挨拶まわりも少なくなるほか、必要以上に気を遣うことがないため心身の負担も軽くなります。
自由度が比較的高く「故人様らしいお見送り」ができる
故人様ご本人やご家族が葬儀に対する「こうしたい」といったご希望をお持ちでも、ご参列者の多い一般葬では世間体を意識して反対意見が出てしまい、ご希望を叶えづらいことがあるかもしれません。その点、家族葬のご参列者は顔なじみの方が中心のため、ご希望は通りやすくなるでしょう。故人様らしさを演出する例として、思い出の曲や写真を披露したり、ご愛用品を飾るなど、生前の思い出をなつかしめる葬儀ができるのも家族葬ならではのメリットで、故人様をよくご存じの方だけが集まるご葬儀だからこそできる演出だといえます。
2.家族葬のデメリット
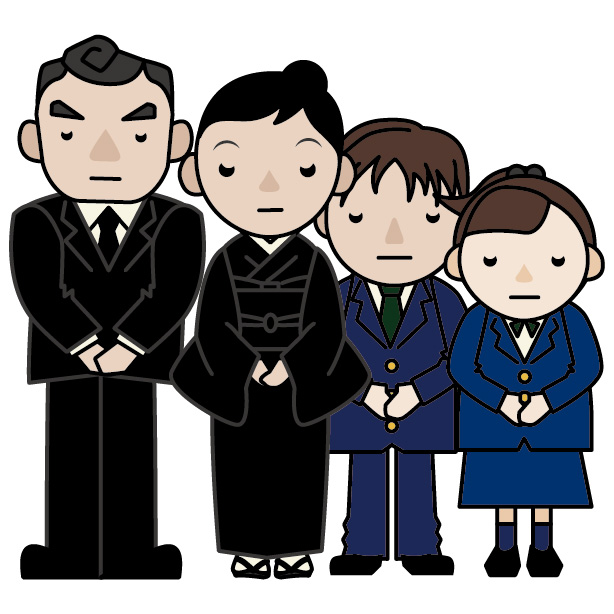
続いて、家族葬のデメリットにはどのようなものがあるのか見ていきましょう。
参列者の親等範囲で揉めるおそれがある
ご本人の両親、お子さま、お孫さまなど、血縁関係の深さによって親等が異なりますが、家族葬に参列する範囲は、故人様の二親等くらいまでとされています。ただし、家族葬に「○親等までお呼びする」という決まりはありません。家族葬の基本的なスタンスは、「故人様とそのご家族がお呼びしたい方を呼ぶ」というものです。
そのため、家族葬のデメリットとしては、葬儀に呼ばれなかったことに対するご親族からの不満の声があげられます。葬儀後にトラブルを起こさないためにも、ご親族には忘れず連絡を入れ、参列をご遠慮いただきたい旨をしっかり伝えるようにしましょう。
「家族葬」を知らない
注目度が高まっている家族葬ですが、そもそも家族葬を知らない、または根づいていない地域も多く残っています。従来の一般葬でのお見送りが定着している地域では、ご参列者を故人様とごく親しい方に絞るという家族葬の考え方を理解してもらえないということも、少なくありません。地域によっては受け入れらない可能性があるというのも、家族葬のデメリットと言えるでしょう。
費用がかかっても香典収入は期待できない
ご参列者の少ない家族葬では、人数に応じて変動するご飲食代や会葬御礼などを抑えることができます。しかし、式場や火葬場の利用料などは、規模に関係なく一定の費用がかかります。小規模で行う家族葬は、ご参列者が少ない分、お香典の収入が見込めません。つまり、お香典で出費をカバーすることができないため、最終的な葬儀費用を自分たちで負担しなければならないデメリットもあります。
3.家族葬で事前に考えておくべきことは?

初めて家族葬を営む場合、メリット・デメリットを把握しておくことはもちろん、家族葬をスムーズに進めるためには、以下の4つのポイントについて事前に考えておくことをおすすめします。
訃報を連絡する範囲とその方法
訃報を連絡する範囲は、お伝えする必要のあるご親戚やご友人、職場関係者へ順に行うとよいでしょう。ここでは家族葬に参列をお願いする方と、そうでない方への連絡方法をまとめました。
参列をお願いする方への連絡方法
参列をお願いする方へは、まず電話で伝えましょう(つながらない場合は、メールなどで補ってもかまいません)。葬儀の日程や場所などの詳細は、決まってから改めて通知します。このときは、手紙、メールなども多く使われています。そのさい、以下の3点を伝えるようにしましょう。
【お伝えすること】
・誰の訃報なのか
・葬儀の日程と場所
・お香典、供花などを辞退すること(辞退する場合のみ)
・喪主様のお名前とご連絡先
参列をお願いしない方への連絡方法
参列をお願いしない方へは、基本的に事後連絡でかまいません。葬儀後3日~1週間ほどの時期に、書面で次の事柄をお伝えします。もし、先方から訃報を聞きつけて連絡が来た場合は家族葬で内々に済ませる旨をお伝えするとよいでしょう。
【お伝えすること】
・誰の訃報なのか
・葬儀を近親者のみで行うこと(終えたこと)
・お香典、供花などを辞退すること(辞退する場合)
・連絡が遅くなってしまったことのお詫び
・生前の故人様へのご厚意に対する感謝の気持ち
お亡くなりになった時期が年末の場合、新年の挨拶を辞退する喪中の連絡とともにお知らせすることもできます。また、近隣の方には町内会の班長に連絡を入れ、町内回覧で訃報をお伝えするとよいでしょう。
お香典、供花などの辞退について
「ご参列者には、必要以上の金銭的な負担をかけたくない」などの理由で、お香典や供花などを辞退することも多いようです。
これらを辞退することは、失礼にはなりません。周囲の方が誤って用意しないよう、訃報の連絡時に「お香典やお供花は辞退させていただきます」と、辞退の意思をしっかり伝えるようにしましょう。
どんな家族葬でお見送りするのか
考える余裕は少ないかもしれませんが、故人様の遺言やご家族の希望などによって、家族葬はご家族の数だけいろいろなお見送りがあります。故人様と過ごす最後の瞬間をどのように表現して送り出してあげたいかを考えることが、後悔のないお見送りにつながります。
葬儀社はどこにするか
納得のいく葬儀をするためにも、葬儀社選びはとても重要です。相談者ご自身が『信頼できる』と感じるかに尽きるでしょう。それを見極めるポイントは、必要な時にいつでも寄り添った相談にのってくれるかどうかです。
寄り添った対応ができる葬儀社を見極めるポイント
・こちらの希望や心情を理解し、寄り添ってくれる姿勢があるか。
・希望する葬儀に具体的な提案をしてくれるか。
・見積り料金の提示など、葬儀前に費用をしっかり把握させてくれるか。
などです。葬儀社選びに悩まれたときはこれらを確認してみるとよいでしょう。
4.家族葬のメリット・デメリットに関するQ&A
A.故人様の意志を尊重しつつ、ご家族の気持ちに配慮できる方法を一緒に考えることが大切です。
葬儀は故人様の人生に敬意を示し、心を込めてお見送りをする大切な儀式です。故人様が明確な希望を残していた場合は、その意思をできる限り尊重することが望ましいでしょう。
一方で、ご家族が「より多くの人に参列してほしい」「火葬式の方がよい」など別の考えを持たれている場合もあります。
両方の想いを大切にするために、例えば式は家族葬の形式で行い、後日お別れの会を開く、あるいは火葬式を選びつつ家族でお別れの時間を設けるなど、双方の意向を調整できる方法を検討されてはいかがでしょうか。
故人様の想いとご家族の気持ちのどちらも大切にすることで、皆が納得のいくお見送りがしやすくなるでしょう。
A.自宅で行う家族葬のメリットは「時間を気にせずお見送りができる点」、デメリットは「近所への配慮が特に必要になる点」などが挙げられます。
住み慣れた自宅で行う家族葬には、「時間に左右されずゆっくりとお別れが可能」「会場を利用しないぶん、費用を抑えやすい」「故人様との思い出がつまった住み慣れた場所で、ご遺族が落ち着いて故人様と過ごせる」といったメリットがあります。
一方でデメリットには、「ご遺族による準備や片付けの負担が大きくなりやすい」「自宅の広さや間取りによっては希望する演出が難しい」「参列者や車の出入り、読経の音などが近隣の迷惑になる可能性がある」などがあります。
葬儀の前後には、ご近所に対し挨拶や丁寧な説明を行い、理解を得ておくことでトラブルの防止につながるでしょう。近隣への挨拶マナーや注意点については「家族葬で必要な近所の対応」を参考になさってください。
A.トラブルを避けることにもつながりますので、デメリットもきちんと共有しましょう。
家族葬は「親しい人を中心とした葬儀が行いやすい」「ご遺族の負担が少ない」といったメリットが注目されがちですが、実際には「訃報を伝えなかった人から後で不満の声が上がった」「費用が思ったよりかかった」など、想定外のトラブルが起きることもあります。
メリットだけでなくデメリットも事前に話し合っておくことで、後悔や誤解を避け、家族全員が納得して故人様を見送ることができるようになるでしょう。特にご親戚や周囲との関係性を重視する方がご家族内にいらっしゃる場合は、形式だけでなく「誰に、どう伝えるか」まで具体的に共有しておくことが重要です。
5.まとめ
家族葬には、「故人様らしいお見送りをしやすく、死と向き合う時間を多くとれる」というメリットがある一方で、「周囲から受け入れられにくい場合がある」などのデメリットもあります。どんな形式の葬儀を選ぶかは、故人様がどのような希望を残していらっしゃったか、大人数で集まりづらいという世の中の事情など、いろいろな面を見て判断するようにしましょう。信頼できる葬儀社であれば、みなさまのご事情を考え、最適な形式を提案してくれるはずです。気軽に相談し、後悔の残らない葬儀をつくっていきましょう。