家族葬の基礎知識 ~場所選びからメリット・デメリット、注意点まで解説~
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

近年、「家族葬」という言葉を耳にする機会が増えています。しかし、一般的な葬儀とどのように異なるかがわからず、判断に迷うことも少なくありません。限られた時間の中で悔いのない選択をするためには、基本的な理解が不可欠です。
そこで今回は、家族葬を検討する際に知っておきたい基礎知識として、定義や場所の選び方、メリット・デメリット、注意点を解説します。これから家族葬をお考えの方や、家族葬の準備を進めている方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
1.家族葬の基礎知識1:家族葬とは?定義と一般葬との違い

家族葬とは、どのような葬儀なのでしょうか。こちらでは、家族葬の定義や一般葬との違いについて解説します。
家族葬の定義
家族葬という言葉に、法律などで定められた明確な定義はありません。一般的に、ご家族やご親族を中心に、故人様と特に親しかった方々のみを招いて故人様を見送る葬儀を指します。「家族」という名称が含まれていますが、必ずしもご家族に限定されるわけではなく、故人様が生前に親しくしていた友人や同僚を招くことも可能です。
ただし、葬儀社によっては「参列者が〇名以内であれば家族葬」「〇名以上は一般葬」など、参列者数を基準にしたプラン設定がされている場合もあるため、検討する際は葬儀社ごとのプランの条件や参列者の範囲を明確にしておきましょう。
家族葬と一般葬の違い
家族葬と一般葬の違いで最も大きいのは、参列者の範囲をご遺族の意向で限定するかどうかという点です。家族葬は参列者を限定するため、進行もご家族の意向に応じて自由に決めやすい傾向にあります。
一方、一般葬は参列者を制限せず、定型的な進行で執り行われるのが一般的です。参列者はご家族やご親族に加え、故人様と仕事や社会活動で関わりのあった方々、地域の知人なども含まれるため、規模は大きくなる傾向があります。
2.家族葬の基礎知識2:費用相場と内訳
2024年に鎌倉新書が実施した「第6回お葬式に関する全国調査」によると、家族葬の平均費用は約105.7万円でした。
平均費用の内訳は、以下のとおりです。
・葬儀費用:約72.0万円
・飲食費:約17.1万円
・返礼品代:約16.5万円
ただし、これらはあくまで平均であり、実際の費用は、会場や参列者の人数、葬儀の内容により大きく異なります。家族葬を検討する際は、必ず葬儀社に相談し、具体的な見積もりを提示してもらうことが重要です。
出典:第6回お葬式に関する全国調査(2024年)|株式会社鎌倉新書「いい葬儀」
URL:https://www.e-sogi.com/guide/55135/
3.家族葬の基礎知識3:家族葬を行う場所の選び方

家族葬をどこで行うかは、ご家族の意向や参列者の人数に応じて選ぶことが大切です。こちらでは、適切な場所を選ぶためのポイントと、斎場とご自宅、それぞれの特徴を解説します。
斎場で行う家族葬~公営斎場と民営斎場~
家族葬を斎場で行う場合、公営斎場と民営斎場のいずれかを選べます。公営斎場は自治体が運営し、民営斎場は葬儀社や企業が運営しています。
公営斎場と民営斎場は、運営主体が異なるため、主に次のような違いがあります。
【公営斎場】
・利用料金が比較的安い
・火葬場が併設されているため、移動の手間が省ける
・利用は地域住民に限定される場合がある
【民営斎場】
・設備やサービスの選択肢が豊富
・施設の規模や演出の自由度が高い
・利用料金は公営より高くなる場合がある
それぞれの特徴を踏まえると、費用を抑えたい場合は公営斎場、設備やサービスの充実度、演出の自由度を重視するなら民営斎場が選択肢となるでしょう。アクセスや施設の清潔感も重要な判断基準です。葬儀社と相談し、ご家族の希望や予算に合わせて適切な斎場を選びましょう。
自宅で行う家族葬(自宅葬)
自宅で行う家族葬は、故人様が住み慣れた場所で、ゆっくりとお別れの時間を過ごしたい方に適しています。
自宅で行う家族葬は、以下のような場合に適しています。
・式の時間や内容を自由に調整でき、ご家族の希望に合わせた進行が可能
・ご自宅で行うため、周囲の目を気にせず静かに故人様を見送ることができる
・故人様が長年暮らした場所で見送りができ、思い出を共有しやすい
ただしご自宅で行う場合、スペースの確保や駐車場の手配、隣近所など周囲への配慮が必要となるため、事前に葬儀社へ相談し、準備を整えておくことが大切です。
4.家族葬の基礎知識4:家族葬のメリット
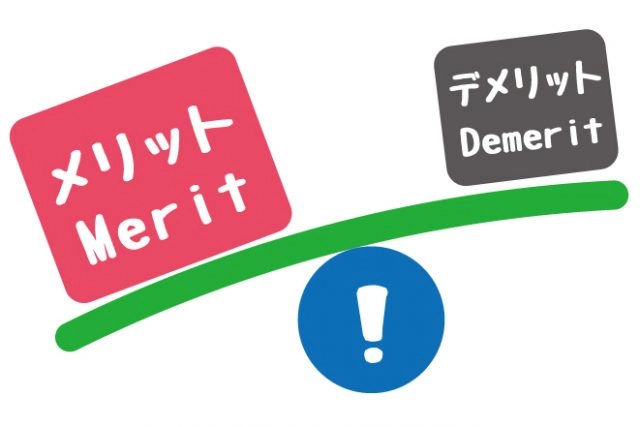
家族葬には、一般葬にはない特有のメリットがあります。家族葬を選ぶことで得られる主な利点を解説します。
プライバシーを守りやすい
家族葬は、ご家族や親しい人のみを招いて行うため、外部の関係者に知られることなく静かに進められます。故人様の思い出を気兼ねなく語り合え、周囲の目を気にする必要がありません。
悲しみに向き合う時間を大切にしたい方や、形式にとらわれずゆっくりとお別れしたい方にとって大きなメリットとなるでしょう。
肉体的・精神的な負担が生じにくい
家族葬は、参列者が少ない分、ご家族の負担も軽減できます。一般葬では、通夜や告別式に多くの参列者が集まり、挨拶や対応に時間と体力を要しますが、家族葬は気心の知れた人々のみに限定されるため、気を遣う場面が少なく、心身の負担を抑えやすいといえます。
故人とのお別れをゆっくり行える
一般葬は、参列者の挨拶や儀式が優先され、ご家族が故人様を見送る時間が限られることがあります。しかし、家族葬であれば、進行や時間配分を自由に調整できるため、故人様とのお別れの時間をしっかり確保できます。
葬儀の内容をご家族の意向に合わせやすい
家族葬は、ご家族の希望に合わせた自由な形式で葬儀を進めやすい点が大きな特徴です。会社関係者や地域の方など様々な立場の人が集まる一般葬では、どうしても「世間体」や「参列者への配慮」といった心理的な制約が働きます。
その点、家族葬であれば、より気兼ねなく故人様やご家族の希望を反映させやすいでしょう。
費用を抑えやすい
家族葬は、参列者を限定するため、会場費や飲食費、返礼品の費用を抑えやすい点が特徴です。
一般葬では、多くの参列者を想定し、大規模な祭壇や広い会場が必要になることがあります。しかし、家族葬はご家族や親しい方のみで行うことも可能であるため、会場使用料、参列者へお渡しする返礼品代、飲食代などを抑えやすいのです。
ただし、必ずしも一般葬より費用が安くなるとは限りません。特別な演出を取り入れるなど、ご希望の内容によっては費用が一般葬と同等か、それ以上になることもあります。
5.家族葬の基礎知識5:家族葬のデメリット

家族葬は、さまざまなメリットがある一方で特有のデメリットも存在します。家族葬の主なデメリットを解説します。
家族葬が理解されず誤解を招くことがある
家族葬は、地域やご親族によっては、理解してもらえないことがあります。特に伝統的な葬儀が根強い地域では、「なぜ招待されなかったのか」「葬儀らしくない」といった不満を抱かれることも少なくありません。
参列者の範囲で揉めることがある
家族葬は、どこまでの範囲の方を招くかで意見が分かれることがあります。たとえば、何親等までに限定するのか、故人様と親しかった友人を招くべきかなど、ご家族の考え方が異なることでトラブルが生じることもあります。
招待されなかった方への配慮が必要
家族葬は参列者を限られた人に絞るため、故人様と親しかった友人・知人が参列できなかった場合、寂しさや戸惑いを感じることも考えられます。家族葬であったことを丁寧に知らせ、「限られた人で静かに見送った」点を理解してもらう配慮が求められます。
お香典の辞退で費用負担が増える場合がある
家族葬ではお香典を辞退するケースが多く見られますが、その場合、葬儀費用はすべてご家族の負担となります。飲食費や返礼品代を抑えて葬儀全体の費用が安くなったとしても、お香典の辞退により、金銭面での負担が大きくなる場合があることも押さえておきましょう。
6.家族葬の基礎知識6:家族葬を行う際の注意点
家族葬を円滑に進め、トラブルを避けるには、事前の準備と配慮が欠かせません。家族葬を行う際、特に注意すべき点を解説します。
参列者の範囲を明確にする
家族葬は限られた方のみで行うため、「誰を招待するか」を明確に決めておくことが重要です。ご親族間で意見が分かれたときに備えて、家族葬に招待する参列者の基準を統一するとトラブルを避けられます。
訃報は参列の有無に応じて連絡方法を分ける
家族葬では、訃報を「誰に」「どのように伝えるか」が重要です。参列をお願いする方と、参列をお願いしない方とで、連絡方法やタイミングを分けることにより、誤解や混乱を避けられます。
【参列をお願いする方】
まず電話で連絡し、つながらない場合はメール等で次の情報を明確に伝えます。
・故人様の訃報
・葬儀の日程と場所
・お香典・供花の辞退(辞退する場合)
・喪主様の氏名と連絡先
日程が未定の場合は、「後ほど改めてご案内いたします」と添えると丁寧です。
【参列をお願いしない方】
家族葬の事後報告として書面を送るのが一般的で、次の内容を簡潔に伝えます。
・故人様の訃報
・家族葬で近親者のみにて執り行ったこと
・お香典・供花などを辞退する旨(辞退する場合)
・訃報が遅くなったことへのお詫び
・生前のご厚情への感謝の気持ち
お香典や供花の辞退を明確に伝える
家族葬では、お香典や供花を辞退するケースも増えています。辞退する場合は、意向を明確に伝えることが大切です。参列者が用意してしまわないよう、訃報連絡時に「お香典、供花は辞退いたします」と伝え、当日も受付でその旨を表示しておきましょう。
宗教儀礼や地域の慣習を軽視しない
家族葬は、ご家族の意向を反映させやすいことが利点ですが、その自由さが思わぬトラブルを招く可能性もはらんでいます。ご家族の判断だけで宗教や地域のしきたりを軽視してしまうと、お付き合いのある菩提寺(ぼだいじ)から納骨を断られてしまう、といったケースも実際に起こり得ます。
菩提寺がある場合は、読経を依頼するかどうか、戒名を誰が授けるかといった点をあらかじめ確認・相談しておきましょう。地域によっては、伝統的な葬儀を当然とする考えが根強いこともあるため、家族葬を選んだ理由を丁寧に伝え、理解を得ることが大切です。
葬儀費用と追加料金を事前に確認
家族葬は一般葬に比べて費用を抑えられる項目もありますが、プランに含まれる内容と追加料金の有無を事前に確認しないと、想定外の出費が起こるかもしれません。見積もりの段階で、式場使用料、火葬料、返礼品、花祭壇の費用がどこまで含まれるかを把握するようにしましょう。
7.家族葬の基礎知識7:葬儀社選びのポイント

家族葬を成功させるためには、信頼できる葬儀社を選ぶことが重要です。家族葬を依頼する葬儀社を選ぶ際のポイントを解説します。
スピーディーな対応が可能か
葬儀は突然の出来事であり、迅速に対応できる葬儀社であることが重要です。連絡を受けたらすぐに搬送を手配し、希望する形の家族葬に合った斎場を速やかに確保できるかが重要になります。葬儀の進行に関する質問にも迅速に回答でき、不安なく準備を進められるかがポイントです。
スタッフの対応が丁寧で信頼できること
家族葬は、ご家族や親しい方のみが集う、プライベートな葬儀です。そのため、ご家族とスタッフの距離が近くなり、スタッフの対応が葬儀全体の雰囲気に直結します。希望をしっかりと理解したうえで最適な提案をしてくれるかなど、信頼関係を築けるスタッフがいるかどうかが、非常に重要です。
事前相談を受け付けている
家族葬を満足のいく形で進めるには、事前相談を受け付けている葬儀社を選ぶことが欠かせません。柔軟に行いやすいからこそ、参列者の人数や範囲、祭壇のスタイル、進行方法など、ご家族の希望を具体的に伝え、希望に沿った提案が可能かを見極めましょう。
家族葬の実績が豊富
家族葬は、ご家族の希望に合わせた柔軟な進行が求められるため、実績が豊富な葬儀社を選ぶことが大切です。過去の事例や施行実績が多く、家族葬の進行に慣れている葬儀社であれば、参列者の範囲や香典辞退の伝え方といった、家族葬で起こりがちな悩みやトラブルにも的確なアドバイスをしてくれるはずです。
基本料金や追加費用が明確
費用負担を軽減したいと考えるご家族もいらっしゃるため、料金の明確さは特に重要です。家族葬の費用は葬儀社によって異なるため、基本プランに含まれる内容が明確で、祭壇や参列者の増加による費用も事前に説明されていることが理想です。料金体系がわかりやすい葬儀社であれば、後から予想外の費用が発生する心配もありません。
葬儀社選びについては、「家族葬を任せる葬儀社の選び方」でさらに詳しく解説していますので、希望に合った葬儀社を見つけるための参考にしてください。
8.家族葬の基礎知識を理解し、納得のいくお見送りを

葬儀のかたちは、時代とともに大きく変化しています。中でも家族葬は、ご家族の想いや価値観に合わせて進めやすい葬儀として、多くの方に選ばれるようになりました。しかしその一方で、自由度の高さゆえに判断に迷ったり、ご親族や周囲の方との調整に悩んだりすることも少なくありません。
大切なのは、家族葬の基礎知識を正しく理解し、自分たちにとって本当に納得のいく葬儀のあり方を選ぶことです。形式や慣習にとらわれすぎず、誰のための葬儀なのかを見つめ直すことが、後悔のないお見送りにつながります。
家族葬に不安がある方や、家族葬をどのように進めるべきか迷っている方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフがご事情に寄り添い、必要な情報と選択肢をご案内いたします。




























