家族葬の挨拶状はどう書く?出すタイミングやマナー・文例を解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
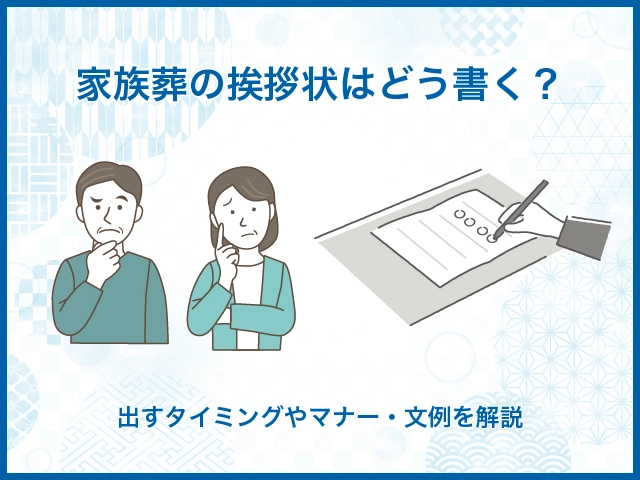
家族葬は一般的な葬儀と比べて形式や対応の流れが異なるため、訃報や葬儀などに関する連絡や挨拶に戸惑いがちです。特に、葬儀を済ませたあとの家族葬の挨拶状をどのように作成し、どの範囲の方に送るべきか悩む方も少なくありません。
そこで今回は、家族葬の挨拶状の書き方や送るタイミング、マナーについて、わかりやすく解説します。シチュエーション別の文例もご紹介しますので、家族葬の挨拶状に不安を感じている方は、ぜひ参考になさってください。
1.家族葬とは

家族葬とは、故人様のご家族や親しい友人など、限られた方のみで行う葬儀を指します。広く訃報をお知らせし、どなたでもご参列いただける一般葬とは異なり、限られた方のみを招待するため、準備や参列者対応に追われることが少なく、故人様との最後の時間を大切にできる点が特徴です。
しきたりや形式にとらわれず、落ち着いた雰囲気の中でお別れをしたい方々に支持されており、近年、葬儀スタイルの一つとして広く選ばれています。
2.家族葬で挨拶状が重要な理由
家族葬の挨拶状は、故人様が亡くなり、葬儀を家族葬で行ったことを知らせるべき人に報告するためのものです。「死亡通知(死亡通知状)」と呼ぶこともあります。
家族葬は近親者だけで執り行う葬儀のため、多くの方に訃報や葬儀について伝える機会が限られます。そこで、参列いただかなかった方に対しては、故人様の訃報や家族葬の事後報告を挨拶状できちんと行う必要があります。
挨拶状は、参列いただけなかったことへのお詫びや、故人様との長年のお付き合いに対する感謝を伝えることもできます。
3.家族葬の挨拶状を出すべき相手
家族葬の挨拶状を誰に対して送るべきか、迷う方も多いでしょう。挨拶状を出すべき相手を詳しく解説します。
基本は「故人と関わりのあった方」
家族葬の挨拶状は、故人様と生前に交流のあった方に送るのが基本です。具体的に考えられるのは、次のような方です。
・故人様のご親族、ならびに故人様の配偶者側のご家族
・故人様が在籍していたお勤め先の関係者
・故人様と親しく交際していた友人・知人
故人様がお亡くなりになる直前までの時系列で、親しく交流していた方、ご家族ぐるみで付き合いのあった方、年賀状のやり取りを続けていた方などを中心に、送る相手を検討するとよいでしょう。
挨拶状を出す範囲に明確なルールはない
挨拶状の送付先の範囲に、厳格な決まりはありません。無理に広範囲に送る必要はなく、あくまでもご家族の判断によって、伝えるべきと考える方を選びます。故人様との関係性を踏まえたうえで、ご縁や交流の深さに配慮しながら送付先を決めましょう。
4.家族葬の挨拶状を出すタイミング
家族葬の挨拶状をいつ送るべきかについて迷う方は少なくありません。一般的な時期と葬儀が年末年始に行われた場合について解説します。
一般的なタイミング
葬儀後から四十九日の法要、または納骨までを目安に送付するのが一般的です。葬儀を終えた旨を落ち着いた形で伝えられ、受け取る側にも失礼のないタイミングとなります。あまりにも訃報の伝達が遅れると、相手の心象が悪くなるおそれもあるため、挨拶状の準備はできるだけ早めに進めることが望ましいです。
家族葬が年末年始にかかった場合
家族葬が年末年始にかかった場合は、ご自身が年賀状のやり取りをしている相手や故人様宛に年賀状を書いてくださった方へは、寒中見舞いで訃報を伝えてもかまいません。
寒中見舞いは、松の内が明けてから、立春(毎年2月4日頃)までに届くように送る、季節の挨拶状です。松の内は、関東地方では1月7日まで、関西地方では1月15日までとされています。
寒中見舞いは、訃報の連絡が遅れた場合に代用されることもあります。しかし、故人様とご縁の深かった方には、正式な挨拶状を送ることをおすすめします。
なお、葬儀の挨拶状と喪中はがきは、混同しないよう注意が必要です。挨拶状は、故人様の逝去と家族葬を執り行った旨を伝える正式な通知です。対して喪中はがきは、ご自身が年始の挨拶を控えることを事前に知らせるためのもので、挨拶状の代わりにはなりません。
5.家族葬の挨拶状に書くべき内容

家族葬の挨拶状には、伝えるべき基本事項があります。それぞれの項目についてご説明します。
挨拶状を構成する基本項目
挨拶状には、受け取った方にとってわかりやすく失礼のない内容とするため、次の項目を記載します。
・故人様が逝去されたこと
・逝去の日付(例:○○年○月○日)
・喪主様から見た故人様との続柄
・葬儀、または納骨が行われたこと
・挨拶状を書いた日付、または発送する日付
・挨拶状を送る喪主様の住所と氏名
挨拶状を受け取る方の中には、故人様と最期のお別れをしたかったと残念に肩を落とされる方もいらっしゃいます。そのため、参列できなかった方への心配りを示す文面を添えましょう。近親者のみで葬儀を済ませたことをお詫びや、お世話になった感謝の気持ちなどを書くことで、受け取る方への配慮が伝わります。
具体的な文例は、この後の「家族葬の挨拶状の文例」に記載しておりますので、そちらも参考にご覧ください。
お香典や供花を辞退する場合
挨拶状を受け取った方の中には、お香典や供花を用意しようと考える方もいます。家族葬でお香典などを辞退する場合は、失礼のないよう丁寧な表現で意向をしっかりと伝えます。
6.家族葬の挨拶状のマナー・注意点
家族葬の挨拶状では、基本的なマナーを押さえることが重要です。挨拶状を書く際、特に注意すべき点は以下のとおりです。
句読点を使用しない
文章内に句読点を用いないことが、伝統的な作法です。江戸時代以前の日本において、改行や空白を用いて文章の格式を保ちつつ、読みやすさを確保してきた慣習に由来します。
季節の挨拶を入れない
通常の手紙に用いるような、時候の挨拶は入れません。訃報や葬儀の報告を優先し、簡潔に伝えることが大切にされるためです。
忌み言葉や重ね言葉を避ける
不吉な意味を持つ「忌み言葉」と、不幸の繰り返しを印象づける「重ね言葉」を避けます。忌み言葉には「死、亡くなる」など死の直接的な表現、重ね言葉には「再び、繰り返し、ますます」など、重なりを連想させる言葉が含まれます。
宗教・宗派の用語の違いに注意する
宗教・宗派によって表現が異なるため、適切な言葉を選ぶことが必要です。
たとえば、仏教では「成仏」「供養」「往生」が広く使われますが、これらは故人様が他の宗教を信仰していた場合は使いません。また、同じ仏教でも浄土真宗では、亡くなるとすぐに仏になるとの教えから、死後の世界の幸福を祈る「冥福を祈る」や、成仏する前の霊を指す「御霊前」といった言葉は使用しません。
神道では人が亡くなることを「帰幽」と表現します。キリスト教では「召天(プロテスタント)」や、「帰天(カトリック)」などが用いられます。宗教・宗派ごとの死生観を理解し、失礼のない言葉を選ぶよう心がけましょう。
縦書きで書く
弔事に関する改まった手紙は、古くから縦書きが基本とされているため、相手への敬意を示す上で最もふさわしい形式と言えます。
横書きで作成してしまうと、特にご年配の方や礼儀を重んじる方に対して、「常識がない」「失礼だ」といった不快感や違和感を与えてしまう可能性があります。故人様やご家族の想いを丁寧に伝えるためにも、家族葬の挨拶状は縦書きで作成するようにしましょう。
7.家族葬の挨拶状の文例【シチュエーション別】
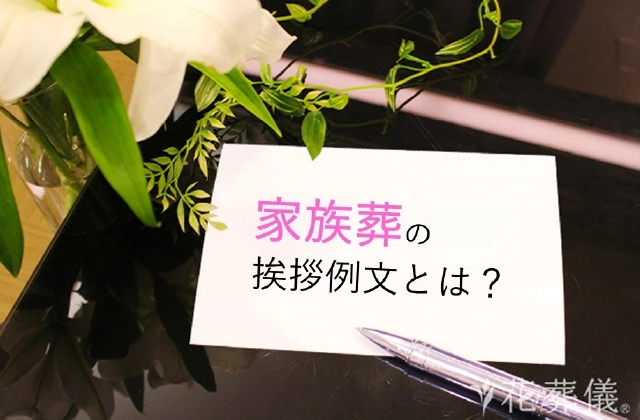
家族葬の挨拶状は、形式を重んじつつ状況に応じた言葉を選ぶことが必要です。こちらでは、シチュエーション別に挨拶状の文例をご紹介します。なお、文例はサンプルとして横書きで掲載していますが、実際に送付する際は縦書きで整えましょう。
宗教・宗派を問わず使える文例
以下は宗教・宗派を問わず、誰にでも幅広く使える一般的な文例です。
【文例】
ここに謹んでご通知申し上げます
葬儀は生前の希望により 近親者のみで執り行いました
なお誠に勝手ながら ご供花 ご芳志の儀は 固くご辞退申し上げます
本来であれば拝顔のうえご挨拶申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもちましてご報告いたします
故人が生前に賜りましたご厚情に対し 心より感謝申し上げます
令和〇年〇月
(喪主住所)
(続柄)喪主名
故人の意向による家族葬の文例
故人様の希望を尊重し、静かな見送りを行ったことへの想いを伝えます。
【文例】
故人の生前の希望により 近親者のみで小規模ながら家族葬を執り行いました
ごく限られた身内で 静かに見送りましたことをご報告申し上げます
早速ご連絡すべきところではございますが
略儀ながら書中をもってご通知申し上げます
生前中に賜りました温かいご厚誼に対し 改めて心より御礼申し上げます
令和〇年〇月
(喪主住所)
(続柄)喪主名
お香典・供花などの辞退を伝える文例
ご厚意に対して深い感謝を示しつつ、負担をかけたくない意向を丁寧に伝えます。
【文例】
ここに謹んでご報告申し上げます
葬儀は近親者のみで家族葬として滞りなく相済ませました
故人の遺志により 誠に勝手ながら
お花 不祝儀などのお心遣いにつきましては 謹んでご辞退申し上げます
また 賜りましたご弔意に対し 遺族一同 深く感謝いたします
本来であれば拝顔のうえ直接ご挨拶申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもってご通知申し上げます
令和〇年〇月
(喪主住所)
(続柄)喪主名
長期療養後に旅立たれた場合の文例
長期療養を支えてくれた方への感謝と、静かな旅立ちを穏やかに報告します。
【文例】
先般 〇〇〇儀 かねてより療養中でございましたが
本年〇月〇日 享年〇〇歳にて静かに永眠いたしました
苦しむことなく安らかに旅立ちましたことをご報告いたします
長きにわたり温かい励ましとご厚情を賜りましたこと 心より御礼申し上げます
葬儀は故人の意向により 近親者のみにて家族葬を滞りなく相済ませました
本来であれば直接伺って ご挨拶申し上げるべきところ
略儀ながら書中をもってご通知申し上げます
令和〇年〇月
(喪主住所)
(続柄)喪主名
8.お香典をいただいたら、忌明け後にお礼の品と挨拶状を送る【文例あり】

家族葬には参列いただかなかったものの、故人様の訃報を受け、お香典を送ってくださる方もいらっしゃいます。お香典をいただいた場合は、忌明け後に挨拶状(添え状)を添えて、香典返しを送りましょう。
忌明けとは、仏式の多くにおいて四十九日法要の後を指しますが、神式や他の宗派でも、おおよそ49日目ごろを目安に送ります。
以下は、香典返しに添える挨拶状の文例です。
【文例】
ご芳志を賜り 誠にありがとうございました
おかげさまで 滞りなく葬儀を執り行うことができました
故人も お心遣いに感謝していることと存じます
お礼の気持ちとして 心ばかりの品を贈らせていただきます
何卒お納めくださいますようお願い申し上げます
今後とも変わらぬご厚情を賜りますようお願い申し上げます
令和〇年〇月
(喪主住所)
(続柄)喪主名
文例は見本として横書きで掲載していますが、実際に用いる際は、縦書きとするのが通例です。香典返しに添える挨拶状の文例やマナーは「香典返しの添え状の書き方」で、詳しくご紹介しております。ぜひ、ご覧ください。
9.家族葬の挨拶状はマナーを守り、想いを丁寧に届けましょう
家族葬の挨拶状は、形式にとらわれすぎず、基本的なマナーを守りながら、ご家族の想いを丁寧に伝えることが大切です。
挨拶状には、故人様と生前お世話になった方々との大切なご縁を、これからもつないでいきたいというご家族の気持ちが込められています。家族葬という小さなお別れだからこそ、一通の挨拶状が、ご縁を大事に結び続ける役割を果たしてくれるはずです。
家族葬の準備や挨拶状に不安をお持ちの方は、ぜひ花葬儀の事前相談をご活用ください。経験豊かなスタッフが、挨拶状の作成をはじめ、ご家族の想いに寄り添いながら、家族葬全般を丁寧にサポートいたします。




























