お別れの会に電報は送っていい?判断のポイントと失礼にならない送り方・文例を解説
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
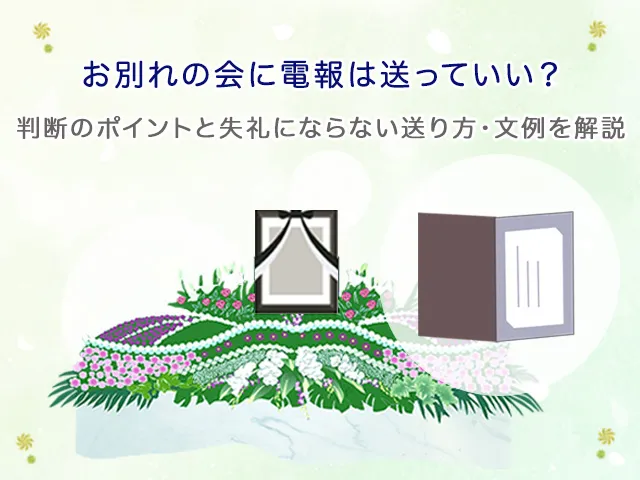
お別れの会に参列できないとき、「電報で気持ちを伝えたい」と考える方は少なくありません。しかし、「電報を送っても失礼にならない?」「どんな文面が適切?」と迷ってしまうこともあるでしょう。お別れの会は形式や規模が多様で、場にふさわしい対応が求められます。
本記事では、電報を送るべきかどうかの判断基準から、マナー、送り方、文例まで丁寧に解説します。大切な方への想いを届けるための参考にしてください。
1.お別れの会と電報(弔電)とは何か

まずは、「お別れの会」と「電報(弔電)」、それぞれの意味や役割を理解しましょう。
お別れの会(しのぶ会)の意味と特徴
お別れの会は、一般的に葬儀後に執り行われる、形式にとらわれない自由な追悼の場です。故人様の逝去後、ご家族やご親族を中心とした葬儀・告別式が一通り済んだ後、あらためてご友人・仕事関係者・知人など幅広い方々が集まり、故人様をしのびます。社葬の一種として執り行われることも多くあります。
宗教的な儀式色が薄く、喪服の着用が必須ではないことや、立食形式の会食を伴うケースも多く、よりカジュアルな雰囲気で行われるのが一般的です。「しのぶ会」「送る会」などとも呼ばれます。
電報(弔電)の定義と歴史的背景
弔電(ちょうでん)は、葬儀や告別式に参列できない場合に、故人様への哀悼の意とご遺族へのお悔やみの気持ちを急ぎ電報で伝えるものです。日本では、古くから葬儀の場で弔意を表す手段として利用されており、現代においてもその役割は変わりません。
2.お別れの会で電報を送ってもいいの?

では、お別れの会で電報を送ってもいいのでしょうか。詳しく解説します。
大切なのは「主催者の意向」と「会の位置づけ」
弔電を送るかどうかを考えるとき、心に留めておきたいのが、その会が「どのような位置づけで、どのような方々が集まるのか」ということです。そして、最も尊重すべきは主催者の方の意向になります。
弔電を送るべきか迷ったときは、まずお別れの会の案内状を確認しましょう。文面に「弔電を披露させていただきます」や「電報受付:◯◯まで」といった記載がある場合は、送って差し支えありません。一方、「供花・供物・弔意の品はご辞退申し上げます」などの文言がある場合は、弔電の送付も遠慮しましょう。
案内状に記載がない場合は、会の「位置づけ」を確認
案内状に明確な記載がない場合は、その会の位置づけを少し考えてみることをおすすめします。
公式な位置づけが強い場合
訃報から1〜2ヵ月後に行われる、企業が主催する社葬・合同葬の一種としてのお別れの会では、電報が公式な弔意表現として重視される傾向があります。また、ご家族だけで葬儀を済ませた後に広く弔意を受け付けるために開かれる会も、「社会的なお別れの場」であるため、公式な位置づけが強いと言えます。
このような会に参列できない場合は、弔電で丁寧にお悔やみの気持ちを伝えることが、心のこもった対応となるでしょう。
なお、通常の葬儀を「お別れの会」と呼ぶケースの場合は、実質的に一般葬と同じ性質を持つため、電報の送付は自然なものです。
私的な位置づけが強い場合
一方で、ごく親しいご友人やごく一部の関係者だけで集う、小規模な集いは、私的な位置づけが強いと言えます。そうした温かい会の中では、弔電という改まった形ではなく、事前に手紙で弔意を伝えるほうが、マナーに沿うこともあるでしょう。最終的にどうすべきか迷う場合には、主催者や事務局に問い合わせることをおすすめします。
参列しても電報を送るケースもある
電報は、参列できない場合に限らず、実際にお別れの会へ出席する予定がある場合にも送られることがあります。企業主催の会のような、お別れの会が社会的な意味を持つケースでは、会社や団体としての弔意を「形として残す」目的で弔電が用いられることがあります。
たとえば、本来は会社の社長が参列すべきところ、どうしても都合がつかずに部長など代理の方が参列する場合に、参列する代理の方とは別に、社長の名前で弔電を送るのです。その際、代理の方は本来参列すべき役職者の名刺を持参するのがマナーとされています。
3.お別れの会で電報を送るタイミング・宛先・差出人のマナー

お別れの会の電報は、いつ・誰宛に・どこへ送ればよいのか迷うところです。ここでは、タイミング・宛名・送り先・差出人の基本マナーをご紹介します。
電報を送るタイミング
お別れの会への電報は、「できるだけ前日までに式場に届くように手配する」のが理想的とされています。式の当日でも間に合う場合はありますが、受付や式場スタッフの準備が整っていないこともあるため、余裕を持って手配することが大切です。
宛名と書き方
宛名には、案内状に記載されている主催者名や代表者名を用いるのが一般的です。たとえば、会社や団体が主催している場合は「〇〇株式会社 代表取締役 △△様宛」などとします。
送り先と書き方
お別れの会では、会場宛に直接送るのが一般的です。送り先の情報は次のように記載します。
- ・会場名・住所
- ・式の名称(例:「○○様 お別れの会」)
- ・主催者名や代表者名
電報サービスでは専用の入力欄が用意されているため、案内状を確認して正確に入力しましょう。案内状に「電報は○○会場宛にお願いします」といった指示がある場合は、必ずその通りに手配します。会場側で取りまとめがしやすく、主催者に確実に届けられるためです。
差出人の書き方・名義のルール
差出人名は、基本的には、フルネームで記載します。会社や団体として送る場合は、代表取締役社長など会社の代表者名とするのが一般的です。社名+部署名+役職名+氏名までを丁寧に書くのが望ましいでしょう。
複数人を差出人として弔電を送る場合は、3名までであれば全員の氏名を記載し、4名以上の場合やグループの場合は代表者名のあとに「他一同」や「一同」のように付記することで対応します。
また、読みやすさや正確さを意識し、必要に応じてふりがなを併記する配慮もおすすめです。とくに、漢字の読みが難しい名前の場合、弔電を読み上げる際もふりがながあれば安心です。
4.電報の文面の書き方の注意点と文例

お別れの会に送る電報は、どう書けばよいのでしょうか。ここでは、文面の書き方の注意点や文例をご紹介します。
文面の書き方の注意点
お別れの会で電報を書く際は、以下の点に注意しましょう。
- ・文面は簡潔にまとめる
- 弔電は長文ではなく、100〜150文字を目安とし、長くても300文字に収めるのが適切とされています。冗長にならないよう、冒頭の弔意・故人様への感謝・結びの祈りなどをバランスよく入れます。
- ・忌み言葉・重ね言葉を避ける
- 「再び」「重ね重ね」「続いて」「またまた」など不幸が重なる印象を与える表現や、「死亡」「四」「苦」など直接的・不吉な表現は避けます。
- ・宗教・宗派に配慮する
- 仏教的な「ご冥福」「成仏」などの表現は、仏教でも浄土真宗やキリスト教、神道では適切ではありません。宗教・宗派に応じて表現を選びます。
シチュエーション別の文例
以下に代表的な3つのシチュエーション別での弔電の文例をご紹介します。状況に合わせてアレンジしてお使いください。
企業主催のお別れの会の文例
ご遺族ならびに社員の皆様には、深い悲しみの中にあられることと存じます。
故人のご功績を偲び、安らかなるご永眠をお祈り申し上げます。
知人のお別れの会の文例
ぜひ参列したかったのですが、やむを得ず断念いたします。
謹んでお悔やみを申し上げるとともに、ご冥福を心よりお祈り申し上げます。
著名な方のお別れ会の文例
○○様の生涯の歩みと輝かしい足跡をしのび、心から敬意を表します。
この場を借りて、安らかな旅立ちをお祈りいたします。
弔電の文例をもっと知りたい方は、さまざまな文例を集めた「弔電の文例集」をご覧ください。
5.電報の手配方法

電報は、どのようにして送ればよいのでしょうか。ここでは、電報の手配方法や主な台紙デザインについても解説します。
事業者の種類
電報は、主に以下のような手段で手配することができます。
- ・伝統的な電報サービス(NTTなど)
- 公的な通信事業をルーツに持つ、歴史の長いサービスです。社会的な信頼性の高さから、官公庁や大企業でも多く利用されています。
- ・インターネット中心の電報サービス
- Webサイトでの申し込みを中心とするサービスで、近年多くのサービスが提供されています。あまり知られていませんが、お別れの会を担当している葬儀社に、弔電を依頼できることもあります。
サービスの種類と価格相場
弔電の台紙は、文面と同じくらい印象を左右する大切な要素です。
以下に主な台紙デザインと価格相場をご紹介します。
メッセージと台紙のみのシンプルなタイプ
伝統的な電報の形式で、お悔やみの言葉を記した台紙のみをお届けするタイプです。一般的な台紙は、グレー・白・紺といった落ち着いた色調で、花模様が施されたものが広く選ばれます。宗教色が強く出にくく、宗派をまたいで使いやすいため、迷った場合はこの“定番”が無難です。
価格は、インターネット中心の“セット型”サービス(台紙+文面+配達)の場合、1500円〜2500円です。NTT系は「台紙代」+「メッセージ料」の合算方式で、総額は数千円~1万円と、やや高価になる傾向があります。
品物と共に弔意を贈るギフト付きタイプ
近年は、プリザーブドフラワーや線香の付いた“特別感”のあるサービスも増えています。故人様とのご縁を丁寧に表したい場合に適しています。価格は添える品物によって変わりますが、5千円〜2万円が相場です。
ギフト付きの弔電を選ぶ際には、案内状に「供花・供物・弔意の品はご辞退申し上げます」といった記載がないか、必ず確認してください。何よりもご遺族の意向を尊重することが大切になります。
準備から送付までの流れ
電報の準備から送付の基本的な流れは、以下のとおりです。
1.案内状の確認と情報整理
お別れの会の日時、場所、宛名(喪主様・主催者名など)を確認し、間違いのないようメモを取ります。送付先の住所や電話番号も正確に記録しましょう。
2.文面の作成・確認
自分で文面を作る場合は、忌み言葉や不適切な表現が含まれていないかを確認し、相手に配慮した表現を選びます。定型文を使う場合でも、送り主の想いが反映されているかを確認します。
3.電報サービスへ申し込み
電話またはインターネットで申し込みます。時間帯によっては当日配達が可能な場合もあるため、できるだけ早めに手配を済ませましょう。
4.料金支払いと最終確認
インターネット申し込みではクレジットカードや電子決済が利用可能です。最終確認の画面で「宛名」「住所」「差出人」などに誤りがないかを慎重に見直しましょう。
6.お別れの会の電報に関するQ&A
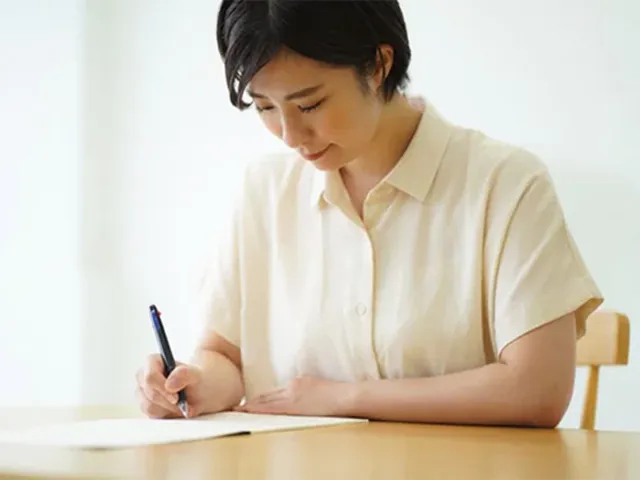
A.お別れの会に出席できない場合は、事前に主催者に手紙や電話などで伝えるのが基本のマナーです。
より丁寧に哀悼の意を示したい場合には、弔電をあわせて送ることも可能ですが、必ずしも両方を送る必要はありません。
A.正式な招待を受けたうえで欠席するなら、多くの場合失礼にはなりません。
家族葬で弔電を辞退する場合もありますが、あらためて行われる「お別れの会」は、広く弔意を受け付ける場として設けられることが多いです。とくに、案内状で弔電の受付が明記されている場合は、マナー違反にはなりません。
ただし、ご遺族の意向に配慮することが何より大切ですから、主催者に確認することをおすすめします。
A.多くの電報サービスが海外からの申し込みに対応しています。
多くの弔電サービスは、インターネット経由での注文に対応しており、海外在住者でも利用可能です。日本国内の式場に直接届けることができるため、時差や物理的距離を超えて哀悼の意を伝えられます。ただし、海外クレジットカードの利用可否や配達可能日数には差があるため、早めの手配と事前確認が大切です。
7.お別れの会への電報は、マナーと気持ちの伝え方を確かめてから

お別れの会では、電報が必ずしもふさわしいとは限りません。弔電は本来、急な訃報への対応として用いられるものであり、開催日が事前に知らされるお別れの会では、原則として送らないのがマナーとされています。
ただし、社葬や合同葬などでは、電報が重視されることもあるため、案内状の文言や会の性質をしっかり確認したうえで判断することが大切です。
「送っていいのか迷う」「失礼にならない文面にしたい」――そんな方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。会の形式や状況に合わせて、専門スタッフが丁寧にアドバイスいたします。




























