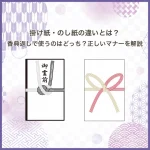【法事の準備】いつから何を用意する?チェックリストもご紹介(四十九日・年忌法要対応)
- 作成日:
- 【 法事・法要の基礎知識 】
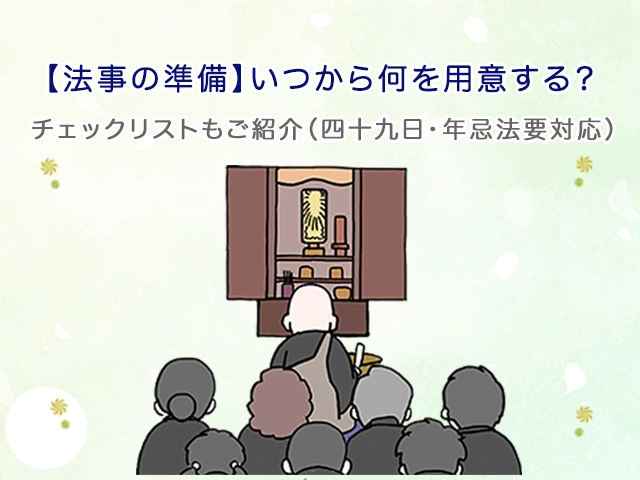
四十九日や一周忌などで、初めて施主様を務める方の中には「何を準備すればよいのか」「どこから手を付けてよいのかわからない」と戸惑う人も少なくないでしょう。法事は準備すべきことが多いため、しっかりと段取りを整えて進めることが大切です。
そこで今回は、法事の準備について、何をいつから準備すべきか、チェックリストも交えながらご紹介します。法事当日の流れや、必要となる費用についても解説しますので、法事を控えている方や、法事に関して情報を集めている方は、ぜひ、この記事を参考になさってください。
1.法事(法要)の基礎知識

法事の準備を始めるにあたり、まずは法事に関する基本的な知識を確認しておきましょう。こちらでは、法事と法要の違いや、主な法要の種類について解説します。
法事・法要とは?
「法事」と「法要」は混同されがちですが、次のように意味が異なります。
- ・法要:僧侶による読経やお焼香など、故人様を供養する宗教的な儀式
- ・法事:故人様をしのぶ仏教の行事で、法要に加えて会食や参列者の交流を含む
法要は法事の一部ともいえますが、近年では2つを厳密に使い分けることは少なくなっているようです。
なお、浄土真宗では、故人様は亡くなるとすぐに極楽浄土へ往生すると考えられているため、法要は供養ではなく、故人様をしのび、ご遺族が仏の教えに触れる機会とされています。
代表的な法要の種類
法要にはさまざまな種類がありますが、大きく「忌日法要・年忌法要・その他の法要」に分けられます。
忌日法要
故人様が亡くなってから49日目まで7日ごとに行われる法要と、100日目の百日法要を指します。特に初七日と四十九日は、故人様の極楽往生を願う重要な忌日法要です。
年忌法要
故人様の祥月命日(故人様が亡くなった月日)に行う法要で、一周忌や、三回忌、七回忌などがあります。それ以降も続きますが、適宜「弔い上げ(とむらいあげ)」として年忌法要を終える場合もあります。
仏教の法要の詳しい種類については「葬儀後の忌日法要・年忌法要一覧」をご覧ください。
その他の法要
忌日法要や年忌法要以外には、納骨法要、お盆法要、彼岸法要などがあり、概要は次のとおりです。
- ・納骨法要:遺骨をお墓に納める際に行う
- ・お盆法要:故人様の霊を自宅に迎え供養を行う。特に初めて迎える「新盆」は大切
- ・彼岸法要:春分・秋分の日を中日とする7日間に行う
いずれの法要を行うにしても、故人様を大切に思う気持ちと、事前の準備が重要になります。
2.法事の準備はいつから、何をすればいいのか

法事をスムーズに進めるには、計画的な準備が欠かせません。こちらでは、法事の準備を、「2~3ヵ月前/1ヵ月前/2~3週間前/1週間前~前日」の4つの期間に分けて説明します。
2~3ヵ月前
法事の大枠を決めることから始めます。僧侶への相談や会場の選定・予約といった、早めの対応が必要な事項を中心に、準備を進めていきましょう。
僧侶に相談して日程を決定
菩提(ぼだい)寺がある場合は、寺院に相談のうえ日程を決定します。菩提寺がない場合は、葬儀社などを通じて僧侶に依頼することも可能です。
法要を行う会場・会食会場の予約
法要を寺院や斎場、また、会食を料理店、ホテル、斎場内の会食室などで行う場合は、会場の予約をします。特にお盆やお彼岸などの法要が多い時期、週末などは希望の日時や場所が埋まりやすいため、早めに予約することが重要です。
案内状の作成と送付
法事の日時や場所が決まったら、参列をお願いしたい方へ案内状を作成し、送付します。返信をいただく期間も考慮し、遅くとも1ヵ月前までには届くよう送ります。
案内状に記載する内容は、以下の点を押さえてわかりやすく伝えましょう。
- ・故人様の情報:故人様の氏名や施主様との関係(続柄)
- ・日時と場所 :法要の日時、場所、開始時間
- ・会食の有無 :法要後の会食の有無や場所
- ・返信のお願い:出欠確認をお願いし、返信期限を設ける
- ・差出人の情報:施主様の名前や連絡先
返信用はがきを同封することで出欠確認もスムーズに行えます。なお、ごく親しいご親族のみなど、少人数で法事を行う場合は、電話やメールで案内することもあります。その場合でも、上記の必要事項を漏れなく、正確に伝えるようにしましょう。
墓石店への依頼(納骨を行う場合)
新しく墓石を建てる場合や墓石に故人様の名前などを彫刻する場合は、墓石店に依頼をしておきます。
1ヵ月前
法事の詳細を具体的に決定し、必要な手続きを始める時期です。参列者の人数を確定させるとともに、納骨を行う場合は、必要な準備も進めましょう。
出欠確認
案内状の返信を確認し、未返信の方には電話やメールで出欠の返事をもらい、参列者のだいたいの人数を把握します。
納骨法要の準備(納骨を行う場合)
納骨に必要な書類の手配や手続きを始めます。
納骨の際には、埋葬許可証が必要なため、事前に役所で申請して入手しておきます。墓地の使用契約書(納骨許可書)が必要になる場合もあるため、事前に墓地を管理している業者や寺院に確認します。書類に押印が求められるケースもあるので印鑑も用意すると安心です。
墓石店に墓石の作成依頼をしている場合は、完成時期を確認します。
2〜3週間前
参列者の人数を踏まえて、より具体的な法事の準備を進めます。
お香典へのお返し、引き出物の選定
お香典へのお返しと、参列に対するお礼の引き出物を選びます。それぞれ適切な金額の目安がありますので、予算や持ち運びやすさなどを考慮して準備しましょう。金額の詳しい目安や考え方については、後述の「6.法事にかかる費用の内訳と相場」で解説します。
会食の手配
会食を行う場合は、料理や飲み物の内容を決定して手配します。
供花やお供え物の手配
法要に必要な供花やお供え物などを準備します。特に供花は、誰が用意するかをご親族と相談することが一般的です。
移動手段の手配
法要と会食の場所が異なるなど、移動が必要な場合は、マイクロバスやタクシーの手配を検討します。参列者に移動の負担がかからないように配慮することが大切です。
1週間前〜前日
細かい点までしっかり最終確認を行い、当日を迎える準備を整えます。
最終打ち合わせ
会場や僧侶、食事の提供先など関係者と最終の打ち合わせを行い、当日の流れも再確認します。
お布施・御車代・御膳料の準備
僧侶へのお礼としてお渡しするお布施や御車代、御膳料を準備します。
- ・お布施
- 僧侶に読経をお願いした際にお渡しする金銭です。読経などの対価や報酬ではなく、あくまで感謝の気持ちを表すものです。
- ・御車代
- 法要を自宅や斎場など寺院以外の場所で行う場合、僧侶が足を運んでくださったことへのお礼として渡します。
- ・御膳料
- 法要後の会食を僧侶が辞退された場合にお渡しする金銭です。本来召し上がるお料理の代わりとして渡します。
これらはそれぞれ、郵便番号欄の無い白無地の封筒に入れるのが一般的ですが、地域によっては水引の付いた不祝儀袋を使うケースもあります。
表書きは、上段に「お布施」「御車代」「御膳料」などと書き、下段には施主様の姓(○○家)、またはフルネームを記載します。
それぞれの金額相場については、「6.法事にかかる費用の内訳と相場」で詳しく解説しています。
当日の持ち物の確認
当日、必要になる持ち物をリストアップし、前日には忘れ物がないようチェックします。法事で施主様が用意する主な物は以下のとおりです。
- ・お布施
- ・御膳料
- ・お車代
- ・香典返し(お香典をいただいた方へお渡しする)
- ・引き出物(参列していただいたことへのお礼としてお渡しする)
- ・数珠(宗派に関係なく手元にあれば持参する)
- ・お供え物
法要当日に慌てることのないよう、席次表や供花の配置などを確認しておくとよいでしょう。
3.法事当日の流れ

法事をスムーズに進めるには、事前に流れを把握しておくことが大切です。一般的な法事当日の流れについて説明します。
1.僧侶・参列者への挨拶
開始時間が近づいたら、施主様やご遺族は早めに会場へ到着し、参列者を迎えます。僧侶が到着された際には感謝の意を込めて挨拶をしましょう。このタイミングでお布施や御車代などを渡すこともあります。
2.僧侶の入場と開式の挨拶
定刻になると、僧侶が入場し、施主様が法要開始の挨拶をします。
3.読経・お焼香
僧侶による読経が始まり、読経の途中から参列者によるお焼香が行われます。
4.法話
読経が終わると、僧侶による法話が行われます。故人様の思い出に触れながら、仏教の教えが説かれることが一般的です。
5.閉式の挨拶と会食の案内
法話が終わり僧侶が退場した後、施主様が法要終了の挨拶をします。会食の予定がある際は、場所や移動方法などの案内をする場合もあります。
6.会食(お斎)
会食の前に、施主様が挨拶を行います。その後、食事を囲みながら、故人様の思い出を語り合います。
7.法事終了
会食が終わる予定時間が近づいたら施主様が法事終了の挨拶をし、参列者が帰途に就く際には、施主様から参列者へ香典返し(お返し)や引き出物を手渡します。
4.法事を滞りなく進めるための準備チェックリスト

法事を滞りなく進めるために準備すべきことには、主に次のような6つの項目があります。
1.参列者への連絡
参列をお願いする方への連絡は、メールや電話で行う方法もありますが、基本的には案内状を郵送するのが最も丁寧な方法です。規模や関係性によっては、電話やメールで連絡してもよいでしょう。
2.お供え物の準備
法事では、「五供(ごくう)」と呼ばれる仏教のお供えの基本にもとづいて5つのお供え物を準備します。
香(お線香)
香りが強すぎないお線香を選び、心地よい香りで故人様をしのびます。
花
仏壇の花立やお墓に供える花を用意します。季節の花や故人様が生前好んだ花を選ぶとよいでしょう。トゲのある花や香りが強すぎる花は避けます。
灯(ろうそく)
ろうそくの光は、仏様の慈悲の象徴で、故人様の霊が安らかに過ごせるように祈る気持ちを表現します。
水
水は、浄化を意味し、霊を清らかに保つ役割を果たします。故人様が好きだったお茶やお酒などの飲み物を供える場合もあります。
飲食(食べ物)
故人様をもてなすために用意される食べ物です。飲食(おんじき)とも呼ばれ、代表的なものは、果物やお菓子などです。
3.お香典へのお返し・引き出物の手配
法事では、お香典をいただいた方へのお返しと、参列していただいたことへのお礼である引き出物の2つを用意します。当日の予想外の参加者増加に備え、香典返し(お返し)も引き出物も、参列者の人数に対して不足しないよう、余裕を持って用意しましょう。
4.お布施などの準備
お布施のほかに、状況に応じて御車代や御膳料を用意します。これらは袱紗(ふくさ)に包んで持参するのが丁寧なマナーです。袱紗がない場合は、清潔な風呂敷で代用することもできます。
5.仏壇の飾り付け
法事の際、仏壇の飾り付けは通常よりも丁寧に行い、故人様への追悼と感謝の気持ちを表します。
普段は仏壇に遺影を飾っていなくても、法事では飾ることもあります。位牌は、四十九日までは仮の「白木位牌」を使用し、四十九日法要を境に「本位牌」になる点に留意しましょう。
なお、仏壇の飾り方や仏具の使い方は宗派によって異なることがあるため、心配な方は事前に寺院や葬儀社などに確認して準備することをおすすめします。
6.お墓の清掃
お墓の清掃をすることは、心を込めた供養の準備として重要です。法要当日は参列者の対応などで忙しくなるため、前日までにお墓をきれいにしておくとよいでしょう。特にお盆やお彼岸などでは、故人様の霊をお迎えする意味を込めて、事前にお墓の清掃を行うことが多くあります。
5.四十九日法要のときは特別な準備が必要

四十九日法要は、一般的には故人様の霊が極楽浄土へ旅立つ節目とされているため、特別な準備が必要です。どのような準備なのか、詳しく解説します。
本位牌の準備
四十九日法要では、一般的に葬儀時に用意した白木位牌(仮位牌)から本位牌へと故人様の魂を移す儀式を行うのが一般的です。そこで、四十九日法要までに本位牌を準備する必要があります。本位牌の作成には通常1~2週間程度かかるため、余裕をもって準備しましょう。
後飾り祭壇の飾り付け
四十九日法要までの間、ご遺骨や位牌を安置するために「後飾り祭壇」を設置します。故人様を供養する重要な場所ですから、四十九日法要時には飾り付けを忘れないようにしましょう。
通常、仏式の後飾り祭壇は、白木の2~3段の祭壇に仏具やお供物を飾ります。上段には、白木位牌、遺骨、遺影を置き、下段には、香炉、燭台、花立てなどの仏具を並べます。また、必要に応じて、お供え物を供えます。
宗教・宗派によって飾り付け方が異なることがあるので、不安な場合は詳しい方や葬儀社に確認することをおすすめします。
仏壇など、故人様をしのぶための場所の準備
四十九日法要を終えたら、後飾り祭壇に飾られていた遺影や位牌などの仏具は仏壇に納めますが、仏壇がない場合は、故人様をしのぶことのできる場所を準備する必要があります。
また納骨をまだ行わない場合は、ご遺骨を自宅で安置するスペースを確保することも重要です。安置場所は、湿気や直射日光を避け、ご家族が手を合わせやすい場所を選びます。
開眼供養の手配(四十九日法要と併せて行う場合)
新たに位牌や墓石を作成した場合には、それらを礼拝の対象とするために、開眼供養(魂入れ)を行います。四十九日法要と同日に開眼供養を行う場合には、僧侶と早めに段取りを調整し、必要な供物や仏具などを手配しましょう。
納骨の準備(四十九日法要と併せて行う場合)
四十九日法要では、納骨を併せて行うことも多くあります。その場合、事前に「納骨法要の準備(納骨を行う場合)」で解説した必要書類を確認・準備しておきましょう。特に「埋葬許可証」は紛失しないよう大切に保管してください。
6.法事にかかる費用の内訳と相場

法事を行う際には、さまざまな費用がかかります。多岐にわたる費用の主な項目を相場とともにご紹介します。
お布施
法要のお布施の相場は、法要の種類や規模によって異なりますが、おおよそ、初七日や四十九日法要では3万円〜5万円程度、一周忌や三回忌などの年忌法要では1万円〜5万円程度です。地域や寺院によっても差があるため、具体的な金額は事前に菩提寺や僧侶に相談しましょう。
お車代
お車代の相場は、往復で5,000円〜1万円程度です。法要を寺院で行った場合は、渡す必要はありません。
御膳料
地域や寺院の慣習によって異なりますが、5,000円〜1万円程度が一般的です。なお、僧侶が会食に参加する場合は、通常5,000円〜2万円程度のお料理を準備します。
会場費
法要を営む会場費は、自宅で行う場合は発生しませんが、寺院では本堂使用料として無料~数万円程度がかかる場合があります。斎場を利用する際は、数万円~10万円程度が一般的です。会場費は、規模や場所などによって大きく変動するため、事前に確認することが重要です。
会食(お斎)の費用
自宅での法事で仕出し弁当を注文する場合、1人前3,000円~5,000円程度が目安です。ホテルやレストランの個室を利用する場合は、1人前5,000円~1万円程度が一般的で、別途会場費がかかるケースもあります。
法事の会食(お斎)の費用は、参加人数や料理の内容、会場の種類によって大きく異なるため、予算に合わせて選びましょう。
お香典に対するお返しの費用
お香典のお返しの金額は、お香典の半額程度が目安です。故人様の知人などが多く参列する法要では、お香典の平均額が5,000円ほどと想定されるので、その半額の2,000円〜3,000円程度のものを選びます。
ただし身内のみの法要では、お香典が高額になることが多いため、3,000円〜5,000円程度の品を用意すると安心です。
引き出物の費用
参列いただいたことへのお礼としてお渡しする引き出物は、2,000円〜5,000円程度が相場とされています。
案内状作成・郵送費用
案内状の作成・印刷費用は、デザインや部数によって変動します。また郵送費用は、部数などによって異なります。発送は、葬儀社に依頼することも可能ですので、詳細を確認するとよいでしょう。
お供え物の費用
お墓や仏壇に備える供花やお供え物の総費用は、1万円~2万円程度が目安となります。
卒塔婆の費用
法要では、ご家族がお墓に卒塔婆(そとば)を備えることもあります。卒塔婆とは、供養の一環として建てる木製の板のことで、故人様の戒名や供養を行った日付などが刻まれます。費用は、1本あたり2,000円~1万円程度が相場です。
7.自宅で法事を行う時に特に準備すること

自宅で法事を執り行う際には、以下の点に特に注意して準備を進めることが重要です。
仏壇や供物台などを整える
仏壇をきれいにして飾り付けるのはもちろん、仏壇の前に参列者が持参するお供え物を置くための供物台を用意します。供物台は、小さな机に白い布をかけて代用することもできます。
焼香台と関連用品の準備
お焼香は法要では必須の儀式のひとつですから、部屋の広さや参列者の人数に応じた焼香台を準備します。そのほか、香炉や灰など必要な道具をそろえて、スムーズにお焼香ができるようにしておきます。お焼香に関する準備に不安がある場合は、菩提寺や葬儀社に相談するとよいでしょう。
椅子や座布団の用意
参列者が座るスペースを確保するとともに、椅子や座布団を用意します。僧侶用の「仏前座布団」の準備も忘れないようにしましょう。
8.法事の準備に関するQ&A

A.法事の服装は、法要の種類などによっても異なります。
初七日法要や四十九日法要・百箇日法要では、基本的に葬儀と同様の服装を着用します。一周忌法要以降も、準喪服を着用する方が多いようです。準喪服とは、正喪服に次ぐ格式の喪服です。男性は光沢のない生地のブラックスーツ、女性は光沢のない黒のスーツやワンピースやアンサンブルスーツなどが該当します。
なお、三回忌をご家族だけで行う場合は平服(略喪服)を選ぶ施主様が増えており、七回忌以降は平服でも問題ないとされています。
A.遠方からの参列者には、交通手段の案内に配慮が必要です。
最寄り駅や空港から会場までのアクセス方法の詳細を伝え、駐車場に関しても必要に応じて案内を行います。宿泊が必要な場合は、近隣のホテルや旅館の情報を提供し、予約のサポートをすると参列者の負担を軽減できます。
A.僧侶の手配は、主に以下の3つの方法で行うことができます。
- 1.インターネットで探す
- 2.知り合いやご親戚に頼んで紹介してもらう
- 3.葬儀社に相談する
葬儀社は、提携している信頼できる僧侶を紹介してくれます。日程調整や法事に関する相談にも対応してくれるため、初めての方でも安心して依頼できます。いずれの方法を選んでも、事前に僧侶と相談し、法事の内容や日程をしっかりと確認することが大切です。
9.法事の準備は余裕を持って計画的に進めましょう

法事の準備は、日程調整や会場手配、僧侶への依頼、引き出物の準備など、やるべきことは多岐にわたります。早めに段取りを決めて始めることで、焦らず心穏やかに法事に臨むことができます。
困ったときは、葬儀社や寺院に相談し、ご家族や周囲と連携すれば、故人様を心からしのぶことができる、あたたかみのある法事になるでしょう。
花葬儀では、葬儀後の法事の準備もお手伝いしております。花葬儀で葬儀をされていない方へのサポートも行っておりますので、法事に関する不安や疑問があれば、花葬儀の事前相談を、ぜひご利用ください。経験豊富なスタッフが、心を込めて大切な法事のお手伝いをさせていただきます。