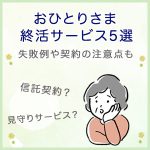親の終活、家族はどうサポートできる?切り出し方から注意点まで解説
- 作成日:
- 【 終活の基礎知識 】
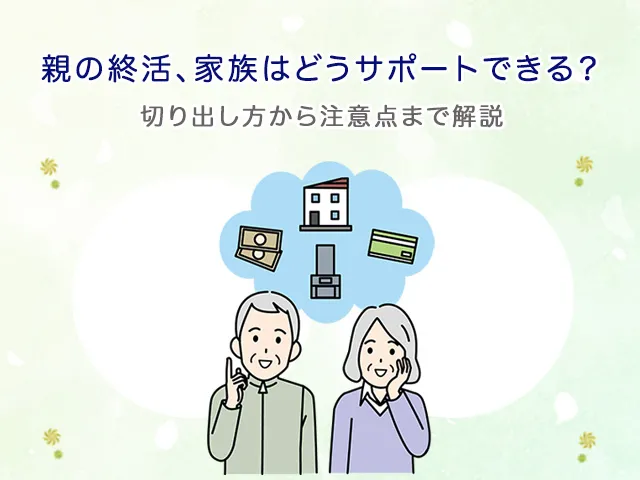
終活の話題は、家族にとって避けがちなテーマかもしれません。「いつか話さなければ」と思いつつ、具体的な行動に移せていない方も多いのではないでしょうか。しかし、親が元気な時こそ、将来に備える絶好のタイミングです。
この記事では、親に終活を促すための自然な切り出し方や、話し合いをスムーズに進めるコツをご紹介します。終活は本人だけでなく、家族全員に関わる重要な活動です。ぜひ最後までご一読ください。
1.そもそも終活とは?知っておくべき意味とメリット

家族で終活の話をする前に、終活の基本的な知識を押さえましょう。
こちらで、終活の意味とメリットをご紹介します。
終活は「今」と「これから」のための準備
「終活」とは、人生の最後に向けた活動の総称です。具体的には「身の回りの整理」「財産管理」「医療・介護に関する備え」「葬儀やお墓の準備」などが挙げられます。
終活には「終」という文字が使われていること、また本能的に「死」を意識することに対しての忌避感から、ネガティブなイメージを持つ方もいらっしゃいます。しかし、終活は本来前向きな活動であり、いつか必ず訪れる人生の最後に向けて備えることで、「今」と「これから」の両方に目を向けることができるようになります。
残りの人生を充実させるためにも、元気なうちから終活を始めるのがポイントです。
家族が親の終活に関わる5つのメリット
終活は一人でも取り組むことができますが、周りの家族がサポートすることでよりスムーズに進められるようになるでしょう。
こちらでは、親の終活に家族が関わることのメリットを5つご紹介します。
1.家族の負担を軽減できる
本人が主体となって終活を行うことで、家族には「負担軽減」のメリットが生まれます。例えば、親が何も準備しないまま亡くなった場合、遺品整理、財産調査、葬儀やお墓の手配などは全て家族が担わなければなりません。しかし、生前にこれらの事柄を整理し、希望を明確にしておけば、残された家族の肉体的、精神的、経済的負担は大きく軽減されます。
2.家族間のトラブルを防止できる
「親の介護・医療」「遺産相続」「葬儀やお墓」などの決定には、デリケートな問題を含みます。それぞれの立場の希望を明確にし、事前に話し合うことで決定がスムーズになり、家族間の争いを回避することができるでしょう。
3.親の意思を尊重しやすい
「どのような介護を受けたいか」「延命治療は望むか」といった親の希望を把握しておくことで、本人との意思疎通が難しくなった場合でも、家族は適切な判断ができるようになります。このように、最期まで本人の意思を尊重した時間を過ごさせてあげられる点も、大きなメリットです。
4.より良い関係を築く機会となる
親の終活に関わることで、家族全員が将来について考える時間を持つようになります。考えを共有するために会話が増え、お互いの価値観や想いを理解し合うことができるでしょう。親の終活をきっかけに、家族の絆がより深まるかもしれません。
5.家族全員の安心につながる
加齢による身体機能の衰え、病気、老後の経済状況、相続など、将来には漠然とした不安がつきものです。しかし家族全員が将来の見通しを共有していれば、いざという時でも「何を優先し、どう対応すべきか」が明確になり、落ち着いて行動することができるようになります。心の余裕につながる「安心感」も、終活で得られるメリットです。
2.【親の終活】家族ができるサポート&心構え

親の終活に対し、家族はどのようなサポートができるのでしょうか。
具体的な内容と、終活に関わる際の心構えをご紹介します。
情報の整理|まずは家族の情報を確認
将来的な話し合いをするためには、現在の状況を把握することが大切です。まずは、終活をする本人である親の情報を整理・確認しましょう。
基本情報と連絡先
本人の基本情報を改めて確認します。ここで言う「基本情報」とは、終活をする際に必要となる情報であり、主に以下が挙げられます。なお、本人が教えたがらない事柄や、プライベートに深く踏み込むようなものに関しては、無理に触れないようにしましょう。
- ・血液型
- ・資産状況(借金などの負債も含める)
- ・加入しているサービス
- ・職場
- ・信仰している宗教
- ・親族の範囲
- ・交友関係 など
緊急時や訃報の際の連絡先は、リストにまとめておきます。なお、基本情報の整理には、エンディングノートの活用がおすすめです。エンディングノートについては、後述する「希望を確実に伝えるための記録・共有」をご覧ください。
重要書類の保管場所
「マイナンバーカード」「印鑑」「運転免許証」「年金手帳」「不動産権利書」など、重要書類の保管場所を確認します。特にマイナンバーカード(マイナ保険証として利用)や資格確認書(※1)など、入院時に必要となる書類は、手の届く場所にまとめて保管しておくと安心です。
本人が遺言書やエンディングノートを作成している場合も、同じように保管場所を確認しておきましょう。いざという時に見つからない事態を避けるためです。
なお、遺言書の種類によっては、相続の決定をする前に家庭裁判所による検認(※2)が必要となるため、家族で情報を共有しておくことが大切です
(※1)2024年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを利用した「マイナ保険証」に原則一本化されます。マイナ保険証を持ってない場合は、代わりに資格確認書を用います。
(※2)相続人に遺言書の存在と内容を知らせるとともに、遺言書が悪用・改ざんされないように守るための手続きです。
かかりつけ医・持病
「持病、アレルギーの有無」「常飲している薬の種類」「かかりつけ医」を確認します。可能であれば、家系の病歴などを調べておくと、将来的にかかる可能性のある病気を予測することができます。
ただし、詳細を家族に知られたくない方もいらっしゃいます。無理に知ろうとしない姿勢も大切です。
物・財産の整理|将来的な負担・トラブルを予防
将来的に家族が担う負担を軽減し、相続による家族間トラブルを防止するためにも、身の回りの整理を行いましょう。物や財産の整理には時間がかかるため、余裕を持って取り組むことをおすすめします。
物の整理サポート
自宅の中の整理整頓を手伝いましょう。「いるもの」「いらないもの」に分け、いらないものは廃棄、または売却します。物が大量にある場合は専門業者によるサポートが必要になるため、事前に相談しておくとスムーズに進めることができるでしょう。
いらないものを処分した後、以下のことについて考えておくと家族全員の安心につながります。
- ・家の動線を見直す(つまずきや転倒防止)
- ・大切なものについて、誰が何を引き継ぐか明確にする
財産目録の作成
財産目録とは、その人の持つ財産の全てを一覧にまとめたものです。預金や不動産、株式などだけではなく、借金を始めとしたマイナスの財産も記載する必要があります。財産目録を作成しておくことで、将来的な資金計画が立てやすくなったり、相続について考えやすくなったりするでしょう。
財産を全て洗い出して自力でまとめるのが難しい場合は、弁護士などの専門家を頼ることをおすすめします。
保険の確認・見直し
現在、加入している保険を見直します。条件や補償内容が見合っていない場合は、解約または変更を検討します。また、生命保険の保険金の受取人が誰になっているのかもこの時に確認しましょう。
加入している保険を調べるには、保険証券を確認する方法がありますが、他にも「保険会社からの郵送物を探す」「引き落としの明細を調べる」などの方法があります。本人が忘れているケースもあるため注意して探しましょう。
デジタル財産の整理
「デジタル財産」とは、デジタル形式で保管されている財産の総称で、主に以下を指します。
- ・ネット銀行、ネット証券の口座
- ・電子マネー
- ・クレジットカードのポイント
- ・暗号資産
- ・デジタル著作権 など
デジタル財産も原則として相続の対象になるため、しっかりと把握しておくことが重要です。目録を作り、IDやパスワードなどの必要情報は控えておくよう、本人に促します。
デジタル財産のほかにも、パソコンやスマートフォンの中に保存されている個人的なデータや、インターネット上のアカウント情報などの整理も大切です。具体的には写真や動画、メール、SNSアカウント、アプリケーション、サブスクリプションなどが挙げられます。
特にサブスクリプションサービスは、契約者が亡くなった後も自動的に解約されず、どのサービスを利用していたか把握しづらい場合もあるため、注意が必要です。不要なものはこの機会に解約し、万が一の時の解約方法などを共有しておきましょう。
意思の表示|本人の希望を明確にする
本人の希望を周りが把握しておくと、万が一の事態に際しても、迅速かつ最適な決定ができるようになります。
こちらでは、あらかじめ確認しておきたい「意思表示」について詳しくご紹介します。
医療・介護の希望
年齢とともに、身体機能の衰えや認知症の発症リスクが高まります。元気なうちから以下についての希望を確認しておきましょう。
- ・介護が必要になった場合のケアの方法
- ・入りたい介護施設
- ・延命治療を希望するかどうか
- ・最期を迎えたい場所
葬儀の希望
まだ元気な人に死後の希望を聞き出すことは容易ではないでしょう。しかし、逝去から葬儀までは慌ただしく、ゆっくり考えている時間はほとんどありません。そのため終活準備として、あらかじめ確認をしておくと、本人の意思を尊重したお見送りができるようになります。
具体的には、以下のような項目を整理しておくと安心です。
- ・葬儀のスタイル(形式、規模、宗教の有無 など)
- ・遺影にしてほしい写真
- ・葬儀社の希望
お墓・供養の希望
「ご遺骨の供養」と一口に言っても、その方法は多岐に渡ります。例えばお墓に埋葬する場合、先祖代々のお墓に入るのか、それとも永代供養をしてもらえるお墓を選ぶのかで必要な準備は異なります。また、埋葬以外にも、粉末にしたご遺骨を自然に撒く「散骨」という方法もあり、本人と供養するご家族双方の意思を伝え合いながら決めることが大切です。
相続・遺言の準備
相続や遺言の準備は複雑で、法的な知識も必要とするため、終活の中でも最も難しいとされる項目です。家族間トラブルを避けるためにも、以下のポイントを踏まえてじっくり話し合うことをおすすめします。
- ・必要に応じて相続や遺言の専門家を交える
- ・相続問題でよくあるトラブルを調べ、理解を深める
- ・相続・遺言の希望や決定は、相続人となる予定の人と広く共有する
希望を確実に伝えるための記録・共有
さまざまな希望を明確にしたとしても、それが家族に伝わらないのでは意味がありません。意思は「遺言書」または「エンディングノート」に記録し、確実に共有できるようにしましょう。
【遺言書とは】
- ・自身の死後について言い残したいこと(主に相続関係)を残すための文書。
- ・遺言書に書かれていることは法的効力を持つが、不備があると無効となる。
【エンディングノートとは】
- ・終活に関係する項目(医療、介護、財産、葬儀、お墓など)の現状や希望を自由にまとめることのできるツール。デジタル形式もある。
- ・法的効力はない。
思い出や家族に向けたメッセージを残したい場合は、写真・動画などが共有できる終活ツールの活用がおすすめです。参考として、弊社が独自に開発した「つなごう」をご覧ください。
3.家族で終活を始めるタイミング

終活を始めるタイミングに決まりはありませんが、加齢や認知症によって判断能力が衰えてしまうと、スムーズに進められなくなってしまいます。本人の健康状態がよく、なおかつ以下のような「自分の人生に目を向けやすい時」に声をかけてみてはいかがでしょうか。
- ・仕事を定年退職した
- ・還暦を迎えた
- ・健康に不安を覚えるようになった
- ・新たなやりがいや目標を見つけた
- ・(本人の)子どもが独立、または結婚・出産をした
次項では、終活について自然に話し合うための切り出し方をご紹介いたします。
4.終活の話を自然に切り出す5つの方法

親の終活をサポートする上で多くの方が悩み、難航するのが「話の切り出し方」です。相続やお墓についてストレートに聞いてしまった結果、親が気分を害してしまうケースも少なくありません。
こちらでは、親に終活の話題を自然に切り出すための5つの方法を、具体例と共にご紹介します。ぜひ参考になさってください。
方法1.「自分が終活を始めた」と切り出す
相手に行動を促すために「まずは自分がやってみる」のは非常に有効です。「なぜ始めたのか」「終活のどのようなところに悩んでいるのか」などを伝えることで、興味を引くことができます。
本格的な取り組みでなくとも、例えば断捨離など比較的誰でも簡単にできることから始めてもよいでしょう。一緒に終活を行う「終活仲間」になれば、楽しく進められるようにもなります。
【切り出し方例】
「誰でも簡単にできる終活ってことで家の整理整頓をやってみたらいい運動になったし、不要品を高値で買ってもらえたんだよね。良かったらお母さんもやってみない?」
「エンディングノートを買って試しに書いてみたんだけど、自分のことが全然わからなくて笑っちゃった。お父さんはこういうの、書こうと思えばすぐ書ける?」
方法2.テレビや知人の話をきっかけにする
有名人や身の回りの人を例に出すのもよい方法です。憧れの人、親しい人の話は受け入れやすく、また興味も持ちやすくなるでしょう。
【切り出し方例】
「お母さんの好きな俳優の〇〇、この間テレビで終活やってるって言ってたよ。まだ元気なのに、早くから将来に備えようとするなんて立派だよね。お母さんもこの機会に初めてみたら?」
「お父さんと同世代の会社の上司が『終活を始めたいんだけど何から取り組んだらいいか分からない』って悩んでたよ。お父さんだったら、どう進める?」
方法3.物・広告をきっかけに話を進める
少し意識してみると、公共交通機関や駅構内、ビルの立て看板などには終活に関係した広告が多くあることに気づきます。それらを目にしたタイミングで切り出すのはいかがでしょうか。
【切り出し方例】
「ペットも埋葬できる納骨堂、だって。すごく素敵だね。我が家の愛犬も、もしもの時はきっと家族と一緒がいいだろうし、ホームページを見てみようか」
「(介護施設の広告を見ながら)こういうのって、いろいろ種類あるけど自由に選べるのかな?確か昔おばあちゃんが〇〇(施設名)にお世話になってたよね?その時はどうやって決めたの?」
方法4.将来の困りごとから必要性を伝える
将来に起こりうるリスクを挙げて、終活を促す方法もよいでしょう。ただし、不安にさせすぎないことが大切です。あくまでも「終活を考えるきっかけになる程度」を心がけましょう。
【切り出し方例】
「認知症って、年齢が上がると発症しやすくなるんでしょう?お母さんがもしもそうなったら私がちゃんと面倒見るからさ、将来のことについての希望は早めに教えてね」
「もう長いこと使ってない空き家、そろそろどうするか決めない?時間が経つほど資産価値も下がるみたいだよ。今度、査定をしてみようよ」
方法5.趣味や楽しみに絡めて話す
ポジティブな目標や目的に絡めれば、終活もやりがいを持って取り組めるようになるでしょう。
【切り出し方例】
「旅行、楽しかったね!お母さんとはこれからもずっと一緒にいろんなことを楽しみたいと思ってるから、将来の心配事を今のうちに整理しておくと、安心して楽しめると思うんだけど、どうかな?」
「お父さん、孫が生まれて嬉しいのはすごくわかるけど、この調子じゃ体力もお金も減る一方だよ?〇〇(孫)とたくさん楽しい思い出を作っていくためにも、もしもの時の準備を一緒に考えようよ」
5.親の終活について、兄弟姉妹との話し合い方

介護や葬儀、相続など、終活で考える項目にはデリケートな問題が含まれます。そのため、一部の家族だけで親の終活を進めてしまうと、他の家族が不満を抱き、やがてトラブルに発展するケースも珍しくありません。
終活を支える際は、家族全員が協力し、一丸となることが大切です。特に兄弟姉妹がいる場合は、以下のポイントを押さえながら話し合いましょう。
- ・終活をする本人から聞いた情報は必ず共有する
- ・介護や葬儀、相続などに関する意向をすり合わせておく
- ・万が一の事態に備え、連絡方法を決めておく
6.終活を家族で進める上で注意すること

親の終活を家族でサポートする際、いくつかの注意点があります。
こちらでは、注意すべきポイントを「親との終活にありがちなトラブル事例」も交えながらご紹介します。
親(本人)の意思を最優先する
終活で最も大切なのは、親(本人)の意思を尊重することです。「お墓は管理が難しいから散骨しよう」と家族が一方的に決めたり、「遺産は平等に分けると今ここで約束してほしい」といった希望を強く要求したりすると、家族関係の悪化や、終活自体を諦めることにつながりかねません。
終活サポートは「本人の話をじっくり聞く」ところから始め、時間をかけて話し合いを重ねる姿勢が大切です。家族全員で親の希望を確認し合い、迷いが生じないよう配慮しましょう。
完璧を目指さず、できることから始める
多岐に渡る終活の項目を完璧に片付けようとすると、本人も周りも精神的に焦ってしまい、よい結果を生みません。完璧を目指さず、本人の気力や体力と相談しながら、できることから進めていくことで、納得のいく決断をしやすくなるでしょう。
家族間で情報をオープンにする
繰り返しになりますが、家族で終活をサポートする際は、関係者全員で情報を共有することが重要です。特定の家族だけで進めてしまうと、感情の対立を招いたり、誤解が生じやすくなったりします。「自分の遺産の取り分が有利になるよう、本人に取り計らった」と疑われてしまう事態を避けるためにも、情報は常にオープンにすることを心がけましょう。
意思表示の方法や法的効力の有無に注意する
特に相続においては、意思表示を残す方法に十分な注意が必要です。例えば以下のようなケースでは、希望通りの遺言が実行できなくなる可能性があります。
- ・相続に関する希望をエンディングノートにだけしか残さなかった
- ・遺言書に法的な不備があった
- ・遺言書そのものを残していなかった
こうした場合、家族は遺産相続の決定に多大な時間と労力を費やすことになりかねません。本人が決めた意志表示や希望は、適切に残すことが大切です。そのためにも、遺言書の種類や法的効力の有無について正しく理解しましょう。
終活に便乗した不適切なサービスに気を付ける
終活をサポートしてくれる外部サービスを、安易に決めてしまうのはおすすめしません。中には、終活に便乗して高額な契約を要求したり、不安を煽ったりする悪質な業者もいるからです。
対策として、以下を参考になさってください。
- ・公的機関が紹介するサービスから選ぶ
- ・ネットの口コミを確認する
- ・家族全員でよく話し合って決める
- ・業者との話し合いには、家族も同行する
7.家族の終活で悩んだら、相談窓口・専門家を活用しよう

終活に関する悩みや課題などについて、家族だけで解決できないこともあるでしょう。その場合は、専門家や企業が設けている相談窓口を積極的に活用することをおすすめします。
以下は、問題別に相談できる専門家のご紹介です。
| 分野 | サポート先一例 |
|---|---|
| 身辺整理 | 生前整理業者、ハウスクリーニング |
| 資産管理 | ファイナンシャルプランナー、銀行、弁護士、司法書士 |
| 相続 | 弁護士、司法書士、行政書士、信託銀行 |
| 医療・介護 | 地方自治体(地域包括支援センター)、病院、介護施設、弁護士(身元保証) |
| 葬儀 | 葬儀社、寺院 |
| お墓 | 葬儀社、寺院、石材店 |
詳しくは「終活サポート」の記事でご紹介しておりますので、そちらも併せてご覧ください。
8.家族で進める終活に関するQ&A

A.無理に進めようとせず、少し時間を置くことも大切です。
終活という言葉の響きや、ネガティブなイメージから終活に消極的な方は多くいらっしゃいます。そこで無理強いをしてしまうと、親御様との信頼関係に大きな影響を与えかねないため、時には時間をおいて見守る姿勢も大切です。落ち着いた頃に終活のメリットを伝え、話し合いを再開できるか様子をうかがってみてはいかがでしょうか。
なお、円満な終活に向けた話しの切り出し方は「終活の話を自然に切り出す5つの方法」が参考になります。
A.お互いが納得できるまで、冷静に意見を交換しましょう。
家族間で意見が対立してしまうことはもちろんあります。そこで感情的になってしまうと家族関係が悪化する可能性もあるため、「親の終活をサポートする」ことの目的と意義を今一度考え、冷静に話し合いを続けることが大切です。
それでもうまくいかない時は、「分野別 終活サポート一覧」としてご紹介した終活サポート窓口に相談することをおすすめします。
A.終活の悩みや不安を聞いてあげる、終活に必要な制度や手続きを代わりに調べてあげるなど、できることはたくさんあります。
終活のサポートは、必ずしも本人の近くにいる必要はありません。遠方にいても、以下のようにさまざまな手伝いができます。
- ・将来に対する悩みや不安を聞いてあげる
- ・終活に関する制度や手続きを調べる
- ・専門家によるサポートを、本人に代わって依頼する
- ・介護施設や葬儀社などのパンフレットを取り寄せる
病気やお金など、将来のことを考えていると不安になってくるものです。「遠方にいるけれどサポートするよ」と伝えてくれる家族の存在が、大きな支えとなるでしょう。
9.本人の意思を最優先にして家族で終活を支えよう

高齢の親を持つ子ども世代にとって「親の終活」は気になる問題です。親(本人)の意思を尊重しつつ、適切なサポートをすることで、家族全員が安心した日々を過ごせるようになるでしょう。
終活に関するご相談は、花葬儀までお寄せください。花葬儀では弁護士などの各種専門家と連携しているため、葬儀だけでなく、介護や不動産などのお悩みをまとめて相談することができます。
「終活の相談にあちこち行く時間も余裕もない」「漠然とした悩みをとりあえず聞いてほしい」といった方におすすめです。まずは無料の事前相談にて、自由にお話しをお聞かせください。ご相談お待ちしております。