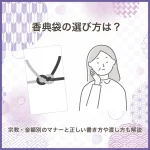家族葬を会社に連絡する方法は?タイミング・文例・香典辞退の伝え方まで解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式のマナー 】

家族葬を選んだものの、「会社にどう伝えるべきか」「お香典や弔電を辞退しても失礼にあたらないか」と悩む方は少なくありません。何をどのように伝えるべきか、判断に迷う場面も多いものです。
そこで今回は、家族葬を会社に連絡する際のマナーや香典辞退の伝え方、具体的な連絡方法まで詳しく解説します。文例もご紹介しておりますので、家族葬を控えている方や、家族葬の会社への連絡に不安がある方は、ぜひこの記事を参考にしてください。
【もくじ】
1.なぜ家族葬でも会社に連絡が必要なのか

家族葬で葬儀を行う場合でも、会社への連絡は欠かせません。以下より、理由やその詳細を解説します。
忌引き休暇の取得や業務の引き継ぎに不可欠
家族葬は参列者が限られた葬儀のため、家族葬についての連絡は、控えめにしたいと考える方もいらっしゃいます。しかし、ご自身が会社員であれば、勤務先への連絡は省略できません。忌引き休暇を取得するためには、会社への正式な報告が必須だからです。
数日間職場を離れる以上、担当業務の引き継ぎや緊急時の連絡方法を共有しておくことは、社会的なマナーです。もちろん、故人様が生前お世話になった勤務先へも、死亡退職に伴う手続きなどのために連絡が欠かせません。
香典などを辞退する場合も必要
訃報を知った方の中には、「せめて弔意だけでも示したい」と、お香典や供花、弔電などを準備しようと考えてくださる方もいらっしゃるでしょう。こういったお気遣いを辞退したい場合は、辞退の意思を確実に伝えるためにも、連絡が必要です。
連絡を入れずにいると、会社側が従来の慣例や社内規定に沿って、お香典や弔電を手配してしまうかもしれません。上司や総務担当者が、それぞれで対応するケースも多く、辞退の意思が明らかでなければ、部署ごとで判断が分かれて混乱を招く可能性もあります。
2.家族葬で会社の香典や弔電の辞退は失礼にあたらない
家族葬では香典や弔電を辞退するケースが多く見られますが、会社にも辞退の意向を伝えていいのでしょうか。判断のポイントや配慮すべき点を解説します。
昨今、香典・弔電の辞退が増えている
かつては、お香典や弔電を受け取るのが礼儀とされていましたが、現在ではその価値観も大きく変わりつつあります。特に家族葬では、ご遺族の負担軽減や故人様の「静かに見送ってほしい」との意向を尊重し、厚意を辞退することも珍しくありません。
ご自身や故人様の勤務先の会社に対しても、あらかじめ辞退の旨を伝えておくことで、余計な気遣いや判断の負担をかけずに済むだけでなく、ご遺族の誠意ある姿勢として受け止められます。
辞退すべきか迷ったときの判断ポイント
家族葬だからといって、必ずしも香典などを辞退しなければならないわけではない、ということです。お心遣いをありがたくお受け取りすることも、弔意を示したいという相手の気持ちに応える、ひとつの形です。どちらを選んでも間違いではありません。
辞退すべきか迷ったときは、感情だけではなく、状況を冷静に整理したうえで検討しましょう。
判断の基準には、以下のような点が挙げられます。
・社内で香典や弔電の取り扱いに関する慣習や規定があるか
・ご遺族として香典返しや弔問対応の負担が大きくなりそうかどうか
最終的にどちらを選ぶにせよ、ご家族で話し合い、状況や気持ちに沿った判断であれば、それが最善の選択です。
辞退を会社に伝える際の配慮
会社に対してお香典や弔電を辞退する旨を伝える際は、言葉の選び方や伝え方に配慮することが重要です。
相手の厚意を否定するような印象を与えないよう、次のような言葉を添えます。
・辞退が「故人様の遺志」または「ご遺族の希望」である
・「ご厚意はお気持ちだけでありがたく頂戴いたします」などの一言
・故人様が在職中にお世話になったことへの感謝の言葉
3.家族葬を自分の会社に連絡する方法と文例

ご遺族がご自身の勤務先への家族葬を連絡する際の順番や、事前に押さえておきたい確認事項を解説します。
自分の勤務先に連絡する際の基本手順
ご自身の勤務先へは、訃報の連絡をできるだけ早めに行うことが大切です。その後、家族葬をすることが決まった時点で、あらためて葬儀について伝えます。
家族葬の連絡時に伝えるべき主な項目は以下です。
・故人様との関係(続柄)
・葬儀の日程(通夜・告別式の日にち)
・家族葬で執り行うこと
・忌引き休暇の希望日数
・休暇中の連絡先
・緊急時の対応が必要な業務の有無
・参列やお香典などを辞退すること(必要に応じて)
葬儀の日時や会場などの詳細について、会社に共有したくない場合は「非公開」と伝えるのもひとつの方法です。ただし、忌引き休暇を取得するにあたり、少なくとも休暇の開始日と終了日は、連絡する必要があるでしょう。
また、会社の規定に応じて総務や人事部門への手続きが必要になる場合は、並行して担当部署へ連絡をします。
会社連絡で事前に整理・確認すべき情報
勤務先に家族葬の連絡をする前には、以下の項目をあらかじめ整理・確認しておくとよいでしょう。
・弔事休暇の日数や取得条件
社内規定を確認し、ご自身の状況に合った休暇日数や取得条件を把握しておきましょう。
・休暇取得期間と復帰予定日
実際に取得する休暇期間と、いつ頃復帰できるか具体的な日付を整理します。
・休暇中の連絡手段や担当者への引き継ぎ内容
休暇中に緊急の連絡が必要な場合の手段や、担当している業務を引き継ぐ際の具体的な内容を確認しておきます。
弔事休暇の取得条件は続柄によって異なるため、社内規定を確認のうえ、必要に応じて有給休暇の取得も検討しましょう。
自分の勤務先に連絡する文例
ご遺族がご自身の勤務先へ、訃報や家族葬について連絡する文例をご紹介します。
訃報を電話で連絡する文例
私事で恐縮ですが、兄が〇月〇日に永眠いたしました。
急なことで大変申し訳ありませんが、
休暇の取得についてご相談させていただきたくご連絡いたしました。
葬儀の詳細については、決まり次第改めてお伝えいたします。
ご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。
家族葬を電話で連絡する文例
私事で恐縮ですが、父の葬儀を〇月○日に
家族のみで執り行うこととなりました。
◯月◯日から◯日間、忌引き休暇をいただきたいと思っております。
ご香典などのお気持ちは、勝手ながら辞退させていただければ幸いです。
業務の件で急ぎのことがあれば、チャット等でご連絡いただけますと助かります。
総務・人事部にメールで連絡する文例(忌引き休暇依頼)
総務部ご担当者様
お世話になっております。◯◯部の□□です。
〇月○日に、父が逝去いたしましたため、
忌引き休暇を取得させていただきたくご連絡申し上げます。
葬儀は家族葬にて執り行う予定であり、
ご厚志などのお気遣いは恐縮ながら辞退申し上げます。
◯月◯日から◯日間の休暇を予定しております。
必要な書類や手続きがございましたら、ご教示いただけますと幸いです。
ご対応のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。
4.故人が勤務していた会社に家族葬を連絡する方法と文例

故人様の勤務先にも、訃報を伝えてから改めて家族葬の連絡をするのが一般的です。連絡方法のポイントを説明します。
会社への訃報の連絡手順
故人様が現役で働いていた場合、会社への訃報連絡は電話で早急かつ正確に行います。ご遺族の代表者が、代表番号にかけ、部署や担当者につないでもらうのが基本です。
伝えるべき主な情報は以下です。
・故人様の氏名と所属部署など会社での立場がわかる情報
・連絡しているご家族の氏名と続柄
・訃報をどこまで社内で共有してよいか(希望があれば)
家族葬の連絡で伝えるべきこと
訃報のあと、家族葬であることを会社に伝える際に押さえるべきポイントは以下です。
・葬儀の日時や会場を非公開にしたい場合はそのこともきちんと伝える
・会社への感謝の気持ちを一言添える
・参列やお香典を辞退する場合は、明確に伝える
故人の勤務先に連絡する文例
故人様が勤務していた会社に、訃報と家族葬を伝える文例をご紹介します。
訃報を電話で伝える文例
突然のことで恐縮ですが、本日は父〇〇が永眠いたしましたことを
ご報告させていただくためにご連絡させていただきました。
生前は大変お世話になり、家族一同、心より感謝申し上げます。
葬儀の詳細につきましては、決まり次第、改めてご連絡させていただきます。
ご不明な点などございましたら、私の方までご連絡いただければ幸いです。
電話番号は、090-0000-0000でございます。
何卒よろしくお願いいたします。
家族葬を電話で伝える文例
先日、訃報のご連絡を差し上げましたが、
葬儀は近親者のみで執り行う家族葬とさせていただくこととなりました。
誠に恐縮ですが、故人の意向でもございますので、
ご香典やご供花、ご弔電などはご辞退申し上げたく存じます
また、葬儀の詳細につきましてはご内密にしていただければ幸いです。
何卒ご了承いただけますようよろしくお願い申し上げます。
家族葬をメールで伝える文例
◯◯部ご担当者様
平素よりお世話になっております。◯◯(故人様の氏名)の長男、□□と申します。
先日は訃報に際しご配慮をいただき、誠にありがとうございました。
葬儀につきましては、故人の希望により、
近親者のみで静かに執り行うことといたしました。
ご厚志につきましても、勝手ながらお断り申し上げたく存じます。
何卒ご理解賜りますようお願いいたします。
5.家族葬後の会社からの香典や慶弔金への対応方
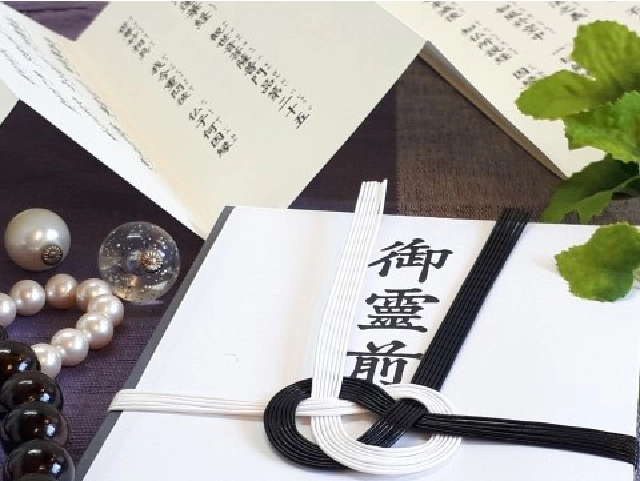
家族葬を終えた後、会社からお香典や慶弔金をいただくことがあります。ご遺族のお考えとして、お心遣いをありがたくお受け取りすることもあれば、深い弔意を示したい方から個別でいただくこともあるでしょう。こちらでは、それらの返礼方法やマナーを解説します。
香典と慶弔金の違い
慶弔金とは、会社の福利厚生制度の一環であり、社員やご家族の祝い事、不幸事の際に支払われるお金のことです。慶弔金と似た言葉で「弔慰金」がありますが、これは社員やそのご家族の死亡時に、会社がご遺族に送るお金を指すもので、慶弔金の一種であると言えます。
会社からの慶弔金や弔慰金については、一般的にお返しは必要ありません。会社の福利厚生規定に基づき、経費として支給されているためです。
一方、お香典は、故人様にお供えするお金、花輪や線香の代わりに渡すものです。次から、会社からいただいたお香典に対する対応を解説します。
会社からいただいた香典への返礼対応とマナー
家族葬で会社からお香典をいただいた場合は、相手との関係性によって返礼の要否や対応のマナーが異なります。
お香典の名義によって、次のような対応をするとよいでしょう。
【会社や社長名義の場合】
全社を代表して贈られるお香典は、福利厚生の一環とされることが多く、基本的に香典返しは必要ありません。お礼状で感謝の気持ちを丁寧に伝えます。
【部署やチームなど連名の場合】
部署やチームが自発的に用意してくれたお香典の場合は、お返しを用意することをおすすめします。一人あたりの金額が数千円未満であれば、個包装の菓子折りなどを渡すとよいでしょう。
一人あたりの金額が3,000円以上になるような場合は、一般的な香典返しと同様に、いただいた金額の3分の1から半額程度を目安にした品物を個別に用意してお渡しすると、より丁寧な対応となります。
【個人名義の場合】
故人様やご遺族との個人的な付き合いでお香典をいただいた場合は、一般的な香典返しと同様に対応するのが基本です。金額の3分の1〜半額程度を目安に品物を選び、必ずお礼状を添えてお渡ししましょう。
6.家族葬の会社への連絡に関するQ&A
A.会社名義の場合は、感謝の気持ちを伝えるだけで十分です。
家族葬で弔電を辞退していた場合でも届いたときは、「お気持ちをありがたく頂戴いたします」といった言葉を添えて、挨拶状か電話でお礼を伝えます。返礼品は基本的に不要ですが、心配な場合は総務や上司に確認しましょう。
A.基本的には、すべての部下やメンバーに家族葬の連絡をする必要はありません。
仕事の連携を円滑にするために、日常的に関わりの深い部下やメンバーには、適切なタイミングで簡潔に知らせるとよいでしょう。個人的な関係性が深くない場合は、直属の上司や関係部署への連絡で十分な場合もあります。
A.メーリングリストや部署全員が参加するチャットなどの使用は、控えるのがマナーです。
家族葬は限られた方のみで執り行う葬儀で、全社的に知らせる必要はありません。お香典や参列の辞退を伝えたい場合でも、直属の上司や関係部署の代表者に個別に連絡し、そこから必要な範囲へ共有してもらうのが適切な対応です。
A.可能ですが、ご自身が一度簡潔にでも直接伝えることをおすすめします。
弔事は突然起こるもので、ご自身が深い悲しみや葬儀準備で動けないこともあります。そうした際は、要点だけでもご自身で会社に伝えたうえで、詳細の連絡や手続きをご親族に任せましょう。
7.家族葬の会社への連絡には配慮とマナーを心がけましょう
会社への連絡をどうするかは、家族葬の準備の中でも意外と迷うものです。会社の慣習や社内での立場によっても対応の方法は異なり、一律の正解がないからこそ、マナーを押さえつつ、「誰に・何を・どのように伝えるか」を丁寧に考えましょう。
会社への家族葬の連絡に不安のある方や、香典辞退などの伝え方を知りたい方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。専門スタッフが、個々のご状況に応じて、会社への連絡方法や内容について丁寧なアドバイスをいたします。