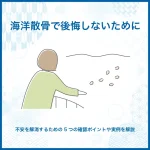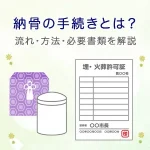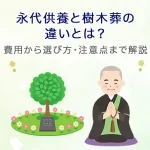お墓はいらない?後悔しないための判断と供養方法を解説
- 作成日: 更新日:
- 【 お墓の基礎知識 】

近年、「お墓はいらない」という価値観が広がりつつあります。ここで言う「お墓」とは、墓石を建てる従来型の一般墓のことです。お墓の引越しを指す「改葬」の件数は全国的に増加傾向にあり、2024年度には約17万6千件を記録しました。
従来の「先祖代々お墓を継ぐ」という価値観が見直されつつあります。とはいえ、「お墓を持たなくて本当に大丈夫だろうか」「ご先祖様をきちんと供養できるのか」と、不安を感じる方も少なくありません。
この記事では、お墓を持たないという選択肢を考える方に向けて、判断のポイント、代わりとなる供養方法や後悔しない選び方を、わかりやすく解説します。
1.「お墓はいらない」と考える人が増えている

まず、「なぜ今お墓はいらないと考える人が増えているのか」「お墓を持たないことのメリット」、そして「それでもお墓を持つ意義」について見ていきましょう。
お墓を持たない人が増加している理由
この十数年で、「お墓を建てない」「お墓を継がない」という選択をする人は急速に増加しています。主な理由として、地方にあるお墓を管理できないケースが多くなっていることが挙げられます。
背景には、少子化や核家族化が進み、家族単位での生活が中心となっていることがあります。また、都市部への人口集中により、ご親族が遠方に分かれて暮らすことで「お墓参りに行けない」「維持が難しい」といった問題が現実化しています。加えて、お墓の管理費・修繕費・交通費などの金銭的負担も少なくありません。
こうした社会的・経済的な背景が、「お墓を持たない」という選択を後押ししているのです。
お墓を持たないメリット
お墓を持たないという選択には、以下のようなメリットがあります。
・管理の手間がかからない
草むしりや墓石の清掃、法要時期の準備など、従来のお墓に必要だった維持管理の負担がありません。
・継承者がいなくても安心
少子化や核家族化により「お墓を守る人がいない」という不安を抱える家庭が増えていますが、無縁化の心配が少なくなります。
・価値観に合わせた自由な供養ができる
緑豊かな場所で眠れる樹木葬、故人をいつでもそばに感じられる手元供養など、ご家族のライフスタイルや故人様の想いを形にする供養方法を選ぶことができます。
さまざまな新しい供養の形が広がることで、「お墓はいらない」という考え方が定着しつつあるのです。
それでも「お墓を持つ」ことの意義
お墓を持たないという考え方が広がる一方で、お墓を持つことにも確かな価値があります。お墓は、ご家族のつながりを感じる場であり、ご先祖様を敬う日本の文化を受け継ぐ大切な存在です。お墓参りを通じてご家族が集まり、世代を超えて思いをつなぐ時間は、心のよりどころにもなります。
また、長年守り続けてきたお墓を継承することは、「家の歴史を大切に受け継いでいる」という安心感や誇りにつながる場合もあります。お墓を持つかどうかは、それぞれの家庭や価値観によって異なりますが、どちらの選択にも尊重すべき意義があると言えるでしょう。
2.お墓がいらない人が知っておきたい「永代供養」の仕組み
永代供養とは、寺院や霊園などがご遺骨を長期にわたり供養・管理してくれる埋葬方法です。永代供養を前提とした供養方法の総称を、永代供養墓と言います。
永代供養を選んだ場合、一定期間個別に安置したのち、他のご遺骨と合祀(ごうし※)するのが一般的です。合祀後は個別に取り出せないため、「後で遺骨を移したい」と考えている場合は注意が必要です。
※合祀:複数のご遺骨をひとつの墓所や納骨施設にまとめて埋葬すること。
3.お墓を建てる代わりとなる供養の形
前の章で解説した「永代供養」は、承継者がいなくても安心できる心強い仕組みです。ここでは、永代供養の仕組みを利用したものも含め、お墓を建てる代わりとなる供養の形を4つご紹介します。それぞれの特徴を比較し、ご自身の価値観やライフスタイルに合った方法を見つけていきましょう。
納骨堂
屋内施設にご遺骨を安置する納骨堂は、近年人気が高まっています。天候や季節に左右されずお参りできるのが、大きな魅力です。さらに、多くの納骨堂は駅から近い便利な立地にあり、エレベーターやバリアフリー設備も整っているため、ご高齢の方でも安心してお参りできます。
樹木葬
樹木葬は、墓石の代わりに樹木や草花を墓標としてご遺骨を埋葬する方法です。自然と共に眠りたいと考える方に多く選ばれています。緑に囲まれた静かな環境の中で、四季折々の花や木々に見守られながら安らかに眠れるのが大きな魅力です。
散骨
散骨は、ご遺骨を粉末状にして自然へ返す供養方法で、海洋散骨(海洋葬)や山林散骨などの形があります。法律上は「節度をもって行う限り」違法ではありませんが、私有地や漁業区域などでは禁止されていることが多く、土地の所有者や自治体のルールに従う必要があります。散骨を検討するならば、専門業者に依頼することをおすすめします。
手元供養
手元供養とは、故人様のご遺骨や遺灰の一部を自宅で保管したり、アクセサリーなどに納めたりして、身近で供養する方法です。「いつでも故人を感じていたい」「お墓参りが難しいけれど、日々祈りを捧げたい」という方に選ばれています。
手元供養には、ミニ骨壺や遺骨ペンダント、遺骨ジュエリーなど、さまざまなスタイルがあります。ご遺骨の一部のみを手元に残し、残りのご遺骨は永代供養や納骨堂に預けることが一般的です。
4.従来型のお墓と別の供養方法の費用の比較
お墓を持つか、持たないかを判断するうえで、気になるのが費用でしょう。
ここでは、発生する費用を比較するとともに将来に向けて持つべき視点もご紹介します。
一般的なお墓
一般的なお墓にかかる費用は、墓石代・永代使用料・工事費などを合わせておよそ100万円〜160万円が目安です。地域や墓地の種類によっては、200万円を超えるケースも見られます。
さらに、維持管理費として毎年5千円〜1万円前後が必要で、特に寺院墓地や設備の整った霊園では、年間2万円以上になる場合もあります。
一般的なお墓以外の供養方法
墓じまいや、お墓を建てずに供養する場合にも一定の費用がかかります。
主な費用の目安は次のとおりです。
納骨堂
ロッカー式、自動搬送式や個室型などさまざまなタイプがあり、10万円〜150万円前後が目安です。
樹木葬
樹木葬の費用は、埋葬方法の違いによって大きく異なります。たとえば、合祀型の場合は、約5万円〜30万円と比較的手頃です。一方で、個人やご家族ごとに専用区画を設ける「個別区画型」では、おおむね20万円〜150万円前後が一般的な目安となります。年間管理費は、無料~3万円程度に設定されているケースが多いです。
散骨
海洋散骨にはいくつかの形式があり、費用は内容によって異なります。チャーター散骨はご家族で船を貸し切る方法で15万円〜40万円程度、合同散骨は他のご遺族と乗り合わせる形で5万円〜20万円ほど、委託散骨は業者に任せる形式で3万円〜10万円前後です。
山林散骨の費用相場は5万円〜30万円ほどです。山林には所有者があり、自治体によっては散骨が禁止されているため、専門業者への依頼が一般的です。業者に一任する場合は約5万円前後、ご遺族が同行する場合は10万円以上になることもあります。
手元供養
手元供養の費用は、選ぶ品物の種類によって変動します。ご遺骨の一部を納める小さな骨壺やペンダントであれば、数千円から選ぶことができます。一方で、ご遺骨を加工したり、デザイン性の高い品であったりするの場合、数十万円になる場合もあります。
5.「お墓はいらない」と決める前に考えること
「お墓はいらない」と決める前に、慎重に考えるべきことがあります。後でご家族やご親族との関係に影響を及ぼしたり、供養の方法で後悔したりすることがないよう、ここでは、判断前に整理しておきたい3つの視点をご紹介します。
ご家族・ご親族との話し合いが不可欠
最も大切なのが、ご家族・ご親族との話し合いです。たとえご自身の意思が明確であっても、「代々守ってきたお墓を閉じる」「お墓を建てない」という決断に感情的な抵抗を覚えるご親族も少なくありません。話し合いを避けたまま進めると、「勝手に墓じまいをした」「供養を軽んじている」と誤解を招くこともあります。
特に地方では、お墓を一族の象徴として大切にする文化が根強く残っているため、事前の合意形成が欠かせません。話し合いの際は、「自分たちがどんな供養を望んでいるか」「今後どのように遺骨を扱うか」を丁寧に説明し、相手の意見にも耳を傾けましょう。葬儀社や行政書士などの第三者に同席してもらうと、冷静な話し合いがしやすくなります。
遺骨と供養の方向性を家族で決めておく
お墓を建てない場合、ご遺骨をどのように供養していくのか、その大まかな方向性をご家族で早めに話し合っておくことが重要です。
たとえば、後継者がいない場合は、寺院が長期的に供養を行う永代供養墓が現実的な選択肢になります。一方、生活拠点の近くでお参りを続けたい場合は、アクセスしやすい屋内型の納骨堂を検討する人も増えています。また、「自然に返りたい」という想いが強い方には散骨など、自然回帰を重視した供養もあります。
お墓を建てない場合の供養方法の種類や特徴については、「お墓を建てる代わりとなる供養の形」で詳しく解説しておりますので、そちらを参考になさってください。
ご自身の心理的リスクを考える
お墓がなくなることで、「手を合わせる場所がない」「故人とのつながりが薄れた気がする」と感じる方も少なくありません。お墓は、故人様をしのぶだけでなく、残された人の心を支える存在でもあったため、その喪失感が思いのほか大きくなることがあります。
また、「この選択で本当によかったのか」「供養の形として十分なのか」といった迷いや不安を自分の中に抱くこともあります。そうした心の揺れを減らすためには、自分にとっての供養の意味を見つめ直し、どのように故人様を想い、心をつないでいくかをあらかじめしっかり考えておくことが大切です。
将来を見据えた選択を
費用を抑えることも大切ですが、心の納得とご家族の理解が伴うことこそ、長い目で見て後悔のない供養につながります。たとえ費用を抑えられても、後になってご家族が不満に感じる方法では、かえって負担を残してしまうことになりかねません。
供養は「終わり」ではなく「続いていくもの」です。将来の見通しを立てて、誰も困らない形を選ぶことが大切です。
6.今あるお墓を墓じまいする手続きと注意点
すでにお墓を所有していて、「お墓はいらない」と考える場合には、お墓を整理するための「墓じまい」を検討する必要があります。
ここでは、墓じまいを行う際の基本的な流れや注意したいポイントを解説します。
墓じまいの基本的な流れ
墓じまいを進める際には、次のようなステップを踏むのが一般的です。
1.ご親族と話し合う
まずは、先祖代々のお墓を取り壊すという重大な決定について、ご親族の理解・合意を得ることが重要です。
2.墓地の管理者に相談する
ご親族の合意が得られたら、現在お墓がある寺院や霊園の管理者に、墓じまいを検討している旨を相談します。このとき、これまでお墓を管理してくださったことへの感謝を伝えることが大切です。特に菩提寺(ぼだいじ)の場合、墓じまいは檀家(だんか)をやめる「離檀(りだん)」にあたるため、丁寧な対話を心がけましょう。
3.改葬(移転)先を決める
現在の墓地から別の場所へご遺骨を移す場合は、新しい納骨先(霊園・納骨堂・永代供養など)をあらかじめ決め、受入証明書など必要書類を取得しておく必要があります。
4.自治体へ申請書を提出する
現在ご遺骨がある墓地が所在する自治体に「改葬許可申請書」を提出し、必要に応じて「埋蔵(納骨)証明書」や「受入証明書」などを添付します。許可がおりて「改葬許可証」が発行されてからご遺骨を移動するのが原則です。
5.閉眼供養(へいげんくよう)を行う
閉眼供養は、お墓に宿る故人様の魂を抜く仏教の儀式で、「魂抜き」や「お性根抜き」とも呼ばれます。僧侶による読経を伴うため、菩提寺がない場合は、あらかじめ地域の寺院などに依頼しておきましょう。
6.墓石を撤去して墓地を原状に戻す
閉眼供養を終えたら、ご遺骨を取り出し、墓石を撤去して区画を更地に戻し、墓地へ返還します。撤去作業は通常、墓石を施工した石材店が担当します。
墓じまいにかかる費用
墓じまいでは、墓石の撤去・整地費用、閉眼供養の読経料、ご遺骨の運搬費などが必要です。総額は幅があり、約30万円〜200万円です。詳しくは「墓じまいの費用の相場」の記事をご覧ください。
よくあるトラブルと回避策
墓じまいでは、離檀料や手続きの不備がトラブルになりやすい傾向があります。
寺院墓地の場合、檀家関係を解消する際に「離檀料」を求められることがあります。離檀料には法的な基準や支払い義務はありませんが、「これまでのお世話になったことへの感謝の気持ちとしてお渡しするお布施」と考え、丁寧にお渡しするとよいでしょう。
また、ご親族に無断でお墓を撤去したことによるトラブルや、石材店との費用面でのトラブルも少なくありません。墓地管理者に改葬許可を得ずに墓石を撤去すると違法行為となる可能性もあるため、トラブルに発展しそうな場合は、墓じまいに詳しい専門家に相談して進めると安心です。
7.お墓がいらない場合に関するQ&A
A.「お墓を持たない」という選択は、世代や地域によって受け止め方が大きく異なります。伝えるときは、「新しい供養の形を考えている」という前向きな言葉を使うのが効果的です。
たとえば、「永代供養で長く安心できる方法にしたい」「自然に返ることができる樹木葬で、故人らしく見送りたい」など、理由と目的を明確に伝えましょう。どうしても話しづらい場合は、葬儀社や行政書士など第三者を交えて冷静に説明する方法もあります。
A.紛失・湿気・相続トラブルなどのリスクに注意が必要です。
ご遺骨は「祭祀財産(さいしざいさん)」として扱われ、法律上は特定の相続人が引き継ぐ権利を持ちます。そのため、親族間で「誰が保管するか」を明確に決めておくことが大切です。
また、湿気やカビを防ぐため、通気性のよい容器を選び、長期間保管する場合は防湿剤を入れるなどの工夫をしましょう。ご遺骨の扱いは自治体によって異なりますので、将来的に永代供養や納骨堂に移す予定がある場合は、事前に自治体へ確認すると安心です。
A.供養の方法によっては後からの変更も可能です。
たとえば、納骨堂や永代供養墓の場合は契約期間が設けられていることが多く、その期間内であれば別の納骨先へ移すことができます。ただし、散骨や合祀のように「遺骨を自然に返す・混ぜる」方法ではご遺骨を取り出せないことが多いため、慎重に判断する必要があります。
後悔を防ぐためには、「いずれ変えるかもしれない」ことを想定し、契約内容に“変更・移転の可否”が明記されているかを確認しておきましょう。
8.ご家族が納得できる、自分たちらしい供養の形を
お墓を持たないという選択は、「供養をやめること」ではなく、「自分たちらしい形で故人様を想うこと」です。永代供養墓や樹木葬、散骨など、供養の形は多様になっていますが、どの方法を選んでも大切なのは故人様への想いです。
費用や形式にとらわれず、ご家族全員が安心して納得できる供養の形を選ぶことが、後悔のない選択につながります。
花葬儀では、永代供養や樹木葬などの多彩な供養プランをご提供しています。ご希望に合った供養の形を検討したい方は、メンバーシップ制度「リベントファミリー」をご検討ください。故人様への想いを大切に、心が穏やかに続く供養の形を、しっかりと選んでいきましょう。