戒名の種類とは?院号・道号・位号の違いと選び方・費用を解説
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
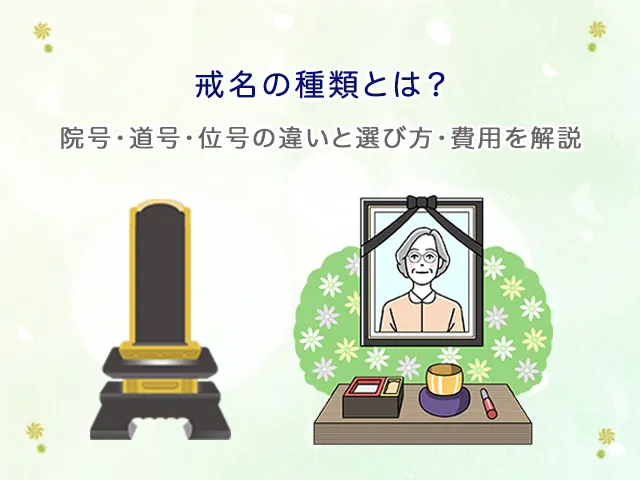
「亡くなった後に授かるもの」というイメージのある戒名(かいみょう)には、いくつかの種類やルールがあります。これから初めて戒名を依頼しようとしている方にとっては、「どんな種類があるのか」「どう選べばよいのか」とわからないことが多いかもしれません。
本記事では、戒名の基本知識から種類・構造の違い、選び方のポイントや費用までを丁寧に解説します。後悔のない選択をするためにも、ぜひ最後までお読みください。
1.戒名とは?意味と授かる理由

戒名は「名前の一種」であると同時に、仏教において大切な意味を持っています。
まずは戒名の本来の意味や、授かる理由について詳しくご紹介します。
戒名の本来の意味と歴史
戒名とは、多くの仏教における「戒律を守る者」、つまり仏門に入った弟子の証しとして僧侶から授かる名前のことです。奈良時代に中国から伝わり、江戸時代に「檀家制度(※1)」ができたことによって、広く浸透したといわれています。
なお、もともと戒名は、生前に仏門に入った方だけに授けられるものでしたが、現代では出家しているかどうかに関わらず、亡くなった後に僧侶から授かるのが一般的です。
(※1)だんかせいど:当時禁止されていたキリシタン(キリスト教徒)を廃絶するため、家単位で特定の寺院に属させることを目的とした制度。寺請制度とも呼ばれる。
戒名を授かる意義と葬儀での役割
戒名は、俗名(ぞくみょう:生前の名前)とは異なるあの世での名前です。故人様の人柄や人生、寺院への貢献度などを基に考えられる戒名には、故人様が仏門に入り、迷うことなく極楽浄土へ導かれるようにとの祈りが込められています。
授かった戒名は、「位牌(いはい)」に記され、葬儀の祭壇やご自宅の仏壇にまつられます。故人様をしのび感謝の気持ちを込めながら手を合わせる対象として、末永く大切な存在となるのです。戒名は、故人様の人生とご家族の想いをひとつの名前に込め、大切な方を送り出す供養のかたちとも言えるでしょう。
2.戒名の種類とは?院号・道号・位号の違い

ここからは、多くの方が気になる「戒名の種類」について詳しくご紹介します。一見同じように見える戒名ですが、実は構造や要素によりいくつかの種類や格式の違いがあります。それらの違いを知ることで、より納得のできる戒名が得られるようになるでしょう。
戒名の基本構造(院号・道号・位号)と各要素の役割
戒名は、いくつかの要素が組み合わさって構成されることが一般的です。代表的な戒名は以下の4つの要素から成り立っています。
- ・院殿号(いんでんごう)/院号(いんごう)
- ・道号(どうごう)
- ・戒名
- ・位号(いごう)
院殿号・院号
院殿号・院号は、戒名の最初に付けられる称号で「〇〇院」や「〇〇院殿」と記されます。
もともとは位の高い貴族や天皇にだけつけることが許されていた号でした。現代では、寺院に高い貢献をした人や、功績を残した人、身分の高い人などに与えられます。
道号
道号は、仏の道を極めた僧侶につけられる称号で「〇号」と記されます。故人様の人柄や趣味、場所や地域などにちなんだ文字(光、翁、老、海、山、月など)がよく用いられます。なお、生まれる前に亡くなったお子様や幼児、未成年者にはつけません。
戒名
戒名はあの世で名乗る仏弟子としてつけられる2文字の名前です。本来の戒名はこの2文字のみを指しますが、院号・道号・戒名・位号を合わせて「戒名」と呼ぶこともあります。
一般的に戒名に用いられる文字は以下の通りです。
- ・俗名
- ・先祖代々受け継いでいる文字
- ・仏様の名前や経典からとった文字
- ・故人様が尊敬している人からとった文字
- ・故人様の生前の職業を想起させる文字
一方で、戒名には以下のような避けるべき文字もあります。ご家族の希望する文字が該当していないか、必ず確認するようにしましょう。
- ・不穏な意味を持つ文字:「死」「病」「争」「狂」など
- ・戒名としては意味をもたない文字:「乃」「也」「於」「但」など
- ・動物を表す文字(※2):「馬」「牛」「犬」「蛇」など
- ・宗派の開祖の名前:「空海」「法然」「日蓮」「最澄」など
- ・天皇の尊号や年号:「大正」「昭和」「平成」「令和」など
(※2)ただし「龍」「鶴」「亀」など吉兆とされる動物を表す文字は使用可能。
位号
位号は戒名の最後に付く尊称です。たとえば、男性なら「居士(こじ)」「信士(しんし)」、女性なら「大姉(だいし)」「信女(しんにょ)」などが用いられます。位号の違いは格式の違いを表し、一般的には以下の表のように、上にいくほど格式が高いとされています。
| 男性の位号 | 女性の位号 |
|---|---|
| 院居士(いんこじ) | 院大姉(いんだいし/いんだいじ) |
| 院信士(いんしんし) | 院信女(いんしんにょ) |
| 居士(こじ) | 大姉(だいし/だいじ) |
| 信士(しんし) | 信女(しんにょ) |
※宗派によっては別の位号を使用することもあります。
これらを組み合わせ、「〇〇院□□道△△居士」というような戒名が授けられます。ただしこの形は一定ではなく、宗派ごとに異なります。詳しくは後述する「宗派別に異なる戒名の特徴と考え方」をご覧ください。
戒名の格式(ランク)を決めるポイント
前述の院号・道号・位号といった構成要素の有無や内容によって、戒名は格式や種類に違いが生まれます。ここでは戒名の格式を左右する要素についてご説明します。
「院号」がつくかどうか
戒名の格式を決める大きな違いは「院号」の有無です。院号が付与される戒名は、格式が高い特別な称号として扱われます。なお、院殿号はもともと院号よりも下位にあたりますが、現代では院号よりもランクが高いものとされています。
位号の違い
位号は、故人様の生前の「社会的な貢献」や「信仰の深さ」に応じて、より高いものが授けられる傾向があります。では、位号の中で最も下位に位置する「信士」や「信女」を授かった方の評価が低いかというと、決してそうではありません。むしろ多くの方に授けられるのはこの「信士」「信女」であり、一般的で標準的な位号であることを覚えておきましょう。
なぜ戒名にはランクがあるのか?
戒名は、高い・低いで供養の質や効果が変わるわけではありません。それでもランクがあるのはなぜでしょうか。
その理由には諸説ありますが、一つの考え方として、「故人様の功績や貢献を戒名のランクに反映させることで、後世に伝えていく役割がある」というものがあります。つまり、戒名というかたちの中に故人様の歩みや人柄を残すことで、お墓を守っていく子孫にご先祖様の存在の大きさを伝えたいという想いが、戒名に込められることもあるのです。
子どもの戒名の構造と種類
未成年のお子様の戒名は、「戒名」「位号」で構成されます。このうち、位号は亡くなったときの年齢によって、以下のように異なります。
| 亡くなったときの年齢 | 男の子 | 女の子 |
|---|---|---|
| 0歳(死産) | 水子(すいし) | |
| 年齢が低い
年齢が高い
|
嬰児(えいじ) 孩児(がいじ) 童子(どうじ) 大童子(だいどうじ) |
嬰女(えいにょ) 孩女(がいにょ) 童女(どうにょ) 大童女(だいどうにょ) |
3.宗派別に異なる戒名の特徴と考え方

戒名の選び方は、ご家族それぞれの想いや価値観によって異なります。しかし、もう一つ重要なポイントがあることをご存知でしょうか。それが「宗派の違い」です。
戒名の呼び方や構造は宗派によって変わる場合があり、宗派独自の考え方を踏まえて選ぶことが必要です。こちらでは、宗派別に異なる戒名の特徴や考え方をわかりやすく解説します。
【宗派別】戒名の呼び方と構造の違い
代表的な宗派の戒名について、以下にご紹介します。
天台宗・真言宗・臨済宗・曹洞宗|院号・道号・戒名・位号
天台宗、真言宗、臨済宗、曹洞宗は「院号・道号・戒名・位号」の並びで戒名がつくられます。なお、位牌に戒名を刻む際は院号の上に「梵字(ぼんじ)」と呼ばれる、それぞれの宗派特有の文字がつけられます。地域や寺院によっては不要とするケースもありますので、位牌作成の前に確認しておくと安心です。
浄土宗|院号・誉号・戒名・位号
浄土宗では、道号ではなく「誉号(よごう)」が男女共に使われます。
(例:女性)
〇〇院□誉△△大姉
時宗|院号・阿号・戒名・位号
時宗も道号を用いません。代わりに、阿弥陀仏号の略である「阿号(あごう)」が使用されます。男性は「阿」、女性は「弌(いち)」とつくのが決まりです。
(例:男性)
〇〇院□阿△△居士
日蓮宗|院号・道号・法号(日号)・位号
日蓮宗では、故人様につける名前を戒名ではなく「法号(ほうごう)」といいます。法号は、男性なら「日」、女性なら「妙」をつけるのが基本です。
(例:女性)
〇〇院□妙△△大姉
浄土真宗
「阿弥陀仏の法を聞くだけで救われる」と考えられている浄土真宗では、戒名ではなく「法名(ほうみょう)」を授かります。
法名は「釋(しゃく)」と呼ばれる言葉に2文字の法名をつけた合計3文字で構成されます。戒名と違い、ランクを表す言葉は使われません。ただし社会貢献度の高い方や、寺院に大きな貢献をされた方には「院号」が授けられることもあり、その場合、以下のような構成となります。
(例:男性)
〇〇院釋□□
また、浄土真宗では位牌を用いる必要がありません。位牌はもともと亡くなった方の魂のよりしろという意味を持ちますが、浄土真宗では「亡くなった人の魂はすぐに極楽浄土に行く」と考えられているためです。
位牌の代わりに用いられるのが、「過去帳」や「法名軸」と呼ばれる帳面や掛け軸です。これらに故人様の記録として没年月日やお名前を記して、まつることがあります。
戒名と法名の違いについては「戒名と法名の違いは?」の記事も併せて参考になさってください。
宗派によっては戒名不要とされるケースも
ここまで各宗派の戒名の特徴を見てきましたが、そもそもすべての宗派で戒名が必須というわけではありません。先ほど解説した浄土真宗のように「法名」を用いる宗派もありますし、特定の宗教にとらわれない無宗教葬(自由葬)を選び、生前の名前でお送りするケースも一般的になってきました。
ここで大切なのは、「戒名や法名を授けることが不要とされるケースでも、故人様を尊ぶ気持ちに違いはない」ことです。「戒名がないから不十分」という考えは不要であり、ご家族が信仰する宗派の教えや考え方を尊重することが大切です。
「こうしなければならない」という固定観念にとらわれず、ご家族それぞれの考えに沿って選択するとよいでしょう。
実際に戒名をつけずに葬儀を行う場合の具体的な注意点については、「7. 戒名なしでの葬儀や位牌の作製は可能か」で詳しく解説しています。
4.戒名の種類別に見る費用相場

戒名の構造や種類の違いの次に気になるのが、戒名の「費用」ではないでしょうか。
この章では、戒名の費用相場と、後悔しないための考え方について詳しく解説します。
【種類別】戒名の一般的な費用目安
戒名をいただいた寺院には、「戒名料」をお支払いするのが基本です。30~50万円が目安とされますが、位号のランクが高くなるにつれ、金額も高くなる傾向にあります。また、菩提(ぼだい)寺の考えや菩提寺との関係性、宗派、地域性も金額に影響しますので、実際の戒名料は同じ寺院で戒名を授かった方に聞くか、菩提寺に直接相談しましょう。
位号のランク別の費用目安は、以下を参考になさってください。
| 位号 | 戒名料の目安 |
|---|---|
| 院居士・院大姉 | 100万円以上 |
| 院信士・院信女 | 院信女(いんしんにょ) |
| 居士(こじ) | 30~100万円以上 |
| 居士・大姉 | 35~80万円 |
| 信士・信女 | 10~50万円 |
戒名の種類で後悔しないためには?
戒名の費用は、決して安価なものではありません。そのため、「安いもので済ませたい」と考えるご家族もいれば、「高額なものを選ぶべきか」と迷う方もいらっしゃいます。そこで重要になるのが、「費用と納得感のバランス」です。
たとえば、費用を最優先して「できるだけ安く」と考えてしまうと、後悔につながってしまう可能性があります。実際、「もっと丁寧に送りたかった」「親族から不満を言われた」というケースも見られます。逆に、「高い戒名を選ばないと失礼かもしれない」と、無理をして費用をかけすぎてしまうと大きな負担になってしまうでしょう。
費用と納得感のバランスを保つポイントは以下を参考になさってください。
- ・戒名における故人様の意向や生前の考え方を尊重する
- ・ご家族自身の「どう送りたいか」という気持ちを大切にする
- ・ご親族の意見も聞き、全員が納得できるよう配慮する
- ・菩提寺や僧侶に費用面の相談をする
戒名料については遠慮せず僧侶や寺院に相談してよいものです。「予算内でお願いできるか」「どう選ぶと良いか」と率直に相談することは、決して失礼にはあたりません。納得できるかたちで進めることが後悔のない選択につながります。
5.戒名はいつまでに用意すべき?

戒名には「いつまでに授からなければならない」という明確な決まりはありません。ただし、多くの場合は葬儀の準備段階で僧侶に依頼することが一般的です。葬儀の打ち合わせの際に、葬儀社から「戒名はどうされますか?」と確認されることが多く、そのタイミングで依頼しておくとスムーズでしょう。
もし葬儀準備のタイミングで戒名をいただかなかった場合は、本位牌を依頼するまでには授かっておくのが理想です。本位牌は四十九日以降の忌明けから使用しますが、作成には1~2週間ほどがかかるため、可能な限り早いうちに取り組むようにしましょう。詳しくは「位牌はいつまでに依頼する?」をご覧ください。
6.「生前戒名」とはどんな種類の戒名?終活で選ぶ新しい選択肢

戒名は「亡くなった後に授かるのが一般的」とご紹介してきましたが、もちろん生前に授かることも可能です。元気なうちから自分の戒名を用意する方もいらっしゃいます。このような生前のうちに授かる戒名を「生前戒名」と言います。
こちらでは、生前戒名の意義やメリット、受ける際の注意点について詳しくご説明します。
生前戒名を授かる意義とメリット
戒名はもともと生前のうちに仏弟子になって授かるものですので、生前戒名は本来の意義に近いと言えます。生前戒名は終活と呼ばれる活動のひとつであり、以下のようなメリットがあります。
自分の希望を戒名に反映できる
生前戒名では、菩提寺や僧侶と直接相談しながら、戒名に入れたい文字や希望を伝えることができます。たとえば「好きだった自然にちなんだ漢字」「人生の信条に合う言葉」など、自分らしさを込めた戒名を授かることが可能です。自分の人生を象徴する“最後の名前”を自ら選ぶことができる点は、大きな安心感につながるでしょう。
ご家族への負担を減らせる
生前に戒名を授かっておくことで、葬儀の際にご家族が戒名の種類や費用で悩むことがなくなります。「どの戒名が適切か」「いくら包むべきか」といった判断が不要になり、残される家族の精神的・金銭的な負担を軽減できる点も大きなメリットです。
残りの人生を前向きに考えられる
生前戒名は、「仏弟子として生きる」という心構えを持つことにもつながります。自分の死後について前向きに考え、自分らしい送り方を準備したいと考える方にとって、生前戒名は納得できる終活の選択肢となるでしょう。
生前戒名の申し込み方法
生前戒名を希望する場合は、次のような流れで進めることが一般的です。
- 1. 付き合いのある菩提寺や僧侶に相談する
- 2. 希望の文字や戒名の方向性を伝える
- 3. 戒名料の目安や授与までの流れを確認する
- 4. 寺院の案内した方法に従って戒名料を支払う
戒名と位牌を生前に用意する場合は、位牌の文字の色に注意が必要です。基本的に位牌に刻む文字の色は金色、もしくは青や黒が用いられます。しかし生前に戒名をいただいた場合は、戒名の部分が「朱色」となるのが原則です。
これは、位牌の持ち主がまだ生きていることを表すとともに、位牌の持ち主が長生きできるよう願いを込めていることを意味しています。
7.戒名なしで葬儀や位牌作成を行う場合の注意点

宗派別に異なる戒名の特徴と考え方でご紹介したように、信仰する宗派によっては戒名が不要なケースもあります。また、ご自身の信仰する宗派で戒名が一般的であっても、戒名をつけずに俗名のままで葬儀や供養を行うことは原則として可能です。
ただし、後になって「こんなはずではなかった」と後悔したり、思わぬトラブルに発展したりしないよう、注意すべき点があります。こちらでは、戒名をつけず俗名のままで葬儀を行う場合の注意点について、詳しく解説します。
故人様が希望を残していないか確認する
まず大切なのは、故人様ご自身がどのような考えを持っていたかを確認することです。戒名について「必要ない」と明確に伝えていた方もいれば、「戒名を付けてほしい」と望んでいた方もいるかもしれません。戒名は仏の世界での名前となる大切なものですから、故人様の遺志が何より優先されるべきでしょう。
エンディングノートや遺言書、ご家族の誰かに話していなかったかなどを確認してから判断することが重要です。
ご家族やご親族の同意を必ず得ること
次に注意したいのは、ご家族やご親族の同意を得ることです。戒名については考え方が人それぞれ異なり、「戒名は大切なもの」と受け止めているご親族もいらっしゃるかもしれません。もし戒名をつけない選択をした場合、後になって「なぜ付けなかったのか」と疑問や不満が生まれることもあります。
そのため、独断で決めるのではなく、ご家族やご親族ともよく話し合い、理解を得ておくことが大切です。お互いの考えを共有し、納得したうえで決めることで、心穏やかに故人様を見送ることができるでしょう。
菩提寺との関係にも考慮する
菩提寺との関係にも注意が必要です。戒名は仏門に入った証とされるため、菩提寺がある場合、戒名なしで葬儀や納骨を行おうとすると以下のようなトラブルになることがあります。
- ・「戒名なしでは納骨できない」と断られる
- ・「法要や年忌法事を受けられない」と言われる
- ・寺院側から「正式な供養にならない」と指摘される など
これは菩提寺側が形式にこだわっているわけではなく、宗派の教えや供養のあり方を大切にしているためです。
こうしたトラブルを避けるためには、必ず事前に菩提寺へ相談し、戒名をつけないことを考えている旨を率直に伝えましょう。場合によっては、宗教的儀式を伴わない「無宗教葬」や、宗教宗派を問わない納骨堂(※3)への埋葬などが必要になるかもしれません。
(※3)ご遺骨を供養するための建物や屋内施設。
8.戒名の種類に関するFAQ
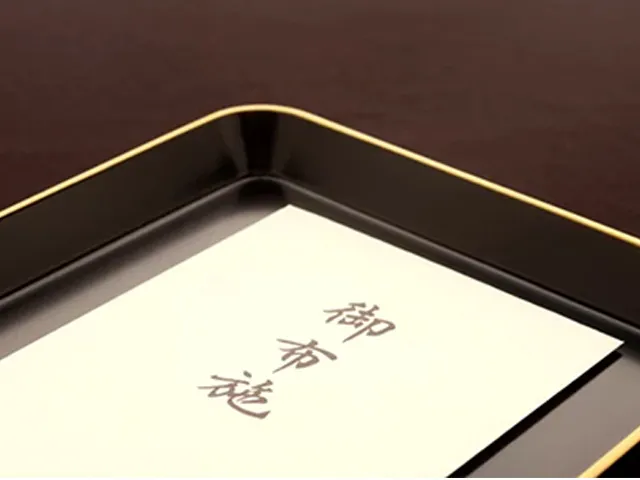
A.必ずしもそうとは限りません。
「高額な院号付きの戒名を選ばないと供養にならないのでは?」と心配される方もいらっしゃいますが、戒名の種類や費用の高さが、供養の質を左右するわけではありません。
戒名は故人様が仏弟子となる証しとして授かる名前です。高額の戒名を選ぶことでより故人様が救われるという考え方は、仏教の本来の教えにはありません。大切なのは、ご家族が「どう送りたいか」という気持ちを込めることです。
戒名の種類や費用で迷った際は、「故人様らしさを大切にしたい」「家族が納得できる送り方はどれか」という視点で判断するとよいでしょう。形式にとらわれず、心のこもった供養を大切にすることが、何より大事なことです。
A.無理にそろえる必要はなく、自分たちの想いに合った選び方で問題ありません。
戒名は、授かる方の人生や寺院への貢献などを基に考えられるため、必ずしもご家族と同じランクにそろえる必要はありません。同じお墓に入る場合は位号を合わせると見た目が整うとも言われますが、形式にこだわりすぎる必要はないでしょう。
とくに「院号」は、高い功績を持つ方や地位のある方に授けられる特別なものです。誰でも受けられる称号ではなく、お布施も高額になるため、配偶者やご家族が院号を持っていたとしても、それに合わせる必要はありません。
A.葬儀を依頼する葬儀社に相談し、寺院を紹介してもらう方法が一般的です。
菩提寺がない場合、戒名は「インターネットで僧侶に依頼する」「自分でつける」「葬儀社に寺院を紹介してもらう」といった方法があります。どの方法を選ぶ場合でも、故人様への想いをしっかりと伝え、納得できる戒名を授かることが大切です。もし迷われた場合は、まずは葬儀を担当するプランナーに相談してみるとよいでしょう。
A.寺院によって対応は異なりますが、位号のみ変更できる可能性はあります。
戒名を後から変更できるかどうかは、基本的に授けていただいた寺院の判断によります。まずは戒名を授かった寺院に直接相談しましょう。
戒名の変更が認められる場合でも、末尾につく敬称(位号)の変更のみ認められる場合が多いようです。たとえば「信士」から「居士」へ変更するなどの調整は対応してもらえる可能性があります。
戒名の変更を依頼する際は、新たに戒名料、もしくはお布施が必要になることが一般的です。さらに、四十九日法要の後で変更する場合は、位牌の作り直しが必要になるため、変更には費用や手間がかかる点にも注意が必要です。これらを踏まえて慎重に検討するとよいでしょう。
A.「相談」という姿勢で状況を説明しましょう。
お布施の金額について尋ねるのは気が引ける、と感じる方は少なくありません。しかし、僧侶の方もご家族が無理をして負担を抱えることを望んではいません。
多くの僧侶は、ご家族が不安や不明点を抱えたままでは心苦しいと考えています。「戒名の種類ごとの費用目安を教えてほしい」「無理のない範囲でお願いしたい」といった内容であれば、率直に伝えても問題ございません。
ただし、大切なのは「値切る」という姿勢ではなく、あくまで「相談」としてお話しすることです。ご家庭の事情や予算について正直にお伝えしたうえで、「この予算内でお願いできる戒名はありますでしょうか」などと尋ねてみるとよいでしょう。
A.まずは故人様を思うお気持ちは皆同じであると信じ、冷静に話し合うことが大切です。
戒名選びでご親族と意見が食い違うことは、決して珍しいことではありません。話し合った上で、ご家庭の事情(費用面など)や、故人様が生前にどのような考え方を持っていたかを丁寧に説明しましょう。もし故人様がエンディングノートなどをのこしていれば、それが最も強い判断材料になります。
どうしても話がまとまらない場合は、僧侶や葬儀社に間に入ってもらう方法もあります。多くのご家族を見てきた経験から、ご親族も納得できるようなアドバイスが得られるでしょう。
9.戒名の種類と選び方を正しく理解して後悔のない判断を

戒名は種類や費用だけで選ぶものではありません。故人様の人生に敬意を示し、ご家族の想いを託す“最後の名前”です。「高い戒名が良い」「格式が高いほど正しい」といった考え方にとらわれず、ご家族の「どのように送りたいか」という気持ちを大切にしながら選ぶことが何より重要です。
とはいえ、「戒名は難しい」「何を選ぶべきか分からない」という不安を抱えるのは自然なことです。そんなときは、無理に一人で悩まず、専門家に相談してみることで安心につながります。
花葬儀では、戒名の種類や選び方についてのご相談を承っております。経験豊富なスタッフと共に、ご家族の想いや故人様らしさを大切にした戒名について、一緒に考えてみませんか。ご相談は無料の事前相談のご利用がおすすめです。この機会にぜひご検討ください。




























