葬儀は誰のために行うの?本質と役割・迷ったときの判断基準を解説
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
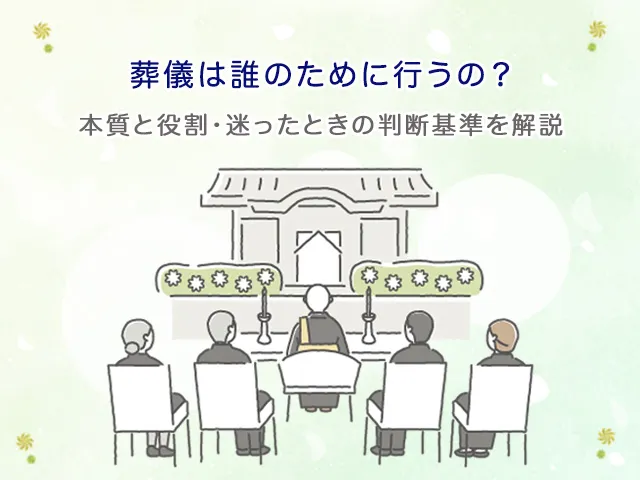
人生には必ず「お別れ」の時が訪れます。しかし、そのときに「葬儀は誰のために行うものなのか?」という問いがご遺族の心をよぎり、「簡単な葬儀にしてもいいのでは?」「葬儀を行わなくてもいいかもしれない」と、迷ってしまうこともあるでしょう。
本記事では、葬儀の起源、故人様・ご家族・参列者(社会)それぞれにおける役割、迷ったときに役立つ判断基準、葬儀を省略した場合に起きやすいトラブルを解説します。納得のいくお見送りを実現するために、ぜひ参考にしてください。
1.葬儀の「これまで」と現状

まずは、葬儀の起源と現状を押さえることで、「誰のためか」を考える土台を築きましょう。
葬儀の起源と移り変わり
古来より人類は、故人様をただ処理するのではなく、共同体の中で見送る儀礼を行ってきました。日本でも古代には「殯(もがり)」という風習があり、故人様を一定期間安置しながら「死」を実感させる時間を設ける習慣がありました。こうした儀礼が発展し、仏教や神道、また地域文化が融合して、葬送儀礼としての葬儀が形作られてきたのです。
多様化する葬儀の選択肢
現代では、通夜・葬儀・告別式を含む典型的な一般葬だけでなく、家族葬や一日葬など多様な選択肢が広がっています。理由としては、核家族化・高齢化・費用負担・価値観の変化などが挙げられます。
また、葬儀を必ずしなければならない義務は法律上はないため、火葬のみで見送る火葬式(直葬)が選択されることもあります。形式の変化が進むほど、葬儀の意味や役割を再確認することが重要になるでしょう。
2.誰のために葬儀を行うのか?3つの視点から考える

葬儀を誰のために行うかを考える際、一つの立場からだけ見るとかたよってしまいがちです。ここでは「故人」「遺族・家族」「社会・参列者」という3つの視点から、葬儀の意義と役割を解説します。
故人のため
葬儀が本来果たしてきた最も基本的な役割は、故人様への深い敬意を表すとともに、故人様の魂が安らかに旅立てるように祈り、送り出すことにあります。宗教や文化の違いはあっても、「安らかであってほしい」と願う気持ちは共通であり、その想いを形にした儀式が長く受け継がれてきました。
たとえば、故人様が生前に語っていた「明るい雰囲気で送ってほしい」「親しい人たちだけでお別れしたい」といった想いを叶えることも、かけがえのない供養のかたちです。
ご家族・ご親族のため
葬儀は、残されたご家族やご親族が悲しみと向き合い、心を癒やす機会ともなります。ご家族同士、ご親族同士で故人様との思い出を語り合うことで、共感や連帯感が生まれ、それが心の支えになることもあります。
さらに、葬儀を通じて「最期をきちんと見送った」という納得感を得ることも、気持ちを整えるうえで重要です。儀礼的な形式や見た目だけでなく、「自分たちらしいかたち」で送れたかどうかが、心の満足に直結することがあります。
社会・参列者のため
葬儀が持つ社会的な役割の一つは、故人様と関わりのあった方々へ、「お別れの場」を提供することです。訃報を受けてもお別れのセレモニーがなければ、ご友人や仕事関係者の方々は、故人様をしのび、弔意を示す機会を得ることができません。葬儀は、そうした方々がきちんと気持ちに区切りをつけるための、大切な儀式となります。
また、参列者が葬儀で故人様をしのぶことで、ご遺族は他者の支えを感じられることがあり、社会的なつながりを確認する場にもなります。
3.葬儀を「誰のため」に行うか迷ったときの判断軸

葬儀の目的は一つではないため、「誰のために行うのか」「何を優先して決めるべきか」迷ってしまうことも少なくありません。 そんなときには、考えを整理するための判断軸を持つことが大切です。ここでは、納得のいく葬儀を選ぶために、どのような視点や判断軸を持てばよいかを具体的にご紹介します。
故人の遺志を汲み取れているか
多くの方が「故人様の遺志を尊重したい」と考えますが、実際に明確な希望が残されていることは少ないものです。まずは、エンディングノートが残されていないか、またご家族との会話の中で「葬儀は簡素でよい」「家族葬にしてほしい」といった言葉がなかったかを振り返ってみましょう。
エンディングノートには、宗教の有無、葬儀の形式、招きたい人の名前、お香典の受け取り可否などを記録できる欄があります。記録があれば参考になり、なければ普段の言動や価値観から推測することもできます。
ご家族の気持ちを尊重できているか
葬儀はご家族が故人様を見送る大切な場でもあります。そのため「ご家族の想いが大切にされているか」を判断の軸にすることが重要です。
たとえば、「好きだった花を飾りたい」「読経をお願いしたい」「遠方の親族に配慮した日程にしたい」といった想いは尊重されるべきです。ご家族の意見が分かれることもありますが、そのような場合は喪主様だけで抱え込まず、葬儀社スタッフなど第三者に相談して選択肢を整理するとよいでしょう。
ご遺族として納得できる判断になっているか
ここまで「故人の遺志」と「ご家族の気持ち」という2つの大切な軸を見てきましたが、最終的に重要になるのは、総合的に考えた上で、ご遺族自身が「これで良かった」と心から思えるか、つまり「納得感」があるかという点です。
たとえば、故人様が「簡素でよい」と希望していたとしても、ご家族が納得できないまま葬儀を省略した場合、「本当にこれでよかったのだろうか」と悔いを残すこともあります。故人様の遺志を大切にしながら、ご家族の気持ちとのバランスをとることが大切です。
また、故人様と親しかった方々への配慮も、ご遺族の納得感に関わってきます。葬儀後に「最後にお別れをしたかった」という声を聞き、心を痛める可能性もあるからです。
さまざまな立場や想いがあることを理解した上で、最終的に「心のこもったお見送りだった」と実感できるかどうかが、大切な判断基準と言えるでしょう。
4.葬儀を省略する前に、知っておきたいこと

納得のいくお見送りの形を模索する中で、近年は「葬儀なし」という選択肢、つまり火葬のみで故人様を見送るご家庭も増えています。
しかし、葬儀を省略したことで、思わぬ後悔や周囲とのすれ違いが生まれる可能性もあります。ここでは、そうした後悔を防ぐために知っておきたいポイントを解説します。
お別れの時間が限られる
火葬式はお別れの時間が限られるため、「しっかりお別れできなかった」と後から寂しさを感じる方もいらっしゃいます。
葬儀は、亡くなったという現実を受け止め、悲しみを表現し、他者と分かち合う場でもあります。これらの機会を失うことで、心の中に未消化の悲しみが残り、後から精神的に負担となることがあります。こうした後悔は数年後に「やっぱり、あのとき式をしておけばよかった」と振り返る形で現れることもあります。
周囲の方々への丁寧な説明と配慮も必要
葬儀を省略した場合、ご親族や関係者から「なぜ知らせてくれなかったのか」「弔う場がなかった」と不満を言われるケースもあります。とくに高齢のご親族や故人様と長い付き合いのあった友人・知人にとっては、弔意を示す場が重要です。
また、あとから訃報を知った場合、「無視された」と感じられてしまうリスクがあります。お香典や弔電の辞退を明記しても、相手が納得してくれるとは限らず、関係にしこりが残る場合もあります。
弔問などへの備えも大切に
葬儀というお別れの機会がない場合、訃報を知った方々が、個別に自宅を弔問されたり、それぞれのタイミングでお香典を送られたりすることがあります。その結果、ご遺族が長期間にわたって対応に追われるケースも少なくありません。
もし葬儀を行わない場合は、こうした状況をあらかじめ想定しておくことが大切です。今後の弔問や香典をどうするかといった方針を事前に決め、訃報を伝える際に併せてお知らせするなどの配慮が、後々の負担を軽くすることにつながるでしょう。
5.葬儀は誰のためかに関するQ&A

A.まずは故人様のお気持ちを尊重した上で、ご家族で十分に話し合うことが大切です。
故人様の意向は大切ですが、葬儀はご家族や関係者の心の整理の場でもあります。そのため、儀式を簡素にしても、最低限のお別れの機会を持つことは多くの人の心を支えます。「葬儀は不要」という言葉の背景には、負担をかけたくないという思いが込められていることも多いため、形式を工夫しつつ気持ちを尊重することが望ましいでしょう。
A.家族葬は今や、社会的に広く認知された葬儀の形ですのでご安心ください。
葬儀の価値は、形式や規模よりも、そこに込められた想いにあります。ご家族や親しかった方々と思い出を語り合ったり、写真や手紙を飾ったりすれば、心の区切りをつける場になります。大切なのは「参列した人が納得できるか」であり、無理のない形を選ぶことが後悔を減らすことにつながります。
A.もちろん、心のこもったご供養になります。最も大切なのは、宗教的な形式そのものよりも、ご家族のお気持ちだからです。
無宗教葬(自由葬)は宗教儀礼を伴わない形式ですが、故人様らしさを表現できる自由なスタイルです。献花や音楽、手紙の朗読などを通じて感謝や想いを伝えられ、参列者の心に深く残る時間になります。宗教にとらわれない分、個性やご家族の希望を反映しやすいのが特徴です。
ただし、ご親族の理解を事前に得ることや、進行に慣れた葬儀社に相談することが成功のカギになります。
6.「葬儀は誰のためか」の答えは、それぞれの心の中に
葬儀は、故人様のためでもあり、ご家族のためでもあり、関係者すべての気持ちに寄り添う大切なものです。だからこそ、「誰のために行うか」に迷ったときは、いろいろな立場の方の想いに目を向けてみてください。
花葬儀では、経験豊富なスタッフが、納得のいく形でのお見送りを一緒に考えるための事前相談の窓口を設けています。迷いや不安を感じたときは、どうぞ抱え込まず、お話をお聞かせください。




























