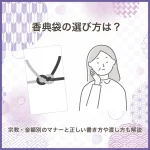大切な人を亡くした友達にかける言葉|心に寄り添う文例とマナー
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式のマナー 】
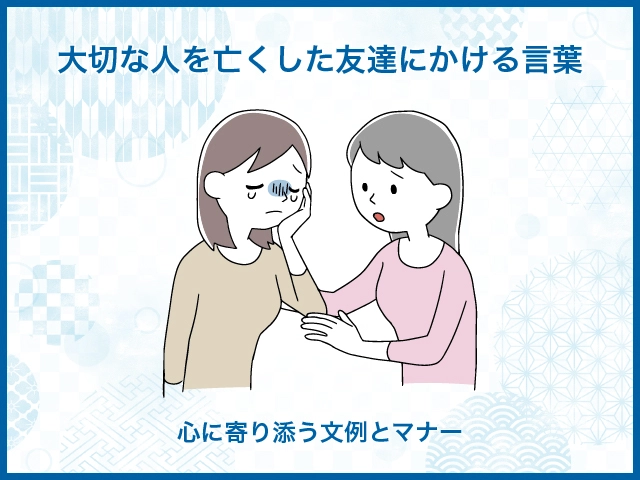
大切な人を亡くした友達に、あなたはどんな言葉をかけられるでしょうか。「何と言えばいいか、わからない」「軽い言葉でかえって傷つけてしまいそう」――そんな不安を抱える人は少なくありません。
本記事では、友人に寄り添うためのマナーや表現のポイント、具体的な文例、フォローの方法などをご紹介します。言葉だけで友達を悲しみから完全に救えるわけではありませんが、“あなたの一言”は、きっと相手にそっと届き、心を癒してくれることでしょう。
1.大切な人を亡くした友達に、かける言葉に迷ったときの考え方

誰もが、大切な人を亡くした友達を前にすると「何と言えばいいのか、わからない」と感じるものです。けれども、その“迷い”こそが、思いやりの出発点でもあります。
本章では、言葉をかけることの意味や限界、そして無理に言葉を探さなくてもできる寄り添い方について考えます。
言葉をかける意味と、その限界
言葉には、「気持ちを受け止めています」という想いを届ける力があります。悲しみの中で孤独を感じている友人にとって、あなたの一言が「自分は一人ではない」と気づくきっかけになることもあります。
ただし、言葉は万能ではありません。どんなに優しい言葉でも、痛みを完全に癒すことはできないのです。だからこそ、相手の心に無理をさせないよう、控えめで誠実な表現を選ぶ姿勢が大切です。
無理に励ます言葉は避ける
「前を向いて」「時間が癒す」といった励ましは、相手に「今の苦しみを否定されている」と感じさせることがあります。また、「頑張ってね」という言葉が、悲しみを抱えた人には重荷にもなりえます。
大切なのは、励ますことよりも「今の痛みに寄り添う」こと。否定しない言葉、焦らせない言葉を選ぶことが重要です。
言葉に迷っても、できることはある
「言葉が見つからない自分を責めなくていい」というメッセージを、まず、あなた自身に届けてください。沈黙もまた、心に寄り添う表現になりえます。
たとえば、顔を見てただそばにいる、手を握る、そっと隣に座る、沈黙の時間を共有する――こうした“言葉以外の寄り添い方”が、時には言葉よりも深く伝わることがあります。迷いながらも寄り添おうとするあなたの姿勢は、相手にとって大きな支えになるでしょう。
2.言葉をかけるにあたって注意すべきこと
どれほど真心を込めても、言葉の選び方一つで相手を傷つけてしまうことがあります。ここでは、実際に友達へ言葉をかける際に意識したい配慮のポイントを整理します。
こちらでご紹介するのは、葬儀などのフォーマルな場面だけでなく、LINEやメールでのやりとりにも役立つ基本的なことです。親しい間柄だからこそ、普段通りの言葉で話したくなるかもしれませんが、まずは丁寧さを第一に心がけましょう。
意図せず相手を傷つけない表現を選ぶ
弔事では、「不幸が続く」ことを連想させる重ね言葉(例:重ね重ね/たびたび/再三/またまた/ますます)を避けるのが基本です。
また、「死ぬ」「死亡」「浮かばれない」などの直接的な言葉も、相手の心を刺激する可能性があるため控えましょう。代わりに、「ご逝去」「お亡くなりに」「ご他界」「永眠」など、柔らかい表現を選ぶと穏やかな印象になります。
言葉遣いを工夫することで、悲しみに寄り添う姿勢を示すことにもつながります。相手のご家族がメッセージを目にする可能性も考え、丁寧な言葉選びを心がけましょう。
相手の信仰に配慮する
お悔やみの言葉は、宗教や宗派によってふさわしい表現が異なります。たとえば、多くの仏教宗派では「ご冥福をお祈りします」が一般的ですが、浄土真宗では教義上「冥福」を用いません。キリスト教では「安らかな眠りをお祈りします」、神道では「御霊のご平安をお祈りします」などの表現が適しています。
負担をかけないよう工夫する
葬儀準備などで忙しい相手にとって、長文や返信を強いるメッセージは負担になる可能性があります。特にメールやLINEでは簡潔にまとめ、「返信は無理しないでね」「急ぎません」などの一言を添えましょう。
メッセージの内容については、死因や詳細を尋ねるのは控えるようにするのがマナーです。
3.大切な人を亡くした友達にかける言葉・文例【手段別・シーン別】
お悔やみの言葉は、伝える手段や場面によって、相手への届き方が変わります。この章では、メール・対面・電話・手紙といった伝える手段ごとに、状況に合わせた文例と注意点をご紹介します。
メール・LINEで送るときの文例
お悔やみのメールやLINEは、相手に負担をかけずに想いを伝えられる便利な手段です。ただし、カジュアルな手段であるからこそ、表現は慎重に、絵文字やスタンプの使用は避けましょう。
できる限り短く、返信を促さないのが基本です。「驚きと悲しみを共有する」「相手を気づかう」「返信を求めない」これら3点を心がけましょう。
【文例】
〇〇さんが安らかであることを心よりお祈りしています。
今はどうかご無理なさらないでください。返信は気にしないでくださいね。
今はまだつらいと思うけれど、何かあればいつでも話聞くからね。
返信は気にしないで大丈夫だから。
「気にかけている」「いつでも頼っていい」という姿勢が、相手の心の支えになります。
対面で伝えるときの文例
面と向かって言葉を交わす場面では、言葉だけでなく表情・声のトーン・沈黙も大切な要素です。特に、落ち着いた静かな言い方が求められます。
タイミングに応じた文例とポイントは以下のとおりです。
個別の弔問の際
個別の弔問のときには、言葉より「寄り添う姿勢」を伝えることが優先です。
【文例】
何もできないけれど、そばにいるよ。
友人には、あなたの存在そのものが力になります。無理に会話を続ける必要はなく、「共にいる」というメッセージが伝われば十分です。
葬儀の場
葬儀の場では、相手が多くの対応に追われています。長話は避け、短く温かい言葉を添えることを心がけましょう。
【文例】
このような言葉は、相手が自分を「気にかけてもらえている」と感じられるきっかけになります。
電話で伝えるときの文例
電話では相手の表情が見えないため、声の落ち着きや間の取り方がとても大切です。長く話すよりも、「気にかけている」という気持ちを静かに伝える言葉を選びましょう。
【文例】
今は何も言葉が見つかりませんが、ずっと気にかけています。
話したくなったら、いつでも聞くから。
電話だからこそ、声のぬくもりで想いを伝えられます。孤独を感じやすいときにも、そっと心を支える手段です。
手紙で伝えるときの文例
直接会うことや連絡が難しいとき、また丁寧に気持ちを伝えたいときには、手紙やお悔やみ状が適しています。時候の挨拶は省き、冒頭から弔意を述べるのが基本です。続いて、故人様との思い出や相手への気遣いを簡潔に添え、最後に「ご自愛ください」「返信は不要です」などの言葉を入れます。
【文例】
お母様が以前、私たちの話を穏やかに聞いてくださったこと、
優しい笑顔が今も心に残っています。
あなたの悲しみにどれだけ寄り添えるかわかりませんが、
何かあればいつでも力になりたいと思っています。
どうか今は、少しでもご自身をいたわる時間を持てますように。
無理に返信はしないでくださいね。
一通の手紙は、相手の心に静かに寄り添う時間を届けることができます。
4.言葉をかけた後にできるフォローと心づかい
言葉をかけるだけでなく、その後の関係の保ち方やフォローこそが、友人の心を支えることもあります。悲しみが癒えるまでの時間は人それぞれ。相手のペースに寄り添いながら、長く支え続けるための工夫や距離の取り方を解説します。
言葉をかけた後も続けたい「存在を示す行動」
一度お悔やみの言葉をかけたからといって、友達の気持ちが整理されるわけではありません。むしろ、葬儀後しばらく経ってからのほうが、喪失感が深まり孤独を感じやすくなるものです。そんな時期こそ、「気にかけているよ」というサインを、何気ないやり取りの中で伝えてみましょう。
たとえば、次のような方法があります。
・「最近どうしてる?」という短いLINE
・季節の挨拶や天候に触れたメッセージ
・誕生日や思い出の日に、さりげない言葉を添える
こうした自然なやり取りの中で、相手にとって「頼ってもいい存在」としての安心感が生まれます。また、お茶への誘いや散歩への声かけなど、軽い提案を添えることで、相手に「受け入れてもらえている」という感覚が届きやすくなります。
相手のペースに合わせた距離の取り方
人が悲しみを乗り越えるスピードはそれぞれです。「そっとしておいてほしい」人もいれば、「話を聞いてほしい」人もいます。あなたの「何かしてあげたい」という気持ちは尊いものですが、友達のペースを最優先にしましょう。
たとえば、以下のように反応のサインを見極めることも大切です。
・返信がない → 「今は距離を置きたい」のサイン
・短い返信 → あまり深く関わることを避けたい可能性
・長文で返ってくる → 話したい・共有したい気持ちがある
たとえ友達から連絡が途絶えても、それは拒絶ではありません。時間をかけて、相手が再び話したくなったときにそっと寄り添える存在でいることが何より大切です。
時間の経過とともに変わる感情に寄り添う言葉
悲しみの感情は、時間の経過とともに形を変えながら続いていきます。その中で、節目となるタイミング――たとえば、故人様の命日や誕生日、喪中はがきが送られてきたときなどは、特別な意味を持ちます。以下のような言葉をかけることで、「忘れられていない」と感じられる瞬間を届けることができます。
・今日はお母様の命日だと聞きました。静かに手を合わせています。
・この季節になると、〇〇さんと一緒に見た桜のことを思い出します。
・喪中のお知らせを受け取りました。年始のご挨拶は控えますが、心からご多幸をお祈りしております。
一見些細な言葉でも、思い出にそっと寄り添うことで、故人様が大切にされた証を残すことになります。そうした「時を超えた寄り添い」は、悲しみの中に癒しをもたらす力となるのです。
こうしたフォローや寄り添いの行動は、グリーフケア(悲嘆を抱える人への心の支援)の一つといえます。
5.友達にかけるお悔やみの言葉に関するQ&A
A.無理に励ましたり、特別な言葉を探したりする必要はありません。「一緒に悲しむ姿勢」を見せることが、何よりの支えになります。
あなた自身も同じ悲しみを抱えているときは、言葉を選ぶのが難しくなるものです。けれども、だからこそ「気持ちを共有する」という誠実な姿勢が、互いの心を支え合います。
たとえば、次のような言葉をかけるとよいでしょう。
「私も本当に悲しくて……。あなたのこともすごく心配です。
「〇〇さんとの思い出を、また一緒に話したい」
同じ痛みを分かち合える人だからこそ、偽りのない言葉が自然と届くはずです。
A.SNS上ではコメントを控え、個別に友達に連絡するのが基本です。
SNSで偶然訃報を見かけた場合は、慎重に行動しましょう。公開コメントで弔意を表すと、意図せず混乱を招くおそれがあります。
そして、友達に連絡を取るときは、DMやLINEなど個別の手段を使いましょう。「SNSで知りました」と一言添え、心からのお悔やみを短く伝えるのが適切です。情報の扱いには、ご遺族や友達への最大限の配慮が必要です。
A.参列できなくても、手紙やメールで心を込めて弔意を伝えましょう。
やむを得ず葬儀に行けない場合でも、友達への想いを届ける方法はいくつもあります。たとえば、以下のような方法があります。
・手紙・メール・LINEでお悔やみを伝える
・弔電を送る
・お香典や供花を送る(相手の意向を確認のうえで)
「行けなかったことへのお詫び」と「心はそばにある」という両面を、丁寧に伝えることが大切です。
A.もちろん、今からでも遅くありません。
悲しみは時間が経っても完全に癒えるわけではなく、むしろ周囲の関心が薄れた頃に、ふとした言葉が大きな支えになることがあります。
たとえば、「あのとき何も言えずにごめんね。ずっと気にかけていました。少し落ち着いた頃かもしれないけれど、もし話したくなったら、いつでも聞かせてね」などの言葉です。
「すぐに連絡できなかったことへのお詫び」と「ずっと気にかけていた気持ち」を正直に伝えると、相手も安心して受け取れるでしょう。
6.「言葉を贈る」というあなたの行動が友達の力になる
大切な人を亡くした友達に、どんな言葉をかければいいのか――その問いに迷うあなたの姿勢そのものが、思いやりに満ちた行動です。正解のない状況だからこそ、無理に何かを伝えようとせず、相手の気持ちに寄り添おうとする気持ちが、そっと支えになることもあります。
友達に寄り添う中で、ご遺族が深い悲しみと同時に、慣れない準備や手続きといった多くの現実に直面することを、間近で感じた方もいらっしゃるかもしれません。
花葬儀では、ご家族の「もしも」に備え、心にゆとりを持っていただくために、会員制度「リベントファミリー」をご用意しております。不安や疑問に、専門のスタッフが丁寧にお応えしますので、ぜひ、ご活用ください。