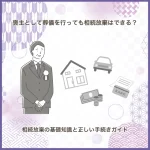デジタル遺品で困らないために|知っておくべき整理方法と備え方・注意点
- 作成日: 更新日:
- 【 相続の基礎知識 】
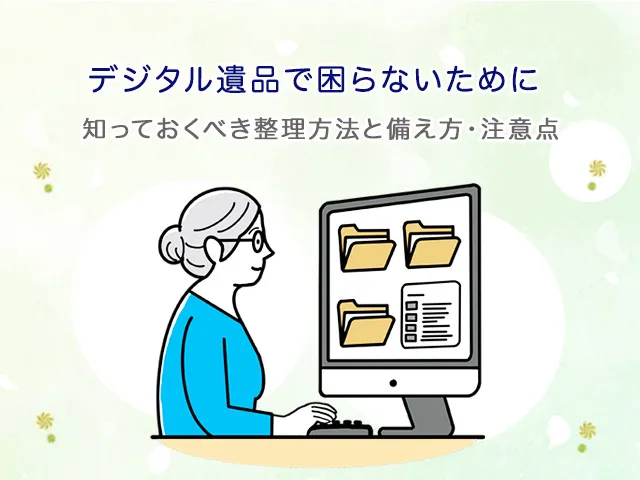
デジタル遺品は、目に見えないからこそ対応が後回しになりがちです。しかし、スマートフォンやパソコン、SNSやネット銀行の情報がそのまま残れば、思わぬトラブルの火種になることもあります。そうならないためには、本人や周りのご家族による備えが必要です。
この記事では、デジタル遺品の整理方法と備え方をわかりやすくご紹介します。最後まで読むことで、死後に残されるデジタルデータをどう整理すべきかが理解できるようになるでしょう。ぜひお付き合いください。
1.デジタル遺品とは何か
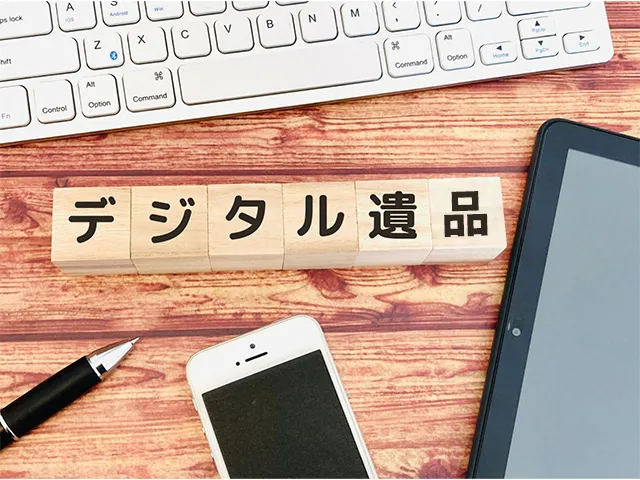
まずは、デジタル遺品の基本情報と、近年デジタル遺品が注目されるようになった背景を解説します。
デジタル遺品の意味・対象範囲
「デジタル遺品」とは、故人様が所有していたスマホやパソコンなどの電子機器に保存されていたデータ、さらにネット上のアカウントや登録情報などを指します。つまり、デジタル上に存在する、非常に広範囲にわたる個人情報や情報資産を含む概念だといえるでしょう。
デジタル遺品に該当する具体的なものは、以下の通りです。
| 財産価値のないもの | ・思い出の写真や動画 ・一般的なメールの履歴 ・趣味の作成物 ・各種コンテンツのアカウント ・アプリ など |
|---|---|
| 財産価値のあるもの (デジタル遺産) |
・ネット銀行、ネット証券の口座 ・仮想通貨 ・電子マネー ・金銭価値のあるポイント ・デジタル著作権 など |
デジタル遺品について理解を深めるためには、まず「遺品」と「遺産」の違いを理解する必要があります。「遺品」とは、価値の有無にかかわらず、故人様が所有していたすべての物を指す一方、「遺産」とは、その中でも財産的価値が認められるものを指す、と覚えておくとわかりやすいでしょう。
なお、現行法上では「デジタル遺品」や「デジタル遺産」に明確な定義は無く、これらは一般的な呼称です。法的なルールがまだ整備されていないからこそ、慎重な扱いが求められます。本コラムでは、「デジタル遺産」も含めた広い意味での「デジタル遺品」について、解説を進めていきます。
なぜ今「デジタル遺品」が注目されるのか?
土地や現金などと違って存在を把握しづらいデジタル遺品は、終活の際に見落とされがちです。そのため、多くのご遺族は所有者の死後になって初めて存在に気づき、対応に戸惑うことになります。
加えて、デジタル遺品は全容の把握自体が困難です。相続の可否やアクセス権に関する明確な法律上の基準がなく、サービスごとに利用規約が異なることも、より対応を複雑にしています。スマートフォンやオンラインサービスが生活に深く根付いた今、このような背景からデジタル遺品への関心が急速に高まっているのです。
2.デジタル遺品によっておこるトラブル事例

デジタル所有物をきちんと整理し、死後に備えておかないと、どのようなトラブルが起こりうるのでしょうか。
事例をご紹介します。
資産の喪失や意図せぬ支払い
金融機関のサービスは厳重に管理されており、パスワードや二段階認証などセキュリティが厳重なため、契約者本人以外のアクセスができないケースが多発しています。サブスクリプションなどの有料サービスも同様で、契約者の死後に家族が解約できず、支払いが続いてしまうケースもあります。
また、財産価値のあるデジタル遺品の存在に気づかないと、相続すべき財産を見落とすことになりかねません。相続手続き中に発覚した場合、手続きをやり直す必要が生じることもあります。
- 【事例①】
- 母が契約していた動画配信サービスの支払いが、死後も続いていたことに気づいた。
- 【事例②】
- 苦労してやっと遺産相続分割協議(相続人による、遺産をわけるための話し合い)が終わったのに、デジタル遺品が見つかって協議がやり直しになった。
個人情報漏洩や故人の尊厳を損なうことも
デジタル遺品をそのままにしておくことで、個人情報の漏洩のリスクも高まります。故人様やご家族の尊厳に関わるプライベートな情報が悪意ある第三者によって利用されないよう、データやアカウントは厳重に保管または破棄することが望まれます。
- 【事例①】
- 亡くなった姉のSNSアカウントが乗っ取られ、姉の名前を使った誹謗中傷が拡散された。
- 【事例②】
- 初期化するのを忘れたまま、亡くなった父の使用していたパソコンを知人に譲った。結果、家族も知らない父のプライベートな情報を知人が見ることになってしまった。
連絡先や重要データへのアクセスが困難に
重要なデータや連絡先、思い出などをパソコンやスマートフォンで管理している人も多いでしょう。どのような情報をどこに保存しているのかを共有しないまま持ち主が亡くなってしまうと、それらが永遠に失われてしまう可能性が高まります。特に重要な情報をデジタル管理している場合は、ご家族がアクセスできるよう準備しておくことが大切です。
- 【事例①】
- 亡くなった母のスマホのロックの解除方法がわからず、大量にあったはずの写真や動画、友人らの連絡先が入手できなくなった。
- 【事例②】
- 個人事業主だった父は、業務の多くをパソコンで管理していた。亡くなった後、パスワードがわからずアクセス不能となり、取引先との契約が履行できなくなってしまった。
3.全てのデジタル遺品が相続できるわけではない

遺品には「相続できるもの」と「できないもの」があります。このうちできないものの代表例として、「他人に譲ったり他人が行使したりすることができないもの」があり、これを専門的な言葉で「一身に専属したもの」と言います。故人様の一身に専属するものの例は具体的に以下の通りです。
- ・親権
- ・故人様が取得した資格
- ・故人様が受けていた生活保護の受給資格 など
デジタル遺品の場合、この「一身専属」に当たるかどうかは、多くの場合サービスの利用規約によって定められています。例えば「LINE」を運営しているLINEヤフー株式会社では、共通利用規約に以下の内容を記しています。
(中略)
4.4. アカウントは、お客様に一身専属的に帰属します。アカウントの登録が必要な当社サービスにおけるお客様のすべての利用権は、第三者に譲渡、貸与その他の処分または相続させることはできません。
引用:LINEヤフー共通利用規約(2025年2月3日改定)
https://terms.line.me/line_terms?lang=ja
つまり、LINEアカウントの持ち主が亡くなると、ご遺族がアカウントを相続することはできないということです。このように、一身に専属したものであるかどうかは、それぞれの利用規約を読むことが大切です。不明な場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
4.【生前からの準備】親のデジタル遺品で困らないための備え

親が亡くなった後、デジタル遺品の扱いでトラブルにあわないようにするためには、どのような備えをしておくべきなのでしょうか。
こちらでは、親のデジタル所有物に対して子どもができるサポートをご紹介します。これからご家族にデジタル遺品を残そうと考えている方も、ぜひ目を通してみましょう。
デジタル資産・個人情報の整理・リスト化を手伝う
まずは使用しているデバイス(パソコンやスマートフォンなど)や利用サービスを把握し、リスト化を行います。親(所有者)の気が進まない場合は、生前整理の重要性や未整理のリスクについて丁寧に伝え、促すことも大切なサポートの一つです。切り出し方に悩まれる方は「家族による親の終活サポート」の記事を参考になさってください。
リスト化の際は、資産価値のあるものとプライバシーに関わるものを区別し、無理にデータを見ようとしない配慮も必要です。IDやパスワードなどの重要情報は親が保管し、その保管場所だけは教えてもらいましょう。
親と一緒にエンディングノートにデジタル情報の扱いを記録する
「エンディングノート」とは、医療や介護、財産、葬儀などに関する希望や個人情報を自由に残すことができる終活ツールです。
エンディングノートにデジタル所有物に関する情報も記載しておくことで、デジタル遺品への扱いが明確になり、ご家族もスムーズに対応を進めることができるようになります。さらに、生前整理の進捗状況が把握しやすくなるため、記入する本人にとっても整理の目安となり、安心感につながるでしょう。
アカウントの死後設定をサポートする
一部のデジタル所有物は、ユーザーの死後、自動的に任意の相手に情報を開示したり、アクセス方法を知らせたりといったことを、あらかじめ設定することが可能です。実際にGoogleやAppleで行えることを以下にご紹介します。
- 【Google】
- 「アカウント無効化管理ツール」を設定しておくことで、長期間利用されていないアカウントの一部データを任意の相手に共有したり、通知したりすることができる。
- 【Apple】
- 「故人アカウント管理連絡先」を設定しておくことで、自分の死後、指定した人物が自分のAppleアカウントのデータにアクセスできるようになる。
- ・消費者センター
- ・葬儀社
- ・デジタル遺品整理専門業者
- ・デジタル遺品整理専門業者
- ・デジタル機器のサポート専門業者
- ・弁護士
- ・税理士
- ・司法書士
設定前には必ず「共有されるデータの範囲はどこまでか」「アカウントに紐づけられた有料サービスはどうなるのか」といったこともきちんと調べることが大切です。
デジタル所有物に関する死後の備えについては「デジタル終活の進め方」の記事も参考になりますので、併せてご覧ください。
出典:
Google アカウント ヘルプ
https://support.google.com/accounts/answer/3036546?sjid=13543628706064562565-NC
Apple サポート (日本)
https://support.apple.com/ja-jp/102631
5.【逝去後】ご遺族がデジタル遺品を取り扱う際の注意点
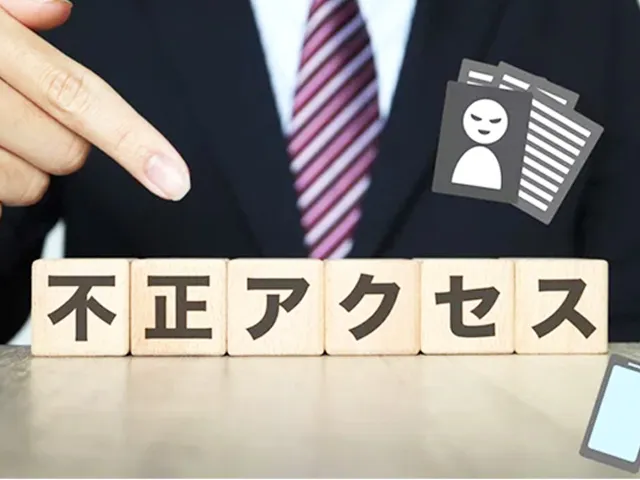
ご遺族が故人様のデジタル遺品を取り扱うにあたり、思わぬトラブルを避けるために、重要な注意点があります。具体的な整理に入る前に、まずは以下の点を必ずご確認ください。
相続人全員の合意を得てから整理を始める
デジタル遺品の整理は、独断で進めてはいけません。必ず相続人全員の合意を得たうえで始めることが大切です。なぜなら、故人様が特定の相続人にだけ伝えていた情報があるかもしれませんし、勝手に整理した結果、相続財産に関わる重要な情報を損なう恐れがあるためです。こうした行為は、のちに相続トラブルを招く原因にもなりかねません。慎重に進めることが、故人様への敬意とご家族の信頼を守る第一歩です。
不正アクセスに注意
ご遺族が故人様の代わりに、Webサービスの退会手続きをしたい場合もあるでしょう。しかしご遺族が故人様のアカウントに、故人様の残したIDやパスワードを使って無断でログインする行為は、「不正アクセス禁止法」に抵触する可能性があるため注意が必要です。
なお、故人様がエンディングノートなどで「自身の死後は、家族が手続きをしてもよい」という明確な意思を残している場合、例外的にその行為の違法性が問われない可能性もあります。ただし、これはあくまで一般的なサービスでの話であり、遺産相続が関係するネット銀行などの金融資産には、この考え方は当てはまりません。
金融資産における注意点については、次項で解説します。
出典:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)
令和7年6月1日 施行(閲覧日:2025年7月14日)
https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128/20220617_504AC0000000068
金融資産は必ず正式な相続手続きを行う
一般的なWebサービスへの不正アクセスも問題とされますが、ネット銀行やネット証券などの金融資産の場合は、さらに深刻な事態に発展する危険性があります。
エンディングノートに故人様の意思表示があったとしても、相続手続きを経ずに故人様のIDを使って無断でログインし、口座を操作する行為は、違法となる可能性があります。遺産は民法で定められた相続ルールに基づき、分けられるべきであるからです。金融資産について少しでも不安なことがあれば、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
プライバシーと個人情報保護に気をつける
デジタル遺品を整理する中で、故人様のプライベートな情報が見つかることがあります。それはご家族が知りたくなかった、もしくは本人が知られたくなかった内容かもしれません。発見しても安易に共有したり、口外したりしない配慮が大切です。また、保管中のデータが外部に流出しないよう、適切な管理と情報保護にも十分注意しましょう。
故人様の意志を尊重する
デジタル遺品を整理する際は、故人様の遺志を最優先に考えることが大切です。エンディングノートなどに希望が記されていれば、それに沿って対応しましょう。判断に迷う場合はご家族内では話し合い、必要に応じて専門家の意見も交えながら検討すると安心です。
6.ご遺族が行うデジタル遺品整理の基本的な手順

前の章で解説した注意点を踏まえ、こちらでは所有者の死後、どのような手順でご遺族がデジタル遺品を整理するのかをご紹介します。なお、相続放棄を検討している場合などは、自己判断で進めず、専門家への相談を優先してください。
デジタル関連機器の探索・保管
まずは、故人様が所有していたパソコンやスマートフォンなどのデジタル関連機器を全て探します。近年は携帯ゲーム機からでもサービスの購入ができるようになっているため、取りこぼしのないように注意しましょう。発見した機器は、紛失したり壊れたりしないよう、大切に保管します。
エンディングノートや契約書類の探索
故人様がデジタル遺品に関する情報や希望を残していないかを確認します。主な確認先は「遺言書」や「エンディングノート」です。IDやパスワードを別に保管されていた場合は、そちらもあわせて探しましょう。
「何も情報が残されていない」「どこにあるのかわからない」といった場合は、クレジットカードの利用明細や故人様宛の郵便物、保管されている契約書類などを手掛かりとすることができます。時間はかかりますが、資産の喪失や意図せぬ支払いを避けるためにもしっかりと探しましょう。
データ・アカウント情報の確認
エンディングノートなどを調べながら、故人様が所有していた全てのデジタル遺品を洗い出します。前述した「デジタル遺品への備え」でリスト化していた場合は省略可能です。
それぞれのデバイスにログインできる状態になっているのが理想ですが、中にはわからないものもあるでしょう。ログインに何度も失敗してしまうとアカウントがロックされてしまうものも多いため、むやみに試みないのが無難です。手がかりを慎重に探し、公式な再設定手続きやサポート窓口を利用しましょう。
必要なデータのバックアップ
デジタル遺品が確認出来たら、必要なデータを安全な場所に移行します。データが膨大にある場合は、それだけバックアップにも時間がかかりますので、ご家族で協力して行うことをおすすめします。
有料サービスの解約手続き
動画配信や定期配送などのサブスクリプションを故人様が契約していた場合は、ご遺族が代わりに解約手続きを行います。契約者が亡くなっていても、解約手続きが行われない限り支払いが発生しますので、速やかに行動しましょう。
「不正アクセスに注意」の項目でも述べた通り、解約目的であっても故人様のアカウントに無断でログインする行為は、法的な問題に発展する可能性があります。まずは各サービスの問い合わせ窓口や、申請フォームを通じて、契約者が亡くなったことを伝えてください。
解約の手続き方法は、それぞれのサービスごとに異なりますが、解約する際には故人様の死亡事実を証明する死亡診断書の写しなどの提出が求められることもありますので、確認してから手続きを行いましょう。
金融資産の相続手続き
ネット銀行やネット証券など、故人様が保有していたデジタル金融資産の相続手続きを行います。遺言書に指定があればその内容に従い、ない場合は相続人同士による話し合いで分割方法を決定します。一般的な相続手続きの流れは以下の通りです。
- 1. 故人様の死亡を金融会社に伝える
- 2. 故人様の資産を守るため、故人様の口座が凍結される
- 3. 遺言書を確認する、または遺産分割協議を行う
- 4. 各金融機関の決まりに従って相続手続きを行う
なお、相続予定の財産を放棄したい場合は3カ月以内、相続した財産に相続税が発生する場合は10カ月以内に申請をしなくてはなりません。「死亡後に行うべき手続きの流れと期限」の記事を参考にしながら、遅れないように気を付けましょう。
SNSアカウント整理や削除依頼
故人様が利用していたSNSアカウントの処遇を考えます。近年はSNSを通した活発な交流も増えているため、単純に削除するというわけにはいかない方も多いのではないでしょうか。しかし、そのままにしておくと第三者による乗っ取りやなりすましの危険性があります。
FacebookやInstagramでは、「追悼アカウント」を設定することができます。この設定を行うことで、アカウントの所有者が亡くなったことをフォロワーに知らせるとともに、不正利用を防ぐことができるようになります。
なお、LINEやX(旧Twitter)では、追悼アカウントへの移行は非対応ですが、アカウント削除の申請が可能です。
不要データの削除・機器の初期化
不正利用や流出を避けるために、不要なデータを削除します。パソコンやスマートフォンの中にあったデータは、オンライン上(クラウドサービス)でも保管されていることがあります。この場合、本体内のデータを消去してもクラウド上には残っていることも多いため、必ず両方を削除しましょう。
データの削除後は、デジタル機器を初期化して処分します。処分方法は信頼できる専門業者に預ける、市区町村のルールに従って廃棄するなどがありますが、形見として保有しておくことももちろん可能です。
7.デジタル遺品に関してご遺族ができること・できないことの判断基準と相談窓口

ここであらためて、「家族はどこまでデジタル遺品に関与してもよいのだろう?」と不安になった方のために、デジタル遺品整理でご遺族が行えること、行えないことを一覧にしてご紹介します。
| ご遺族側の行動 | 可否 |
|---|---|
| 故人様のデジタル機器を使用する | 〇 |
| 故人様のデジタル機器のロックを解除する | 〇 |
| デジタル機器の中のデータを閲覧する | 〇 |
| 故人様のIDやパスワードを使ってサービスにログイン、操作する | × |
| 故人様のSNSアカウントを引き継ぐ | × |
| 金融資産に該当するデジタル遺品が他にあることを知りながら放置する | × |
可否は個々の状況に応じて変わる場合もあります。判断に迷った際の主な相談先は、以下の通りです。
【デジタル遺品に関する初期の包括的な悩み】
【デジタル遺品の調査、復旧に関する悩み】
【デジタル遺品に関する相続問題や法的な悩み】
また、遺品整理に関する専門書を読んでおくと、理解が進みやすくなるでしょう。「終活に役立つおすすめ本26選」でもご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
8.デジタル遺品に関するQ&A

A.全てのデジタル遺品が相続の対象となるわけではありません。デジタル遺品の性質によって、「相続できるもの」と「できないもの」に分かれます。
【相続できるものの代表例】
・財産的価値のあるもの
ネット銀行の預金やネット証券の株式、暗号資産など、お金に換算できるものは遺産として相続の対象になります。
・パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器本体
機器そのものは「有体物」にあたるため、相続が可能です。機器の所有権を相続した相続人は、その中に保存されたオフラインのデータも引き継ぐことができると考えられており、自由に処分する権利があります。
【相続できないものの代表例】
・SNSや各種Webサービスのアカウント利用権
多くのサービスでは、アカウントは「一身に専属したもの」とされ、第三者への譲渡や相続が禁止されています。代表的な例はLINEのアカウントです。一身に専属したものかどうかは利用規約で確認することができますので相続の際はぜひ調べてみましょう。
A.まずは故人様のプライバシーに配慮し、「本当にそのデータを確認する必要があるか」を一度考えることが大切です。
相続に関する重要な情報や、どうしても残したい思い出の写真が保管されているなど、中身を確認しなければならない明確な理由がある場合は、エンディングノートなどで解除方法が残されていないか確認しましょう。
見つからない場合、やみくもに解除を試みるのは危険です。連続して間違えると永久にロックされたり、機器が強制的に初期化されたりする恐れがあります。不明な場合は、デジタル遺品整理業者に相談することをおすすめします。
A.不正アクセス禁止法に抵触する恐れがあるため、控えましょう。
第三者が故人様のSNSアカウントにログインして操作することは「不正アクセス」とみなされ、場合によっては法に触れることになります。それは、ご家族であっても同じです。
亡くなった方のアカウントを削除したい場合は、運営元への削除依頼が必要です。運営元の指定する書類を提出し、リクエストが正式に承認され次第、アカウントは削除されます。必要書類や削除依頼ができる人の範囲は各社で異なりますので、必ず調べた上で申請するようにしましょう。
A.まずは、各金融会社に故人様が亡くなったことを報告しましょう。
金融資産となるデジタル遺産を見つけた場合は、各金融会社に権利者の死亡を伝えます。そうすると、各金融会社は故人様の資産を守るために口座を一時的に凍結します。遺産の分割方法を相続人が決めた後、必要な手続きに従って必要書類を提出すると、相続手続きが進められるようになります。
相続放棄をする場合や、相続税の申告が必要になった場合はそれぞれ期限が設けられていますので、遅れないように注意しましょう。
9.デジタル遺品で困らないためにも事前の準備をしっかりと進めよう
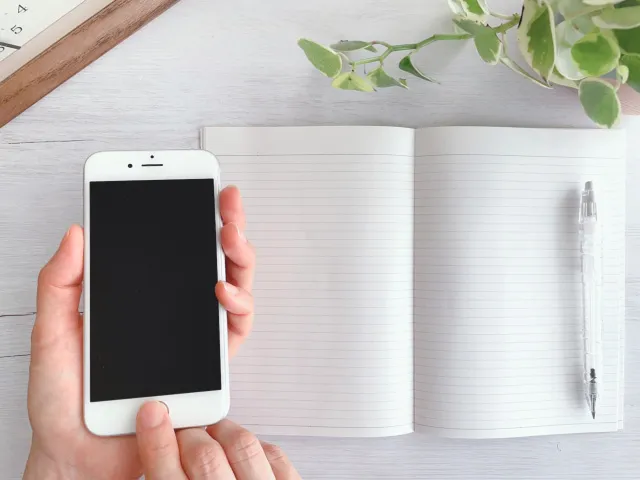
デジタル遺品は外からは見えにくいため、ご遺族が対応に戸惑うことが多くあります。持ち主は情報や希望を整理して残し、ご家族はその準備を支えつつ、いざという時に備えて必要な知識をあらかじめ確認しておくことがトラブルを防ぐカギです。
デジタル遺品を始めとした遺品整理、財産管理に関するお困りごとは、花葬儀までお寄せください。弁護士や司法書士などの専門家とも連携しながら、お客様のお悩みをサポートいたします。会員サービス「リベントファミリー」へご加入いただくと、より専門的なお悩みへのご相談がスムーズに行えるようになります。この機会にぜひご検討ください。