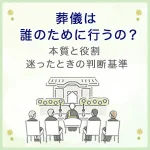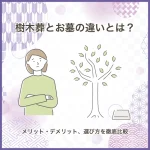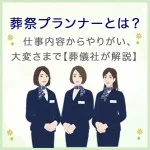看護師が行うエンゼルケアとは?現場で求められる知識と心遣い
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

エンゼルケアは、患者様が亡くなられた直後に行う大切なケアです。故人様の扱われ方ひとつで、ご遺族の心は大きく左右されます。不慣れな対応が「ぞんざいに扱われた」という深い悲しみを残すことがある一方、慈しむように丁寧な姿勢は、ご遺族に大きな安心感を与えます。しかし、初めてエンゼルケアに関わる際には、不安や戸惑いを覚える方も少なくありません。
本記事では、看護師の方がエンゼルケアに向き合うための知識や心構え、実際の手順、ご遺族への対応、そして多職種との連携の工夫などを丁寧に解説いたします。ご遺族に寄り添いながら、ご自身も納得のいくケアができるよう、ぜひ参考になさってください。
【もくじ】
1.エンゼルケアとは?看護師として知っておきたい基本
エンゼルケアは、単なる後処置ではなく、「看取りの一部」として重要な意味を持ちます。まずは、エンゼルケアの基本的な定義と目的、そして看護師として果たす役割について整理していきましょう。
エンゼルケアの基本的な定義と意味
エンゼルケアとは、患者様が亡くなられた後に行われる、尊厳を守るための包括的な死後処置を指します。お身体を清め、身だしなみを整えることを通じて、故人様が生前のような穏やかなお姿でご遺族とお会いできるよう準備をするのが目的です。
単なる後片付けではなく、故人様への敬意を示すと同時に、ご遺族が死を受け入れ、穏やかなお別れをするための大切な時間を作る重要なプロセスの一部でもあります。文化的・宗教的な配慮を含むこともあり、施設や地域によって内容や順序が異なる場合もあることに注意が必要です。
看護師として求められる配慮と役割
エンゼルケアにおいて看護師に求められるのは、処置の技術だけではありません。「どう寄り添うか」という姿勢もまた、大きな意味を持ちます。
たとえば、故人様の表情や姿勢を丁寧に整えることは、ご遺族に「大切に扱われた」と感じていただくきっかけになります。慎重かつ丁寧な対応が、ご遺族の心を静かに支えることにもなるのです。亡くなられた方と生前から関わってきた看護師だからこそ、その人らしさを思い出しながらエンゼルケアを行うことができます。
2.エンゼルケアはいつ、どのように行う?流れと進め方
看護師の方がエンゼルケアに関わる場面では、処置の目的や心構えに加えて、「どのタイミングで、どのような流れで行うのか」を理解しておくことが大切です。準備不足による混乱を防ぐためにも、基本的な工程について整理しておきましょう。
エンゼルケアを行うタイミング
エンゼルケアは、医師による死亡確認の直後におこなうのが一般的です。体温の低下や死後硬直が進む前に対応することで、お身体を無理なく整えやすくなります。血液や体液の漏出を防ぐ意味でも、早めの処置が望ましいでしょう。
ただし、ご遺族のお気持ちに配慮する姿勢も欠かせません。「もう少しだけ一緒に過ごしたい」と希望される方も多くいらっしゃるため、処置を急がず、適切なタイミングを見極めてお声がけをすることが大切です。「ご準備が整いましたら、お知らせください」と一言添えるだけでも、ご遺族の安心感につながります。
施設や病棟の事情で、安置室への移動や他の入院患者さまへの配慮が必要な場合もありますが、限られた時間の中でもご遺族の意向を尊重し、冷静に対応する姿勢が大切です。
エンゼルケアの基本的な流れ
エンゼルケアは、一連の手順に沿って行われますが、施設やご家族の希望によって一部の内容や順序が変わることもあります。ここでは、一般的な工程を順を追ってご紹介します。
まず、ご遺族がお別れに一区切りつけるのを待ちます。処置のために一時的に席を外していただく場合は、「これより準備をいたしますね」といった声かけをするとよいでしょう。ご遺族が混乱している際は、無理に引き離さず、気持ちが落ち着くのを優先します。
また、ケアに立ち会いたいと希望されるご遺族もいらっしゃいますので、参加の意向を確認すると、より丁寧な対応になります。
一般的なエンゼルケアの工程は、以下の通りです。
1.グローブを着用し、医療器具を除去します。
人工肛門や弁などの医療器具を除去し、必要に応じて止血処置を行います。ペースメーカーは火葬時の爆発を防ぐため、必ず摘出いたします。出血が続く場合は、絆創膏や包帯で適切に押さえます。
2.アルコール綿で汚れ(血液、目やになど)を拭き取ります。
投与した薬剤の影響で皮膚間に水疱が生じ、破れると強い臭気を発したり、細菌感染のリスクがあるため、特に注意が必要です。
3.口が開いている場合は、閉じます。
4.目も同様に閉じます。
5.血液や体液の漏出を防ぐため、鼻腔や耳腔に綿を詰めます。
なお、弊社ではお身体を傷つけないよう、臀部への詰め物は行いません。
6.ご遺族がご用意された新しい衣類、もしくは病院が用意した浴衣に着せ替えを行います。
7.最後のお見送りを行います。
病院によっては、次の患者様の入室を優先するため、早期の退室を求められることがあります。また、他の患者様の目に触れないよう、安置室までの専用ルートが設けられている場合もあります。個々の事情もふまえ、限られた時間の中でも丁寧で思いやりのある対応を心がけましょう。
3.病院と葬儀社、それぞれのエンゼルケアの役割の違い

エンゼルケアのすべてを病院側で担うわけではありません。実際には、葬儀社との役割分担があります。看護師としてどこまで関わるかを整理しておくことが、ご遺族への丁寧な対応にもつながります。
看護師が行うエンゼルケア
看護師が行うエンゼルケアは、主に医療的な器具の取り外しや身体の清拭(せいしき)、整容の補助などが中心です。
ご遺族がその場にいらっしゃる場合は、希望に応じてお着替えや髪を整えるお手伝いを行うこともありますが、宗教的な作法や高度な整容は基本的に病院の範囲外とされます。ケアのすべてを完璧にしようと背負い込む必要はありません。
葬儀社による専門的な整容(ラストメイクなど)

葬儀社が担うのは、より高度な整容技術やご遺族の心情に寄り添うケアです。肌の乾燥を防ぐための保湿や、生前の印象に近づける髪型の整え、肌の色調を整えるラストメイクなど、専門的な知識と経験が求められます。
こうした処置を行うために、葬儀社は専用の「エンゼルケアセット」を持参します。
こちらは、弊社「花葬儀」が使用するセットの一例です。セットにはマスクやグローブ、ピンセット、まき綿などが含まれています。なお、葬儀社は医療行為を行わないため、ガーゼはあくまで保護や清潔保持の目的で使用します。

具体的なケア内容や工夫の詳細については、弊社花葬儀で行っているラストメイクの実例を、「エンゼルケアとは何?」の記事でもわかりやすくまとめています。ご遺族向けの内容にはなりますが、医療や福祉の現場でエンゼルケアに関わる方にも役立つ情報が多く含まれていますので、あわせてご覧ください。
故人様のお身体の状態を維持するための専門技術
葬儀社は、湯かんやエンバーミングといった、病院では行うことのできない処置も担います。
湯かんは、故人様のお身体をお湯で洗い清める、古くから伝わる儀式です。一方、エンバーミングは、お身体に防腐・殺菌などの処置を施し、お体を長期間衛生的に保全する技術を指します。この技術により、特に夏場のご安置や、故郷への長距離搬送、海外への移送などが可能になります。
葬儀社ならではの高度な知識と経験を生かすことで、このような専門処置を行うことができるのです。
専門家との連携で看護師が意識したいこと
エンゼルケアは一見誰でもできるように見えますが、実際には講習や経験の有無によって、仕上がりに大きな違いが生まれます。たとえば口を閉じる方法ひとつとっても、入れ歯の有無や筋力の違いで調整が必要です。
病院と葬儀社、それぞれのケアの目的や方法には違いがありますが、根底に、「故人様とご遺族を尊重する」という思いが共通している点は、決して忘れてはならないでしょう。
看護師の皆様には、ご自身の施設で「できる範囲」を理解し、その先は専門家へ適切に託す視点が大切です。「どこまで関わるか」よりも、「どう丁寧に橋渡しするか」を意識することで、より円滑に連携できるようになります。
4.看護師として行う処置のポイントと注意点
エンゼルケアについて理解したうえで、実際の処置では「どのように行うか」「何に気をつけるか」が重要になります。同じ工程でも、故人様の状態やご遺族の想いに配慮した手順や対応を行うことで、ケアの印象が大きく変わります。ここでは、看護師の方が押さえておきたい処置の基本と、状況に応じた工夫について解説します。
身体の清拭と皮膚の保護
エンゼルケアでは、処置の正確さだけでなく、「丁寧で自然に整える」という姿勢が大切になります。
まず、清拭ではアルコール綿や蒸しタオルを用いて、顔や手、首元などご遺族の目につきやすい部分から始めると安心につながります。
故人様の皮膚は非常にデリケートになっていることがあるため、強くこすらず、ガーゼで軽く押さえるように拭き取るなど、素材と力加減にも配慮が必要です。耳や鼻に詰める綿も、外から見えないよう、深く詰めすぎないように注意します。
宗旨に配慮したお顔と手の整え方
故人様のお顔や手元は、ご遺族が最も目にされる部分であり、特に丁寧な配慮が求められます。
目や口が開いている場合、やさしく閉じますが、無理に閉じる必要はありません。仏教では、お釈迦様の最期の姿に由来する「半眼半口(はんがんはんこう)」といって、目と口がうっすら開いている状態を穏やかな表情と捉える宗旨もあります。ご家族に意向を確認するか、自然な状態に留めるのが良いでしょう。
また、手の組み方も宗旨によって作法が異なります。つい胸の上で組ませてしまいがちですが、後からどのようにも整えられるよう、特定の組み方はせず、腹部の上に置くか、体の脇に自然に下ろしておくのが丁寧な対応です。
着替えの工夫と体位の保持
ご家族が用意された服に着替えを行う際は、できるだけその方の好みに合った形で着せられるよう心がけましょう。死後の硬直(こわばり)が始まっている場合は、関節を温めたり、片腕ずつゆっくり通したりといった工夫も必要になります。
無理に関節を動かすと皮膚を傷つける恐れがあるため、焦らず丁寧に進めます。作業の効率よりも、「一つひとつに気持ちを込める」ことが、ご遺族の安心感を生む大切なポイントです。
5.看護師と他職種が協力するチームでのエンゼルケア
ご遺族への心配りや宗教的な配慮は、看護師一人で完結するものではありません。医師や葬儀社スタッフなど、複数の職種が連携して支える「チームケア」として行われます。
ここでは、看護師がどのような姿勢で関わるとよいのか、連携のポイントを解説します。
役割分担とチーム内の確認事項
エンゼルケアは、患者様が亡くなられた直後から迅速に進められることが多いため、職種ごとの役割をあらかじめ確認し、必要な連携をスムーズに行うことが求められます。特に医師による死亡確認後、看護師が処置を開始するタイミングや、看護助手の関与範囲を共有しておくことは非常に大切です。
看護師が医療器具の除去や清拭、体位の調整を担当し、介護士が着替えや物品の準備をサポートするといった役割分担が行われることもあります。また、葬儀社への連絡タイミングや搬送準備についても、担当者を明確にしておくことで混乱を避けられます。
ご遺族対応に関しても、「誰が説明するか」「誰が同席するか」を決めておくと、声かけが重なったり、伝わる内容に差が出るのを防ぐことができます。看護師の方は処置の中心に立ちながら、他職種との橋渡し役としてチーム全体の動きを見渡す視点を持つことが重要です。
より良いチーム連携のために、看護師ができること
チームでの連携をより良くするためには、日常的な声かけや事前準備が大きな助けになります。
たとえば、エンゼルケアに関わる物品をまとめた「セット」を共有し、どこに何があるかを全員が把握しておくことで、準備にかかる時間や負担を軽減できます。また、エンゼルケアを行う際に「今から処置に入りますね」とチーム内で声をかけておくことで、必要なサポートを得やすくなります。処置後に「〇〇さん、着替えのご用意ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えることも、職種間の信頼関係を築くうえで効果的です。
ご遺族の前では、「どのような姿勢でチーム全体が臨んでいるか」が印象として残ります。看護師の落ち着いたふるまいや、他職種と連携しながら丁寧に進める様子が、ご遺族に「安心できる現場」と感じていただくことにつながるでしょう。
さらに、会社の規定などにより葬儀への参列が難しい介護士やケアマネジャーにとって、エンゼルケアの時間が、故人様に最後のお別れを伝える唯一の場となることも少なくありません。エンゼルケアは、故人様を支えたすべてのスタッフの想いをかたちにする、かけがえのない時間でもあるのです。
6.エンゼルケアの学び方と、看護師としての向き合い方
看護師の方一人ひとりの理解と経験が、エンゼルケアの質を大きく左右します。ここでは、エンゼルケアを学ぶ機会や、経験を通して看護師として何を得られるのかについて考えていきます。
OJTや研修を通じた学び
エンゼルケアの現場では、多くの看護師が技術面と精神面で不安を抱えています。ある調査(※)では、経験年数にかかわらず95%以上がケアに不安を感じ、同様に95%が「教材があれば学びたい」と回答しました。
これほど多くの方が不安を抱える背景には、多くの医療機関でエンゼルケアを体系的に学ぶ機会が限られ、現場でのOJT(実地指導)に頼らざるを得ない現状があります。「先輩のやり方を見て覚える」という状況では、初めて関わる際に戸惑いを感じるのも無理はありません。では、こうした状況で知識と技術を深めていくには、どうすれば良いのでしょうか。
まず基本となるのは、現場での学びを着実に進めることです。OJTにおいては、最初からすべてを完璧にこなそうとせず、まずは見学から始めましょう。先輩の手順やご遺族への声かけ、一つ一つの所作をじっくり観察することが、学びの第一歩になります。その後、先輩の支援を受けながら部分的な業務を担い、少しずつ経験を重ねていくのが実践的な習得の流れと言えます。
さらにスキルアップを目指すのであれば、OJTだけに頼らず、外部の研修にも目を向けることが有効です。施設によっては内部研修や、私たちが実施しているような専門機関の外部講習を取り入れているところもあります。こうした機会を活用すれば、処置の流れやマナー、ラストメイクの基本などを体系的に学べるでしょう。
(※)
出典:日農医誌65巻4号,田中勝男ほか「エンゼルケアに関する実態調査からの考察」(2016)
URL:https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrm/65/4/65_879/_pdf
時代と共に変わるエンゼルケアの価値観
エンゼルケアへの関心が高まっている背景には、故人様への向き合い方の変化があります。
かつてのエンゼルケアは、医療的な後処置としての意味合いが強いものでした。しかし現在では、ラストメイクや、生前お好きだったお洋服へのお着替えなど、ご遺族の目に触れる部分をいかに穏やかで美しいお姿に整えるか、という点に価値が置かれるようになりました。
映画『おくりびと』の影響で「湯かん」という言葉が広く知られるようになったことも、この変化を象徴しています。湯かんは故人様のお身体を洗い清める儀式で、生前お風呂が好きだった方には特にご遺族から喜ばれます。
こうした変化の根本にあるのは、故人様の尊厳を最期まで大切にしたいという考え方の広がりです。看護や介護の現場で故人様と長く関わってきた看護師の方々が、「最後まで心をこめてお見送りをしたい」とエンゼルケアを熱心に学ばれるケースが増えています。
まさに社会全体で故人様の尊厳を守る方向へとシフトしているのです。弊社にも「ケアの仕方を学びたい」というご要望が増えておりますが、それもこうした時代の流れを反映していると言えるでしょう。
一人の看護師としてエンゼルケアに向き合う意味
エンゼルケアは、看護師の方にとって、「ケアの最終章」に立ち会う機会です。長く関わった患者様の旅立ちに際し、一つひとつのケアに「お疲れさまでした」といった思いが自然とこもることがあるでしょう。ご遺族からの感謝の言葉は、看護師自身の大きな励みとなり、今後につながるはずです。
エンゼルケアは、ご遺族のためだけでなく、患者様を看取った看護師自身の「グリーフケア」としての側面も持ち合わせているのです。唯一の正解がないからこそ、自分なりの気づきや学びが深まります。どのような最期を支えるのか──その問いと向き合うことが、看護師としての成長へとつながっていくでしょう。
7.看護師が担うエンゼルケアに関するQ&A
A.医療施設や介護施設の方針、ご遺族の希望などにより、エンゼルケアを誰が担当するかは異なります。
必ずしも看護師がすべてを担う必要はありませんが、医療器具の取り外しや処置の判断が必要な場合、医療職としての役割が求められることが多いのが実情です。
特に介護施設によっては、葬儀社との連携が前提になることもあり、ケア全体を分担しながら進めるケースも多くあります。「一人で背負うのではなく、チームで支える」という意識が大切です。
A.はい、もちろん関わっていただくことは可能です。
エンゼルケアはデリケートな処置であり、新人の皆様が最初に全体を任されることに不安を感じるかもしれません。しかし、多くの看護師がそうであるように、見学や部分的な関与から始め、少しずつ経験を重ねていくことで自信を培っていくことができます。
初めてのケアの後には「これで良かったのだろうか」と感じることもあるかもしれません。しかし、その一つひとつの振り返りこそが、次のケアをより丁寧にするための大切な原動力となるでしょう。
A.すべての宗教や作法を把握しておく必要はありません。大切なのは、「わからないまま進めること」ではなく、「ご家族に確認をとる姿勢」をもつことです。
たとえば、「手の位置や整え方にご希望はございますか?」といった一言が、十分な配慮になります。判断に迷う場合は、無理に整えず、中立的な整容にとどめることで、どの宗派にも対応しやすくなります。
何よりも、「丁寧に、大切に扱ってくれた」という印象が、ご遺族の安心感につながることを忘れないようにしましょう。
A.亡くなられた場所や状況、施設の体制、ご遺族の希望によって、看護師が主要な役割を担う場合もあれば、介護士や葬儀社の専門家が中心となる場合もあります。
【病院の場合】
医師による死亡確認後、看護師が中心となってエンゼルケアを行うのが最も一般的です。
【自宅・介護施設の場合】
看取りを行う医師や施設の看護師・介護士が初期対応をし、その後、駆け付けた葬儀社が専門的なケアを引き継ぐケースが多いでしょう。
【警察が介入した場合】
事件や事故などで警察が介入した場合、故人様は最低限の状態でご家族のもとへ戻るのが実情です。ご遺族の心のケアの点からも、その後の葬儀社による丁寧なエンゼルケアが特に重要となります。
いずれの場合も、看護師の方が必ずしも一人で完結させるわけではなく、葬儀社など次の専門家へきれいなバトンを渡すことも、大切な役割の一つと言えます。
8.看護師として、自信を持って故人様とご遺族に寄り添うエンゼルケア

エンゼルケアは、故人様のお身体を整える処置であると同時に、ご遺族の深い悲しみに寄り添い、安心感を届ける看護の一環でもあります。病院・介護・葬儀がそれぞれ分断されるのではなく、関わるすべての人が連携しながら、故人様の尊厳を守る社会を目指したいと願っております。
その実現に向け、花葬儀では病院や介護施設の皆さまを対象とした無料のエンゼルケア講習を行っています。「化粧品は何をそろえればよいか」「このケースではどうすべきか」といった現場の具体的なご相談にも応じます。私たちが持つ専門知識やラストメイクの技術をお伝えし、皆さまが自信を持ってケアにあたれるよう全力でサポートいたします。
看護師や介護の現場に携わる方々、また、故人様を見送ることにご心配があるご家族の方、どなた様でも歓迎いたしますので、どうぞ一度、お気軽にご相談ください。