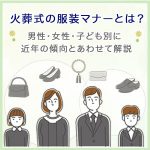自宅葬とは?自宅で葬儀を行うときの流れや費用相場
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀の種類 】

様々ある葬儀の種類、故人様をご自宅でお見送りする方法の中で、「自宅葬」という葬儀の形に今、注目が集まっています。自宅葬とは、故人様が住み慣れたご自宅でゆっくりとお見送りするという、日常の延長線上にあるような葬儀の形です。
そこで今回は、その自宅葬について、葬儀の流れや費用も含めてご紹介いたします。
自宅葬とは、どんな葬儀?

自宅葬とは、故人様の住み慣れたご自宅で行う葬儀の総称です。昔は自宅で葬儀を行うことが普通でしたが、現代では、住居環境の変化や近所との連携の難しさから、斎場での葬儀が一般的になりました。それでも近年は、少子高齢化が進み、故人様がご高齢で、お付き合いがあるご友人が少ない状況であるという現実もあり、家族葬という少人数での葬儀の形が普及すると共に、再び自宅葬が注目されているのです。
自宅葬の特徴は?
自宅葬の特徴は、故人様のご自宅で行う葬儀であることです。
つまり、故人様を知る多くの方に見送っていただく「一般葬」であっても、ご家族や親しい方々だけでお見送りをする「家族葬」であっても、葬儀の場所がご自宅である場合には、すべて「自宅葬」と呼ばれます。
自宅葬には決まったルールや形がありません。自宅を上手に利用し、工夫次第で多様なアレンジができ、自由度が高いという点が、自宅葬の特徴のひとつです。しかし、自由度が高い反面、準備や段取りに戸惑うということが多いのも事実です。自宅葬を希望する場合は、事前に葬儀社に相談しておくと、ご自宅でも安心して葬儀を執り行うことができるでしょう。
我が家でも自宅葬は可能?
自宅葬はどんなご自宅でも可能なのでしょうか。自宅葬を執り行う際に注意しておかなくてはならないポイントをご紹介します。
①葬儀を行うスペースの確保
自宅葬を執り行うスペースとしては、故人様がお休みになるお布団と枕飾り(故人様の枕元に飾る仮祭壇)が置くスペースとして、おおよそ6帖ほどの広さが目安といわれています。
ご自宅に葬儀を行うスペースがあるかどうか、予め確認しておきましょう。
②近隣住民への配慮
葬儀当日は参列者だけでなく、葬儀社スタッフや司祭者など、人や車の出入りが増えることになります。また、僧侶の読経なども響くことがあるため、隣近所には事前にご挨拶をしておきましょう。マンションの場合には、隣だけでなく上下階の住民にもご挨拶に行っておくことをおすすめします。
③駐車場の確保
自宅葬を行う際は、葬儀を行う室内のスペースだけでなく、ご親族やご参列者はもちろん、霊柩車や司祭者のお車が駐車できるように、余裕のある駐車スペースを確保できるかどうかも事前に確認しておきましょう。
④室内移動時の動線の確保
自宅葬をスムーズに執り行うためには、故人様が移動する際のストレッチャーや棺の搬入搬出が可能かどうか、玄関や階段など室内移動時の動線の広さを確認しておきましょう。
⑤マンション管理側の許可
マンションなどの集合住宅で自宅葬を行う場合は、事前にオーナーまたはマンション管理会社へ、自宅葬を行うことができるかどうかを確認しましょう。マンションによっては、規約で禁止しているところもありますので、注意してください。
⑥階層移動スペースの確認
マンションなどの集合住宅で2階以上の場合、階段、またはエレベーターでストレッチャーまたは棺が移動できるかどうかも予め確認しておく必要があります。
これらはあくまでも一般的な注意点ではありますが、その時を迎えてからでは慌ただしく、また確認や相談する内容が多いことからストレスに感じてしまう可能性もあります。
集合住宅で自宅葬を行う場合は、予めオーナーや管理会社に確認をとってから葬儀社に相談をするとスムーズに進めることができ、いざというときにも慌てずに安心して自宅葬を執り行うことができるでしょう。
自宅葬が選ばれるのはなぜ?
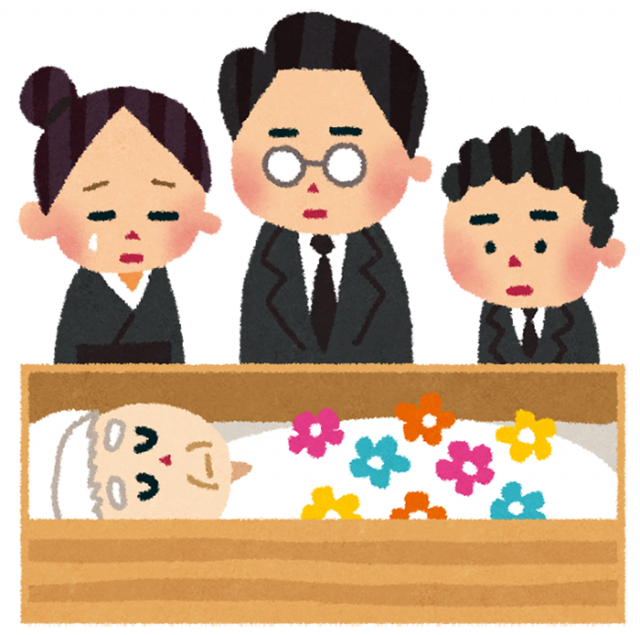
近年、宗教観の変化や、経済的な理由など様々な理由から、家族や親族、親しい方々だけで執り行う家族葬が増加傾向にあり、合わせて自宅葬にも注目が集まっています。
自宅葬のメリットとは?
自宅葬の主なメリットをあげてみましょう。
- ・葬儀場のように利用時間の制限がないため、故人様と一緒に過ごす時間がゆったりと確保できる
- ・葬儀場のルールにとらわれず、自由な形で葬儀を執り行うことができる
- ・葬儀場の使用料金がかからない
- ・参列者の人数を少人数に制限しやすい
自宅葬は、時間の制限や葬儀場のルールにとらわれず、少ない人数でゆっくりと安らかに故人様とのお別れができる葬儀の形であると言えます。
また、故人様の「最期は住み慣れた自宅で、リラックスして過ごしたい」という思いや、ご遺族の「故人と一緒に住んだ思い出の詰まった自宅から見送りたい」というご希望など、近年の自由度の高い形を求める方々にとって、自宅葬は理想的な葬儀の形であるともいえるでしょう。
花葬儀の「自宅葬」プラン
花葬儀では「自宅葬」のお手伝いもしております。プランニングスタッフがご家族から故人様のお人柄や思い出、ご家族の葬儀に対するご希望などを伺いながらフラワーデザイナーとともに、故人様のためだけの花祭壇をお作りします。すべての方が生きてきた道程が異なるように、花葬儀の花祭壇も二つと同じものはなく、そこに故人様が息づくような、そんな祭壇をお作りいたします。
祭壇だけでなく、葬儀に必要な物品とサービスを含めた基本プランをご用意していますので、ご家族の皆様にとって不慣れな葬儀でも、不足なく、安心して自宅葬が迎えられるような段取り、サポートを整えております。
住み慣れたご自宅で故人様と一緒に最期のときを過ごす「自宅葬」。その空間を故人様らしく、美しく彩るお手伝いをしております。
花葬儀の自宅葬について もっと詳しい情報はこちらをご確認ください。
https://www.hana-sougi.com/plan/jitakuso/
自宅葬の流れとは?通夜は必要?
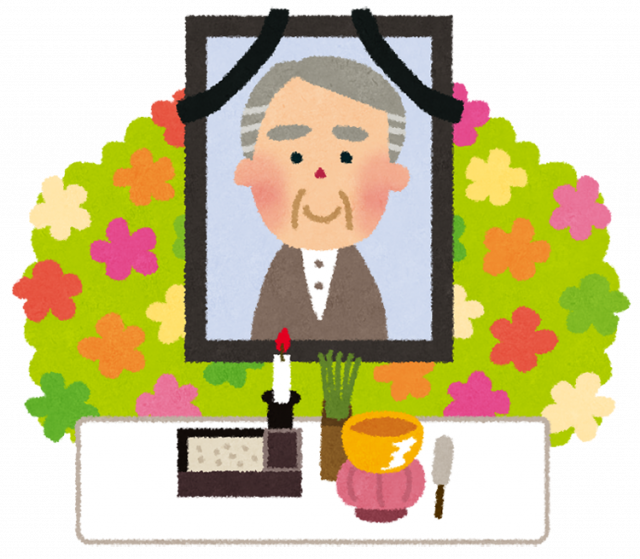
葬儀とは、故人様に代わって生前の感謝を伝える場でもあります。自由度の高い自宅葬であっても、ご参列いただく方々に失礼のないよう、葬儀の基本や自宅葬の流れについては、しっかりと理解しておきましょう。
自宅葬の一般的な流れ
一般的な自宅葬の流れをご紹介します。
1.臨終
①ご自宅で亡くなった場合:
なるべく動かさず、そのままの状態で、かかりつけ医に「死亡診断書」を発行してもらい、かかりつけ医がいない場合には、警察に連絡し、「死体検案書」を交付してもらいましょう。
②病院で亡くなった場合:
医師による死亡確認を受け、「死亡診断書」を受け取りましょう。
2.葬儀社へのご連絡
病院で亡くなった場合、寝台車で故人様をご自宅へ搬送します。
3.ご自宅にて故人様を安置、枕飾り(仮祭壇)を設置
故人様へ装束を着せ 死化粧などを施し、旅立ちの準備をします。ドライアイスの処置も行います。
4.葬儀社とお打合せ
日程、喪主、葬儀の種類、祭壇デザイン、棺、お料理、返礼品などについて決めていきましょう。
5.親族へのご連絡
血縁の近いご親族から連絡をして、葬儀日程が決まり次第、遠方のご親族や、葬儀にご参列いただきたい方へ連絡をするようにしましょう。
【お通夜当日】
6.ご納棺
お通夜当日に、棺に納めます。
7.祭壇などの設営
8.通夜
お通夜では、僧侶の読経がおこなわれ、ご参列者は焼香をします。
9.通夜ぶるまい
お酒や軽食で弔問客をもてなし、思い出を語りながら故人様を偲びます。
【葬儀・告別式当日】
10.葬儀告別式
僧侶による読経とご参列者の焼香をし、故人様と最後のお別れをします。
*初七日法要も併せて行なうことも多い。
11.出棺
霊柩車へ棺を乗せて、火葬場へ向かいます。ご参列者も後に続いて
火葬場へ向かいます。
12.火葬、お骨上げ
火葬場に到着したら1~1.5時間前後の時間をかけて火葬をし、火葬後はお骨を骨壺に納める収骨(お骨上げ)をします。
13.精進落とし
ご自宅に戻り、お食事(精進落とし)を振舞います。ご参列者にお礼を伝えましょう。(料理屋や寺院で行うこともあり)
*ご自宅に戻られたタイミングで初七日法要を行うこともあり。
14.後飾り祭壇への遺骨安置
遺骨は、ご自宅に戻りお墓に納骨するまで自宅に安置し、弔問してくださった方にはその祭壇にお参りしていただきます。
自宅葬でもお通夜は必要?
葬儀というとお通夜をすることが当たり前とお考えの方もいらっしゃいますが、自宅葬ではお通夜を行わないという選択肢もあります。
お通夜はもともと、ご家族やご親族が故人様とゆっくりしたお別れの時間を確保するため故人に付き添い夜通し行われていた儀式であり、告別式は、親族以外のご参列者のために執り行っていたという説もあります。
つまり、お通夜はご家族が故人様をお見送りする心の準備の時間であると考えれば、ご家族、ご親族が中心となる自宅葬では、お通夜を行わなくても問題はないと言えるでしょう。2日に渡って行われるお通夜・告別式は、ご遺族の方々には体力的なご負担もかかります。お通夜を行わないという選択肢があることを頭に入れておくと、気負わずに自宅葬を執り行うことができるかもしれません。
自宅葬にかかる費用相場

自宅葬にかかる費用相場は、葬儀会社に相談しながら執り行う場合と、業者を通さず自分達で自宅葬を行う場合で違いがあります。また、どのような自宅葬を執り行いたいかというご意向によっても費用は変わってくるでしょう。
ここでは、自宅葬にかかる費用相場について、参考となる具体的な金額も含めてご紹介いたします。
葬儀業者を通さない場合の費用
自宅葬と一口に言っても、その形や規模は様々です。家族だけで、僧侶なども呼ばずシンプルに執り行うという場合には、会場費やお布施代など、大きな金額の負担がないため、10万円以内で執り行うこともできるでしょう。
ただし、必要な段取りのすべてをご家族だけで執り行うとなると、棺や骨壺のお手配や、火葬場まで棺を移送する段取りまですべてがご家族の負担となりますので、現実的ではないかもしれません。落ち着いて家族だけでの葬儀がしたいとお考えで自宅葬の選んだのに体力的にも精神的にも負担を抱えてしまい、故人様を気持ち良く見送りができなくなってしまっては意味がありません。気持ちを落ち着かせて、しっかり故人様とのお別れの時を迎えるためにも、葬儀社に相談することをおすすめします。
葬儀業者に依頼する場合の費用
葬儀会社に依頼して自宅葬を執り行う場合の費用は、その形や規模によっても幅がありますが、おおよそ40万円~100万円程度と考えておきましょう。
ただし、自宅葬は、決まった形があるわけではなく、故人様やご遺族のご希望により多様なアレンジも可能であるために、そのこだわりで費用がかさみ、相場を越えてしまうようなことも考えられます。
一方で、自宅葬の場合、ご参列は家族や親族が中心で、一般のお通夜や告別式のような大人数にはならないことが多く、人数が少ない分、会食や返礼品をご用意する数も少なく済みますので、費用も抑えられるということも考えられます。
葬儀業者に依頼するということは、自分達ですべてを執り行うよりは費用が掛かる方法ですが、故人様との最後のお別れの時に、余計な心配や焦りは、思っている以上にご負担になります。安心して葬儀を執り行えるように、自宅葬の場合でも葬儀社に相談することをおすすめいたします。
自宅葬にはデメリットもある?

「自宅葬」は時間の制限や葬儀場のルールにとらわれず、少ない人数で、しっかりと故人様とのお別れができる比較的自由度の高い葬儀の形ではありますが、デメリットについてもしっかりと理解しておきましょう。
まず、自宅葬の場合、前述の通り自宅のスペースや動線の確保や、ご近所への配慮が必要になります。その点は予め確認をしておきましょう。
また、自宅内で行うということは、スペースを確保するために多少でも家具を移動したり、戻したり、食器類なども通常よりも多く使用することになりますので、後片付けの負担がかかる場合もあります。
葬儀社に依頼した場合でも、家具の移動や物の管理など、そのご家族の判断が必要になる部分も出てくるため、ストレスに感じてしまうこともあるかもしれません。故人様のご希望ももちろん大切ですが、葬儀を取り仕切ることになる喪主様や、ご家族にとって、負担になりすぎないことも大切です。予めご家族でしっかり話し合いをしておきましょう。
自宅葬に参列するときのマナー

自宅葬という選択をされたご遺族は、「身内だけでゆっくり見送りたい」と考える方がほとんどです。ご遺族から案内がない場合には、葬儀へのご参列や、弔問は控えるのがマナーですので、ご遺族のお気持ちを尊重しましょう。
直接訃報のお知らせを受けた場合や、葬儀の日時が明記されたメール等を受け取った場合には、参列して問題ありません。
ここでは、自宅葬に参列するときのマナーについてご紹介いたします。
自宅葬に参列するときの服装は?
自宅葬に参列する場合、特別な指定が無い限りは、一般葬に参列するときと同じように「喪服」で参列するようにしましょう。案内状やメールに「平服でお越しください」という文言が書かれていることがありますが、この場合の平服は、文字通りの普段着という意味ではありませんので注意しましょう。
喪服には、格式の高い順に「正喪服」「準喪服」「略喪服」と種類があり、葬儀でいう平服というのは、「略喪服」に当たります。この「略喪服」は「正喪服」「準喪服」に比べて、もう少し緩く、モノトーンで少装飾な服装が良いとされています。
バックや靴などの小物は革製品でも良いですが、革の素材感が強調されるようなものはNGとされるので、光沢感や艶感の無いものを選びましょう。
自宅葬の場合のお香典・お供花
自宅葬の場合、ご遺族がお香典を辞退するケースが多いのですが、訃報の案内などに香典は辞退するという旨記載がない場合には、基本的にはお香典は必要だと覚えておきましょう。
お供花についても、ご遺族が辞退されている場合には、案内状に記載があるのが一般的ですので、手配する前に確認しましょう。
ご遺族がお香典やお供花を辞退されている場合には、お香典やお供花は控える、というのがマナーになります。気を配ったつもりでお送りしてしまうと、香典返しや返礼品など、ご遺族の負担を増やしてしまうことになってしまいますので、自宅葬の場合には、ご遺族の気持ちを尊重するようにしましょう。
自宅葬に参列するときの当日の振舞い方
自宅葬は、ご家族やご親族を中心とした親しい方だけで故人を見送る葬儀の形です。その少ない人数の中でお声がけいただいたご参列者は、喪主様やご遺族の思いを汲んで、故人様を偲び、故人様との最期のお別れの時間を大切に過ごしましょう。
また、お食事についてもお誘いがあった場合にはお受けし、お食事をしながら故人様との思い出を語り合いましょう。このような時間をとることで、ご家族の気持ちも次第に整い、故人様とのお別れの準備ができてくるのです。
そして、自宅葬に参列した場合には、ご家族が葬儀を終えた報告をするまでは、自分では口外しないようにしましょう。自宅葬はご家族やご親族が中心のため、故人様を知る人の中にも、葬儀に招かれなかった方も多くいらっしゃる可能性があります。他者にそのことを話して広まってしまうと、故人様とお別れをしたかった方々が故人様のご自宅に弔問に訪れる可能性があります。自宅葬を終えてすぐに予定外の弔問客への対応は、ご遺族にとって負担になってしまいますので、ご遺族のお気持ちを第一に考え、その気持ちに寄り添った行動をするように気を付けましょう。
自宅葬とは?自宅で葬儀を行うときの流れや費用相場
A.祭壇の設置は必須ではありませんが、一般的には設けられます。
葬儀の祭壇は、遺影写真や供物、宗教のシンボルなどをお供えし、故人様を供養するための大切な台です。設置が義務づけられているわけではありませんが、特別な事情がない限り設けるのが一般的です。
しかし、ご自宅の広さによっては、一般的なサイズの祭壇(白木祭壇など)を設置するのが難しいこともあるでしょう。そうした場合には、「部屋のサイズや雰囲気に合わせたオリジナルの祭壇」を設けることも可能です。
花葬儀では、花で彩る「花祭壇」を全てオーダーメイドでお作りしており、限られた空間の中でも故人様への想いがしっかりと伝わる、心温まるお見送りが可能です。詳しくは花葬儀の「自宅葬プラン」をご覧ください。
A.「家族の訃報とこれまでのお付き合いに対する感謝」「自宅葬を執り行う旨」「迷惑をおかけする可能性へのお詫び」です。
自宅葬では普段より多くの人や車両の出入りがあるため、周囲への配慮は欠かせません。葬儀前にご近所を訪ね、以下の点を丁寧に伝えましょう。
・家族の訃報と生前のお付き合いに対する感謝
これまでのご縁や支えに感謝の意を伝えることで、訃報を共有するだけでなく、故人への思いをともに分かち合う場にもなります。
・自宅葬を執り行うことと日程
事前に日時や式の概要を知らせることで、無用な誤解や不安を防ぐことができます。
・葬儀当日に迷惑をおかけする可能性へのお詫び
駐車スペースの不足や通行の妨げ、葬儀車両の出入りによる騒音などに対し事前に謝意を示すことで、ご近所の理解を得やすくなります。
特に葬儀が「家族葬」のかたちで行われる場合には、近親者のみで見送る旨を事前にお伝えすることで、不要な混乱を防ぐことができます。
なお、葬儀が終わった後は、改めて近所にお礼とお詫びの挨拶をすることも大切です。「家族葬で必要な近所への対応」の記事も参考になさってください。
A.ご自宅で葬儀を行う場合は時間やルールの制約が少ないため、形式にとらわれず、自宅ならではの空間で行えるお葬式です。
葬儀会場を使用しないため、独自のスタイルでのお見送りができます。具体的には以下のような特徴があります。
・限られたスペースでも可能
6畳ほどのスペースがあれば執り行うことができ、住環境に合わせた工夫が可能です。
・住み慣れた空間での安心感
病院で療養されていた方が「最後は自宅に帰りたい」と望まれる場合や、ご家族が「住み慣れた場所で見送りたい」と思われる場合に選ばれることが多く、自宅そのものが「故人様らしさ」を表現する舞台となります。
・自宅全体を活かした空間演出
庭や居間など、ご自宅全体を活用して式を組み立てることができます。たとえば花葬儀でお手伝いした事例では、庭いじりがお好きだった故人様のために、ご自宅の庭全体を活かした空間演出(ガーデン葬)を実施。お庭に祭壇と棺を設け、開放的であたたかな雰囲気の中、ご家族によるピアノの演奏や、お花の壺活けを照らすライトアップ、和傘を使った演出など、随所に故人様らしさを表現。ご遺族からは「その人らしい式になった」と大変ご満足いただきました。式の詳細については、お客様インタビュー「お父様が愛した自宅のお庭でのガーデン葬」をご覧ください。
・自由な形式でのアレンジ
「立食スタイルでのおもてなし」「宗教儀式を最小限にし、ご家族だけの時間を大切にする」など、柔軟な対応が可能です。
このように、自宅葬は「自宅というかけがえのない場所で、限られたスペースを活かしながら、故人様の趣味・思い出やご家族の希望を取り入れ、故人様らしいお見送りができる」という点が大きな魅力です。実績豊富な葬儀社であれば、環境に合わせた柔軟な提案を受けることができるでしょう。
まとめ
自宅葬に参列したことがないと、その葬儀の形に想像がつかず、周りと違う葬儀をして大丈夫かと不安に思うこともあるかもしれません。ですが、これまでご紹介したように、現代の多様な価値観や、宗教観の変化などにより、葬儀の形も様々な形に変化しています。その中でも自宅葬は自由度が高く、これからの葬儀に求められる理想の形のようにも思います。
故人様とご家族にとって、本当にベストな最期の時間というのは、どういう形なのか、ご家族で話し合い、その思いをぜひ花葬儀にお聞かせください。故人様とご家族の大切な時空を彩るお手伝いをさせていただきます。
花葬儀の事前相談
https://www.hana-sougi.com/first/jizensoudan/