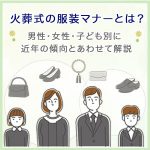社葬の損金算入の範囲と必要な手続き
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀の種類 】
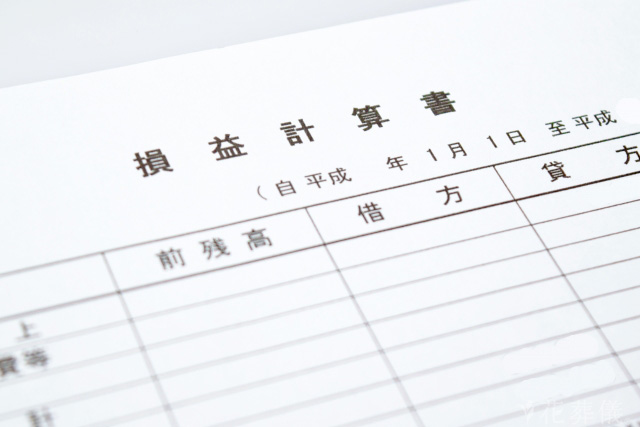
社葬を執り行うにあたり、会社として費用はどのように扱えばよいのか、いわゆる「お金」のことを気にされたこともあるのではないでしょうか。今回は、社葬を執り行うとき、その費用は税法上どうなるのか、損金算入との範囲と必要な手続きをまとめました。
1.社葬の損金算入の範囲を決めるには、まず「社葬取扱規程」の確認から

社葬の費用をどうするかを確認するにあたり、まずは社内に「社葬取扱規程」があるかを確認しましょう。この規程は、費用の話だけではなく、社葬をミスなく進める指針となる、非常に重要なものです。もし作成されていれば、社葬を執り行うための決め事は、この内容に則って検討、判断することになります。もちろん、費用の取り扱いも基準が決められているため、それをベースに考えましょう。
「社葬取扱規程」が作成されていない場合は、それを作ることから始めます。そのさい、規程の作成をサポートできる、社葬経験が豊富で知識、経験、提案力のある葬儀社を探しましょう(もちろん、私ども「花葬儀」も、作成をイチからサポートさせていただきます)。
「社葬取扱規程」の中で具体的に決めていく内容は、おおむね以下のとおりです。
社葬の対象者を決定する
社葬の対象となる方は、一般的には創業者、現職の代表者、役員など。役職者以外ですと、会社の大きな発展に携わった功労者や、殉職された方が対象となります。対象となる方をあらかじめ決めておくことで、社内の重要な方に業務上の不幸が発生した場合にも備えることができます。
社葬の費用の負担割合を決定する
社葬にかかる費用について、すべての案件で会社側が全額負担するのか、あるいは案件や対象者によって負担割合を変えるかを定めます。こちらもあらかじめ取り決められていると、見込まれる費用の確保や進行がスムーズになります。
社葬の形式を決定する
これら以外で、社葬において決めるべきことを箇条書きで並べます。
- ・責任者の選定
- ・服装
- ・御霊前(お香典)について
- ・供花、供物の取り扱い
- ・会場(式場)の選定
- ・当該企業単体でおこなうのか、ご遺族や関係団体との合同葬とするのか
もちろん、故人様の役職や勤続年数によって扱いを変えることもあるでしょう。それらも細かく記載することが、物事のスムーズな決定につながります。
2.社葬の費用の法人税上の取り扱いは?経費範囲として認められるもの、認められないもの

社葬の費用は、
事案が起こったら「社葬取扱規程」に則り、社葬開催の決定、その費用を税務上損金で処理するために取締役会において承認を得る
という流れで決められます。
先ほど、社葬の費用の負担割合について少し触れましたが、次は損金の対象となる経費について、法人税法上の取り扱いをご案内します。
社葬費用の損金処理ついて
社葬の費用について、国税庁では法人税基本通達(法基通9-7-19)で以下のように示しています。
—————————————————–
法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬の為に通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。また、会葬者が持参した香典等については、法人の収入としないで遺族の収入とすることができます。
参考:国税庁HP No.5389 社葬費用の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5389.htm
—————————————————–
「社会通念上相当」と認められるときとは、どのようなこと?
「社会通念上相当」についての判断は、対象者の職務上の地位や貢献度、あるいは死亡した理由などで決まります。「社葬取扱規程」で挙げた『社葬の対象者を決定する』要素は、この「社会通念上相当」と認めるかの判断にあたります。総合的に「会社として費用を負担することに十分である」と判断される場合には、福利厚生費として損金に計上することができます。
一方、「相当しない」と判断される場合は、福利厚生費としての計上は認められません。また、ご参列者が持参した御霊前(お香典)は、企業ではなく、ご遺族の収入とするとよいでしょう。法人で受理される場合は、雑収入として計上する必要があります。
社葬経費の範囲として具体的に認められるもの、認められないもの

次に、社葬の費用に含めるものを決めるにあたり、経費の範囲として認められるもの、認められないものをまとめました。
■社葬経費範囲として認められるもの
- ・基本プランの料金
- ・祭壇費
- ・写真、ビデオなどの撮影費
- ・案内通知状、御礼状などの印刷、発送費
- ・移動に伴う交通費
- ・訃報広告費
- ・会葬御礼品、記念品などの費用
- ・会場費
- ・飲食費(認められない場合もあるようです)
- ・宗教家への謝礼(僧侶へのお布施など)
- ・スタッフの人件費
「社葬を執り行うために必要とされるもの」として、領収証も大切に保管し、勘定科目ごとに分けておきましょう。
■社葬経費範囲として認められないもの
- ・戒名料
- ・火葬料
- ・収骨容器(骨壺)代
- ・位牌代
- ・香典返しの費用
- ・墓地、埋葬費
「故人様に帰するもの」は、原則的に経費としては認められないと考えておくとよいでしょう。
また、以下のような場合は会計処理(勘定科目)が異なります。
- ・役員賞与(ご遺族が役員の場合)
- ・寄付金(ご遺族が当該法人関係者でない場合)
社葬経費以外のやむを得ない支出については「弔慰金」として処理し、一定額を超える場合は死亡退職金として処理することもあります。弔慰金として受理した場合は非課税ですが、死亡退職金として受理した場合は相続税の課税対象になります。
3.社葬の損金算入の範囲と必要な手続きに関するQ&A
A.僧侶へのお布施は領収書が発行されにくいため、不祝儀袋の写しや読経の証明を用意しておくと、精算の際に役立ちます。
僧侶へのお布施は「感謝の気持ち」「修行の一環」という位置づけから領収書を受け取りにくいのが実情ですが、社葬費用として必要性・妥当性が認められる場合には、損金算入できることがあります。可能であれば領収書を依頼し、会社経費として計上しにくい「戒名料」とは分けて発行してもらうように依頼しましょう。
領収書が受け取れない場合は、以下のような書類を保管しておくことで、支出の証明として役立てることができます。
・不祝儀袋の表(住職名)と裏(金額記載)の写し
・僧侶が読経を行ったことを示す証明
・出金伝票
ただし、経費計上の可否は会社の社葬取扱い規定や税務署の判断によって異なります。必ず社内規定を確認するとともに、必要に応じて顧問税理士へ相談してください。
A.合同葬の費用負担は、ご遺族と会社の話し合いによって決められます。
社葬には主に3つの形態があり、そのうち「合同葬」はご遺族と会社が共同で喪主となり、葬儀を執り行います。
費用の内訳は話し合いで決定しますが、一般的には会場費や設営費など損金処理できる部分を会社が、香典返しや宗教儀礼に関わる費用など私的性質の強い部分をご遺族が負担するケースが多くみられます。詳しくは「合同葬とは?」の記事もぜひ参考になさってください。
A.社葬の費用は、一定の条件を満たす場合に限り損金算入できます。
社葬にかかる費用が損金算入できるかどうかは、前提として「社会通念上相当と認められること」が条件となります。具体的には、以下の通りです。
・故人様が会社で重要な役職を務めていたなど、企業への貢献度が高い場合
・就業中の事故など、業務上の理由による死亡である場合
社葬で見送られた経営層のご親族が会社に所属しており、なおかつ上記のいずれかに該当する場合には、その葬儀費用は損金として認められます。一方、これらの条件に該当しない場合は、損金算入の対象にはなりません。
4.まとめ
具体的な経費項目を把握しておき、どれだけ細かいものでもなるべく「社葬取扱規程」に落とし込んでおくことが大切です。
社葬をミスなく、スムーズに執り行う為にも、作成のさいは社葬知識のある葬儀社のサポートを得るようにしましょう。