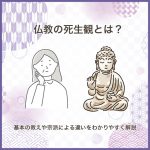もし自分が余命宣告を受けたら?自分らしく過ごすヒントや、今できることとは
- 作成日: 更新日:
- 【 生き方のヒント 】
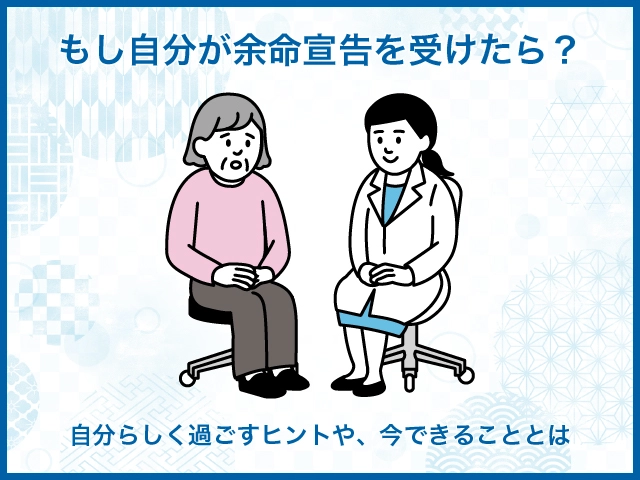
この記事は、余命宣告を受けた方、自分が余命宣告を受けた場合に備えて、受け止め方や過ごし方を知りたい方に向けてお届けします。
「ドラマや映画の中だけの話だと思っていたことが、自分の身に起こるなんて……。」
「なぜ自分なのか、どうして今なのか、何が悪かったのか。」
「命に限りがあることはわかっていても受け入れられない。気持ちの整理がつかない。」
余命宣告を受けた方がこのように感じるのはごく自然なことです。しかし、宣告をどのように受け止め、どう過ごすかによって、残りの時間で得られるものは大きく変わります。
この記事では、余命宣告を受けた「自分」がどう心を守り、残された時間を穏やかに過ごせるかを、丁寧にお伝えします。つらい気持ちを抱えている方にとって、少しでも心が軽くなるヒントが見つかれば幸いです。
1.余命宣告とは?

まずは、余命宣告の意味や現実的な捉え方について基本的な情報を整理します。
余命宣告の意義
余命宣告とは、医師が医学的データや経験に基づき、「生存期間の目安」を患者やご家族に伝えることです。「余命宣告=死の宣告」と捉えられがちですが、決してそうではありません。むしろ、残りの人生の時間をどのように過ごすか、治療や生活の選択を考えていただくための、大切な情報提供と言えます。
宣告されやすい病状・例
余命宣告は主に、がんなど治療が難しい進行性の病気で行われます。例えば末期がん、心不全、慢性呼吸不全などが代表的です。
治療が限られる中で、緩和ケア(※1)への移行の選択肢などとともに、医師が説明する場面が多いでしょう。「余命を患者本人に伝えない方針」の病院もありますが、本人・ご家族の希望次第で、告知するケースも増えています。
(※1)病気に伴う身体的・精神的苦痛を和らげることを目的としたケア。
宣告される余命は「確定した未来」ではない
医師の伝える「余命」は、あくまで過去の統計データに基づく目安に過ぎません。つまり、その期間で必ず亡くなるわけではないということを押さえておきましょう。実際には、告げられた余命より長く生きる方も多くいらっしゃいます。
大切なのは、「余命」という言葉にとらわれず、残された時間の価値をどう見つめるかということです。悲観だけでなく、「生きられる時間を大切に過ごす」ための目安と捉えてみてください。
2.余命宣告を受けた「自分」の心の状態
余命宣告を受けたとき、多くの方は冷静ではいられません。人は突然の現実を前にしたとき、「心の防衛反応」がはたらきます。特に有名なのが、精神科医エリザベス・キューブラー・ロスが提唱した「悲嘆の5段階モデル」です。
これは否認、怒り、交渉、抑うつ、受容という5つの過程を経て、人は心の整理を進めていくというもので、具体的には以下の通りです。
【悲嘆の5段階モデル】
・否認:事実を受け入れられず、事実を否定する
・怒り:「なぜ私なのか」という怒りが湧く
・交渉:事実から逃れるために交渉を試みる
・抑うつ:気持ちがふさがる
・受容:事実を受け入れ、容認する
余命宣告を受けた場合も、この流れに沿って感情が変化していく方が多いようです。必ず順番通りではなく、心の変化を行ったり来たりしながら、少しずつ心が落ち着いていくとされています。
3.余命宣告後に自分に訪れる体調変化
病状が進行すると、心だけでなく身体にもさまざまな変化が訪れます。症状が強くなる日もあれば、体調が安定する日もあるでしょう。
主な病気ががんの場合、痛みや倦怠(けんたい)感、食欲の低下などの症状が少しずつ現れることがあります。抗がん剤治療を続けている方は副作用による吐き気や脱力感を感じやすいでしょう。呼吸器系の病気の場合は息苦しさが生じることもあります。
こうした自分に訪れる体調変化には、波もあります。つらい日々が続くと身体だけでなく、心にも大きな負担がかかってしまうでしょう。しかし、身体的な苦痛は、緩和ケアなどで和らげる場合もあります。決して一人で我慢せず、医療スタッフに相談することが大切です。
次からは、体調の変化と向き合いながら、少しでも穏やかに日々を過ごすためのヒントをご紹介します。
4.余命宣告後の過ごし方|残りの時間を自分らしく過ごすために
余命宣告を受けた後、何をどうすればよいのか悩む方は多くいらっしゃいます。現実を受け止めることさえ難しい中で、行動に移すことは簡単ではありません。
しかし、今後を考えることは「限られた時間をどう過ごすか」を見つめ直す機会にもなります。ここでは、残された時間を自分らしく生きるための選択肢をお伝えします。
まずは「気持ちを出すこと」から始める
余命宣告を受けた後、心の中に抱える不安や戸惑いを一人で抱え込んでいませんか。無理に前向きにならなくても大丈夫です。まずは、今感じていることを表に出してみましょう。
信頼できる人に話す
話す相手は家族や友人でなくてもかまいません。医療スタッフやカウンセラーなど、専門の相談先を利用してもよいでしょう。苦しみや不安を信頼できる人に話すことで少しずつ心が整理され、これからの時間と向き合う準備が整っていきます。
書き出して自分と対話する
誰かに話すことが難しいときは、ノートやスマホのメモアプリに気持ちを書き出してみましょう。思いつくままの言葉でも十分です。自分自身の本音に気づくきっかけになるかもしれません。
「治療方針」を自分の意志で選ぶ
体力があるうちに考えておきたいのが、今後の治療方針です。医師やご家族と相談しつつも、「自分はどうしたいか」を大切にしてください。
治療の選択肢を確認する
余命宣告を受けた後の治療について、どのようにしたいかを考えます。選択肢は主に以下の通りです。
・完治を目指す治療を続ける
・延命を目的とした治療を受ける
・痛みを和らげる緩和ケアに移行する
どの選択肢が正解ということはありません。「今はどこまで治療を頑張れそうか」「どんな過ごし方をしたいか」に目を向け、自分が納得できる道を選んでみましょう。
セカンドオピニオンの活用
治療方針に迷ったときは、セカンドオピニオンを利用するのも一つの方法です。担当医以外の医師に意見を求めることで、新しい視点が得られることがあります。医師によって方針が異なる場合もあるため、選択肢を広げる意味でも相談してみるとよいでしょう。
「やりたいことリスト」で小さな夢を形に
体力や気力があるときには、「何をしてみたいか」を考えてみましょう。いわゆる「やりたいことリスト」「バケットリスト」と呼ばれるものを作成します。
「好きな景色をもう一度見たい」「昔の友人と話したい」「おいしいものを食べたい」など、小さなことでも大丈夫です。書き出してみると、今できることが自然と見えたり、前向きな気持ちが湧いてきたりすることもあります。
特にリストに加えることをおすすめしたいのが、「大切な人と過ごす時間」です。多くの人が人生の最後に「もっと家族や友人と一緒に過ごせばよかった」「感謝を伝えられなかった」と後悔すると言われています。特別なことでなくても、何気ない日常を誰とどのように過ごしたいか考えてみることが、後悔しないための第一歩になるでしょう。
「身の回りの整理」で心と向き合う
体調や気持ちが落ち着いているときに、身の回りの品や思い出の品を少しずつ見直してみましょう。物を減らすことが目的ではありません。これまでの人生を静かに振り返り、「自分にとって大切なものは何か」に目を向ける時間です。
整理を進める中で、ふと心が軽くなる瞬間が訪れることもあります。無理なく自分のペースで取り組んでみてください。
「自分の希望」を記す
少し心が整ってきたら、「自分の希望」を形にしてみましょう。延命治療や緩和ケアの希望、葬儀のこと、大切な人へのメッセージなど、自分の考えや願いを書き残しておくことで、気持ちが穏やかになることもあります。「どう書けばいいかわからない」と感じたときは、書きやすい項目から始めてみてください。
「何もしない日」も大切に
調子の良い日は何かしてみたくなるかもしれませんが、動けない日は「今日は休む日」と割り切ることも大切です。何もできない日があって当然です。自分を責めず、ゆったりと過ごしてください。好きな音楽を聴いたり、窓の外を眺めたりするだけでも、心は少し穏やかになれるはずです。
5.心身に余裕があるときに取り組みたい「終活」の準備
余命宣告を受けた後でも、心と体に少し余裕がある方は、これからの時間を整える準備に目を向けてみませんか。
人生の最後に備えた活動は「終活」と呼ばれ、「余命宣告を受けた・受けていない」に関わらず多くの方が取り組んでいます。「終」のつく言葉の響きから、つらい印象を持たれるかもしれません。しかし終活の目的は、“自分らしく生きるための準備”という前向きな行動です。以下の中から、自分のペースでできることを見つけてみましょう。
エンディングノートで想いと希望を書き残す
病気が進行して自分の意思を伝えることが難しくなった時のために、もしくは万が一のときにご家族が困らないようにするために、想いと希望を書き残しておきましょう。残しておくとよいとされる情報は、主に以下の通りです。
【医療に関する希望】
・延命処置の有無
・臓器提供の意思
・投薬やその他治療に関する希望 など
【財産に関する情報と希望】
・財産情報
・相続について など
【葬儀やお墓に関する希望】
・葬儀形式
・葬儀に呼んでほしい人の情報
・埋葬方法 など
【その他】
・貴重品の保管場所
・契約中のサービス
・ご家族に対するメッセージ など
こうした「自分の気持ち」をまとめるための道具として、エンディングノートがあります。エンディングノートは、あなた自身のために自由に書くことができるノートです。
エンディングノートに法律的な効力はありませんが、ご家族にとってはあなたの想いを知る大切な手がかりになります。話しづらいことも、言葉にしておくことで安心につながるはずです。
決まった書き方はないので、思いつくことから自由に書き始めてみましょう。「何を書けばいいかわからない」と迷うときは、市販の専用ノートや無料テンプレート、「エンディングノートの書き方」の記事などを参考になさってください。
財産や相続の整理を考える
ご自身の財産や相続について考えることも大切です。通帳や不動産、保険証券などの財産は、わかりやすく整理しておくだけでもご家族の負担を減らせます。
財産の分け方などについて具体的な意向がある場合は、遺言書を作成することも選択肢です。遺言書は法律に則って書く必要があるため、専門家のサポートを受けると安心です。無理なくできる範囲で構いませんので、気になることから少しずつ準備を進めてみてください。
自分らしい「葬儀」や「お墓」の希望を考える
「どんな葬儀にしたいか」「お墓はどうしたいか」なども考えてみましょう。たとえば次のような希望が挙げられます。
・小規模で静かな家族葬にしたい
・お花の多い明るい葬儀にしてほしい
・宗教にとらわれない自由な式にしたい
・お墓ではなく樹木葬(※2)や納骨堂(※3)を希望したい
(※2)墓石の代わりに樹木を墓標とし、その下に埋葬する方法。
(※3)ご遺骨を供養するための建物や屋内施設。多くの場合、ご家族に代わって納骨堂がご遺骨の供養・管理を行う「永代供養」が受けられる。
自分の幕の下ろし方を、生前に自分で準備される方は最近増えています。事前に決めておくことで、ご家族が本来進める負担を軽減できるだけでなく、最期に向けての気持ちが整うこともあるようです。
実例として、ご自身の葬儀について前向きに考え、旅立たれた方のご家族から伺ったお話をご紹介します。故人様が思い描かれたあたたかな葬儀と、その実現に向けて取り組まれた日々は、ご家族にとっても大切な記憶となっています。
<花葬儀 お客様インタビュー>
奥様のこだわりを全て盛り込んだ完全オーダーメイドのガーデン葬
ご自身の最期をどう迎えたいか──。迷いながらこの記事を読まれている方の心に、そっと寄り添うことができれば幸いです。
自分自身の人生をふり返る時間を持つ
終活は手続きだけではありません。これまでの人生を静かにふり返る時間を持つことも、大切な準備のひとつです。
たとえば、写真を整理したり、これまでの思い出をノートに書き留めたりといった時間が、「自分はどんな人生を歩んできたのか」「何を大切にしてきたのか」に気づくきっかけになります。
思い出を残す方法はさまざまですが、そのひとつとしてWebサービス「つなごう」をご紹介します。「つなごう」は、スマートフォンの中にある写真やアルバムの中に眠っている写真を、デジタル上で保管し、ご家族と共有することができるツールです。大切な方へのメッセージを残すこともできます。詳しくは公式ページをご覧ください。
「つなごう」公式サイト
https://tunago.us/
6.自分が余命宣告を受けた際に頼れる専門家・支援制度
余命宣告を受けたご本人やご家族は、多くの不安や課題を抱えています。しかし、そのすべてを自分たちだけで解決しようとする必要はありません。
医療や介護、法律などの分野には、頼りになる専門家が存在します。こちらでは、心と生活の支えとなる相談先をご紹介します。
医師・緩和ケアチーム
治療や身体的な痛みのことは、まず担当医や病院内の緩和ケアチームに相談しましょう。緩和ケアは、がんの末期だけのものではありません。診断直後から、心身の苦しさを和らげるために利用できます。
痛みや不安を和らげることは、生きる力を取り戻すことにもつながります。迷ったときは、主治医に相談することが大切です。
カウンセラー・臨床心理士
「家族には話せない」「誰かに気持ちを整理してもらいたい」と感じたら、カウンセラーや臨床心理士に相談するのもおすすめです。病院によっては無料で利用できる相談窓口が設けられています。
専門家に話すことで、「こんなふうに思っていいのか」と自分の本音に気づける方も少なくありません。悩みを抱え込まず、少しでも安心できる場所を持つことが心の支えになります。
行政・NPO・民間企業
身辺整理、葬儀やお墓、相続手続きなど、いわゆる「終活」に関するお悩みは、行政やNPO法人、民間企業に相談することができます。無料の相談窓口を設けていたり、定期的にセミナーを開催したりしているので情報を集めましょう。
「誰に聞けばよいかわからない」という場合は、お住まいの地域の行政サービスを確認してください。また、「終活サポートとは」の記事も参考になります。
7.生きる実例から気づく“今本当に大切なこと”
余命宣告を受けた人たちは、残された時間の中で何を大切にしたのでしょうか。ここでは、実際に余命を受け入れながら人生を歩んだ人たちの姿から、“生きる”ことの意味を考えてみたいと思います。
著名人のドキュメンタリー・書籍から学ぶ
終末期医療の専門家である大津秀一医師の著書『死ぬときに後悔すること25』には、多くの患者が「やりたいことをやらなかった」と後悔していた事実が記されています。
会いたい人に会えなかった、旅行に行かなかった、おいしいものを食べなかった──そんな小さな後悔が、人生の終わりに重くのしかかることもあるのです。大津医師は「限られた時間だからこそ、やりたいことに目を向けることの大切さ」を語っています。
また、流通ジャーナリスト・金子哲雄さんは、自らの余命を受け入れながら最後まで仕事を続けました。病と向き合いながらも日常を大切にし、家族のために準備を整えていく姿は、著書『僕の死に方 エンディングダイアリー500日』に詳しく描かれています。「自分の人生を最後まで生き抜く」という姿勢は、多くの人に生きる力を与えてくれることでしょう。
映画やエッセイ作品からヒントを得る
エッセイや映画に触れることでも、「人生の終わり」に対する考え方が明確になるかもしれません。
映画『エンディングノート』は、がん告知を受けた父親と家族の姿を追ったドキュメンタリーです。段取り好きの父親が、自身の死後のことまで懸命に準備する姿は、切なくも温かい気持ちにさせてくれます。
身近な人や著書、作品から実例を知ることで、あなた自身にとっての「本当に大切なもの」が見つかるはずです。限られた時間の中でも、できることはきっとあります。あなたらしい選択を、大切にしてください。
8.自分が余命宣告を受けた場合に関するQ&A
A.医師が伝える余命は過去の統計に基づいた目安であり、確定した期限ではありません。実際には、告げられた期間より長く生きられる方も多くいらっしゃいます。
余命とは、過去の治療成績や生存率といった医学的なデータをもとに、「現時点で予測できる目安」として示される数字です。がんの場合は「5年相対生存率」という指標が基準になることが多いと言われています。これは、同じ病気を持つ人たちが5年後にどのくらい生きられるかを、同年代の健康な人たちと比較した割合です。
つまり、「5年生きられる確率」を示すものではなく、「一般的な人たちと比べて、どのくらい生存に影響があるか」を見る指標といえるでしょう。
また、余命宣告のとおりの期間で亡くなる方はほとんどいないとも言われています。医学は日々進歩しており、治療法や薬が変われば状況も変わるからです。
さらに、医師は伝える際に「実際より少し短めに余命を伝える」ことが多いとも言われています。これは、もしその期間より長く生きられたときに、希望を感じてもらえるようにという配慮によるものです。
余命はあくまで「目安」であり、「確定した期限」ではありません。宣告された言葉にとらわれすぎず、ご自身の今とこれからの時間を大切にすることを心に留めておくとよいでしょう。
A.重い病気の診断を受けた早い段階から受けることができます。
重い病気と診断されたとき、身体的な痛みだけでなく、不安や落ち込みといった心のつらさも、早い段階から現れることがあります。緩和ケアは、こうした「身体と心の苦しさ」を和らげることを目的とした医療です。治療と同時に受けられる支えであり、「より自分らしく過ごすためのサポート」といえるでしょう。
症状がつらいと感じたときは、「もう我慢できない」と思う前に、主治医や看護師に相談してみてください。「緩和ケアを受けたい」と伝えるだけで大丈夫です。痛みや息苦しさは、我慢する必要のないものです。あなたの生活や心を守るために、早めに声をあげてみましょう。
A.そうとは限りません。ご自宅、病院、介護施設など、ご自身の希望を尊重した場所で過ごすことができるケースがほとんどです。
最期を過ごす場所は「病院」「介護施設」「自宅」などがあり、特別な事情がない限りは自分で選ぶことができます。たとえば「病院より自宅で穏やかに過ごしたい」と思われた場合、自宅療養や在宅緩和ケアという方法があります。医師の往診や訪問看護を受けながら、自宅でも医療的なケアを継続することが可能です。
しかし、余命宣告を受けたときに、病気の症状や認知症などによって自分の意思を伝えられない状態になっていることも考えられます。希望する場所がある場合は、医師やご家族に伝えておくようにしましょう。特に自宅で過ごすことを希望される方は「終末期を在宅で迎えるために」の記事を、ぜひ併せてご覧ください。
A.医療、介護、自治体、民間企業など、サポートしてくれる存在は身近なところに多くあります。まずは将来に備えることから始めましょう。
頼れる近親者が周りにいない「おひとりさま」にとって、余命宣告を受けるということは言葉以上の重みを感じるかもしれません。しかし、余命宣告を受けた方へのサポートは、身近なご家族以外からも受けることができます。以下は、その一部です。
医師/地域包括支援センター/社会福祉協議会/介護施設/弁護士/行政書士/民間の介護サービス/葬儀社 など
金銭や手続きなど、身体的な面以外のサポートは「死後事務委任契約」や「任意後見契約」「介護保険」などの制度を利用することでまかなうこともできます。しかしいずれにしても大切なのは、余命宣告を受ける前に備えておくことです。「おひとりさまの終末期の課題と準備」の記事を参考に、今からできることを始めましょう。
9.余命宣告後に安心して過ごすために、できることから始めましょう
余命宣告は「どう生きるか」を考えるための時間の始まりでもあります。今できることを少しずつ見つけ、自分のために穏やかな時間を積み重ねていくことが大切です。
終活やこれからの準備を進める中で、誰に、何を相談すれば良いのか、戸惑うこともあるかもしれません。そのような時、いつでも気軽に話せる相談窓口があることは、大きな心の支えになります。
もし、「どこから手を付けて良いか分からない」「なるべく負担を軽減しながら、安心して準備を進めたい」とお感じになることがありましたら、花葬儀にご相談ください。花葬儀は終活に関係するさまざまなお悩みをワンストップで相談できる総合窓口です。
ご相談は24時間365日受付の電話、もしくは無料の事前相談をご利用ください。抱えている不安が少しでも解消できるよう、迅速・丁寧に対応させていただきます。