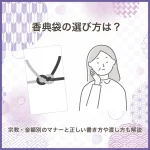葬儀後に行う法要とは?種類・時期・準備・お布施までを解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式のマナー 】

大切な方を見送ったあと、迎えるのが「法要」という次の節目です。初めて施主様を務める方や、法要の手配や準備を一緒に進めるご家族の方の中には、「何を、いつ、どのように行うのか」がわからず、戸惑いを感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、葬儀後に行う法要に関して、種類や実施時期、準備の流れ、お布施の相場までを解説します。初めて法要を迎えるご家族でも安心して進められるよう、丁寧に説明しています。法要の準備を始める際の参考として、ぜひご活用ください。
1.葬儀と法要の違いとは

葬儀と法要は、いずれも故人様をしのぶための大切な儀式ですが、両者には明確な違いがあります。「葬儀」と「法要」の基本的な違いと、「法要」と「法事」の使い分けについても説明します。
葬儀と法要の目的と役割の違い
葬儀と法要の目的と役割には、以下のような明確な違いがあります。
●葬儀
葬儀は、故人様を見送り、現世から旅立つための最初の儀式です。亡くなられた直後に行われ、故人様の安らかな旅立ちを祈ります。
●法要
葬儀の後、節目ごとに行われる追善供養(ついぜんくよう)の儀式です。のこされた者が善い行いをすることで、故人様がより良い世界へ導かれるよう願います。
どちらもご家族やご親族の心の整理に深くかかわる大切な営みですが、葬儀が「お別れの儀式」であるのに対し、法要は「供養を重ねていく時間」といえます。
ただし、浄土真宗では故人様は亡くなるとすぐに仏になる(往生即成仏)とされるため、法要は追善供養ではなく、「故人様を縁として仏様の教えを聞くための大切な機会」と位置づけられています。このように、宗派によって法要の捉え方が異なる場合があることも心に留めておくと良いでしょう。
法要と法事の違い
法要と法事の違いは、以下のように整理できます。
●法要
僧侶による読経など、仏教の作法に基づいた供養の儀式そのものを指します。
●法事
読経などの法要と、その前後に行う会食なども含めた、全体の流れを含む行事の総称です。
供養の儀式が「法要」、それを含む一連の行事が「法事」と定義づけられますが、日常的には区別なく使われているのが現状です。
2.葬儀後に行われる法要の種類
仏教における法要は、大きく「忌日法要」と「年忌法要」の2つに分類されます。ここでは、それぞれの意味と詳しい内容を解説します。
忌日法要
忌日法要とは、故人様のご逝去から四十九日までの間に、七日ごとの節目に営まれる供養のことを指します。また、百日目に行われる供養もこの流れのひとつとされています。
多くの仏教宗派では、亡くなられてから四十九日間、故人様の魂は成仏せずにさまよい、生前の行いについて審判を受けるとされています。この間、ご遺族は七日ごとに読経やお供えを通じて供養を重ね、故人様が無事に極楽浄土へと導かれるよう祈ります。
忌日法要の種類と行われる時期・概要は下の表のとおりです。
| 法要の種類 | 行う時期 (命日から) |
概要 |
|---|---|---|
| 初七日(しょなのか) | 7日目 | 最初に迎える重要な法要。葬儀当日に行うことがほとんど。 多くの場合、省略される。行ってもご家族だけですませる。 |
| 二七日(ふたなのか) | 14日目 | |
| 三七日(みなのか) | 21日目 | |
| 四七日(よなのか) | 28日目 | |
| 五七日(いつなのか) | 35日目 | |
| 六七日(むなのか) | 42日目 | |
| 四十九日 | 49日目 | 最も重要視される法要で、故人様が成仏される節目となる。 |
| 百箇日(ひゃっかにち) | 100日目 | 省略されることが多い。悲しみに区切りをつける法要。 |
年忌法要
年忌法要は、故人様が亡くなられてから1年目以降の祥月命日(しょうつきめいにち)に営まれる仏教の法要です。祥月命日とは、故人様が亡くなられた月日と一致する命日で、毎年その日に供養を行います。
年忌法要の種類と行う時期・概要は下の表のとおりです。
| 法要の種類 | 行う時期 | 概要 |
|---|---|---|
| 一周忌 | 1年後 | 特に大切な節目となる。僧侶による読経に加え、ご親族や親しい友人も参列することが多い。 |
| 三回忌 | 2年後 | 一周忌と同程度か、やや小規模になることも多い。 |
| 七回忌 | 6年後 | この法要から規模が徐々に簡素になる傾向がある。 |
| 十三回忌 | 12年後 | ご家族のみで行うのが一般的。 |
| 十七回忌 | 16年後 | ご家族を中心に行うか、省略する場合も多い。 |
| 二十三回忌 | 22年後 | |
| 二十七回忌 | 26年後後 | |
| 三十三回忌 | 32年後 | この法要をもって、法要を最後にする「弔い上げ(とむらいあげ)」とすることが多い。 |
| 五十回忌 | 49年後 | 「弔い上げ」とする宗派もある。 |
| 百回忌 | 99年後 | 宗派や地域の慣習によっては、百回忌まで営まれることもある。 |
葬儀当日に法要を行うこともある
本来、初七日法要はご逝去から7日目に営むのが正式ですが、現代では葬儀当日に初七日法要を繰り上げて行うケースがほとんどです。
背景には、ご遺族や参列者の負担を減らすための配慮があります。葬儀のあとに再びご親族が集まるのは時間的にも体力的にも大変なことから、葬儀に続けて初七日法要を実施するスタイルが広く受け入れられています。
主に行われるその他の法要
忌日法要や年忌法要のほかにも、故人様やご先祖様への想いを込めて営まれるさまざまな法要があります。主なものをご紹介します。
彼岸法要(彼岸会)
春分の日・秋分の日を中心とした前後1週間のお彼岸の時期に営まれる法要で、「彼岸会(ひがんえ)」とも呼ばれます。私たちが住む「此岸(しがん)」と、悟りの世界である「彼岸(ひがん)」がもっとも近づく時期とされ、故人様やご先祖様の供養を行う大切な機会と位置づけられています。
新盆法要
新盆(にいぼん)は、故人様が亡くなって初めて迎えるお盆に行う法要で「はつぼん」とも呼ばれます。お盆の時期は地域によって異なりますが、8月15日を中心とする期間が一般的です。無縁仏などを供養する「施餓鬼会(せがきえ)」が行われることもあります。
開眼供養・閉眼供養
「開眼供養(かいげんくよう)」は、新たに設けたお墓や位牌、仏壇に魂を入れる儀式です。「閉眼供養(へいげんくよう)」は、それらを整理・処分する際に魂を抜く儀式で、いずれも僧侶にお願いして執り行います。
納骨法要
納骨式とも呼ばれる、故人様の遺骨をお墓に納める際に行う法要です。形式は宗派や地域によって異なるため、事前に菩提(ぼだい)寺や葬儀社などに相談して進めましょう。
3.法要の準備と施主の役割
法要を主催し、取り仕切る立場の方を「施主(せしゅ)」と呼びます。多くの場合、葬儀の代表者である喪主様や、そのご家族が務めます。
施主様は単に法要当日を取り仕切るだけでなく、準備段階から全体を見通して進める立場です。事前に法要の流れを把握し、必要に応じて葬儀社など専門家のサポートを受けましょう。
ここでは、法要の準備を進めるための手順と、それぞれのポイントを解説します。
1.日程・場所の候補を挙げる
僧侶の予定やご親族の都合を確認し、法要の日程と会場の候補を挙げます。法要の会場は、ご家族の意向や参列者の人数、宗派の慣習などによって適切な場所を選ぶことが大切です。
代表的な会場ごとの特徴と手配時の注意点は以下のとおりです。
●自宅
ご家族だけの小規模な法要に適しており、慣れ親しんだ空間で落ち着いて供養ができます。ただし、座席の確保や仏具の準備など、事前の段取りには十分な配慮が必要です。
●菩提寺
宗派に沿った正式な法要が行えるのが大きな利点です。日程の調整や会場の広さに制約があるため、早めの相談が望まれます。
●会館・斎場
椅子席や控室、会食室など設備が充実しているため、ご年配の方や遠方からの参列者にも配慮できます。
2.僧侶への依頼と日程の確定
菩提寺やお付き合いのあるお寺に連絡を入れ、日程と内容を相談します。
連絡の際は次の点を押さえておきましょう。
●連絡のタイミング
遅くとも法要予定日の1か月前には連絡を入れるのが理想です。特にお彼岸やお盆などは寺院側も多忙になるため、早めの連絡が必要です。
●確認すべき内容
希望する法要の種類・日時・場所の希望などを伝えます。
菩提寺がない方は、葬儀をお願いした寺院や葬儀社に相談すると、法要に対応可能な僧侶を紹介してもらえることがあります。また、お布施の準備も施主様の役割です。お布施の詳細については、「お布施の相場と渡し方」で解説いたします。
3.会場を確定し、案内状を送付する
僧侶との日程調整を終えたら、会場を正式に確定します。その後、法要に参列していただきたい方々を選定し、速やかに案内状を送付しましょう。案内状には、法要の種類、日時、場所、会食の有無、返礼品の有無など、必要な情報を漏れなく記載することが大切です。
4.会食(お斎)・返礼品を手配する
案内状の返信が届き、参列者の人数が確定したら、会食と返礼品の手配に移ります。「お斎(おとき)」とも呼ばれる法要後の会食は、故人様をしのびながら、参列者との親交を深める大切な場です。ただし最近は、省略するご家庭も増えています。
実施の判断や準備のポイントを以下に整理しました。
●会食を行うかどうかの判断基準
参列者の人数、予算、衛生面への配慮などから、必ずしも実施しない選択も認められています。省略する場合は、代わりに懐石弁当などを渡すのが一般的です。
●会食の手配方法と準備
仕出し料理を利用する場合、斎場や自宅への配達対応が可能かを確認します。会食を行う場合は、席順や挨拶のタイミングなどを施主様が把握しておくことが重要です。
●宗教的・地域的なマナーへの配慮
お酒の提供可否、精進料理の内容や料理の種類など、宗派や地域によって慣習が異なるため、心配な方は、寺院や年長者に相談して判断します。
返礼品については「法要の返礼品の相場とふさわしい品物」で解説しますので、そちらをご覧ください。
4.法要当日の進行の流れ
法要当日は、宗派によって多少異なる場合もありますが、一般的には以下のような流れで進みます。
1. 受付・参列者の案内
施主様やご遺族は早めに会場入りし、受付や席次の確認を行います。
2. 僧侶による読経・焼香
法要が始まると僧侶が読経を行い、参列者が順にお焼香を行います。読経の内容は宗派や法要の種類によって異なります。
3. 僧侶による法話
読経のあと、僧侶による法話が行われることがあります。静かに耳を傾け、故人様への想いを深めます。
4. 会食・解散
法要後は会食の場が設けられることも多く、故人様をしのびながらご親族や友人が語らいの時間を過ごします。
5.お布施の相場と渡し方
お布施は、読経などを依頼した際に僧侶にお渡しする金銭で、「いくら包むべきか」「どのように渡すべきか」と悩む方も多い部分です。
法要のお布施の目安や渡し方のマナーは以下のとおりです。
●相場の目安
お布施の相場は、法要の種類や宗派、地域によって異なりますが、主な法要である初七日や四十九日、一周忌では 3万円〜5万円程度が目安です。
●渡し方のマナー
市販のお布施袋、または白無地の封筒に「お布施」と表書きし、水引は基本的に不要です。直接手渡しするのではなく、切手盆やふくさにのせて渡します。
法要でのお布施に関しては、「法要のお布施」の記事をご覧ください。法要の種類ごとのお布施の相場や渡し方についても詳しく解説しております。
6.法要の返礼品の相場とふさわしい品物
葬儀と法要では、返礼品の種類や意味、渡し方が異なります。法要の返礼品は、葬儀の香典返しとどう違うのかを解説します。
法要の返礼品は2種類ある
法要では、以下の2つの品物を参列者にお渡しします。
●引き出物
法要の当日に参列された方全員へ渡す、参加していただいたことへの感謝を示すお礼の品です。
●香典返し(お返し)
法要でいただいた金銭(お香典、お供物料など)に対して渡す返礼品です。
参列のお礼として渡す「引き出物」の相場と贈り方
引き出物の相場は、地域や法要の規模にもよりますが、おおむね2千円〜5千円程度が一般的です。持ち帰りやすいように包装し、法要が終了したあとのお見送りの際に手渡しします。
香典返しの相場と贈り方
香典返し・お返しの相場は、いただいた金額の半分程度の半返しが基本です。当日に金額の目安を立てて返礼品を用意し、引き出物と同様に、お見送りの際に手渡しします。高額なお香典をいただいたときは、あとから別に返礼品を郵送しましょう。
法要の返礼品にふさわしい品と避けたいもの
法要の返礼品には、感謝の気持ちを表しつつ、弔事にふさわしい品を選ぶことが大切です。返礼品としてふさわしいものと避けるべき品をご紹介します。
返礼品にふさわしい品物の例
返礼品として選ばれるものには、次のような特徴があります。
●お茶・海苔・和菓子など
お茶や海苔などの軽い品は持ち帰りやすく、賞味期限が長いため、幅広い世代に喜ばれます。
●タオル・洗剤・石けんなど
「使ってなくなる物」は、使い切ることで無駄が出ず、後に物として残らないため、よい兆しをもたらすとされています。
●カタログギフト
贈る側が選ぶ手間を減らせる上に、受け取った方が自由に商品を選べるため、近年では定番の選択肢です。
避けたほうがよい品物の例
一方で、以下のような品物は弔事には不適切とされています。
●肉・魚・果物など
傷みやすい上に、仏教の考えでは「殺生」を連想させるため、法要にはふさわしくありません。
●現金や商品券
受け取る側が負担や気まずさを感じやすく、略式とみなされがちです。地域によっては失礼と受け取られる場合もあります。
●高価なブランド品や食材など
一部の人にだけ高額な返礼品を贈ったり、特別扱いのような贈り物をすると、配慮の不足や誤解が生じる可能性があります。
7.葬儀後の法要を簡素化・省略する場合の考え方
ここまで伝統的な法要の進め方を解説してきましたが、近年はご家庭の事情も多様化しています。高齢化や核家族化などを背景に、「これまで通りの法要を行うのが難しい」と感じる方も少なくありません。
この章では、そうした現代的な視点から、法要を簡素にしたり、省略したりする場合の考え方や、注意すべき点を解説します。
自宅供養・献花など代替手段の選択肢
法要を省略する場合でも、気持ちの整理や故人様への想いを形にするために、以下のような代替手段を検討しましょう。
・命日に合わせて仏壇でお線香を手向ける
・ご自宅に花を飾って静かに手を合わせる
・故人様との思い出の品や写真を眺めながらご家族で語り合う
・故人様の好きだった食事をお供えする
親族との調整・トラブル防止のための注意点
法要を行わない選択は、ご家族の自由ですが、ご親族との意思のすれ違いが起こることもあります。
ご親族とのトラブルに発展しないよう以下の点に注意してください。
・省略する理由(健康・距離・意向など)をあらかじめ丁寧に説明する
・一部のご親族が希望する場合は、個別に供養の機会を設けることも検討する
・「供養の気持ちは大切にしている」という姿勢を伝える
8.葬儀後の法要に関するQ&A
A.ご親族や故人様と関係の深い方には、事前に丁寧な説明をしておくことが大切です。
ご家族だけで葬儀や法要を行う場合、参列を希望していたご親族や友人・知人の方から不満が出ることもあります。トラブルを避けるためには、あらかじめ「家族のみで行う予定です」と、参列を考えそうな方に伝えておくことが重要です。
A.可能であれば、同じ僧侶に依頼するのが望ましいでしょう。
同じ僧侶であれば、宗派やこれまでの供養の内容を把握しており、法要も滞りなく進められることが多いため安心です。ただし、都合が合わず別の僧侶に依頼する場合でも、宗派や葬儀での供養内容を事前に共有しておけば、問題なく執り行うことができます。
A.はい、四十九日法要の服装は、葬儀と同様の喪服とするのが一般的です。
四十九日法要は仏教において重要な節目とされており、多くの場合、ご家族以外にもご親族や関係者が参列するため、格式を保った喪服がふさわしいとされています。
ただし、ご家族のみで執り行う場合や、「平服でお越しください」と案内がある場合には、地味な色の準喪服でも差し支えありません。心配な場合は、事前に案内状の指示やご家族の意向を確認しておくと安心です。
9.法要について正しく理解し、大切な方の供養を丁寧に進めましょう
葬儀後の法要は、故人様の冥福を祈るだけでなく、ご家族やご親族が想いを共有する大切な機会です。仏教の習わしに沿って節目ごとに供養を行うことで、故人様への感謝や別れの気持ちを形にできます。納得のいく法要を行うために、準備や確認を丁寧に進めましょう。
法要の準備に不安がある方や、参列者の選定や日程調整に迷われている方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが、ご家族の事情や宗派に応じて、ご家族らしいご供養の仕方をご提案いたします。