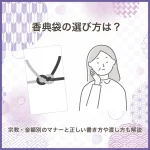友引に葬儀は避けるべき?意味や注意点、現代の考え方も解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式のマナー 】

葬儀の日程を決める際、カレンダーに記された「友引」の文字に、不安や迷いを感じる方も少なくありません。故人を送る大切な儀式だからこそ、友引に葬儀を執り行ってもよいものか、悩むのはもっともなことです。
今回は、友引の葬儀が避けられる理由や葬儀を行う際の注意点、現代における捉え方について解説します。友引の日程で葬儀を検討している方や、葬儀の日取りに迷っている方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
【もくじ】
1.友引とは?意味と由来
「友引」とは何を意味し、どのように広まってきたのでしょうか。歴史的な背景と日本での使われ方を解説します。
友引の起源と定義
「友引(ともびき)」は、日本で広く知られている「六曜(ろくよう)」のひとつです。六曜は「先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口」の6つから構成され、14世紀ごろに中国から日本に伝わったとされています。
六曜のそれぞれには吉凶が割り当てられており、もともとは勝負事や契約ごとなどの日取りを決める際の参考にされていました。友引はもともと「共引」と書かれ、「共に勝つ」「勝負がつかない」と解釈されていました。民間信仰として、「午前・夕方は吉、正午は凶」といった時間帯による吉凶の考え方もあります。
日本での友引の使われ方
六曜は元来中国の暦に由来するものですが、日本では「縁起を担ぐための目安」として広まり、日常生活の中に根づいていきました。特に冠婚葬祭をはじめとする人生の節目では、日取りを決める際に六曜を意識する風習が長く続いています。
友引は、大安に次いで縁起がよいとされ、結婚式や開店日など、前向きな節目の日として選ばれることもありますが、弔事ではしばしば避けられます。
2.宗教的観点から見た友引の葬儀
友引の日の葬儀は、宗教上どのように捉えられているのでしょうか。仏教における六曜の位置づけや、地域や寺院による対応の違いについても説明します。
仏教と六曜は関係がない
結論から言うと、仏教の教えと六曜は関係がありません。先に述べたように、六曜は仏教とは異なるルーツを持つため、仏教の経典や教義にその記述はないのです。そのため仏教では、友引に葬儀をしても支障はないとされます。
実際、多くの寺院では、六曜にとらわれず、友引の日でも問題なく葬儀を受け入れています。六曜を気にして葬儀の日程を決めるのは、あくまで習慣や地域の慣例に基づくものだといえます。
友引に対する仏教寺院の実際の対応
上記のように仏教の教えと六曜に直接的な関係性がないことに加え、各地の寺院の実際の対応を見ても、友引に葬儀を執り行うこと自体が宗教上の問題となるわけではないことがわかります。
たとえば愛知や大阪のように、仏教寺院が数多く集まる地方でも、友引に葬儀が執り行われることは珍しくありません。つまり、仏教との関わりが深い地域においても、六曜の風習が必ずしも優先されているわけではないことがうかがえます。
「友引の葬儀は避けるべき」という慣習はありますが、寺院によっては「仏教の教えとは無関係である」と明示しているところもあります。お世話になっている菩提(ぼだい)寺がある場合は、友引の葬儀についての方針を直接確認されるとよいでしょう。
出典:
名古屋市|名古屋市立第二斎場 名古屋市港区
http://nagoya-city-daini-crematorium.jp/
大阪市|市立斎場のご案内
https://www.city.osaka.lg.jp/kankyo/page/0000369334.html
3.友引に葬儀が避けられる理由
宗教的な根拠がないにもかかわらず、なぜ友引に葬儀を行うことが避けられるのでしょうか。その理由を説明します。
「友引」は縁起が悪いとされる
友引は、「友を引く」という語感から「故人が友人を道連れにする」と連想され、葬儀の日取りとして縁起が悪いと考えられるようになりました。「亡くなった人に引き寄せられて友人が後を追う」といった解釈が広まり、特に告別式や火葬で避ける傾向が強くあります。中には通夜を避ける方もおり、判断基準は地域や個人によって異なるようです。
友引に休業する火葬場が多い

友引に葬儀が避けられるもうひとつの大きな理由は、多くの火葬場が友引を休業日に設定しているからです。利用者が友引を忌避する傾向に配慮した運営方針によるもので、友引の火葬の受け入れ自体が行われていない地域も存在します。
休業する火葬場が多く、葬儀の日程調整が困難になるケースが多い点も、友引に葬儀が行われない一因となっています。友引に火葬場が休業することで、友引の前後に予約が集中してしまい、葬儀の日取りを見直さざるをえない場合も少なくありません。
4.友引に葬儀を行う際の注意点
友引を避ける慣習がある一方で、火葬場の空き状況やご家族の都合などから、友引に葬儀を行わざるを得ない場合もあるでしょう。その際にトラブルを避け、故人を穏やかにお見送りするためには、いくつか押さえておきたい注意点があります。
参列者や親族への配慮
友引の葬儀には、ご親族や参列者に対する十分な配慮が欠かせません。友引を縁起が悪いと考える方も一定数いるため、事前に説明を行い、理解を得る努力をします。特に年長のご親族や、地域の風習を重んじる方に対しては慎重に対応しましょう。
説明する際は、友引と宗教的教義とは関係がないことや、葬儀日程の調整が難しかった事情を丁寧に伝えます。縁起を気にされる方がいる場合は、そのお気持ちを尊重し、友引の日を避けることも一つの選択肢となります。配慮を欠くと、ご親族間のトラブルにつながる可能性があるため注意が必要です。
葬儀社と寺院への事前相談は必須

友引の葬儀の実施では、葬儀社や寺院への事前相談が非常に重要です。葬儀社に相談すれば、過去の事例をもとに、友引に配慮した葬儀の進め方や、適切な段取りを提案してもらうことができます。
菩提寺がある場合は、必ず確認しましょう。檀家に入っている場合、友引に葬儀ができるかは、寺院の考え方によっても変わります。基本的に友引の日程で葬儀をすることに問題はありませんが、日程変更をすすめる寺院もあるため、忘れずに確認することが大切です。
5.現代における友引の葬儀の捉え方
友引に葬儀を行うことに対する考え方は、時代の流れとともに変化しています。現代の友引の葬儀の捉え方をご紹介します。
多様化する葬儀と友引への意識の変化
近年では、家族葬や一日葬など、従来の一般葬にとらわれない多様な葬儀形式が選ばれています。比較的小規模で参列者が限定される葬儀が増える中で、日程の柔軟性に対する要望が高まり、友引を特別に避ける意識が薄れる傾向が見られます。
ご家族の事情を総合して判断
友引にこだわると、火葬場の予約が難航してご家族の負担が大きくなるかもしれませんが、地域やご親族の意向を尊重しなければならないご家族もいます。葬儀をいつにするかは、ご家族ごとの事情を総合的に考慮して判断するようになっています。
6.友引の葬儀に関するQ&A
A.友引の日の葬儀自体が、マナー違反になることはありません。
本来、六曜のひとつである友引は宗教とは無関係であり、友引に葬儀をしても問題はありません。ただし、友引は縁起が悪いと考える方もいるため、ご親族や参列者への説明や気遣いは必要です。
A.「友を引く」という言葉の響きから、「故人が友人をあの世へ連れて行ってしまう」と連想されるようになったのが、最も大きな理由です。
六曜での友引は「勝負がつかない日」とされていますが、日本では「友を引く」という言葉の響きから、亡くなった方に友人や知人が引き寄せられると連想され、葬儀の日取りとして避けられるようになりました。
A.友引の日に、通夜を行っても大丈夫です。
通夜は「前夜に故人をしのぶ儀式」であるため、「友を引く」という意味の影響を受けにくいとされており、多くの地域で通夜のみを友引に行うケースもあります。
地域によっては友引を避ける慣習が残っている場合があるため、事前にご親族や関係者と相談して準備を進めましょう。
A.友引に葬儀をする際は、参列者に説明し、葬儀社へ相談することが大切です。
参列者の中には友引を気にされる方もいるため、葬儀の日程を友引に設定した理由を丁寧に伝えます。また、地域によっては友引に火葬場が休業している場合もあるため、必ず葬儀社に相談し、火葬場の利用状況を確認します。
7.友引に葬儀を行うかはご親族や参列者へ配慮して判断しましょう
友引の日に葬儀を行うかどうかは、一概に「良い」「悪い」で判断できるものではありません。六曜の考え方には地域差や世代差もあり、参列者やご親族によって受け止め方が大きく異なることがあります。
大切なのは、友引の葬儀について正しく理解したうえで、ご家族、ご親族、参列者へ配慮して判断することです。
縁起を気にされる方がいる場合は、そのお気持ちを尊重し、友引の日を避けることも一つの選択肢となります。仮に友引の日を選ばざるを得ない場合は、あらかじめ事情を丁寧に説明し、納得と安心を得られるよう心がけましょう。火葬場の休業日や寺院の対応も確認しながら、無理のない日程を選ぶことも重要です。
友引の日の葬儀に不安を感じている、また、葬儀の日程調整で迷っている方は、ぜひ花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが、安心して葬儀を進められるよう丁寧にお手伝いいたします。