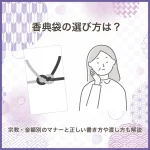浄土真宗の葬儀とは?宗派ごとの流れと考え方・マナーをわかりやすく解説
- 作成日:
- 【 葬儀・葬式のマナー 】

浄土真宗の葬儀は、流れや儀式に込められた意味合いが他宗派と異なることをご存じでしょうか?なじみのない方にとっては、葬儀を執り行ったり、参列したりすることに大きな不安を感じるかもしれません。
この記事では、「浄土真宗とは何か」といった基本から、葬儀の流れ、言葉遣いやマナー、よくある質問までを丁寧に解説します。安心して故人様を見送るための基本的な情報が詰まっていますので、ぜひ最後までご覧ください。
1.浄土真宗とは

葬儀の話をする前に、まずは「浄土真宗とは何か?」「代表的な宗派は?」という基本的な事項から解説します。
浄土真宗の基本と死生観
浄土真宗は、鎌倉時代に親鸞(しんらん)という僧侶によって開かれた仏教の一派です。阿弥陀如来(あみだにょらい)を信仰し、「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」の念仏を唱えれば、死後誰でも極楽浄土に行ける “他力本願(※1)”の死生観を持っています。自力の修行を重ねる他宗派とは異なり、阿弥陀如来の救いに身を委ねる点が特徴です。
他宗派の死生観や教義も押さえることで、浄土真宗との違いがより理解できるようになるでしょう。ぜひ「仏教の死生観」の記事も併せてご覧ください。
(※1)広く浸透している「他人まかせ」という意味ではなく、全ての人を救いたいという阿弥陀如来の願い(本願)によるはたらきを指す。
代表的な宗派
浄土真宗には10以上の宗派がありますが、中でも特に信者数の多いのが、「本願寺派(西本願寺)」と「真宗大谷派(東本願寺)」です。これらは親鸞の教えを受け継ぐ主要な宗派で、葬儀の進行や作法、読経の節回しなどに微妙な違いがあります。例えば本願寺派は「なんまんだーぶ」と読経の節回しが高音域であるのに対し、大谷派は「なんまんだぶ」と低めの調子で唱えるのが特徴です。
この記事では、本願寺派と真宗大谷派それぞれの葬儀の流れについて詳しく解説します。
2.浄土真宗の葬儀の考え方
多くの人にとって葬儀とは、「故人様を供養する場」というイメージが強いかもしれません。しかし浄土真宗では、そのような目的とは異なる考え方が根本にあります。
ここでは、他宗派との違いとともに、浄土真宗ならではの葬儀観をご紹介します。
故人を“供養”しない?葬儀の捉え方
仏教の多くの宗派では、死者が迷いの世界を経て仏になるとされ、その過程を助けるために追善供養(※2)が行われます。故人様のために読経や焼香が行われ、安らかに旅立てるよう祈りを捧げるのが基本です。
これに対し浄土真宗では、人は死後すぐに仏になるとする考えを重視します。そのため、葬儀は故人様の霊を鎮めたり、冥福(めいふく)を祈ったりする目的では営まれません。“供養”という発想自体が存在しないのです。
(※2)法要(法事)、読経、墓参りなど故人様の冥福を願う行為のこと。追善供養として行った善行が、故人様の徳につながると考えられている。
浄土真宗の葬儀は「聞法の場」
浄土真宗の葬儀が持つ本質的な意味合いは、「聞法(もんぼう)の場」にあります。「聞法」とは、仏法を聞いて理解しようとする姿勢のことです。
「南無阿弥陀仏」を唱えることで救われると説く浄土真宗においては、念仏の意義を深く知るためにも、この「聞法」が大切にされています。そのため葬儀の中には法話の時間が設けられ、参列者は故人様を見送ると同時に、阿弥陀如来の教えを聞き、仏法にふれる貴重な機会を得ることができます。
故人様の死をきっかけに、参列者一人ひとりが「生と死」や「念仏の教え」と真摯に向き合う場──それが、浄土真宗における葬儀の大切な役割なのです。
3.【宗派別】浄土真宗による葬儀までの流れ
浄土真宗の葬儀は、宗派によって進行に違いが見られます。その独自性をより深く理解するために、まずは比較の基準となる一般的な仏式の葬儀の流れを確認しておきましょう。
他宗派で見られる一般的な例も踏まえながら、それぞれの流れを説明します。
一般的な仏教の場合
仏教の多くの宗派の葬儀は、主に以下の流れに沿って執り行われます。なお、通夜を省略する「一日葬」や、火葬のみを行う「直葬」など、形式によっては異なる点もありますが、ここでは従来のスタイルである一般葬を例にご紹介します。
1.納棺
故人様のお体を棺に納める儀式。「湯かん」「死装束へのお着替え」「ラストメイク(死化粧)」などを行った後、お体と副葬品を棺に納めます。
2.通夜
故人様と最後の夜を過ごしながら別れを惜しむ儀式。参列者が集まり、僧侶による読経、焼香などが行われます。通夜後、参列者には「通夜振る舞い」という会食の席が設けられるのが一般的です。夜通し故人様のそばに寄り添うのが慣例でしたが、近年は1~2時間ほどで終了する「半通夜」が増えています。
3.葬儀
故人様の冥福を祈る宗教的な儀式。僧侶による読経、焼香、弔辞読み上げなどが行われます。
4.告別式
故人様とお別れする社会的な儀式。棺の中に花などを納め、火葬場へと出棺します。葬儀と続けて行われることが一般的です。
葬儀の流れについて詳しくは「死亡から葬儀・その後の手続きまでの流れ」の記事でまとめておりますので、そちらもぜひご覧ください。
ご説明した一般的な流れを踏まえた上で、浄土真宗の葬儀がどのように進むのか、流れを次項から見てみましょう。
浄土真宗の場合【通夜までの流れ】
浄土真宗では、阿弥陀如来を本尊とする教義に沿い、葬儀全体は「仏法に出会うための場」として位置づけられています。
こちらでは、逝去から通夜までの流れをご紹介します。
逝去後~臨終勤行
亡くなった方のお身体を整え、導師(僧侶)を招いて「臨終勤行(りんじゅうごんぎょう)」を行います。臨終勤行とは読経のことを指しますが、他宗派と違い、故人様の冥福を祈るのではなく、阿弥陀如来の導きに感謝を捧げるのが特徴です。
納棺
故人様のお召し物を変え、棺に納めます。多くの宗派では死出の旅に出るための死装束に着替えるのが原則ですが、浄土真宗ではすでに極楽浄土に往生していると考えるためつけません。故人様にとって思い入れのある服を選ぶのが一般的です。
通夜
亡くなった当日に近親者のみで行う「仮通夜」と、翌日に一般の弔問客を迎える「本通夜」があります。近年は、ご逝去後すぐに病院の霊安室などへ移送される事情もあり、仮通夜は省略されることが増えました。
導師による「阿弥陀如来に対する」読経以外は、法話、焼香、通夜振る舞いなど、他宗派の通夜と大きな違いはありません。
浄土真宗の場合【葬儀・告別式の流れ】
浄土真宗の葬儀において、宗派による最も大きな違いが現れるのが葬儀・告別式です。ここでは本願寺派と真宗大谷派、それぞれの儀式の流れを詳しく見ていきましょう。
本願寺派(西本願寺)
本願寺派の葬儀は「出棺勤行(しゅっかんごんぎょう)」と「葬場勤行(そうじょうごんぎょう)」の2つに大きく分けて行われます。
【出棺勤行】
故人様が住み慣れた自家を離れ、葬儀場に向かう前に行うお別れの勤行。お経のひとつである「帰三宝偈(きさんぼうげ)」「短念仏(たんねんぶつ)」を唱えます。なお、近年では葬儀場で「葬場勤行」と合わせて行うケースが増えています。
【葬場勤行】
葬儀場で行う儀式の一般的な流れは以下の通りです。
1.導師入場
2.開式のことば
3.三奉請(さんぶじょう:仏様を迎えるための詩)
4.導師焼香、表白(ひょうびゃく:葬儀の趣旨をつづった文章の読み上げ)
5.正信偈(しょうしんげ:親鸞が書き残したとされる詩の読み上げ)
6.念仏(南無阿弥陀仏を唱える)
7.和賛(わさん:仏様の徳や教えをたたえる歌の読み上げ)
8.回向(回向文の読み上げ)
9.導師退場
10.閉式のことば
11.喪主挨拶
12.出棺
真宗大谷派(東本願寺)
次は、真宗大谷派による葬儀の一般的な流れをご紹介します。真宗大谷派による葬儀は、「葬儀式第一」「葬儀式第二」の2部構成である点が特徴です。
【葬儀式第一】
葬儀式第一は自宅で行う「棺前勤行(かんぜんごんぎょう)」と葬儀場で行う「葬場勤行」に分かれています。一般的な流れは以下の通りです。
(棺前勤行)
1.導師入場
2.総礼(そうらい:参列者全員で礼をする)
3.勧衆偈 (かんしゅうげ:中国の仏書にあるお経を唱える)
4.短念仏十遍(短い念仏を10回唱える)
5.回向
6.総礼
7.三匝鈴(さぞうれい:小さな鈴から大きな鈴へと順番に鳴らす)
8.路念仏(じねんぶつ:南無阿弥陀仏を含んだ念仏を唱える)
(葬場勤行)
1.三匝鈴
2.路念仏
3.導師焼香・表白
4.三匝鈴
5.路念仏
6.弔辞
7.正信偈
8.和讃
9.回向
10.総礼
なお、近年は棺前勤行を自宅ではなく、葬場勤行とまとめて葬儀場で行うケースが主流です。
【葬儀式第二】
1.導師入場
2.総礼
3.伽陀(かだ:仏様を迎えるための詩の読み上げ)
4.勧衆偈
5.短念仏十遍
6.回向
7.総礼
8.三匝鈴
9.路念仏
10.三匝鈴
11.導師焼香・表白
12.三匝鈴
13.正信偈
14.短念仏
15.三重念仏(さんじゅうねんぶつ:法然が説いたとされる3つの念仏を唱える)
16.和賛
17.回向
18.総礼
4.浄土真宗の葬儀における言葉遣い
葬儀の場では、故人様やご遺族への敬意や弔意を示すために言葉選びが非常に重要です。とりわけ、浄土真宗では教義にそぐわない表現を避ける必要があります。
ここでは、一般的には使用されるものの浄土真宗では適さない表現や、代わりに用いるべき言い回しについて解説します。
浄土真宗の葬儀で避けるべき表現
故人様は亡くなったその瞬間に仏と成るという考えがある浄土真宗では、「冥福を祈る」などの表現は使用しません。「冥福」には「冥土」という、魂が転生するまでの間に過ごす世界を指す言葉が含まれているためです。以下のような言い回しは避けましょう。
・「ご冥福をお祈りします」
・「冥途へ旅立つ」
・「草葉の陰から見守っていることでしょう」
・「成仏されることを願っています」
これらはいずれも「迷いや未練のある霊魂やあの世の存在」を前提としており、「すでに仏となっている」と考える浄土真宗の思想とは根本的に矛盾しているので注意が必要です。
浄土真宗の葬儀で実際に使える言葉
では、どのような言葉が浄土真宗の教義に配慮した適切な表現なのでしょうか。悲しみに寄り添いつつも宗派の思想を尊重した言い回しとして、以下のような例が挙げられます。
・「謹んで哀悼の意を表します」
・「残念でなりません」
・「心よりお悔やみ申し上げます」
・「阿弥陀如来のご加護のもと、安らかにお休みください」
宗教的な言及を避けたい場合は、「ご家族のお気持ちが少しでも癒やされますよう、お祈りしております」といった中立的な表現がおすすめです。
5.浄土真宗の葬儀や流れに関するQ&A
A.「御仏前」と書きましょう。
お香典の表書きには「御霊前」「御仏前」などいくつかあります。一般的には四十九日前までにお渡しするものを「御霊前」、四十九日以降を「御仏前」とするルールがありますが、浄土真宗の場合、故人様は亡くなった直後に仏と成るという教義があるため、四十九日前であっても「御仏前」と記載するのが正解です。
A.本願寺派は1回、真宗大谷派は2回焼香を行う違いがあります。
焼香の作法として一般的に知られているのは、「3本の指で香をつまみ、額近くに持っていき(“おしいただく”と言います)、香炉に落とす」ですが、浄土真宗では額近くに持っていくことはしません。また、本願寺派と真宗大谷派では焼香の回数に違いがあるのが特徴です。それぞれの作法は以下を参考になさってください。
【本願寺派】
香をつまむ→香炉に落とす→合掌→「南無阿弥陀仏」と唱える→一礼
【真宗大谷派】
香をつまむ→香炉に落とす→香をつまむ→香炉に落とす→合掌→「南無阿弥陀仏」と唱える→一礼
A.戒名の代わりに「法名」、位牌の代わりに「法名軸」などを用意します。
戒名とは、仏様の弟子になった証として授かる「あの世での名前」です。本来は生きている間にいただくものですが、死後に授かることの方が多いかもしれません。
一方、浄土真宗では戒名ではなく「法名(ほうみょう)」を授かります。また位牌ではなく、故人様の死亡年月日や法名が記載された法名軸(掛け軸)を用意するのが通例です。ただし全ての浄土真宗の宗派が位牌を用いないわけではないため、詳細は寺院やご家族に確認することをおすすめします。
A.必ずしも必要ではないため、無理に用意することはありません。
仏式の葬儀では数珠を持参するのがマナーとされていますが、神道やキリスト教など、他の宗教を信仰している方が参列するケースもあります。そのような場合は無理に用意する必要はないためご安心ください。ただし、「他の人から借りる」のはマナー違反となるため注意しましょう。
数珠には正式な形として二輪のものが存在しますが、略式の一連でも問題はありません。「お葬式に数珠は絶対に必要?」で、より詳細を解説しておりますので、そちらもあわせてご覧ください。
A.伝統的には菊などが用いられてきましたが、近年はお好みの花を飾る傾向にあります。
浄土真宗に限らず、仏教には「好まれる花」があります。邪気をはらうとされている菊や、ランなどの和花、やさしい色合いが特徴のカーネーションが代表的です。反対に、毒やトゲを持つ花、香りや色味の強い花は避けられる傾向にありました。
しかしこれらは、絶対的な決まりではありません。近年は宗派の考えを大切にしつつも、柔軟に花を選ぶ方が増えています。例えばヒマワリやアジサイ、バラなど、故人様にとって思い入れの深い花、または故人様らしさを表現できる花などです。
そのような花を選ぶことで、故人様をより身近に感じられるあたたかいお見送りができるようになるでしょう。参考として「花祭壇で故人様のお人柄を表現」をご覧ください。
6.浄土真宗の教えを理解して、心穏やかな葬儀を
浄土真宗の葬儀は「死後すぐに極楽浄土に行く」という教義を前提に、「故人様の供養」ではなく「阿弥陀如来の教えを聞く場」として営まれます。
宗派によって葬儀の流れや作法には違いがあるものの、共通して「聞法」の意義を大切にしている点が特徴です。浄土真宗が重要視している教えを理解することで、大切な人を落ち着いた心でお見送りすることができるでしょう。
花葬儀は、宗派によって異なる浄土真宗の葬儀にも柔軟に対応できる葬儀会社です。経験豊富なスタッフが、故人様やご遺族の想いを大切にしたお見送りをサポートさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。ご相談は24時間365日受付の電話、もしくは無料の事前相談がおすすめです。