骨葬とは?選ばれる理由やメリット・デメリット、実例を解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】
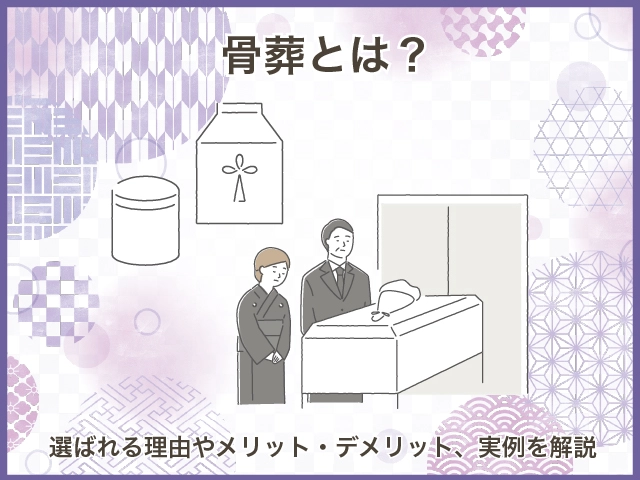
「火葬は、葬儀や告別式の後に行うもの」と考えている方が多いかもしれません。しかし、火葬を先に行い、その後に遺骨を安置して葬儀を執り行う「骨葬(こつそう)」と呼ばれる葬儀があるのをご存知でしょうか。
今回は、骨葬の詳しい意味や選ばれる理由、注意点などを解説します。具体的な実例もご紹介しますので、骨葬を検討している方や、骨葬に関心のある方は、ぜひこの記事を参考になさってください。
【もくじ】
1.骨葬とは?意味と特徴

骨葬とは、葬儀・告別式に先立って火葬を行う葬儀形式で、「前火葬(まえかそう)」とも言います。一般的な葬儀(後火葬)は、葬儀・告別式の後に火葬場へ向かいますが、骨葬は逆で、火葬後に遺骨を祭壇に安置し、参列者は遺骨を前に故人様をしのびます。
葬儀当日の儀式の流れは、棺の代わりに祭壇へご遺骨を安置する点を除けば、一般的な葬儀と大きくは変わりません。僧侶による読経や参列者のお焼香といった儀式は、通常通り執り行われます。
2.骨葬が選ばれる理由とは?
火葬をしてから葬儀を行う骨葬は、どのような理由で選ばれるのでしょうか。主な理由を解説します。
地域の風習として根付いている場合
骨葬は、地域の風習として選ばれることがあります。たとえば、地域特有のさまざまな理由でご親族が集まるのに時間がかかり、葬儀が遅れることが多かった地域では、お身体の長期にわたる安置が難しい状況であったため、骨葬が定着し、現在も風習として根付いています。
骨葬の風習が見られる具体的な地域については、後段の「地域別の骨葬の実例」で詳しく紹介します。
お身体の保存が難しい場合
骨葬は、お身体の保存が難しい状況で選ばれることもあります。高温多湿な環境や、保存設備が整っていない場合、火葬を先に行うことで、安心して葬儀を行うことが可能です。夏季など気温が高い時期にも、ご遺族の心のご負担を軽くすることができるでしょう。
遠方で亡くなられた場合
遠方でご家族が亡くなられた場合、骨葬はご遺族の心身の負担を軽くすることにつながります。たとえば海外で亡くなったような場合、お身体をそのまま搬送するには高額な費用と手続きが必要になるため、現地で火葬を行い、遺骨を持ち帰り葬儀を行うのが一般的です。
国内でも、遠方で亡くなった場合は、やはり搬送が困難であるため、骨葬が選択されることがあります。
お身体の状態が著しく損なわれた場合
事故や災害による外傷や孤独死による発見の遅れなどで、お身体の状態が著しく損なわれた場合も、骨葬が適しています。故人様の尊厳を守りながら、ご家族が心の負担を感じることなく、遺骨を前に穏やかにお別れの時間を過ごしていただくことが可能です。
大規模な葬儀を計画する場合
著名な方などが逝去した場合、多くの関係者への連絡や会場手配に時間がかかります。お身体を安置したままで大規模な葬儀を準備するのは難しいため、まずご親族のみで葬儀を行い、火葬を済ませた後に「本葬」として骨葬を執り行う形式が選ばれます。
3.骨葬をスムーズに行うためのポイント
骨葬を円滑に進行するには、事前準備が欠かせません。スムーズに進めるためのポイントを解説します。
火葬場の早期予約を行う
骨葬は火葬を先に行うため、火葬場の予約を早めにすることが重要です。特に、お盆、年末年始、連休は予約が取りにくくなるため、日程が決まり次第、すぐに火葬場を確保します。
遺骨の保管場所の確保
火葬後の遺骨は、葬儀までの安置場所を確保しておくことが大切です。自宅で安置する場合は、湿気や直射日光を避け、風通しがよい場所を用意しましょう。また、自宅での安置が難しい場合には、葬儀社を通じて一時保管先を紹介してもらうことも可能です。
参列者への事前説明
骨葬は、一般的な葬儀とは異なるため、参列者が戸惑われたり、誤解されたりする可能性があります。葬儀の案内状や事前の連絡で「火葬を先に済ませているため、当日は遺骨を前にした葬儀になります」と丁寧に伝えることが必須です。
供養方法を決めておく
「どこに納骨するべきか」でご家族間の意見が分かれ、トラブルにならないために、遺骨の供養方法を決めておきましょう。
供養方法の選択肢としては、以下があります。
・寺院や霊園のお墓、納骨堂への納骨
菩提(ぼだい)寺や霊園に構えるお墓は、代々受け継いでいくことも、新しく建てることもできる供養の形です。近年では天候に左右されない屋内型の納骨堂を選ばれる方も増えています。
・自然散骨(海洋散骨・樹木葬)
故人様が自然志向の供養を希望される場合、海洋散骨や樹木葬という選択肢もあります。
・分骨して複数の場所で供養
ご家族が複数の地域にいる場合、分骨してそれぞれで供養することも可能です。
・自宅での手元供養
ご家族がいつでも故人様をしのべるよう、ご自宅で遺骨を保管します。
4.骨葬のメリット
骨葬には、一般的な葬儀にはない、火葬を先にするからこそのメリットがあります。
日程調整が柔軟にできる
火葬を先に行うことで、葬儀の日程を参列者の都合に合わせて柔軟に調整することができます。参列者が集まりやすい日に葬儀を行うことも可能になるため、より大勢の方と共に故人様をしのぶことができるでしょう。
安置場所に関する負担が軽減される
火葬後はご遺骨の状態でご安置するため、場所の確保について悩むことが少なくなります。ご自宅のスペースや季節などに左右されることなく、安心して故人様をお見送りできるでしょう。
遠方からの搬送が円滑になる
遠方や海外で逝去した場合、現地で火葬し、遺骨を持ち帰って葬儀を行うことで、お身体を搬送する費用や手続きの負担が軽減されます。特に、国際線でのお身体の搬送は手続きが複雑ですが、遺骨であればより円滑に通関手続きを行うことができます。
会場の選択肢が広がる
大規模な葬儀やお別れの会を計画する際、会場選びの自由度が高まります。ホテルや貸しホールなど、お身体を安置できない場所でも、遺骨であれば持ち込みが可能な場合もあります。
ただし、施設ごとにご遺骨の扱いやお焼香の可否は異なりますので、ご希望の場所でのお見送りを検討される際は、必ず事前に確認することが重要です。
5.ご家族が納得して骨葬を選ぶための注意点
骨葬にはメリットがある一方で、その特性を十分に理解せずに進めると、後悔に繋がる可能性もございます。ご家族や関係者の皆様が心から納得できるお見送りにするために、特に大切な注意点を解説します。
故人の顔を見てお別れができない
葬儀時には遺骨しかないため、参列者は故人様の顔を見てお別れすることができません。直接顔を見て故人様に別れを告げる機会がなくなるため、ご家族や親しい友人にとっては寂しさを感じることがあります。
この点については、ご家族で事前によく話し合うことが不可欠です。火葬前に近親者のみで「お別れの儀」の時間を設け、故人様と過ごす時間を作るといった方法もございます。
参列者への丁寧な事前説明を心がける
骨葬が一般的でない地域では、参列者が慣れない葬儀形式に戸惑うことがあります。棺がなく、遺骨のみを祭壇に安置していることに驚かれる場合もあるでしょう。
皆様に心穏やかにお参りいただくため、案内状には「誠に勝手ながら諸事情により、火葬を済ませたうえで、遺骨にて葬儀を執り行います」といった一文を加え、事前に葬儀の形式をお伝えしておきましょう。
宗教・宗派による骨葬の可否を確認
宗教や宗派によっては、故人様のお身体を前にして儀式を執り行うことを非常に重視するため、骨葬が伝統的な教えにそぐわないとされることがあります。お身体を前にした祈りを通じて、故人様の魂が安らかに導かれると考えるためです。
骨葬を検討される際は、後々のトラブルを避けるためにも、必ず事前に菩提(ぼだい)寺や所属する教会などへご相談されることをおすすめします。
葬儀社に骨葬対応を相談
骨葬は、すべての葬儀社が対応できるわけではありません。葬儀社へ「骨葬に対応しているか」を質問し、骨葬のプランや費用を確認します。ご家族の希望によっては、無宗教形式にできるか、宗教者の手配が可能かなども確認しておくと安心です。
6.地域別の骨葬の実例
最後に、骨葬が特にどのような地域で定着しているのかをご紹介します。ここでは、具体的な地域の実例をいくつかご紹介しましょう。
東北地方の骨葬の実例
東北地方では、青森県をはじめとした一部地域で骨葬が行われています。その由来の一つとして、初代津軽藩主・津軽為信(つがるためのぶ)公の逸話が挙げられます。
為信公は遠征先の京都で亡くなった際、お身体が傷むのを防ぐために現地で火葬されました。その後、遺骨として故郷の津軽へ戻り、改めて葬儀が執り行われたと伝えられています。
また、気候が厳しく葬儀の際にご親族が集まりにくいことや、農業や漁業の繁忙期を避けて葬儀を行うため、火葬を先に済ませて遺骨で葬儀を行う形式が定着したと考えられます。
九州地方の骨葬の実例
九州地方でも、骨葬の風習が見られます。熊本県の天草市や阿蘇市などでは、火葬を先に済ませて遺骨で葬儀を行う形式が、一部地域で受け継がれています。ご親族が集まるまでに時間がかかるため、お身体を安心して安置できる状態にする目的で、骨葬が根付いたとされています。
大分県の佐伯市周辺の沿岸部でも、漁業の関係でご親族がすぐに集まることができないことから、骨葬の風習が残っている地域があります。
その他地域での骨葬事例
北海道の函館市や釧路市、根室市などの漁師町でも、骨葬の風習が見られます。背景は諸説ありますが、海難事故が多かったことや、衛生面やご遺族の負担を考慮して、火葬を優先したとする説が有力です。
また、こうした伝統的な事例とは別に、近年では都市部でも骨葬が行われるようになりました。たとえば都市部で亡くなった方の故郷が遠方にある場合、先に火葬だけを行い、後日地元で骨葬を行うケースも見られます。
7.骨葬に関するQ&A
A.骨葬は、ご家族や近親者のみでの家族葬として行うことも可能です。
骨葬を家族葬として行えば、故人様の希望やご家族の意向を尊重したシンプルな葬儀も実現できます。参列いただかなかった方のために、後日「お別れの会」や「しのぶ会」を開き、故人様を悼む場を設けることも選択肢の一つです。
A.火葬をしてから骨葬を行うまでの期間に、特別な決まりはありません。
一般的に火葬後、1週間以内に葬儀を行うことが多いですが、ご親族や参列者の都合に合わせて日程を調整してかまいません。ただし、火葬から葬儀までの期間が長い場合は、遺骨を清潔で湿度管理が可能な場所で保管することが必要です。
A.骨葬では棺を安置しないため、祭壇も一般的な葬儀とは異なります。
一般的な葬儀では棺を中心に祭壇が組まれることが多いですが、骨葬の場合は棺ではなく、遺骨を安置します。遺骨の周囲に遺影や花を飾る形が多いようです。なお、祭壇の規模や装飾はご遺族の希望や宗教によって異なります。
8.骨葬の注意点を理解して後悔しない選択をしましょう
骨葬を選ぶ際は、メリットやデメリット、注意点をしっかり把握し、ご家族全員で十分に意見を共有することが重要です。各自の価値観を尊重しながら進めることで、全員が納得できる葬儀の形を実現できます。
骨葬を検討している方や、骨葬に不安のある方は、花葬儀の事前相談までご連絡ください。経験豊富なスタッフが、無宗教形式から宗教儀式の手配、参列者への案内方法まで、事前相談でご不安を解消いたします。




























