仏式と神式の違いとは?儀式・作法・費用の特徴を丁寧に解説
- 作成日: 更新日:
- 【 葬儀・葬式の基礎知識 】

日本の葬儀では、仏式と神式が多くの方に選ばれています。どちらも宗教の教義に沿って執り行われますが、「どう違うのか」がいまいちわからない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、葬儀における仏式と神式それぞれの背景や儀式の流れ、参列マナーや費用の違いまで、丁寧に解説します。宗教葬を考えている方、これから仏式または神式の準備を進める方は、ぜひ最後までご覧ください。
1.仏式と神式、まずは基本の違いを押さえよう

まずは、仏式と神式の葬儀が、それぞれどのような宗教観を基にしているのかを解説します。
仏式の特徴とは|冥福を祈る仏教の教え
仏式の葬儀(仏教葬)は、日本で最も広く行われている宗教葬です。
仏教の多くの宗派において、「死」は終わりではなく、新たな生の始まりとされ、魂はあの世での長い旅路を経て輪廻転生(※1)すると考えられています。そのため仏式では、故人様が極楽浄土へ旅立てるよう、冥福(めいふく)を祈る儀式が中心となります。
なお、同じ仏教でも浄土真宗では「人は亡くなると、すぐに仏になる」と考えるため、冥福を祈ったり、魂の旅路を見送ったりする概念がありません。この記事では、多くの宗派で共通する一般的な仏式の考え方を中心に解説を進めます。
(※1)りんねてんせい:命あるものが死と再生を繰り返すという考え方。
神式の特徴とは|祖霊となって祀(まつ)られる神道の考え方
神式の葬儀(神葬祭/しんそうさい)は、日本古来の宗教である神道に基づく宗教葬です。神道では、故人様の魂は死後も現世に留まり続け、家の守護神となると考えられています。
また、神道では死を「穢(けが)れ」としており、葬儀では「故人様に対する感謝」や「死による穢れをはらう」といった概念が大切にされます。ここで言う穢れとは、生命エネルギーが著しく低下した忌むべき状態のことです。
それぞれの基本的な特徴をまとめると、以下の通りです。
| 仏式 | 神式 | |
|---|---|---|
| 宗教 | 仏教 | 神道 |
| 死生観 | 死後の魂は極楽浄土に旅立ち、やがて輪廻転生する | 死後の魂は現世に留まり、家の守護神となる |
| 葬儀の目的 | 極楽浄土に行けるよう、冥福を祈る | 故人様への感謝と、死による穢れをはらう |
※仏式の死生観や葬儀の目的は、浄土真宗など一部の宗派を除く一般的な仏教の考え
2.【仏式と神式】儀式の流れの違い

仏式と神式は、通夜から火葬までの流れにも大きな違いがあり、前項で述べた宗教観の違いが儀式の進め方や名称にも反映されています。
こちらでは、それぞれの儀式の流れと意味を解説します。
仏式の流れ──通夜・葬儀・告別式・火葬
仏式の儀式は、一般的に以下のような流れで行われます。
- 1.通夜(つや)
- 2.葬儀(そうぎ)
- 3.告別式(こくべつしき)
- 4.火葬(かそう)
- 5.骨上げ・精進落とし
通夜
「通夜」とは故人様との最後の夜を過ごす儀式です。もともとは、灯りを絶やさず一晩中故人様を見守る形式が一般的でしたが、近年は日付が変わる前に終わる「半通夜」が増えています。僧侶による読経、法話、焼香、喪主様挨拶の後に、通夜振る舞い(※2)の流れが主流です。
具体的な通夜の過ごし方やご遺族が行う準備については「お通夜の過ごし方」の記事をご覧ください。
(※2)故人様の供養ならびに参列者への感謝を込め、喪主様から参列者に振る舞う飲食。
葬儀
通夜の翌日に行うのが葬儀です。葬儀では、故人様の冥福を祈るための読経、焼香などの宗教儀式が行われます。
告別式
告別式は、故人様にお別れを告げる社会的儀式です。葬儀と意味は異なるものの、葬儀・告別式と続けて行われるのが一般的です。告別式では、参列者による弔辞、棺への花入れ、出棺などが行われます。
火葬・骨上げ・精進落とし
火葬場に移動して故人様を火葬し、その後ご遺骨を骨壺に納める「骨上げ」の儀式を執り行います。火葬後には、参列者や僧侶をねぎらう「精進落とし」という会食の席が設けられますが、地域によっては火葬中に行うこともあります。
神式の流れ──通夜祭・葬場祭・火葬祭など
神式では、仏式と異なる呼び名で儀式が進行します。一般的な流れは次の通りです。
- 1.通夜祭(つやさい)・遷霊祭(せんれいさい)
- 2.葬場祭(そうじょうさい)
- 3.火葬祭(かそうさい)
通夜祭・遷霊祭
通夜祭・遷霊祭は、仏式の通夜にあたる儀式です。それぞれ別の儀式ですが、同じ日取りで行われることが増えています。通夜祭では神職によるおはらいが、遷霊祭では故人様の霊を霊璽(れいじ:仏式でいう位牌)に移す儀式がそれぞれ行われます。
葬場祭
葬場祭は、仏式でいうところの葬儀・告別式です。神職によるおはらいの後、故人様がご遺族の守り神になるための儀式を行います。
火葬祭

火葬直前に行う儀式が「火葬祭」です。神職が祭詞を読み上げ、参列者は玉串(たまぐし)と呼ばれる榊(さかき)の枝に紙垂(しで)をつけたものを捧げます。火葬後すぐにご遺骨をお墓に埋葬するのが本来の流れですが、近年は一度自宅に持ち帰り、忌明け後に埋葬するのが一般的です。
神式の葬儀一連で行う儀式の名称や意味は、「神式の葬儀の特徴や基本的な流れ」で詳しく解説しておりますので、そちらも併せてご覧ください。
3.【仏式と神式】祈りの形の違い

葬儀の流れを見てきたなかで、それぞれの儀式における“祈りの形”にも違いがあることがわかります。
ここでは、仏式の読経・焼香と、神式の祭詞奏上(さいしほうじょう)・玉串奉奠(たまぐしほうてん)という祈りの方法について、その意味や役割を詳しく見ていきましょう。
仏式における読経と焼香の意味
仏式では、僧侶が仏教の教えに基づいたお経を唱えます。お経は、多くの宗派において故人様の成仏を願い、極楽浄土へ導くための大切な祈りとされています。読経の間、ご遺族や参列者は焼香を行い、仏様に香を捧げます。
焼香には、香の煙で空間と心身を清める意味があり、同時に「故人様への供養」と「仏様への敬意」を表す行為でもあります。宗派によって焼香の回数や作法に違いはありますが、どれも敬虔(けいけん)な気持ちを込めて行われるものです。作法について詳しくは「参列時のマナーや香典の表書きによる違い」にて後述します。
神式における祭詞奏上と玉串奉奠の意味
神式では、仏式の読経にあたるものとして「祭詞(さいし)」があります。これは神職が神様や祖霊に向かって、故人様の人生を報告し、感謝の言葉を伝える神聖な言葉です。
祭詞奏上の間、参列者は玉串を神前に捧げます。これを「玉串奉奠」といい、玉串を捧げることで故人様の魂に思いを届けるとされています。
4.【仏式と神式】葬儀を行う場所の違い

祈りの方法に違いがあるように、葬儀を執り行う「場所」についても、仏式と神式では宗教的な価値観に基づく違いが見られます。
ここでは、それぞれの形式で選ばれやすい場所や、その背景にある考え方をご紹介します。
仏式では寺院や斎場を中心に行われる
仏式は、寺院や民間の斎場などで執り行われるのが一般的です。特に菩提(ぼだい)寺(※3)がある場合は、住職に依頼して本堂で読経をしていただくケースも多く見られます。
寺院での葬儀には、仏前で手を合わせるという意味が込められており、仏教に帰依する姿勢が強く反映されています。一方、斎場では宗派に応じた祭壇の設営や僧侶の招へいも可能で、近年は利便性やアクセスの良さから斎場の利用が主流となっています。
(※3)先祖代々がお世話になっている、縁の深い寺院。
神式では斎場や自宅が中心で神社は使われない
死を「穢れ」と考える神道では、神様がいらっしゃる神社で葬儀を行うことは基本的にありません。そのため神式の葬儀は、斎場や自宅で行われることがほとんどです。
自宅で葬儀を行う場合は、神様に穢れが移らないよう、神棚を閉じて白い半紙などで覆う「神棚封じ」を行う必要があります。詳しい方法や注意点は「神棚封じとは?」でご紹介しておりますのでぜひご覧ください。
5.【仏式と神式】死後の名前の違い

故人様に贈られる「死後の名前」にも、仏式と神式では違いがあります。
こちらでは、それぞれの死後の名前について、意味と特徴をご紹介します。
仏式では戒名(かいみょう)が授けられる
「戒名」とはあの世での名前であり、故人様が仏の教えに帰依し、仏道に入ったことを示すものです。浄土真宗では「法名(ほうみょう)」、日蓮宗では「法号」と呼ばれます。
戒名は、故人様の人柄や生前の功績などを反映し、僧侶によって命名されます。宗派によって命名の形式や文字数に違いはありますが、「〇〇信士」「〇〇大姉」といったように、性別や人生の歩みに応じた名前が与えられます。
戒名は必然ではありませんが、戒名を付けない場合、寺院での納骨を断られたり、ご親族から反対が起こったりなどのトラブルにつながりやすくなるのが実情です。戒名を不要とする考えを持っていた場合でも、ご家族内でよく話し合ってから決めることをおすすめします。
神式では諡(おくりな)で故人様をたたえる
一方の神式では「諡(おくりな)/諡号(しごう)」と呼ばれる、守り神としての名前をつけます。諡は故人様の生前の名前を使用するのを基本とし、性別や年齢に応じた語句を組み合わせ、最後に「命(みこと)」で締めくくります。この「命」は、現在の「様」と同じ意味合いです。
戒名とは異なり、諡は形式が決まっているため「依頼して授けてもらう」ものではありません。例えば男性で71歳以上の方の場合、「〇〇〇〇(本名)翁 命」となります。
6.【仏式と神式】供養のかたちによる違い

仏式と神式では、葬儀後に行われる「供養」にも違いがあります。
それぞれの目的やタイミングをご紹介します。
仏式の供養
仏式の供養は、初七日(しょなのか/しょなぬか)、四十九日、一周忌、三回忌など、節目ごとに法要を重ねていくのが特徴です。法要は一般的に、故人様の成仏と現世の家族の平穏を祈るために行われます。
亡くなってから49日目に迎える四十九日は、法要の中でも特に大切な節目です。仏式では四十九日をもって忌明けとし、法要と共に納骨を行うケースが一般的です。
神式の供養
神式の供養は「霊前祭(れいぜんさい)」や「式年祭(しきねんさい)」と呼ばれ、それぞれの違いは以下の通りです。
| 内容 | 儀式の種類 | |
|---|---|---|
| 霊前祭 | 故人様の御霊は不安定な状態にあるとされるため、安らかに鎮まるよう祈る | 帰家祭(きかさい)・十日祭・五十日祭など |
| 式年祭 | 守り神となった故人様の御霊を、新たな「祖霊神(それいしん)」として奉る | 三年祭・十年祭・五十年祭など |
亡くなってから50日目にあたる「五十日祭(ごじゅうにちさい)」は、仏式での四十九日にあたる重要な節目であり、ここで忌明けとされることが一般的です。各儀式の詳細は「神式における法要」の記事を参考になさってください。
7.【仏式と神式】参列時のマナーや香典の表書きによる違い

葬儀の形式が異なれば、参列者として求められるマナーや持ち物にも違いが生じます。とくにお香典の表書きや数珠の扱い、拝礼の作法などは、仏式と神式で大きく異なるポイントです。
こちらでは、仏式と神式の葬儀に参列する際のマナーをご紹介します。
香典の表書きと水引の違い
仏式と神式では、お香典の表書きの言葉や、使用する水引にも以下のような違いがあります。
| 仏式 | 神式 | |
|---|---|---|
| 香典袋 | 「白黒」「黄白」「双銀」のいずれかの水引がついた不祝儀袋 | ・「白黒」「黄白」「双銀」のいずれかの水引がついた不祝儀袋 ・蓮の花が印刷されたものはNG |
| 表書き | ・四十九日前は「御霊前」 ・以降は「御仏前」「御佛前」 |
「御霊前」「御玉串料」 「御榊料」「御神前」のいずれか ※御神前は式年後から使用可 |
なお、浄土真宗では故人様が霊になることはないため「御仏前」と書きます。詳しくは「御霊前と御仏前の違い」にてご紹介しておりますので、そちらをご覧ください。
服装や持ち物など参列時の注意点
葬儀における服装や持ち物は、仏式と神式で大きな違いはありません。仏式・神式いずれの葬儀においても、基本的には黒を基調とした喪服の着用がマナーとされています。
仏式と神式で大きく違うのは、数珠の有無です。仏式の葬儀では、故人様に敬意や供養の気持ちを示すために数珠を持参することがマナーとなっています。一方、神式では数珠を用いません。仏式の葬儀に参列することになった場合も、神式を信仰している方の場合、数珠は必須ではないため、ご自身の考えによる判断で差し支えないでしょう。
焼香と玉串奉奠
仏式の焼香と、神式の玉串奉奠の作法についてご紹介します。
焼香の作法
焼香は、故人様と関係の深かった方から順番に行います。基本的な作法は以下の通りです。
2. 位牌、遺影にそれぞれ黙礼
2. 位牌、遺影にそれぞれ黙礼








焼香の回数や宗派によって異なりますので、参列者は先に行うご遺族の焼香回数を参考にされるとよいでしょう。詳しくは「焼香のやり方やマナー」をご参照ください。
焼香の回数や宗派によって異なりますので、参列者は先に行うご遺族の焼香回数を参考にされるとよいでしょう。詳しくは「焼香のやり方やマナー」をご参照ください。
焼香の回数や宗派によって異なりますので、参列者は先に行うご遺族の焼香回数を参考にされるとよいでしょう。詳しくは「焼香のやり方やマナー」をご参照ください。
玉串奉奠の作法
玉串奉奠の作法は以下の通りです。
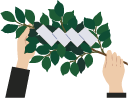
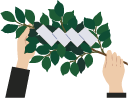






8.【仏式と神式】葬儀費用の違い

仏式と神式の葬儀費用の中で、大きく違うのは宗教者へお渡しする謝礼です。仏式ではこれを「お布施」、一方の神式では「祭祀料(さいしりょう)」と呼びます。
お布施とは、葬儀などの仏事で僧侶にお渡しするお金を指します。ここで注意したいのは、「お布施=対価」ではないという点です。お布施は古くから仏教に伝わる修行のひとつであると同時に、寺院に対する感謝や寄付の気持ちを表します。
一方、神道の祭祀料は、儀式を執り行っていただいた神主や神官への謝礼としてお渡しします。
どちらも明確な金額設定がないため、いくら用意すべきかご遺族は戸惑われるかもしれません。以下に一般的な目安をご紹介しますので参考になさってください。戒名料については「最新版お布施の相場」の記事にて詳しく取り上げております。
| 仏式 | ・葬儀のお布施:15~20万円 ・お車代(交通費):5千円~1万円 ・御膳料(お食事代):5千円~1万円 ・戒名料:戒名の位に応じて異なる |
|---|---|
| 神式 | ・祭祀料:15~20万円(宗教者1人あたり) ・お車代:5千円~1万円 ・御膳料:5千円~1万円 |
9.「心をこめて送り出す尊さ」は仏式も神式も同じ

ここまで、仏式と神式の葬儀における違いをさまざまな視点からご紹介してきました。宗教観の根本的な違いから、儀式の進め方、祈りの形、参列マナー、そして費用の考え方に至るまで、それぞれの形式には独自の意味や伝統があります。
一方で、どちらの宗教葬にも共通しているのは「故人様の人生に敬意を示し、心を込めて送り出すという想いに支えられている点」です。もちろん、それは仏式や神式に限らず、他の宗教や無宗教の葬儀にも当てはまります。
「どのように故人様を見送りたいのか」「どのような想いを表現したいか」を考えて執り行われる葬儀は、宗教宗派を問わず、尊いものなのです。
10.仏式と神式の違いに関するFAQ

A.はい、必ずしも仏式や神式を選ぶ必要はありません。
葬儀に関する価値観が多様化している近年では、特定の宗教宗派にとらわれない「無宗教葬(自由葬)」を選ばれる方も増えています。ただし、無宗教葬では焼香や読経などの宗教儀式が省略されることもあるため、伝統的な葬儀を重んじる方からは賛同を得にくいというデメリットもあります。
無宗教でも葬儀を執り行うことは可能ですが、仏式や神式に準じた形を取り入れつつ、故人様らしさを大切にした内容を盛り込むなど、柔軟な対応を検討されるとよいでしょう。
A.もともとは神道の教えが由来ですが、現在は宗教を問わず配られることが多いようです
葬儀で参列者に配られる清め塩は、塩によるお清め効果について記されていた「古事記」から発生したと考えられています。もともとは神道の「死による穢(けが)れ」をはらうために使用されていましたが、現在は一部の仏式葬儀でも配られることがあります。使用するかは、ご自身の判断で差し支えありません。
A.教義の解釈や伝統に基づいて推奨される花はありますが、近年は自由な花を選ぶ傾向にあります。
例えば仏教ではランや菊、ユリといった和花が好まれ、毒やトゲのある花、強い香りのする花は避けられてきました。一方、神式では菊を中心とした白い和花が一般的です。
しかし近年では、伝統を重んじつつも、自由な花を祭壇に飾る傾向が主流となりつつあります。周りからの反対がない限りは、故人様のお人柄や好みを反映させた花を選び、より華やかなお見送りを検討なさってはいかがでしょうか。詳しくは「花祭壇と宗教」の記事をご覧ください。
11.仏式や神式に違いはあっても故人様の安寧を願う気持ちは同じ

仏式と神式の葬儀には死生観や儀式に違いがあるものの、共通しているのは「故人様への感謝と敬意を込めて、心静かにお見送りすること」です。それぞれの特徴を押さえた上で、ご家族や故人様にとって納得できるお別れを執り行いましょう。
花葬儀では、仏式・神式のどちらにも対応できる柔軟なプランとともに、事前のご相談も無料で承っています。ゆっくりと安心してお話しいただける環境をご用意しておりますので、迷いや不安を感じたら、ぜひ花葬儀の事前相談をご活用ください。




























